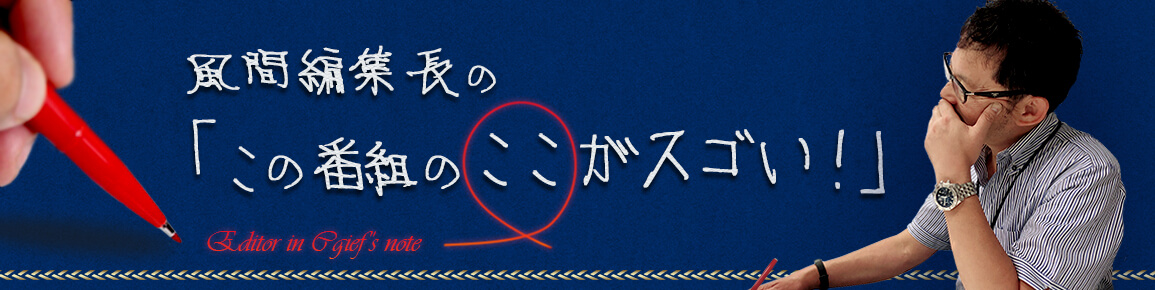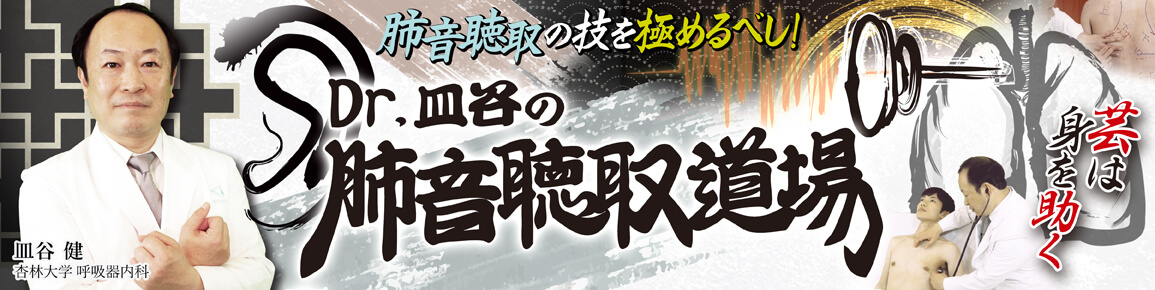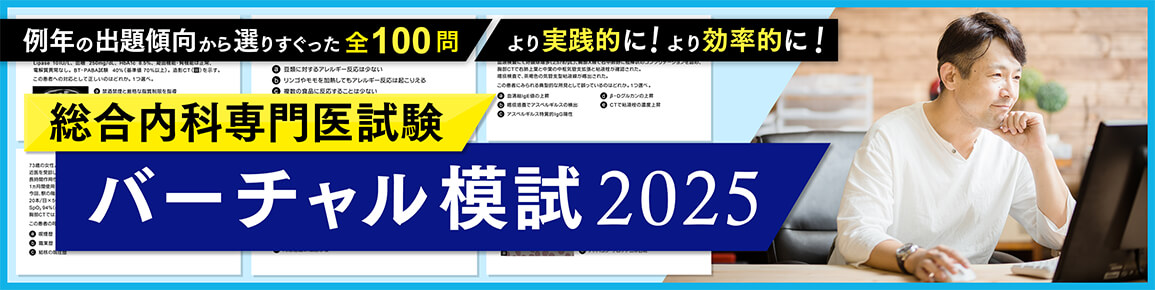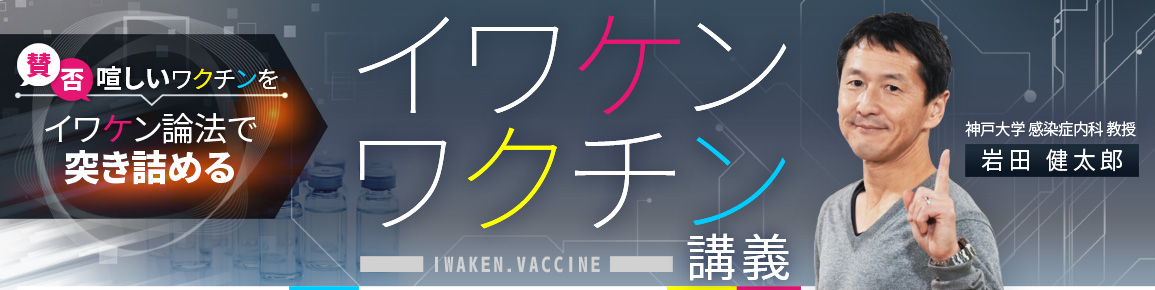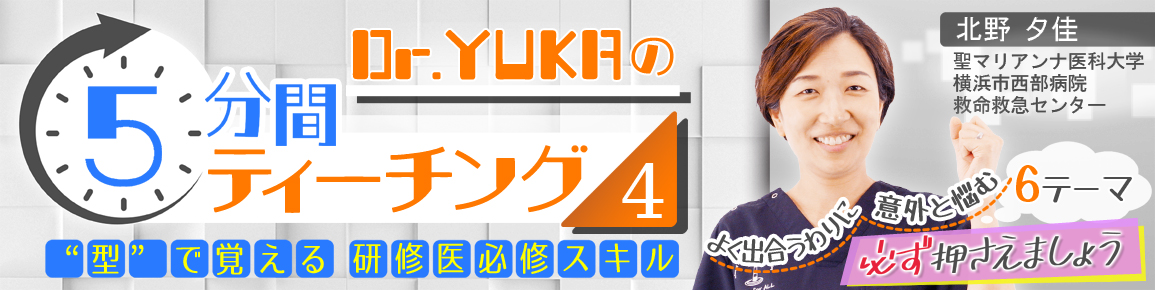「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」
株式会社ケアネットが新しいパーパスを発表しました。ケアネットのコーポレートサイトでは、医師を支える「知」と「情熱」と「行動力」の赤い三従士の雄姿をご覧いただけます。
ただし、今日この場で書きたいのはこのパーパスの話ではありません。支えられている医師が手に持っているもの。そう、聴診器の話です。
テレビやネット広告などで医師のイメージ写真を見ることがあると思いますが、白衣を着たモデルを医師にするために僕らは聴診器を持たせます。白衣だけでは薬剤師や化学者と区別がつかない。聴診器を持つ、または首からかけるとその人は医師になります。そういう“お約束”です。
しかし、医師のシンボルとしては現役の聴診器ですが、実臨床では(循環器科医と呼吸器科医は別にして)徐々に使われなくなっています。もともと体表から体の内部の音を聞き、体内で何が起こっているかイメージするという原始的なメカニズムで成り立っている聴診器。X線、エコー、CTといった画像診断機器が普及すれば、百聞は一見に如かず、画像で病変を見ればいいじゃんとなるのは当然の流れです。
それでもなお、聴診の有用性はあります。軽くてどこにも持ち運べ手軽ですぐ使える。非侵襲で患者の負担はゼロ。電力も必要ない。そういった意味ではSDGsが叫ばれる現代に合ったエコな診断ツールといえるかもしれません。
「Dr.皿谷の肺音聴取道場」は、肺音に特化し、呼吸器専門医の皿谷健先生がそのさまざまな聴取方法の極意を指南する番組です。
たとえば、やぎ音。患者の胸に聴診器を当て、「いー」と発声してもらいます。肺炎があるとその場所は音の伝導がよくなり、「いー」が「えー」と聞こえる現象で、肺炎を示唆する所見です。ヤギの鳴き声のように音が変化するためそう呼ばれます。
非常に簡単な手技で音の違いもはっきりわかります。書籍では実際の音を聞くことはできませんが、そこは動画のCareNeTV。音を繰り返し聞くことができるので確実に身につけることができます。
ほかにも喘息や肺がんの肺音、肺炎の種類による肺音の違いなど一般的に習得すべき肺音聴取のテクニックをほぼ網羅しています。実臨床では、最終的には画像で診断し治療方針を決めることになるとは思いますが、音で病態をイメージできれば診療の質は確実に向上します。
また、患者さんの胸に聴診器を当てることは患者に安心感を与える“効果”があるともいわれます。検査機器の高度化などで医師が直接患者の身体に触れる機会が少なくなるなか、診療に対する患者の満足度という面でも聴診器は貢献するかもしれません。最近、聴診器をあまり使ってないなーという先生方、「肺音聴取道場」にちょっと入門して、医師のシンボルを実臨床にもっと活用してみてはいかがでしょうか。