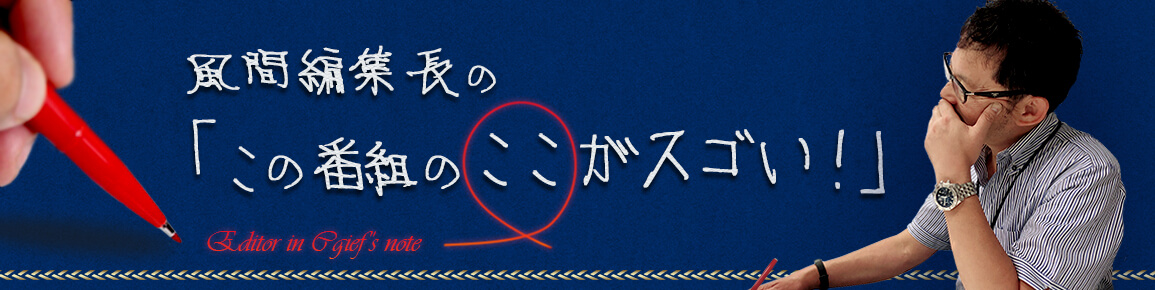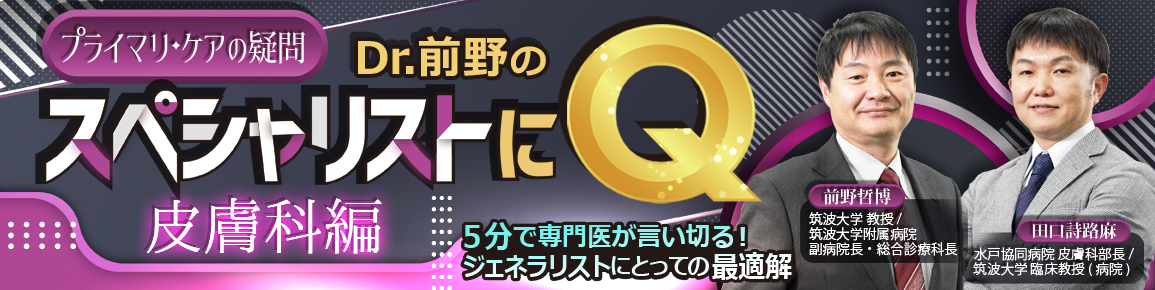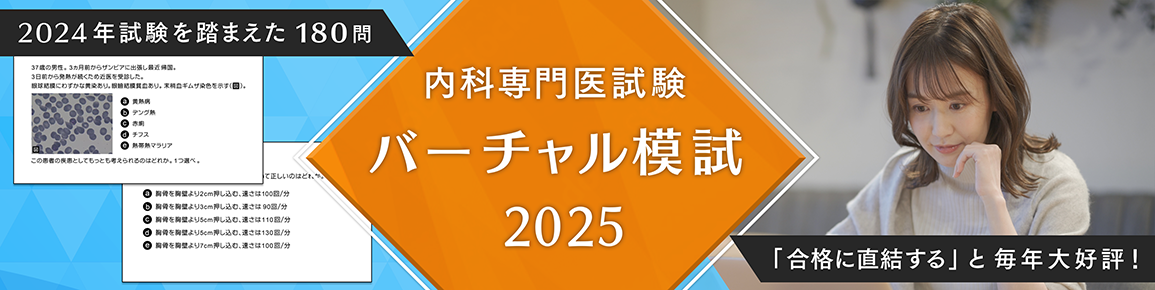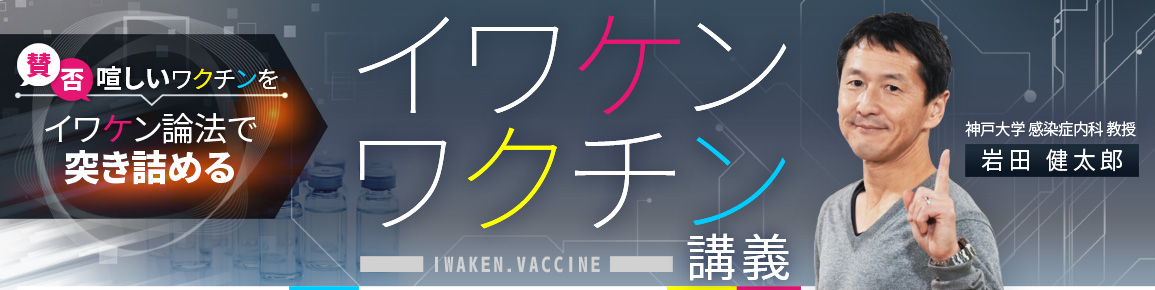数多あるCareNeTV番組の中で、長く支持を集め続ける作品には、それなりの理由がある。ヒット作の見所を、講師の先生の素顔、収録秘話を含め、ケアネット編集長の風間がご案内します。
-
血ガスハンターDr.増井がケアネット30年の歴史で無二なところは? 2026/01/25
 ケアネットは今年、創立30周年を迎えます。ご存じの方も多いと思いますが、弊社の祖業はCS衛星放送で医療情報を提供する「ケアネットTVメディカルCh.」です。会社設立2年後の1998年に開局しています。「ケアネットDVD」の発売が2004年、ネット配信の今の「CareNeTV」が誕生したのが2013年です。「Dr.林の笑劇的救急問答」「Dr.岩田の感染症アップグレード」といったCareNeTVの定番である「Dr.〇〇の××」というタイトルが定着したのはケアネットDVDの頃から。もちろん今はいろいろなパターンのタイトルがありますが、王道はやはりコレ。時代は大きく下って2023年リリースの「Dr.増井の血ガスハンティング」も「Dr.〇〇の××」の流れにあるタイトルですが、ちょっと違いがあります。増井伸高先生のCareNeTV第1作目は「Dr.増井の心電図ハンティング」です。「Dr.増井の骨折ハンティング」もあります。おわかりいただけたでしょうか?「Dr.林の笑劇的救急問答」は20年以上にわたりSeason19まで続く長寿シリーズですが、テーマは一貫して救急です。それに対して増井先生は、異なる臨床テーマを「ハンティング」シリーズとして展開しているのです。衛星放送から続くケアネットの長い歴史の中で初でしょう。それだけ増井先生の「ハンティング」が支持されているということです。では「ハンティング」とは何なのか?もちろん「獲物を狩る」という意味の英語のhunt(ハント)から来ているのですが、漠然と目の前に動物がいるから打つのではなく、なぜ狩るのか?どうやって狩るのか?狩ってどうするのか?ということを常に明確に意識させて講義するのが「ハンティング」スタイルです。血ガスハンティングでも、すべての症例で、まず何のために血ガスを取るのか(あるいは取られたのか)を考えます。次に、データを評価するわけですが、あくまで目的に対して最短距離で行ない、目的に対してあまり重要でない評価は時に割愛する方法を提案します。そして最後に、その評価を基づいて実施すべきアクション、マネジメントを述べます。「ハンティング」レクチャーに通底するこの考え方は、極めて合理的であり、かつ実臨床に即しています。それこそが増井先生の講義の真骨頂であり、高い評価を集めている最大の理由。ただの言葉遊びではないのです。増井先生、次は何を狩りに出かけるのかなー?
ケアネットは今年、創立30周年を迎えます。ご存じの方も多いと思いますが、弊社の祖業はCS衛星放送で医療情報を提供する「ケアネットTVメディカルCh.」です。会社設立2年後の1998年に開局しています。「ケアネットDVD」の発売が2004年、ネット配信の今の「CareNeTV」が誕生したのが2013年です。「Dr.林の笑劇的救急問答」「Dr.岩田の感染症アップグレード」といったCareNeTVの定番である「Dr.〇〇の××」というタイトルが定着したのはケアネットDVDの頃から。もちろん今はいろいろなパターンのタイトルがありますが、王道はやはりコレ。時代は大きく下って2023年リリースの「Dr.増井の血ガスハンティング」も「Dr.〇〇の××」の流れにあるタイトルですが、ちょっと違いがあります。増井伸高先生のCareNeTV第1作目は「Dr.増井の心電図ハンティング」です。「Dr.増井の骨折ハンティング」もあります。おわかりいただけたでしょうか?「Dr.林の笑劇的救急問答」は20年以上にわたりSeason19まで続く長寿シリーズですが、テーマは一貫して救急です。それに対して増井先生は、異なる臨床テーマを「ハンティング」シリーズとして展開しているのです。衛星放送から続くケアネットの長い歴史の中で初でしょう。それだけ増井先生の「ハンティング」が支持されているということです。では「ハンティング」とは何なのか?もちろん「獲物を狩る」という意味の英語のhunt(ハント)から来ているのですが、漠然と目の前に動物がいるから打つのではなく、なぜ狩るのか?どうやって狩るのか?狩ってどうするのか?ということを常に明確に意識させて講義するのが「ハンティング」スタイルです。血ガスハンティングでも、すべての症例で、まず何のために血ガスを取るのか(あるいは取られたのか)を考えます。次に、データを評価するわけですが、あくまで目的に対して最短距離で行ない、目的に対してあまり重要でない評価は時に割愛する方法を提案します。そして最後に、その評価を基づいて実施すべきアクション、マネジメントを述べます。「ハンティング」レクチャーに通底するこの考え方は、極めて合理的であり、かつ実臨床に即しています。それこそが増井先生の講義の真骨頂であり、高い評価を集めている最大の理由。ただの言葉遊びではないのです。増井先生、次は何を狩りに出かけるのかなー? -
「皮膚疾患は難しい」の常識を覆した!シン診断スタンダード 2025/12/27
 表皮水疱症、色素性乾皮症、弾性線維性仮性黄色腫、水疱性類天疱瘡、紅斑性天疱瘡、後天性真皮メラノサイトーシス…皮膚疾患は3000種類もあると言われ、その分類も複雑です。定番書とされる「あたらしい皮膚科学」(中山書店)にも1500を超える疾患が掲載されているそうです。皮膚科専門医はそれらの疾患を基本的には皮疹の形状、発現場所、対称性などを見て、触って鑑別・診断するというのですから、その専門性には驚かされます。非皮膚科医がそれらをすべて覚えておくことはできないし、その必要もないでしょうが、一方で、皮膚疾患ほど見つかりやすい疾患はありません。言うまでもなく、それは皮膚に目に見える形で現れるので、ほかならぬ患者自身が異常に気づくからです。なので、皮膚科医でなくても、日々患者を診ている臨床医であれば、否応なく皮膚疾患にも遭遇し対応を求められるはずです。その時、どうすればいいか?どこまで診られればいいのか?そこにフォーカスした番組が「Dr.松田のフローチャート皮膚診断」です。松田先生によれば、非専門医が知っておくべきものは実はそれほど多くなく、ポイントを押さえれば、膨大な数の皮膚疾患の中でそのほとんどを鑑別できるというのです。ダーモスコピーも必要ありません。番組構成も皮膚科診断の基本的な考え方を説明したうえで、まず皮疹の表面がザラザラかツルツルかで分類し、ザラザラであったなら、次に何を考えるか?というようにフローチャートで進んでいきます。皮膚科医の頭の中にある思考アルゴリズムを、簡素に“見える化”した流れになっているのです。2023年リリースの番組ですが、視聴した先生方からも大好評で、ある30代の内科勤務医の先生からは「非常にわかりやすく非専門医ですが関心がもてました。今年のベストレクチャーです」と最大級の賛辞をいただきました。皮膚科診断の考え方は古びることはありません。この先もずっと非皮膚科医のための皮膚科学習コンテンツのスタンダードとして活用いただければと思います。
表皮水疱症、色素性乾皮症、弾性線維性仮性黄色腫、水疱性類天疱瘡、紅斑性天疱瘡、後天性真皮メラノサイトーシス…皮膚疾患は3000種類もあると言われ、その分類も複雑です。定番書とされる「あたらしい皮膚科学」(中山書店)にも1500を超える疾患が掲載されているそうです。皮膚科専門医はそれらの疾患を基本的には皮疹の形状、発現場所、対称性などを見て、触って鑑別・診断するというのですから、その専門性には驚かされます。非皮膚科医がそれらをすべて覚えておくことはできないし、その必要もないでしょうが、一方で、皮膚疾患ほど見つかりやすい疾患はありません。言うまでもなく、それは皮膚に目に見える形で現れるので、ほかならぬ患者自身が異常に気づくからです。なので、皮膚科医でなくても、日々患者を診ている臨床医であれば、否応なく皮膚疾患にも遭遇し対応を求められるはずです。その時、どうすればいいか?どこまで診られればいいのか?そこにフォーカスした番組が「Dr.松田のフローチャート皮膚診断」です。松田先生によれば、非専門医が知っておくべきものは実はそれほど多くなく、ポイントを押さえれば、膨大な数の皮膚疾患の中でそのほとんどを鑑別できるというのです。ダーモスコピーも必要ありません。番組構成も皮膚科診断の基本的な考え方を説明したうえで、まず皮疹の表面がザラザラかツルツルかで分類し、ザラザラであったなら、次に何を考えるか?というようにフローチャートで進んでいきます。皮膚科医の頭の中にある思考アルゴリズムを、簡素に“見える化”した流れになっているのです。2023年リリースの番組ですが、視聴した先生方からも大好評で、ある30代の内科勤務医の先生からは「非常にわかりやすく非専門医ですが関心がもてました。今年のベストレクチャーです」と最大級の賛辞をいただきました。皮膚科診断の考え方は古びることはありません。この先もずっと非皮膚科医のための皮膚科学習コンテンツのスタンダードとして活用いただければと思います。 -
心電図検定“全盛”時代のヒット作「Dr.翼の3級合格ポイント塾」+オンラインスクール 2025/11/29
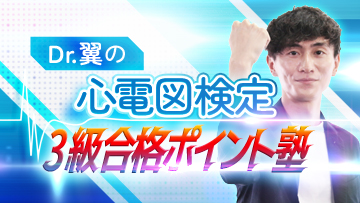 心電図検定の受験者が年々増えています。医療現場における心電図判読スキルの重要性が再認識されている表れと言えるでしょう。特筆すべきは、受験者の層が多様化している点です。かつては循環器内科医や経験豊富な臨床検査技師が中心でしたが、現在では一般内科医、救急医、看護師、理学療法士、そして医学生や看護学生といった幅広い医療者が意欲的に挑戦しています。「心電図を読めること」が特定の専門家のスキルではなく、すべての医療者に求められるものになりつつあります。また、そのスキル習得を心電図検定の「級」として客観的に示すことが自らのキャリアにとっても有利に働くと多くの医療者が感じているようです。心電図が患者の心臓の状態を非侵襲的かつ迅速に評価できる、極めて価値の高い診断ツールであることは論を待ちません。しかし、心電図は波形の多様性や複雑さから苦手意識を持つ医療者も少なくありません。独学での体系的な理解には限界があり、専門的な知識と実践的な学習が求められます。そうしたニーズに応えるため、CareNeTVではさまざまな心電図の番組を配信していますが、「Dr.翼の心電図検定3級合格ポイント塾」は、冒頭で述べた昨今の心電図検定の人気を背景に心電図検定におけるレベルを明確にしている点が最大の特徴です。番組では、心電図検定1級合格者である駒井翼先生が自身の経験に基づき、3級合格に必要な知識と効率的な学習法を凝縮して解説しています。全10回の講義で、洞不全症候群、房室ブロック、心房細動、心筋梗塞といった検定頻出の重要疾患・波形パターンを網羅。単なる知識の羅列ではなく、動画内で一時停止して模擬問題に取り組む形式を採用することで、受講者が能動的に考え、実践的な判読スキルを身につけられるよう工夫されています。「Dr.翼の心電図検定3級合格ポイント塾」を通じて体系的に学習することは、検定合格という目標達成につながるだけでなく、日々の臨床現場における自信とスキルアップに直結します。例えば、救急外来での急患対応時や病棟でのモニター心電図の変化に直面した際、確かな知識に基づいた迅速かつ適切な初期判断が可能となります。また、多職種間で心電図所見について共通の認識を持つことで、より円滑で正確な情報共有が実現し、患者安全の向上に大きく貢献します。駒井先生のレクチャーが「圧倒的にわかりやすい」と好評なため、心電図検定3級受験者に対象を絞ったオンラインスクール「心電図の達人 Dr.翼の心電図検定3級 必勝講座」も開講しました。Zoomを使ったライブ講義では、動画コンテンツでは得られないリアルタイムでの質疑応答や、講師との直接的なコミュニケーションを通じて、受講者の疑問をその場で解消できます。一方的な受講ではなく、双方向の学習環境が、心電図判読へのさらなる理解と自信を深めてくれるはずです。3級合格を確実にしたい人にとって極めて有効な学習機会となると確信しています。※CareNeTVスクール「心電図の達人 Dr.翼の心電図検定3級 必勝講座」は終了しました。
心電図検定の受験者が年々増えています。医療現場における心電図判読スキルの重要性が再認識されている表れと言えるでしょう。特筆すべきは、受験者の層が多様化している点です。かつては循環器内科医や経験豊富な臨床検査技師が中心でしたが、現在では一般内科医、救急医、看護師、理学療法士、そして医学生や看護学生といった幅広い医療者が意欲的に挑戦しています。「心電図を読めること」が特定の専門家のスキルではなく、すべての医療者に求められるものになりつつあります。また、そのスキル習得を心電図検定の「級」として客観的に示すことが自らのキャリアにとっても有利に働くと多くの医療者が感じているようです。心電図が患者の心臓の状態を非侵襲的かつ迅速に評価できる、極めて価値の高い診断ツールであることは論を待ちません。しかし、心電図は波形の多様性や複雑さから苦手意識を持つ医療者も少なくありません。独学での体系的な理解には限界があり、専門的な知識と実践的な学習が求められます。そうしたニーズに応えるため、CareNeTVではさまざまな心電図の番組を配信していますが、「Dr.翼の心電図検定3級合格ポイント塾」は、冒頭で述べた昨今の心電図検定の人気を背景に心電図検定におけるレベルを明確にしている点が最大の特徴です。番組では、心電図検定1級合格者である駒井翼先生が自身の経験に基づき、3級合格に必要な知識と効率的な学習法を凝縮して解説しています。全10回の講義で、洞不全症候群、房室ブロック、心房細動、心筋梗塞といった検定頻出の重要疾患・波形パターンを網羅。単なる知識の羅列ではなく、動画内で一時停止して模擬問題に取り組む形式を採用することで、受講者が能動的に考え、実践的な判読スキルを身につけられるよう工夫されています。「Dr.翼の心電図検定3級合格ポイント塾」を通じて体系的に学習することは、検定合格という目標達成につながるだけでなく、日々の臨床現場における自信とスキルアップに直結します。例えば、救急外来での急患対応時や病棟でのモニター心電図の変化に直面した際、確かな知識に基づいた迅速かつ適切な初期判断が可能となります。また、多職種間で心電図所見について共通の認識を持つことで、より円滑で正確な情報共有が実現し、患者安全の向上に大きく貢献します。駒井先生のレクチャーが「圧倒的にわかりやすい」と好評なため、心電図検定3級受験者に対象を絞ったオンラインスクール「心電図の達人 Dr.翼の心電図検定3級 必勝講座」も開講しました。Zoomを使ったライブ講義では、動画コンテンツでは得られないリアルタイムでの質疑応答や、講師との直接的なコミュニケーションを通じて、受講者の疑問をその場で解消できます。一方的な受講ではなく、双方向の学習環境が、心電図判読へのさらなる理解と自信を深めてくれるはずです。3級合格を確実にしたい人にとって極めて有効な学習機会となると確信しています。※CareNeTVスクール「心電図の達人 Dr.翼の心電図検定3級 必勝講座」は終了しました。 -
米国内科レジデンシーと「5分間ティーチング」 2025/10/31
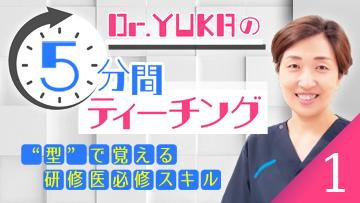 日本で働いている臨床医で米国の内科専門医を取得している先生がいます。そうした先生方は日本で医師免許を取得した上で米国の医師国家試験であるUSMLEに合格し、米国で少なくとも3年間内科レジデントとして働いたわけですから、当然ながら、志が高くプロアクティブでかつ優秀です。もちろんそんな医師は割合としてはごくわずかですが、僕は仕事柄、米国内科専門医を持っている日本人医師をたくさん知っています。CareNeTVの講師の中にも相当数いますし、その中の何人かとは親しくさせていただいています。時折、彼ら彼女らから、米国の研修について話を聞く機会があります。みな共通して強調するのは、米国の内科レジデンシープログラムは体系化されておりシステムとして確立している、ということです。誰でも3年間みっちりやれば内科医師として臨床で動ける知識とスキルが確実に身につくと言います。みな日本でも医師としての研修を経験しているので、比較対象が日本となるわけですが、残念ながら、彼我の差があるようです。日本と米国では医学部の年数など医学教育システムが異なるので単純比較はできませんが、要は、日本は臨床研修も専攻医のプログラムも属人的な要素が強く、教わる病院や指導医によってバラつきがあるということのようです。北野夕佳先生もそうした経歴を持ち米国の内科レジデンシーの臨床医学教育としてのすばらしさを語ってくれた1人です。「では、先生が米国の内科レジデンシーで習得したことをCareNeTVの番組にしてくれませんか?」「Dr.YUKAの5分間ティーチング1 “型”で覚える研修医必修スキル」は、そんな僕の“ゆるいお願い”から始まりました。北野先生は、その時すでに聖マリアンナ医科大学の研修医たちに、いわば米国仕込みの指導を行っており、それを「5分間ティーチング」としてサイトに書き溜め始めていました。「まだ途中だけど、日本の研修医向けにまとめたらこんな感じになるとは思うけど…」と北野先生。「『5分間ティーチング』いくつで米国内科レジデントの必要最低限を網羅できるんですか?」と僕が食い気味に尋ねると、「うーん、50くらいかな?」先生は超多忙でそこから番組リリースまで紆余曲折がありましたが、現在第4作計24話まで来ています。今やCareNeTVを代表する人気シリーズになったので、Dr.YUKAには、ぜひとも50話までがんばってほしいものです。それと、あまりに人気なので、電子書籍化もしちゃいました。医書jpだけでなくAmazonのKindleでも読めるので、こちらもぜひご活用ください。
日本で働いている臨床医で米国の内科専門医を取得している先生がいます。そうした先生方は日本で医師免許を取得した上で米国の医師国家試験であるUSMLEに合格し、米国で少なくとも3年間内科レジデントとして働いたわけですから、当然ながら、志が高くプロアクティブでかつ優秀です。もちろんそんな医師は割合としてはごくわずかですが、僕は仕事柄、米国内科専門医を持っている日本人医師をたくさん知っています。CareNeTVの講師の中にも相当数いますし、その中の何人かとは親しくさせていただいています。時折、彼ら彼女らから、米国の研修について話を聞く機会があります。みな共通して強調するのは、米国の内科レジデンシープログラムは体系化されておりシステムとして確立している、ということです。誰でも3年間みっちりやれば内科医師として臨床で動ける知識とスキルが確実に身につくと言います。みな日本でも医師としての研修を経験しているので、比較対象が日本となるわけですが、残念ながら、彼我の差があるようです。日本と米国では医学部の年数など医学教育システムが異なるので単純比較はできませんが、要は、日本は臨床研修も専攻医のプログラムも属人的な要素が強く、教わる病院や指導医によってバラつきがあるということのようです。北野夕佳先生もそうした経歴を持ち米国の内科レジデンシーの臨床医学教育としてのすばらしさを語ってくれた1人です。「では、先生が米国の内科レジデンシーで習得したことをCareNeTVの番組にしてくれませんか?」「Dr.YUKAの5分間ティーチング1 “型”で覚える研修医必修スキル」は、そんな僕の“ゆるいお願い”から始まりました。北野先生は、その時すでに聖マリアンナ医科大学の研修医たちに、いわば米国仕込みの指導を行っており、それを「5分間ティーチング」としてサイトに書き溜め始めていました。「まだ途中だけど、日本の研修医向けにまとめたらこんな感じになるとは思うけど…」と北野先生。「『5分間ティーチング』いくつで米国内科レジデントの必要最低限を網羅できるんですか?」と僕が食い気味に尋ねると、「うーん、50くらいかな?」先生は超多忙でそこから番組リリースまで紆余曲折がありましたが、現在第4作計24話まで来ています。今やCareNeTVを代表する人気シリーズになったので、Dr.YUKAには、ぜひとも50話までがんばってほしいものです。それと、あまりに人気なので、電子書籍化もしちゃいました。医書jpだけでなくAmazonのKindleでも読めるので、こちらもぜひご活用ください。 -
CTクイズを出されたら、答えたくなるのが医者の性 2025/09/28
 僕は以前ある医学雑誌の編集長をしていました。紙の雑誌の編集長じゃなくなったのは2007年なので18年も前のこと。その雑誌自体ももうないので「昔話」として読んでください。 その雑誌で毎月どの記事がどのくらい読まれたか読者調査をしていました。読者はもちろんすべて医師です。いわばテレビの視聴率調査みたいなものですが、正直あまり良い数字ではありませんでした。 その中で相対的にもっともスコア(と当時呼んでいました)が良かったのが、クイズでした。練りに練った特集記事よりも、尖った企画記事よりも、連載よりもニュースよりもたいていクイズのスコアが一番高かった。 患者背景、主訴、時に検査データとともにX線写真やCT画像、心電図、皮膚所見などを提示し、読者に診断してもらう。奇数ページに一面ドーンと画像などが載っていて、裏の偶数ページに解答と解説がある。クイズといっても極めて医学的で教育的なものでした。 この手法は、インターネット時代になっても人気があるようです。いや、むしろ今はもっともコモンな医学教育の形の1つといえるかもしれません。たとえばNEJMのWebサイトでは、「IMAGE CHALLENGE」というコーナーで日替わりでそんな“クイズ”を掲載しています。先生方はその問題になんとなくチャレンジし、嬉々としてSNSに投稿したりしています。 変わったなあと思うと同時に変わらないなあと思います。 「Dr.金井のCTクイズ」は、つまるところ僕の雑誌時代の人気企画をそのまま動画化した番組です。想定通り視聴者からの評判はよく、CareNeTVの人気番組の1つになりました。 それはそれでよかったのですが、実は、僕の13年のCareNeTVでの動画制作の経験の中で、この番組ほど制作に時間がかかったものはありません。 「Dr.金井のCTクイズ 初級編」がリリースされたのは2021年4月ですが、僕が金井先生に最初にこの企画を提案しに行ったのは、メールを遡ると2018年6月です。企画提案から日の目を見るまで3年近くかかっています。 しかも、その時点から「初級編」「中級編」「上級編」を制作することが決まっており、構成も固めていました。しかし、その「上級編」の第1回がリリースされたのが今年の8月(スターウォーズじゃないんだから…)。 その間、コロナパンデミックが起こったなどさまざまな原因があるのですが、一番の問題は、最初ともかく画像データの扱い方がわかっていなかったこと。当時のシステム環境もありますが、大容量DICOMデータのどれがキー画像かわからないし、変換し動画化しようとしてスタックしたりと、作業が一向に進まない。また、アニメーションの女性医師キャラクターを作ってナレーターにしゃべらせたりと、演出も凝りすぎましたね。反省しています。 そんな裏話はさておき、「Dr.金井のCTクイズ 初級編」はリリースから5年を過ぎた今も、多くのCT画像初学者の若い先生方に見られています。今チェックしてみると、今月の視聴ランキングでも多くの新作の中で堂々の第12位! 医学画像クイズのニーズは今も昔不変なのです。
僕は以前ある医学雑誌の編集長をしていました。紙の雑誌の編集長じゃなくなったのは2007年なので18年も前のこと。その雑誌自体ももうないので「昔話」として読んでください。 その雑誌で毎月どの記事がどのくらい読まれたか読者調査をしていました。読者はもちろんすべて医師です。いわばテレビの視聴率調査みたいなものですが、正直あまり良い数字ではありませんでした。 その中で相対的にもっともスコア(と当時呼んでいました)が良かったのが、クイズでした。練りに練った特集記事よりも、尖った企画記事よりも、連載よりもニュースよりもたいていクイズのスコアが一番高かった。 患者背景、主訴、時に検査データとともにX線写真やCT画像、心電図、皮膚所見などを提示し、読者に診断してもらう。奇数ページに一面ドーンと画像などが載っていて、裏の偶数ページに解答と解説がある。クイズといっても極めて医学的で教育的なものでした。 この手法は、インターネット時代になっても人気があるようです。いや、むしろ今はもっともコモンな医学教育の形の1つといえるかもしれません。たとえばNEJMのWebサイトでは、「IMAGE CHALLENGE」というコーナーで日替わりでそんな“クイズ”を掲載しています。先生方はその問題になんとなくチャレンジし、嬉々としてSNSに投稿したりしています。 変わったなあと思うと同時に変わらないなあと思います。 「Dr.金井のCTクイズ」は、つまるところ僕の雑誌時代の人気企画をそのまま動画化した番組です。想定通り視聴者からの評判はよく、CareNeTVの人気番組の1つになりました。 それはそれでよかったのですが、実は、僕の13年のCareNeTVでの動画制作の経験の中で、この番組ほど制作に時間がかかったものはありません。 「Dr.金井のCTクイズ 初級編」がリリースされたのは2021年4月ですが、僕が金井先生に最初にこの企画を提案しに行ったのは、メールを遡ると2018年6月です。企画提案から日の目を見るまで3年近くかかっています。 しかも、その時点から「初級編」「中級編」「上級編」を制作することが決まっており、構成も固めていました。しかし、その「上級編」の第1回がリリースされたのが今年の8月(スターウォーズじゃないんだから…)。 その間、コロナパンデミックが起こったなどさまざまな原因があるのですが、一番の問題は、最初ともかく画像データの扱い方がわかっていなかったこと。当時のシステム環境もありますが、大容量DICOMデータのどれがキー画像かわからないし、変換し動画化しようとしてスタックしたりと、作業が一向に進まない。また、アニメーションの女性医師キャラクターを作ってナレーターにしゃべらせたりと、演出も凝りすぎましたね。反省しています。 そんな裏話はさておき、「Dr.金井のCTクイズ 初級編」はリリースから5年を過ぎた今も、多くのCT画像初学者の若い先生方に見られています。今チェックしてみると、今月の視聴ランキングでも多くの新作の中で堂々の第12位! 医学画像クイズのニーズは今も昔不変なのです。 -
糖尿病(心身症)という病名は『19番目のカルテ』に記載されたのか 2025/08/30
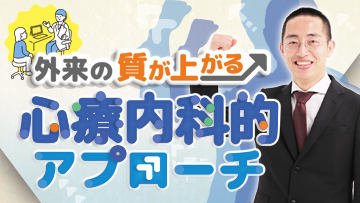 心と身体は密接に結びついていて、心の問題が身体症状として現れることがあり、これを心身症と言います。医師であれば誰でも知っていることですが、実際に、先生方はそのような視点を「常に」意識して日々の診療を行なっているでしょうか?このような問題意識から誕生したCareNeTV番組が「外来の質が上がる 心療内科的アプローチ」です。この視点、もちろん僕が思いついたわけではありません。心身内科に関する番組が何か作れないかと大武陽一先生に相談した際に、総合内科と心療内科の専門医である先生がまさにそのような問題意識を持っていて、企画の切り口として提案を受けたのです。「治療に難渋している身体疾患の患者の中には、心療内科的に診れば治せる患者が実はたくさんいる」と。僕がそのような病気として真っ先に思い浮かべたのは、いわゆる“ストレス胃炎”。正式な病名では胃潰瘍や機能性ディスペプシアでしょうか? あるいは過敏性腸症候群。しかし先生が代表としてまず挙げたのは2型糖尿病でした。(えっ、糖尿病って心身症なの?)糖尿病そのものはもちろん血中のグルコース濃度が慢性的に高くなる身体疾患ですが、心の問題が病状の悪化や治癒の妨げになっているケースが少なくなく、逆にいえば、心療内科的にアプローチすることで、解決できる症例も多いと言うのです。そのような病態を「糖尿病(心身症)」という病名で表すとも教わりました。というわけで、「外来の質が上がる 心療内科的アプローチ」では、一般的にはあまり心身症らしくない糖尿病をいの一番に取り上げています。ところで、今、TBSテレビで放映されている『19番目のカルテ』が話題です。総合診療を真正面から取り上げたドラマで、当の総合診療医の先生方の視聴率は異様に高いのでは?と思うほど、いろいろな先生方がSNSでコメントされています。その第4話(ここからはネタバレを含むので避けたい方は読まないでください)。健康診断で糖尿病が見つかった男性サラリーマン。妻は、食事管理を徹底し、毎回病院にも付き添うなど献身的にサポートしています。しかし半年経っても検査結果は改善しません。妻は自分の努力が数値改善につながらないことにイライラし、「なんで良くならないのよ」と患者である旦那に厳しく当たり、ついには担当医が悪いとクレームを入れます。松本潤扮する主役の総合診療医がこの問題を“解決”するわけですが、その手段は薬物療法などの“治療”ではありません。夫婦関係から生じた患者の気持ち、その気持ちから起こった患者の行動、つまり原因は心の問題であり、それを解きほぐしたのです。あっ、これも糖尿病(心身症)の1症例なのかなと思った次第。さて、カルテに病名はどう記載されたのでしょうか?
心と身体は密接に結びついていて、心の問題が身体症状として現れることがあり、これを心身症と言います。医師であれば誰でも知っていることですが、実際に、先生方はそのような視点を「常に」意識して日々の診療を行なっているでしょうか?このような問題意識から誕生したCareNeTV番組が「外来の質が上がる 心療内科的アプローチ」です。この視点、もちろん僕が思いついたわけではありません。心身内科に関する番組が何か作れないかと大武陽一先生に相談した際に、総合内科と心療内科の専門医である先生がまさにそのような問題意識を持っていて、企画の切り口として提案を受けたのです。「治療に難渋している身体疾患の患者の中には、心療内科的に診れば治せる患者が実はたくさんいる」と。僕がそのような病気として真っ先に思い浮かべたのは、いわゆる“ストレス胃炎”。正式な病名では胃潰瘍や機能性ディスペプシアでしょうか? あるいは過敏性腸症候群。しかし先生が代表としてまず挙げたのは2型糖尿病でした。(えっ、糖尿病って心身症なの?)糖尿病そのものはもちろん血中のグルコース濃度が慢性的に高くなる身体疾患ですが、心の問題が病状の悪化や治癒の妨げになっているケースが少なくなく、逆にいえば、心療内科的にアプローチすることで、解決できる症例も多いと言うのです。そのような病態を「糖尿病(心身症)」という病名で表すとも教わりました。というわけで、「外来の質が上がる 心療内科的アプローチ」では、一般的にはあまり心身症らしくない糖尿病をいの一番に取り上げています。ところで、今、TBSテレビで放映されている『19番目のカルテ』が話題です。総合診療を真正面から取り上げたドラマで、当の総合診療医の先生方の視聴率は異様に高いのでは?と思うほど、いろいろな先生方がSNSでコメントされています。その第4話(ここからはネタバレを含むので避けたい方は読まないでください)。健康診断で糖尿病が見つかった男性サラリーマン。妻は、食事管理を徹底し、毎回病院にも付き添うなど献身的にサポートしています。しかし半年経っても検査結果は改善しません。妻は自分の努力が数値改善につながらないことにイライラし、「なんで良くならないのよ」と患者である旦那に厳しく当たり、ついには担当医が悪いとクレームを入れます。松本潤扮する主役の総合診療医がこの問題を“解決”するわけですが、その手段は薬物療法などの“治療”ではありません。夫婦関係から生じた患者の気持ち、その気持ちから起こった患者の行動、つまり原因は心の問題であり、それを解きほぐしたのです。あっ、これも糖尿病(心身症)の1症例なのかなと思った次第。さて、カルテに病名はどう記載されたのでしょうか? -
統計がカンタンに“ある程度”わかる!を追求したらバーチャルアイドルになった 2025/07/27
 町から本屋さんが消えつつありますが、どんな本屋さんにも必ず棚があるビジネス書の代表といえば「会計」「決算書」ですよね。「会計を理解したい」「決算書をすらすら読めるようになりたい」というのは多くのビジネスパーソンの願望ですが、会計は本格的な学問であり、成書を読んで学習するにはハードルが高い。一般向けの簡単な入門書で大枠だけでもわかりたいというニーズは常に幅広く存在します(僕も4、5冊買いました)。 僕の感覚では、医師にとっての「統計」が、ビジネスパーソンにとっての「会計」に近いのではないかと想像します。もちろん研究を本職としている医師は統計を熟知しています。それは経営を本職とするビジネスパーソンにとっての統計もしかりです。一方、臨床医は必ずしも統計を知らなくても日常臨床はできる一方、それを学びたい、“ある程度”わかるようになりたいと考えている人がかなりいるように思えます。CareNet.comのアクセス状況でもそれを実感できます。CareNet.comでは、手を替え品を替え、医師が統計を学ぶための記事を配信していますが、常に安定的な人気があります。これがCareNeTVで「バーチャルアイドルが教えるやさしい統計学」が生まれたそもそもの発端です。臨床の知識やスキルを提供するCareNeTVとしては異色の番組ですが、それに近しい学びのニーズがあると考えたのです。でも、なんでバーチャルアイドルになったのか?医師に統計を教えるといっても、どんな講師がどんなレベルで教えたらいいのか?僕らとしても“本業”じゃないのでよくわかりません。そこで、先のCareNet.comの記事で医師の閲覧実績からウケがよいものをほぼそのまま動画化することにしたのです。記事は、もともと医師のニーズに合うように企画され、医師にわかりやすいように工夫して書かれています。実際に評価が高かったわけですから、無理に手を加える必要もないだろうと。当該記事の著者の協力の下、記事をナレーション原稿に書き換え、人間の動きをそのまま動くアニメーションにする技術を用いて、バーチャルアイドル講師を誕生させました。アイドルにしたのは、制作会社にすでにそのバーチャルアイドルが“いた”(製作されていた)ので、統計を勉強したい先生は若手が多いだろうから、こんなテイストもアリなんじゃないか?といういささか安易な流れでした。この見慣れない講師を先生方がどう受け止めるのかやや不安だったのですが、蓋を開けると大変好意的で、胸をなで下ろしたのを覚えています。この番組のリリースは2022年2月。当時は上記のような“手づくり”で制作したのですが、3年後の今なら、生成AIを使えばはるかにカンタンにできてしまいますね。見方を変えれば、この番組は来るべきAI時代を先取りしていたのかも?臨床の第一線で活躍する先生方が熱っぽく語る臨場感のある講義がCareNeTVの一番のウリですが、テーマによってバーチャル講師をもっと登場させてもいいのかもしれませんね。
町から本屋さんが消えつつありますが、どんな本屋さんにも必ず棚があるビジネス書の代表といえば「会計」「決算書」ですよね。「会計を理解したい」「決算書をすらすら読めるようになりたい」というのは多くのビジネスパーソンの願望ですが、会計は本格的な学問であり、成書を読んで学習するにはハードルが高い。一般向けの簡単な入門書で大枠だけでもわかりたいというニーズは常に幅広く存在します(僕も4、5冊買いました)。 僕の感覚では、医師にとっての「統計」が、ビジネスパーソンにとっての「会計」に近いのではないかと想像します。もちろん研究を本職としている医師は統計を熟知しています。それは経営を本職とするビジネスパーソンにとっての統計もしかりです。一方、臨床医は必ずしも統計を知らなくても日常臨床はできる一方、それを学びたい、“ある程度”わかるようになりたいと考えている人がかなりいるように思えます。CareNet.comのアクセス状況でもそれを実感できます。CareNet.comでは、手を替え品を替え、医師が統計を学ぶための記事を配信していますが、常に安定的な人気があります。これがCareNeTVで「バーチャルアイドルが教えるやさしい統計学」が生まれたそもそもの発端です。臨床の知識やスキルを提供するCareNeTVとしては異色の番組ですが、それに近しい学びのニーズがあると考えたのです。でも、なんでバーチャルアイドルになったのか?医師に統計を教えるといっても、どんな講師がどんなレベルで教えたらいいのか?僕らとしても“本業”じゃないのでよくわかりません。そこで、先のCareNet.comの記事で医師の閲覧実績からウケがよいものをほぼそのまま動画化することにしたのです。記事は、もともと医師のニーズに合うように企画され、医師にわかりやすいように工夫して書かれています。実際に評価が高かったわけですから、無理に手を加える必要もないだろうと。当該記事の著者の協力の下、記事をナレーション原稿に書き換え、人間の動きをそのまま動くアニメーションにする技術を用いて、バーチャルアイドル講師を誕生させました。アイドルにしたのは、制作会社にすでにそのバーチャルアイドルが“いた”(製作されていた)ので、統計を勉強したい先生は若手が多いだろうから、こんなテイストもアリなんじゃないか?といういささか安易な流れでした。この見慣れない講師を先生方がどう受け止めるのかやや不安だったのですが、蓋を開けると大変好意的で、胸をなで下ろしたのを覚えています。この番組のリリースは2022年2月。当時は上記のような“手づくり”で制作したのですが、3年後の今なら、生成AIを使えばはるかにカンタンにできてしまいますね。見方を変えれば、この番組は来るべきAI時代を先取りしていたのかも?臨床の第一線で活躍する先生方が熱っぽく語る臨場感のある講義がCareNeTVの一番のウリですが、テーマによってバーチャル講師をもっと登場させてもいいのかもしれませんね。 -
精神科医の頭と言葉で学ぶと、いつもの抗不安薬・睡眠薬処方が深くなる 2025/06/22
 子どもの頃、目が腫れて目医者さんに行ったり、歯が痛くなって歯医者さんに行ったりするのは、普段お医者さんに行くのとは少し違う体験でした。幼少期の僕にとって、この3者は違う先生だったのです。後に、普通のお医者さんと目医者さんは医学部を卒業した同じ医師で、歯医者さんは医師とは違う教育を受けた歯科医師という別の資格だと知ることになります。精神科医はもっと違うイメージでした。僕が生まれ育った町には精神病院がありましたが、おそらく多くの人がそうであったように、そこは少し近寄りがたい特殊な場所だと感じていました。精神科医は歯科医のように違う先生だと当然思っていましたが、基本的には同じ医師だと知ったときは驚いた記憶があります。成人してこの仕事をするようになり、実にたくさんの医師の方とお話しする機会を得ましたが、診療科による性格の傾向みたいなものはやはりあると思います。良い悪いとかではなく、その診療科を選択しているのはその先生自身なので、一定の傾向が出るのは当然です。そのような意味合いにおいて、他科の先生と異なる“その診療科らしさ”を感じることが一番多いのは、やはり精神科医かもしれません。身体の疾患を診る先生方とは、基本的な考え方や疾患に対する実際のアプローチの仕方が随分違うなーと思うことがよくあります。形而上的な思考をされるというか…その対極は整形外科医でしょうか?一方で、1人の人間は身体疾患と精神疾患を同時に発症しうるし、各々に対してどのような介入が必要なのかは千差万別です。「非精神科医のための向精神薬の使い方」は、精神科専門医の思考とアプローチを他科の先生方に案内する意図で制作しました。うつ、不眠、不穏、せん妄、認知症など、非精神科医も日々遭遇し対応を迫られる疾患、症状。それらに対して薬をどう使えばいいのかが最も興味があるだろうと考え、向精神薬を軸にしました。しかしあくまで精神医学の視座でエキスパートが本質的な部分から解説しているのが大きな特徴です。そのため、内容はやや専門的な部分もありますが、対症的な使い方から一歩踏み込んで向精神薬を理解し使いこなせるようになるのではないかと自負しています。「基礎医学的知見からのアプローチは、“理解”を伴った処方に必須と思います。実践的且つ科学的なレクチャーをありがとうございます」。番組に対してこんなコメントを寄せてくれた皮膚科の先生がいました。まさに我が意を得たりで、うれしくなりました。この番組は、構成はオーソドックスですが、他の番組とはちょっと違った趣きと味わいがあり、一見の価値ありです。番組のテーマもさることながら、誰が誰に対してどのような視点からどのように語るのか?その大切さを改めて考えさせられた、僕にとっても思い出深い作品です。
子どもの頃、目が腫れて目医者さんに行ったり、歯が痛くなって歯医者さんに行ったりするのは、普段お医者さんに行くのとは少し違う体験でした。幼少期の僕にとって、この3者は違う先生だったのです。後に、普通のお医者さんと目医者さんは医学部を卒業した同じ医師で、歯医者さんは医師とは違う教育を受けた歯科医師という別の資格だと知ることになります。精神科医はもっと違うイメージでした。僕が生まれ育った町には精神病院がありましたが、おそらく多くの人がそうであったように、そこは少し近寄りがたい特殊な場所だと感じていました。精神科医は歯科医のように違う先生だと当然思っていましたが、基本的には同じ医師だと知ったときは驚いた記憶があります。成人してこの仕事をするようになり、実にたくさんの医師の方とお話しする機会を得ましたが、診療科による性格の傾向みたいなものはやはりあると思います。良い悪いとかではなく、その診療科を選択しているのはその先生自身なので、一定の傾向が出るのは当然です。そのような意味合いにおいて、他科の先生と異なる“その診療科らしさ”を感じることが一番多いのは、やはり精神科医かもしれません。身体の疾患を診る先生方とは、基本的な考え方や疾患に対する実際のアプローチの仕方が随分違うなーと思うことがよくあります。形而上的な思考をされるというか…その対極は整形外科医でしょうか?一方で、1人の人間は身体疾患と精神疾患を同時に発症しうるし、各々に対してどのような介入が必要なのかは千差万別です。「非精神科医のための向精神薬の使い方」は、精神科専門医の思考とアプローチを他科の先生方に案内する意図で制作しました。うつ、不眠、不穏、せん妄、認知症など、非精神科医も日々遭遇し対応を迫られる疾患、症状。それらに対して薬をどう使えばいいのかが最も興味があるだろうと考え、向精神薬を軸にしました。しかしあくまで精神医学の視座でエキスパートが本質的な部分から解説しているのが大きな特徴です。そのため、内容はやや専門的な部分もありますが、対症的な使い方から一歩踏み込んで向精神薬を理解し使いこなせるようになるのではないかと自負しています。「基礎医学的知見からのアプローチは、“理解”を伴った処方に必須と思います。実践的且つ科学的なレクチャーをありがとうございます」。番組に対してこんなコメントを寄せてくれた皮膚科の先生がいました。まさに我が意を得たりで、うれしくなりました。この番組は、構成はオーソドックスですが、他の番組とはちょっと違った趣きと味わいがあり、一見の価値ありです。番組のテーマもさることながら、誰が誰に対してどのような視点からどのように語るのか?その大切さを改めて考えさせられた、僕にとっても思い出深い作品です。 -
これだけは知っておけ!?耳鳴を主訴とするAIも知らない良性疾患とその対処法 2025/05/25
 「Dr.藤原のこれだけ耳鼻咽喉科」。2022年8月にリリースしたこの番組は、プライマリケアの現場で出合うことはあっても、内科系の先生方は学ぶ機会がほとんどないであろう耳鼻咽喉科の診療ポイントをまとめています。プライマリケア医として耳鼻咽喉科領域は「これだけ」押さえておけば合格点ではないかというのが企画趣旨で、そうした意味でこの番組名をつけました。比較的頻度が高く、プライマリケアで対応可能な疾患、病態に絞りこんでいるのが一番の特徴です。なので、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など、プライマリケアの先生方にもなじみ深い疾患が多いのですが、その中で意外と知られていないかもしれない病名が1つ出てきます。「これだけ耳鼻咽喉科」の中でもとくに「これだけ」知っておくとよいかもしれません。僕がそう思ったのには理由があります。実は、僕の親族にこんなことがありました。僕が医療関係の仕事をしているということで、たまに知り合いに病院や病気のことを聞かれることがあるのですが、その人が苦しんでいたのが「耳鳴」。彼女は高齢で心臓の手術もしていたので、かかりつけ医に定期的に診てもらっていたのですが、その先生に相談しても原因はわからず、お決まりのメチコバールが処方されただけ。先生がわからないのに僕が聞いても仕方ないじゃない?と思いながら話を聞くと、その耳鳴の症状がバッチリ当てはまったんです。この番組の第2回の「耳鳴をはじめとした耳疾患」で出てくるある疾患に。番組を見た後だったので、すぐに思い至りました。最終的に彼女はやはり心配で総合病院の耳鼻咽喉科を受診したんですが、僕が予想した病名を自分から口にしたら「その通りです」と、先生にとても驚かれたそうです。その病名は、耳管開放症。藤原先生は、番組の中で耳管開放症を耳鳴を主訴とする割とよくある良性疾患として紹介しています。もちろん知っている先生も多いでしょうが、僕の親族の主治医のように知らない先生も結構いるのではないかと思います。この疾患は根本的な治療法はないのですが、番組では藤原先生がその対処法を教えています。これが実に簡単で効果的。僕の親族が病院で指導された内容も基本的に同じで、彼女はそれで治りました。治ったというより、原因がわかって安心して症状が気にならなくなったという感じですが。ともかく問題は解決したのです。試しに、いま流行りの生成AIに「高齢者の耳鳴の主な鑑別疾患を挙げてください」と聞いてみました。すると、突発性難聴、メニエール病など教科書的なものを当然挙げてきますが、耳管開放症という病名は出てきません。この原稿がCareNeTVのサイトに掲載されて、しばらくすると、AIも学習してくれるかなー?
「Dr.藤原のこれだけ耳鼻咽喉科」。2022年8月にリリースしたこの番組は、プライマリケアの現場で出合うことはあっても、内科系の先生方は学ぶ機会がほとんどないであろう耳鼻咽喉科の診療ポイントをまとめています。プライマリケア医として耳鼻咽喉科領域は「これだけ」押さえておけば合格点ではないかというのが企画趣旨で、そうした意味でこの番組名をつけました。比較的頻度が高く、プライマリケアで対応可能な疾患、病態に絞りこんでいるのが一番の特徴です。なので、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など、プライマリケアの先生方にもなじみ深い疾患が多いのですが、その中で意外と知られていないかもしれない病名が1つ出てきます。「これだけ耳鼻咽喉科」の中でもとくに「これだけ」知っておくとよいかもしれません。僕がそう思ったのには理由があります。実は、僕の親族にこんなことがありました。僕が医療関係の仕事をしているということで、たまに知り合いに病院や病気のことを聞かれることがあるのですが、その人が苦しんでいたのが「耳鳴」。彼女は高齢で心臓の手術もしていたので、かかりつけ医に定期的に診てもらっていたのですが、その先生に相談しても原因はわからず、お決まりのメチコバールが処方されただけ。先生がわからないのに僕が聞いても仕方ないじゃない?と思いながら話を聞くと、その耳鳴の症状がバッチリ当てはまったんです。この番組の第2回の「耳鳴をはじめとした耳疾患」で出てくるある疾患に。番組を見た後だったので、すぐに思い至りました。最終的に彼女はやはり心配で総合病院の耳鼻咽喉科を受診したんですが、僕が予想した病名を自分から口にしたら「その通りです」と、先生にとても驚かれたそうです。その病名は、耳管開放症。藤原先生は、番組の中で耳管開放症を耳鳴を主訴とする割とよくある良性疾患として紹介しています。もちろん知っている先生も多いでしょうが、僕の親族の主治医のように知らない先生も結構いるのではないかと思います。この疾患は根本的な治療法はないのですが、番組では藤原先生がその対処法を教えています。これが実に簡単で効果的。僕の親族が病院で指導された内容も基本的に同じで、彼女はそれで治りました。治ったというより、原因がわかって安心して症状が気にならなくなったという感じですが。ともかく問題は解決したのです。試しに、いま流行りの生成AIに「高齢者の耳鳴の主な鑑別疾患を挙げてください」と聞いてみました。すると、突発性難聴、メニエール病など教科書的なものを当然挙げてきますが、耳管開放症という病名は出てきません。この原稿がCareNeTVのサイトに掲載されて、しばらくすると、AIも学習してくれるかなー? -
あの2人が帰ってきた!気楽で愉快な内科勉強法にあなたもきっとハマる 2025/04/27
 今年もあの2人が帰ってきた!「えっ、どの2人?」という声が聞こえそうですが、僕にとって「あの2人」といえば、高槻病院の筒泉貴彦先生とマウントサイナイ医科大学の山田悠史先生しかいません。かつて東京の病院で同僚として共に働き、大阪とニューヨークにそれぞれ拠点を移した後も親交を続け、さまざまな臨床医学教育のアウトプットを生み出し続ける名コンビです。その代表作が医学書院から発行されている「THE内科専門医問題集」。ケアネットでは医学書院とのコラボレーションで、この書籍をベースとした「THE内科専門医問題集“見るラヂオ”」を配信しています。「THE内科専門医問題集“見るラヂオ”」の誕生は4年前。日本内科学会の専門医試験実施時期に合わせ、毎週日曜日に全10回。休みの朝にラジオを聴き流すように内科の勉強をしてみませんか?というライフスタイル提案も込めて始めました。最近ケアネットの配信で定番になりつつある“見るラヂオ”スタイルとでもいうべき収録方法もこの番組がきっかけでしたね。山田先生はニューヨークにお住まいなので当然オンライン収録。ラジオのように軽やかなトークを聴きながら、キースライドはちゃんと「見られる」を基本コンセプトとしました。番組では、内科の各領域で「THE内科専門医問題集」から毎週2問出題。問題の解説をしたうえで関連する臨床のTipsを紹介していくのですが、上記のコンセプトから、僕は当初からお2人に番組の冒頭と終わりの“雑談“をお願いしました。これが見事にハマっていて、勉強になるだけでなく、バラエティ番組での芸人のフリートークのように聴いていて楽しいのです。僕はCareNeTVの番組収録によく立ち会いますが、スタジオでの収録はスライドを確認しながら講義におかしなところがないか集中して聴いていなければならないので、それなりに神経を使います。しかし「“見るラヂオ”」はZoom収録で僕自身も自宅にいますし、休みにくつろぎながらただ2人のトークを楽しんでいる感じです。今シーズンのライブ配信は、実は来週5月4日の日曜日が最終回。でも残念がる必要はありません。CareNeTVでアーカイブをいつでも見られます。腰を据えて勉強するというより、ソファでくつろぎながら、あるいは料理や掃除をしながら聴き流し、気になる箇所は画面でスライドをチェックする。そんな学び方がいいのではないかと思います。未体験の方はぜひ。内科専門医試験を受ける人はもちろん、そうでない人も臨床に役立ちますし、何より楽しい!愉快な2人のベタなトークにきっとハマりますよ。
今年もあの2人が帰ってきた!「えっ、どの2人?」という声が聞こえそうですが、僕にとって「あの2人」といえば、高槻病院の筒泉貴彦先生とマウントサイナイ医科大学の山田悠史先生しかいません。かつて東京の病院で同僚として共に働き、大阪とニューヨークにそれぞれ拠点を移した後も親交を続け、さまざまな臨床医学教育のアウトプットを生み出し続ける名コンビです。その代表作が医学書院から発行されている「THE内科専門医問題集」。ケアネットでは医学書院とのコラボレーションで、この書籍をベースとした「THE内科専門医問題集“見るラヂオ”」を配信しています。「THE内科専門医問題集“見るラヂオ”」の誕生は4年前。日本内科学会の専門医試験実施時期に合わせ、毎週日曜日に全10回。休みの朝にラジオを聴き流すように内科の勉強をしてみませんか?というライフスタイル提案も込めて始めました。最近ケアネットの配信で定番になりつつある“見るラヂオ”スタイルとでもいうべき収録方法もこの番組がきっかけでしたね。山田先生はニューヨークにお住まいなので当然オンライン収録。ラジオのように軽やかなトークを聴きながら、キースライドはちゃんと「見られる」を基本コンセプトとしました。番組では、内科の各領域で「THE内科専門医問題集」から毎週2問出題。問題の解説をしたうえで関連する臨床のTipsを紹介していくのですが、上記のコンセプトから、僕は当初からお2人に番組の冒頭と終わりの“雑談“をお願いしました。これが見事にハマっていて、勉強になるだけでなく、バラエティ番組での芸人のフリートークのように聴いていて楽しいのです。僕はCareNeTVの番組収録によく立ち会いますが、スタジオでの収録はスライドを確認しながら講義におかしなところがないか集中して聴いていなければならないので、それなりに神経を使います。しかし「“見るラヂオ”」はZoom収録で僕自身も自宅にいますし、休みにくつろぎながらただ2人のトークを楽しんでいる感じです。今シーズンのライブ配信は、実は来週5月4日の日曜日が最終回。でも残念がる必要はありません。CareNeTVでアーカイブをいつでも見られます。腰を据えて勉強するというより、ソファでくつろぎながら、あるいは料理や掃除をしながら聴き流し、気になる箇所は画面でスライドをチェックする。そんな学び方がいいのではないかと思います。未体験の方はぜひ。内科専門医試験を受ける人はもちろん、そうでない人も臨床に役立ちますし、何より楽しい!愉快な2人のベタなトークにきっとハマりますよ。 -
臨床研修。医師人生で1度きりの2年間に何を経験すべきか?麻酔科医スーさんの至言 2025/03/30
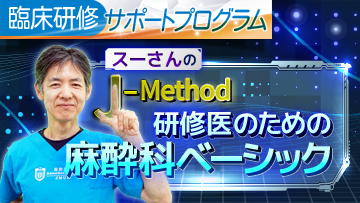 CareNeTVでは、昨年から研修医に特化した「臨床研修サポートプログラム」を配信しています。研修期間に研修医に何をどのレベルで教育しているかは、臨床研修病院によって、また担当する指導医によってもかなり異なります。良い悪いは別にして、そのような実態があることはよく知られています。「臨床研修サポートプログラム」は、そのような実情を踏まえて、臨床研修のローテート必修科目について、研修医が2年間に身につけるべき必要十分な知識とスキルをコンパクトな動画パッケージにしました。現場での研修の予習復習に使え、また現場で結果的に触れる機会がなかったテーマについては動画で補足でき、当該診療科で研修医必達レベルを示すことを目指しています。この4月から研修医になるbrand-newな先生方にはぜひ活用してほしいシリーズですが、中でも思い入れがあるが「研修医のための麻酔科ベーシック」です。というのは、そもそも僕がこの企画を考えたきっかけの1つが、この番組の講師である鈴木昭広先生との会話だったからです。鈴木先生は「スーさんの急変エコー裏ワザ小ワザ」制作以来、CareNeTVスクールでも毎年講師をお願いするなど、長年協力いただき、親しくさせていただいています。そのような意味で、鈴木先生は僕にとって「エコーの先生」だったのですが、本来は麻酔科医です。あるとき、先生に「ケアネットで麻酔科の番組作りませんか?」と提案を受けました。最初、僕は正直ピンと来ませんでした。麻酔科は麻酔科を専攻するごく一部の医師が勉強することであり、CareNeTVの主たる視聴者である一般の臨床医がなぜ麻酔科を勉強する必要があるのか理解できなかったからです。しかし、先生と話していて、先生が何をしたいのか?なぜ麻酔科を非麻酔科医が学ぶ必要があるのか?わかってきました。鈴木先生が言っていたことはだいたいこんなことです(記憶だけで書いているので正確ではありません)。「ほとんどの医師は麻酔科医にならないし、麻酔に関心もない。ただ、どんな医師も全身麻酔がかかったようなクリティカルな状況を臨床で山ほど経験する。だから、安全が確保された環境でその状態を経験できる麻酔科の初期研修は貴重なんです。ほとんどの医師は臨床研修が終わったら麻酔科を経験できる機会はない。私は、初期研修医にこの先50年臨床医として生きていくために必要な“麻酔に関する最小限”のことを教えているつもりです」「研修医のための麻酔科ベーシック」は鈴木先生の言葉がそのまま体現されています。そして「臨床研修サポートプログラム」は、この鈴木先生の研修医指導に対する考え方を他の診療科に敷衍したものです。麻酔科は必修科目のなかでは特殊ですが、他科でも似た側面はあるはずだと考えたのです。臨床研修の2年間は、いわば一人前の医師になるための助走期間ですが、その期間にしかできないことがある。二度とないこの限られた時間を自分のこれからの長い医師人生に最大限活用しなければもったいない。「臨床研修サポートプログラム」がその気づきにつながれば本望です。
CareNeTVでは、昨年から研修医に特化した「臨床研修サポートプログラム」を配信しています。研修期間に研修医に何をどのレベルで教育しているかは、臨床研修病院によって、また担当する指導医によってもかなり異なります。良い悪いは別にして、そのような実態があることはよく知られています。「臨床研修サポートプログラム」は、そのような実情を踏まえて、臨床研修のローテート必修科目について、研修医が2年間に身につけるべき必要十分な知識とスキルをコンパクトな動画パッケージにしました。現場での研修の予習復習に使え、また現場で結果的に触れる機会がなかったテーマについては動画で補足でき、当該診療科で研修医必達レベルを示すことを目指しています。この4月から研修医になるbrand-newな先生方にはぜひ活用してほしいシリーズですが、中でも思い入れがあるが「研修医のための麻酔科ベーシック」です。というのは、そもそも僕がこの企画を考えたきっかけの1つが、この番組の講師である鈴木昭広先生との会話だったからです。鈴木先生は「スーさんの急変エコー裏ワザ小ワザ」制作以来、CareNeTVスクールでも毎年講師をお願いするなど、長年協力いただき、親しくさせていただいています。そのような意味で、鈴木先生は僕にとって「エコーの先生」だったのですが、本来は麻酔科医です。あるとき、先生に「ケアネットで麻酔科の番組作りませんか?」と提案を受けました。最初、僕は正直ピンと来ませんでした。麻酔科は麻酔科を専攻するごく一部の医師が勉強することであり、CareNeTVの主たる視聴者である一般の臨床医がなぜ麻酔科を勉強する必要があるのか理解できなかったからです。しかし、先生と話していて、先生が何をしたいのか?なぜ麻酔科を非麻酔科医が学ぶ必要があるのか?わかってきました。鈴木先生が言っていたことはだいたいこんなことです(記憶だけで書いているので正確ではありません)。「ほとんどの医師は麻酔科医にならないし、麻酔に関心もない。ただ、どんな医師も全身麻酔がかかったようなクリティカルな状況を臨床で山ほど経験する。だから、安全が確保された環境でその状態を経験できる麻酔科の初期研修は貴重なんです。ほとんどの医師は臨床研修が終わったら麻酔科を経験できる機会はない。私は、初期研修医にこの先50年臨床医として生きていくために必要な“麻酔に関する最小限”のことを教えているつもりです」「研修医のための麻酔科ベーシック」は鈴木先生の言葉がそのまま体現されています。そして「臨床研修サポートプログラム」は、この鈴木先生の研修医指導に対する考え方を他の診療科に敷衍したものです。麻酔科は必修科目のなかでは特殊ですが、他科でも似た側面はあるはずだと考えたのです。臨床研修の2年間は、いわば一人前の医師になるための助走期間ですが、その期間にしかできないことがある。二度とないこの限られた時間を自分のこれからの長い医師人生に最大限活用しなければもったいない。「臨床研修サポートプログラム」がその気づきにつながれば本望です。 -
簡単に身につく肺音聴取のコツ!ハイテク時代だからこそ見逃せない2つの効用 2025/02/23
 「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」株式会社ケアネットが新しいパーパスを発表しました。ケアネットのコーポレートサイトでは、医師を支える「知」と「情熱」と「行動力」の赤い三従士の雄姿をご覧いただけます。ただし、今日この場で書きたいのはこのパーパスの話ではありません。支えられている医師が手に持っているもの。そう、聴診器の話です。テレビやネット広告などで医師のイメージ写真を見ることがあると思いますが、白衣を着たモデルを医師にするために僕らは聴診器を持たせます。白衣だけでは薬剤師や化学者と区別がつかない。聴診器を持つ、または首からかけるとその人は医師になります。そういう“お約束”です。しかし、医師のシンボルとしては現役の聴診器ですが、実臨床では(循環器科医と呼吸器科医は別にして)徐々に使われなくなっています。もともと体表から体の内部の音を聞き、体内で何が起こっているかイメージするという原始的なメカニズムで成り立っている聴診器。X線、エコー、CTといった画像診断機器が普及すれば、百聞は一見に如かず、画像で病変を見ればいいじゃんとなるのは当然の流れです。それでもなお、聴診の有用性はあります。軽くてどこにも持ち運べ手軽ですぐ使える。非侵襲で患者の負担はゼロ。電力も必要ない。そういった意味ではSDGsが叫ばれる現代に合ったエコな診断ツールといえるかもしれません。「Dr.皿谷の肺音聴取道場」は、肺音に特化し、呼吸器専門医の皿谷健先生がそのさまざまな聴取方法の極意を指南する番組です。たとえば、やぎ音。患者の胸に聴診器を当て、「いー」と発声してもらいます。肺炎があるとその場所は音の伝導がよくなり、「いー」が「えー」と聞こえる現象で、肺炎を示唆する所見です。ヤギの鳴き声のように音が変化するためそう呼ばれます。非常に簡単な手技で音の違いもはっきりわかります。書籍では実際の音を聞くことはできませんが、そこは動画のCareNeTV。音を繰り返し聞くことができるので確実に身につけることができます。ほかにも喘息や肺がんの肺音、肺炎の種類による肺音の違いなど一般的に習得すべき肺音聴取のテクニックをほぼ網羅しています。実臨床では、最終的には画像で診断し治療方針を決めることになるとは思いますが、音で病態をイメージできれば診療の質は確実に向上します。また、患者さんの胸に聴診器を当てることは患者に安心感を与える“効果”があるともいわれます。検査機器の高度化などで医師が直接患者の身体に触れる機会が少なくなるなか、診療に対する患者の満足度という面でも聴診器は貢献するかもしれません。最近、聴診器をあまり使ってないなーという先生方、「肺音聴取道場」にちょっと入門して、医師のシンボルを実臨床にもっと活用してみてはいかがでしょうか。
「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」株式会社ケアネットが新しいパーパスを発表しました。ケアネットのコーポレートサイトでは、医師を支える「知」と「情熱」と「行動力」の赤い三従士の雄姿をご覧いただけます。ただし、今日この場で書きたいのはこのパーパスの話ではありません。支えられている医師が手に持っているもの。そう、聴診器の話です。テレビやネット広告などで医師のイメージ写真を見ることがあると思いますが、白衣を着たモデルを医師にするために僕らは聴診器を持たせます。白衣だけでは薬剤師や化学者と区別がつかない。聴診器を持つ、または首からかけるとその人は医師になります。そういう“お約束”です。しかし、医師のシンボルとしては現役の聴診器ですが、実臨床では(循環器科医と呼吸器科医は別にして)徐々に使われなくなっています。もともと体表から体の内部の音を聞き、体内で何が起こっているかイメージするという原始的なメカニズムで成り立っている聴診器。X線、エコー、CTといった画像診断機器が普及すれば、百聞は一見に如かず、画像で病変を見ればいいじゃんとなるのは当然の流れです。それでもなお、聴診の有用性はあります。軽くてどこにも持ち運べ手軽ですぐ使える。非侵襲で患者の負担はゼロ。電力も必要ない。そういった意味ではSDGsが叫ばれる現代に合ったエコな診断ツールといえるかもしれません。「Dr.皿谷の肺音聴取道場」は、肺音に特化し、呼吸器専門医の皿谷健先生がそのさまざまな聴取方法の極意を指南する番組です。たとえば、やぎ音。患者の胸に聴診器を当て、「いー」と発声してもらいます。肺炎があるとその場所は音の伝導がよくなり、「いー」が「えー」と聞こえる現象で、肺炎を示唆する所見です。ヤギの鳴き声のように音が変化するためそう呼ばれます。非常に簡単な手技で音の違いもはっきりわかります。書籍では実際の音を聞くことはできませんが、そこは動画のCareNeTV。音を繰り返し聞くことができるので確実に身につけることができます。ほかにも喘息や肺がんの肺音、肺炎の種類による肺音の違いなど一般的に習得すべき肺音聴取のテクニックをほぼ網羅しています。実臨床では、最終的には画像で診断し治療方針を決めることになるとは思いますが、音で病態をイメージできれば診療の質は確実に向上します。また、患者さんの胸に聴診器を当てることは患者に安心感を与える“効果”があるともいわれます。検査機器の高度化などで医師が直接患者の身体に触れる機会が少なくなるなか、診療に対する患者の満足度という面でも聴診器は貢献するかもしれません。最近、聴診器をあまり使ってないなーという先生方、「肺音聴取道場」にちょっと入門して、医師のシンボルを実臨床にもっと活用してみてはいかがでしょうか。 -
整形外科の王道にして内科的「藤井チャート」なら確かにわかる! 2025/01/26
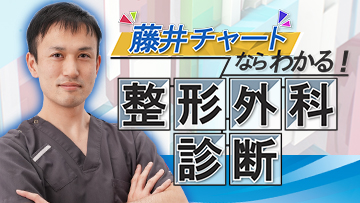 肩の痛み、腰の痛み、膝の痛み…中高年の多くの方が抱えている悩みであり、内科疾患でかかっている患者さんからもそうした訴えを聞くことはよくあるでしょう。 あまりに日常的すぎて決定的な解決策もなく、内科医としては湿布を出すくらいしかできない。そう思い込んでいないでしょうか。 確かに、そうした面は否定できません。しかし、患者の主訴から鑑別診断を挙げ、所見を取り、必要な検査を行い、可能性が低い疾患を除外して診断を絞り込んでいく。整形外科疾患にもそういう王道のアプローチが当然あります。 「藤井チャートならわかる!整形外科診断」は、まさにそこにフォーカスした番組です。 肩痛、腰痛、膝痛などを「ある程度の年になったら仕方ない」で済まさず、偏見を排して白紙から診断して治療につなげるプロセスをロジカルに展開します。整形外科ど真ん中のコンテンツですが、そのアプローチは極めて“内科的“で、コアなCareNeTV視聴者に高い評価をいただいています。 たとえば、膝痛。高齢女性に頻発する症状ですが、どうアプローチしていくか?まず初めに①外傷かどうか②関節液貯留はあるか③疼痛部位はどこか、の3点を考えます。関節液は、色が黄色・透明なら変形性膝関節症、黄色・混濁なら感染、炎症、血腫が引けたら靭帯損傷、骨折が原因と考えられます。 高齢者によく見られる変形性膝関節症は、鵞足炎との鑑別が重要です。ヒアルロン酸注射が適応になるか否かなど、治療法が異なるからです。いずれも歩行時痛が主訴となることが多いですが、疼痛部位が異なり、変形性膝関節症は内側関節裂隙、鵞足炎は脛骨近位内側(鵞足部)です。それぞれの身体所見の取り方、評価の仕方も実技でわかりやすく解説しています。 なお、変形性膝関節症では、関節液はある場合もない場合もあります。 番組では、こうした症状を起点とした、身体所見、検査、鑑別、治療というオーソドックスな診療の流れを、頸部、肩、肘、手関節、腰、鼠径部、膝、足関節と上から下へ指南していきます。あくまで体系的かつ論理的に、わかりやすく。 王道ゆえに派手さはないかもしれませんが、内科系のプライマリケア医、専門医に、整形外科の視座から診療に確かな深み与えてくれる。そんな良質な作品だと思います。
肩の痛み、腰の痛み、膝の痛み…中高年の多くの方が抱えている悩みであり、内科疾患でかかっている患者さんからもそうした訴えを聞くことはよくあるでしょう。 あまりに日常的すぎて決定的な解決策もなく、内科医としては湿布を出すくらいしかできない。そう思い込んでいないでしょうか。 確かに、そうした面は否定できません。しかし、患者の主訴から鑑別診断を挙げ、所見を取り、必要な検査を行い、可能性が低い疾患を除外して診断を絞り込んでいく。整形外科疾患にもそういう王道のアプローチが当然あります。 「藤井チャートならわかる!整形外科診断」は、まさにそこにフォーカスした番組です。 肩痛、腰痛、膝痛などを「ある程度の年になったら仕方ない」で済まさず、偏見を排して白紙から診断して治療につなげるプロセスをロジカルに展開します。整形外科ど真ん中のコンテンツですが、そのアプローチは極めて“内科的“で、コアなCareNeTV視聴者に高い評価をいただいています。 たとえば、膝痛。高齢女性に頻発する症状ですが、どうアプローチしていくか?まず初めに①外傷かどうか②関節液貯留はあるか③疼痛部位はどこか、の3点を考えます。関節液は、色が黄色・透明なら変形性膝関節症、黄色・混濁なら感染、炎症、血腫が引けたら靭帯損傷、骨折が原因と考えられます。 高齢者によく見られる変形性膝関節症は、鵞足炎との鑑別が重要です。ヒアルロン酸注射が適応になるか否かなど、治療法が異なるからです。いずれも歩行時痛が主訴となることが多いですが、疼痛部位が異なり、変形性膝関節症は内側関節裂隙、鵞足炎は脛骨近位内側(鵞足部)です。それぞれの身体所見の取り方、評価の仕方も実技でわかりやすく解説しています。 なお、変形性膝関節症では、関節液はある場合もない場合もあります。 番組では、こうした症状を起点とした、身体所見、検査、鑑別、治療というオーソドックスな診療の流れを、頸部、肩、肘、手関節、腰、鼠径部、膝、足関節と上から下へ指南していきます。あくまで体系的かつ論理的に、わかりやすく。 王道ゆえに派手さはないかもしれませんが、内科系のプライマリケア医、専門医に、整形外科の視座から診療に確かな深み与えてくれる。そんな良質な作品だと思います。 -
骨粗鬆症、見つけて骨折を防ぐのは内科医の役目 2024CareNeTV MVV 2024/12/06
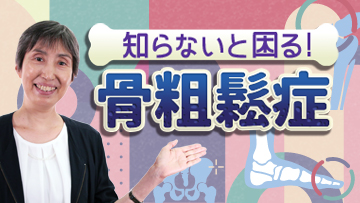 年の瀬が近づいてきました。この連載では、主に過去の番組を収録当時のエピソードや制作秘話などを交えて作り手の視点でご紹介していますが、今回は初の試みとして、今年1年で一番僕の印象に残った番組を取り上げます。 編集長が選ぶCareNeTVの2024年のMVPならぬMVV(Most Valuable Video)です。 その作品は、東京都健康長寿医療センターの千葉優子先生による「知らないと困る!骨粗鬆症」です。 視聴数がもっと多い、華があって目立つ番組はほかにもいくつかあるのですが、僕がこの番組を選んだ理由は、誰でも知っている骨粗鬆症という平凡な疾患を取り上げた「地味な番組」にもかかわらず、視聴者から高い評価を得られている点です。 その最大の理由は、この記事のタイトルに書いたキャッチコピーにあると僕は考えています。 骨粗鬆症とはどういう疾患でしょうか? 痛みがあるわけでなく、放置してもそれ自体で患者が苦しむことはありません。しかし、骨が脆くなると転倒時の骨折リスクが格段に高まり、高齢者がひとたび骨折するとそのまま寝たきりになることが多々あります。 とくに症状があるわけではないので、患者の訴えから見つかることはまずありません。一方で、高齢になれば、一般的に骨密度が低下することは一般人でも知っています。つまり、検査さえすれば、骨粗鬆症はかなりの確率で発見できるのです。 この考えてみれば当たり前の事実、つまり骨粗鬆症を見つけて対応すれば高齢者が寝たきりになるリスクを低減でき、それを見つけ出すのは(骨折になってから治療をする整形外科医よりむしろ)普段から患者を診ているかかりつけの内科の役目なのだ、というメッセージをしっかり伝えられていることが、この番組の最大の価値だと僕は思っています。 内科医がそのような意識を持って骨粗鬆症を見つけようとするならば、骨粗鬆症の病態や診断方法・基準、治療法などを一通り知っている必要があります。先生にはあくまでその観点から必要十分な情報を整理してもらって います。 どのようなコンテンツでも、一番大事なのは取り上げるテーマそのものですが、その次は「切り口」です。どのよう角度からそのテーマを料理するか?そこで作品としての優劣がほぼ決まります。その「切り口」は、誰もが聞いた瞬間に感心するような鮮やかなものがもちろん理想ですが、時に言われなければ気づかないようなちょっとした差異でも大きな効果を生むことかあります。そこがコンテンツづくりの面白いところです。 ところで、CareNeTVでは好きな番組を単品で購入できるPPV(Pay Per View)を大幅値引きで提供する年末キャンペーンを開催中です。「知らないと困る!骨粗鬆症」を含め、僕が今年この連載で紹介してきた作品と「ケアネットまつり」のプログラムなど普段PPVで販売していないコンテンツもご覧いただけるので、チェックしてみてください。 ※「CareNeTV 編集長のオススメ番組 MAX70%OFF」キャンペーンは2024年12月25日で終了しました
年の瀬が近づいてきました。この連載では、主に過去の番組を収録当時のエピソードや制作秘話などを交えて作り手の視点でご紹介していますが、今回は初の試みとして、今年1年で一番僕の印象に残った番組を取り上げます。 編集長が選ぶCareNeTVの2024年のMVPならぬMVV(Most Valuable Video)です。 その作品は、東京都健康長寿医療センターの千葉優子先生による「知らないと困る!骨粗鬆症」です。 視聴数がもっと多い、華があって目立つ番組はほかにもいくつかあるのですが、僕がこの番組を選んだ理由は、誰でも知っている骨粗鬆症という平凡な疾患を取り上げた「地味な番組」にもかかわらず、視聴者から高い評価を得られている点です。 その最大の理由は、この記事のタイトルに書いたキャッチコピーにあると僕は考えています。 骨粗鬆症とはどういう疾患でしょうか? 痛みがあるわけでなく、放置してもそれ自体で患者が苦しむことはありません。しかし、骨が脆くなると転倒時の骨折リスクが格段に高まり、高齢者がひとたび骨折するとそのまま寝たきりになることが多々あります。 とくに症状があるわけではないので、患者の訴えから見つかることはまずありません。一方で、高齢になれば、一般的に骨密度が低下することは一般人でも知っています。つまり、検査さえすれば、骨粗鬆症はかなりの確率で発見できるのです。 この考えてみれば当たり前の事実、つまり骨粗鬆症を見つけて対応すれば高齢者が寝たきりになるリスクを低減でき、それを見つけ出すのは(骨折になってから治療をする整形外科医よりむしろ)普段から患者を診ているかかりつけの内科の役目なのだ、というメッセージをしっかり伝えられていることが、この番組の最大の価値だと僕は思っています。 内科医がそのような意識を持って骨粗鬆症を見つけようとするならば、骨粗鬆症の病態や診断方法・基準、治療法などを一通り知っている必要があります。先生にはあくまでその観点から必要十分な情報を整理してもらって います。 どのようなコンテンツでも、一番大事なのは取り上げるテーマそのものですが、その次は「切り口」です。どのよう角度からそのテーマを料理するか?そこで作品としての優劣がほぼ決まります。その「切り口」は、誰もが聞いた瞬間に感心するような鮮やかなものがもちろん理想ですが、時に言われなければ気づかないようなちょっとした差異でも大きな効果を生むことかあります。そこがコンテンツづくりの面白いところです。 ところで、CareNeTVでは好きな番組を単品で購入できるPPV(Pay Per View)を大幅値引きで提供する年末キャンペーンを開催中です。「知らないと困る!骨粗鬆症」を含め、僕が今年この連載で紹介してきた作品と「ケアネットまつり」のプログラムなど普段PPVで販売していないコンテンツもご覧いただけるので、チェックしてみてください。 ※「CareNeTV 編集長のオススメ番組 MAX70%OFF」キャンペーンは2024年12月25日で終了しました -
循環器から皮膚科まで「5分で専門医が言い切る」価値に気づいてほしい 2024/11/24
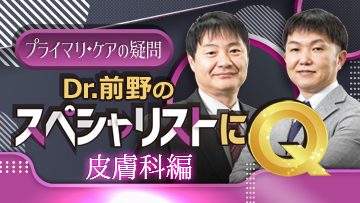 動画コンテンツを制作する際に、どのようなタイトルをつけるかはとても重要です。とくにネットにあふれる「手軽な動画」の場合、タイトルやバナーなどのビジュアルを目にした一瞬で興味を持たれなければ、観られることはありません。本体の動画コンテンツがどんなに良いものであったとしても、タイトルで惹きつけてクリックさせなければ、評価の対象にすらならずネット空間に埋もれていきます。もちろん例外はありますが、言わんとすることは理解いただけるでしょう。だから僕らはタイトルづけには腐心します。考えて考えて考え抜きます。それが出演いただいている講師への最大の敬意であるし、潜在的な視聴者に対する(その動画の価値を伝えるという)大切な情報提供だからです。「プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ」このタイトルはどうでしょうか?まあ悪くないと思います。しかし、初めて見たすべての人が見た瞬間にその内容を想起できるでしょうか?「Qって何?」と思う人もいるかもしれませんね。他人事のように書いているのは、このタイトルは僕がつけたわけではないからです。プライマリケア医の立場から前野哲博先生が各科のスペシャリストに疑問をぶつけて答えてもらう形式の番組で、循環器編、神経内科編というように、僕がケアネットに入社する前から長期にわたって続いているシリーズです。「あなたの悩みを5分で解決!一問一答Q&A番組」「はっきり!スッキリ!あなたのすべきことがわかる一問一答Q&A番組」「5分で専門医が言い切る!プライマリ・ケアのベストチョイス」これらは「スペシャリストにQ」のキャッチコピーの変遷です。キャッチコピーとは、商品や作品の魅力を伝えるために人の注意を引く宣伝文句のこと。タイトルを補完するものとしてネット空間ではタイトルと同じくらい重要になります。3つの中でどのコピーが一番いいかは一概には言えませんが、僕はもっとも新しい「5分で専門医が言い切る!」が気に入っています。実は、この「言い切る」という言い回しは、前野先生が収録現場でよく相手のスペシャリストの先生に言っている言葉でもあります。「専門家の間では議論があるところでも、あいまいにせずに、ズバっと言い切ってほしいんです。そうしないと僕ら(プライマリケア医)はどっちがいいのか、どうしたらいいのかわからないので」ガイドラインに書いてある内容をそのまま話すのではなく、臨床現場でその先生は実際どうしているのか?プライマリケア医にはどこまでやってほしいのか?そこをクリアにする。そのポイントを端的に話す。それこそが、この番組の最大の特徴であり、「5分で専門医が言い切る!」はその特徴をかなり表現できているコピーだと自負しています。先生方は、そんなややこしいことを考えず直感的にCareNeTVの番組を選んでご覧いただいていると思いますし、それでよいのですが、たまにはそんな視点でタイトルやキャッチコピーを見返してみると、そのコンテンツから学べる「最大の価値」(と作り手が考えているもの)が何なのか気づくかもしれません。
動画コンテンツを制作する際に、どのようなタイトルをつけるかはとても重要です。とくにネットにあふれる「手軽な動画」の場合、タイトルやバナーなどのビジュアルを目にした一瞬で興味を持たれなければ、観られることはありません。本体の動画コンテンツがどんなに良いものであったとしても、タイトルで惹きつけてクリックさせなければ、評価の対象にすらならずネット空間に埋もれていきます。もちろん例外はありますが、言わんとすることは理解いただけるでしょう。だから僕らはタイトルづけには腐心します。考えて考えて考え抜きます。それが出演いただいている講師への最大の敬意であるし、潜在的な視聴者に対する(その動画の価値を伝えるという)大切な情報提供だからです。「プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ」このタイトルはどうでしょうか?まあ悪くないと思います。しかし、初めて見たすべての人が見た瞬間にその内容を想起できるでしょうか?「Qって何?」と思う人もいるかもしれませんね。他人事のように書いているのは、このタイトルは僕がつけたわけではないからです。プライマリケア医の立場から前野哲博先生が各科のスペシャリストに疑問をぶつけて答えてもらう形式の番組で、循環器編、神経内科編というように、僕がケアネットに入社する前から長期にわたって続いているシリーズです。「あなたの悩みを5分で解決!一問一答Q&A番組」「はっきり!スッキリ!あなたのすべきことがわかる一問一答Q&A番組」「5分で専門医が言い切る!プライマリ・ケアのベストチョイス」これらは「スペシャリストにQ」のキャッチコピーの変遷です。キャッチコピーとは、商品や作品の魅力を伝えるために人の注意を引く宣伝文句のこと。タイトルを補完するものとしてネット空間ではタイトルと同じくらい重要になります。3つの中でどのコピーが一番いいかは一概には言えませんが、僕はもっとも新しい「5分で専門医が言い切る!」が気に入っています。実は、この「言い切る」という言い回しは、前野先生が収録現場でよく相手のスペシャリストの先生に言っている言葉でもあります。「専門家の間では議論があるところでも、あいまいにせずに、ズバっと言い切ってほしいんです。そうしないと僕ら(プライマリケア医)はどっちがいいのか、どうしたらいいのかわからないので」ガイドラインに書いてある内容をそのまま話すのではなく、臨床現場でその先生は実際どうしているのか?プライマリケア医にはどこまでやってほしいのか?そこをクリアにする。そのポイントを端的に話す。それこそが、この番組の最大の特徴であり、「5分で専門医が言い切る!」はその特徴をかなり表現できているコピーだと自負しています。先生方は、そんなややこしいことを考えず直感的にCareNeTVの番組を選んでご覧いただいていると思いますし、それでよいのですが、たまにはそんな視点でタイトルやキャッチコピーを見返してみると、そのコンテンツから学べる「最大の価値」(と作り手が考えているもの)が何なのか気づくかもしれません。 -
皮疹の魔力、クイズの惹力 2024/10/25
 このコラムの愛読者なら、僕に会ったことがなくても、僕がどんな人でどんなキャリアを歩んできた大方わかっていると思います。が、今この文章をたまたま読んでいる大半の方は、そんな人であるわけもないので、簡単に申し上げると、大学を出て社会人になってからずっと(実に30年以上)医療関係者に向けたメディアでコンテンツを作って発信してきました。で、タイトルにあるクイズの話です。メディアには、雑誌であれテレビであれ、テキストであれ動画であれ、読者・視聴者に伝えたい「何か」がまずあります。それをより多くの人に届けるために(まあ、とりあえず見てもらうために)、いろいろ工夫をするわけですが、クイズはその代表的な方法といえます。アイデアとしては、もっともありきたりでもっとも凡庸なんですが、確実に効果がある。人間というのは、目の前にクイズを提示されると、解こうとしてしまう本能があるようです。クイズにはなぜか人を惹きつける力がある。都内で電車に乗っていると、車内ディスプレーでいつもどうでもいいクイズが流れているのも頷けます。僕らメディア側からすると、クイズはいわゆる“鉄板”の手法ということになります。で、皮疹です。医学的には所見の1つということになるでしょうが、血液検査や心電図、X線など他の多くの所見と異なる特徴があります。それは、検査しなくても見ることができることです。医師にも患者本人にも好むと好まざるとにかかわらず見えてしまう。医師は、診察室でオーダーもしていないのに、まず提示されてしまうわけです。クイズのように。熟練の皮膚科医は、その皮疹を見ただけで、聞いたこともないような疾患をあらかた診断できてしまいます。もちろん他の検査で確認するわけですが、その視診力ともいうべき技術に非皮膚科医は驚かされると聞きます。「Dr.安部の皮膚科クイズ 中級編」は、そのような謎めいた所見である皮疹を鉄板の手法であるクイズで仕立てた番組です。ウケないわけがありません。制作は大変でしたが、高い評価をいただき、ロングセラーになっています。初級編を前に一度ここで取り上げたので、今回はちょっと違った角度から紹介させていただきました。なお、タイトルにある「惹力」というのは僕の造語です。辞書で引いてもありませんので、ご注意を。でも、意味はわかりますよね?
このコラムの愛読者なら、僕に会ったことがなくても、僕がどんな人でどんなキャリアを歩んできた大方わかっていると思います。が、今この文章をたまたま読んでいる大半の方は、そんな人であるわけもないので、簡単に申し上げると、大学を出て社会人になってからずっと(実に30年以上)医療関係者に向けたメディアでコンテンツを作って発信してきました。で、タイトルにあるクイズの話です。メディアには、雑誌であれテレビであれ、テキストであれ動画であれ、読者・視聴者に伝えたい「何か」がまずあります。それをより多くの人に届けるために(まあ、とりあえず見てもらうために)、いろいろ工夫をするわけですが、クイズはその代表的な方法といえます。アイデアとしては、もっともありきたりでもっとも凡庸なんですが、確実に効果がある。人間というのは、目の前にクイズを提示されると、解こうとしてしまう本能があるようです。クイズにはなぜか人を惹きつける力がある。都内で電車に乗っていると、車内ディスプレーでいつもどうでもいいクイズが流れているのも頷けます。僕らメディア側からすると、クイズはいわゆる“鉄板”の手法ということになります。で、皮疹です。医学的には所見の1つということになるでしょうが、血液検査や心電図、X線など他の多くの所見と異なる特徴があります。それは、検査しなくても見ることができることです。医師にも患者本人にも好むと好まざるとにかかわらず見えてしまう。医師は、診察室でオーダーもしていないのに、まず提示されてしまうわけです。クイズのように。熟練の皮膚科医は、その皮疹を見ただけで、聞いたこともないような疾患をあらかた診断できてしまいます。もちろん他の検査で確認するわけですが、その視診力ともいうべき技術に非皮膚科医は驚かされると聞きます。「Dr.安部の皮膚科クイズ 中級編」は、そのような謎めいた所見である皮疹を鉄板の手法であるクイズで仕立てた番組です。ウケないわけがありません。制作は大変でしたが、高い評価をいただき、ロングセラーになっています。初級編を前に一度ここで取り上げたので、今回はちょっと違った角度から紹介させていただきました。なお、タイトルにある「惹力」というのは僕の造語です。辞書で引いてもありませんので、ご注意を。でも、意味はわかりますよね? -
意表をついて大好評!“医師のマナー”を「まつり」で学べ 2024/09/15
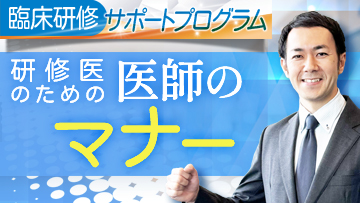 ケアネットでは、今月21日、22日の2日間にわたって「ケアネットまつり」を開催します。CareNeTVでお馴染みのスター講師陣が、立て続けに趣向を凝らしたオリジナルレクチャーを繰り出すオンラインイベント。2年連続2回目。僕としては、フジロックのように観客を熱狂させ、24時間テレビのように人々の心を動かし、紅白歌合戦のように全国民が注目する医療界のビッグイベントに育てたいと思っています。今年は、医師向けだけでなく、医学生、看護師のためのプログラムも複数用意しましたが、中でも異色なものとして、メイヨークリニックの松尾貴公先生による「若手医師のためのマナーと仕事術」があります。松尾先生は、正直CareNeTVでお馴染み!では決してなく、今年度からスタートした「臨床研修サポートプログラム」の、しかも最後の最後に登場した先生です。「研修医のための医師の仕事術」「研修医のための医師のマナー」の2シリーズを公開中。「臨床研修サポートプログラム」は、医師になってからの最初の2年間、臨床研修をより実りあるものにすることを支援する目的で立ち上げた新企画です。臨床研修のローテーションで回る必修診療科で必ず学ぶ臨床トピックから始め、続いて、診療科にかかわらず研修医が押さえておくべき臨床テーマを「全科共通」番組としてリリースしてきました。実は、松尾先生と知り合い、意見交換する機会を得たのはまったくの偶然で、それらの企画があらかた決まった後でした。長年研修医教育に携わってきた松尾先生が強調していたのは、「全科共通」よりさらに手前、いわば「社会人共通」のようことだと僕は受け止めました。それを医師という職業に限定してまとめてみたらどうかと。でも「今の若い人って、ビジネスマナーとか興味あるのかなー」最初そう思いましたが、よくよく考えて、真逆の結論に達しました。僕らのような古い世代の人間は、そうしたものをきちんと学んでいたのだろうか?否。むしろ、それらはマニュアル的に明文化され、体系的に教育されるものではなく、上司や先輩方の背中を見て「暗黙のうちに」身につけていくものではなかったか?一方、Z世代の人々は、そんな「阿吽の呼吸」みたいな話、意味わかんないしー、知っておかなきゃならないことがあるなら、短時間でわかりやすく簡潔に教えてよ!と考えるのではなかろうか?実際リリース後、期待通りの好意的な意見をあちこちからいただいているので、異色ではありますが、今回「ケアネットまつり」でそのエッセンスを濃縮した特別版を全医療者に向けて広く公開することとしました。9月21日午後14時35分から。若い先生方のみならず、中堅、ベテランの先生方にも耳が痛い話が多いはず。目から鱗が落ちること請け合いです。
ケアネットでは、今月21日、22日の2日間にわたって「ケアネットまつり」を開催します。CareNeTVでお馴染みのスター講師陣が、立て続けに趣向を凝らしたオリジナルレクチャーを繰り出すオンラインイベント。2年連続2回目。僕としては、フジロックのように観客を熱狂させ、24時間テレビのように人々の心を動かし、紅白歌合戦のように全国民が注目する医療界のビッグイベントに育てたいと思っています。今年は、医師向けだけでなく、医学生、看護師のためのプログラムも複数用意しましたが、中でも異色なものとして、メイヨークリニックの松尾貴公先生による「若手医師のためのマナーと仕事術」があります。松尾先生は、正直CareNeTVでお馴染み!では決してなく、今年度からスタートした「臨床研修サポートプログラム」の、しかも最後の最後に登場した先生です。「研修医のための医師の仕事術」「研修医のための医師のマナー」の2シリーズを公開中。「臨床研修サポートプログラム」は、医師になってからの最初の2年間、臨床研修をより実りあるものにすることを支援する目的で立ち上げた新企画です。臨床研修のローテーションで回る必修診療科で必ず学ぶ臨床トピックから始め、続いて、診療科にかかわらず研修医が押さえておくべき臨床テーマを「全科共通」番組としてリリースしてきました。実は、松尾先生と知り合い、意見交換する機会を得たのはまったくの偶然で、それらの企画があらかた決まった後でした。長年研修医教育に携わってきた松尾先生が強調していたのは、「全科共通」よりさらに手前、いわば「社会人共通」のようことだと僕は受け止めました。それを医師という職業に限定してまとめてみたらどうかと。でも「今の若い人って、ビジネスマナーとか興味あるのかなー」最初そう思いましたが、よくよく考えて、真逆の結論に達しました。僕らのような古い世代の人間は、そうしたものをきちんと学んでいたのだろうか?否。むしろ、それらはマニュアル的に明文化され、体系的に教育されるものではなく、上司や先輩方の背中を見て「暗黙のうちに」身につけていくものではなかったか?一方、Z世代の人々は、そんな「阿吽の呼吸」みたいな話、意味わかんないしー、知っておかなきゃならないことがあるなら、短時間でわかりやすく簡潔に教えてよ!と考えるのではなかろうか?実際リリース後、期待通りの好意的な意見をあちこちからいただいているので、異色ではありますが、今回「ケアネットまつり」でそのエッセンスを濃縮した特別版を全医療者に向けて広く公開することとしました。9月21日午後14時35分から。若い先生方のみならず、中堅、ベテランの先生方にも耳が痛い話が多いはず。目から鱗が落ちること請け合いです。 -
名講義は時を越える!新人研修医が絶賛する18年前の「身体診察」の傑作 2024/08/25
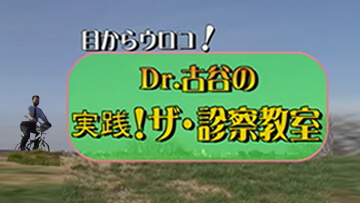 いきなり言ってしまいます。今回取り上げるCareNeTV番組はコレ。古谷伸之先生の「目からウロコ!Dr.古谷の実践!ザ・診察教室」。2006年8月にケアネットDVDとして発売された“ふた昔前”の作品です。2ヵ月前のこのコラムでも、20年前の浅岡俊之先生の漢方番組のすばらしさをお伝えしましたが、昔の名講義で「今」勉強できるのは、膨大な動画コンテンツに瞬時にアクセスできるデジタル時代ならではですよね。しかし、今回この古谷先生の番組を掘り起こしたのは、実は僕でありません。今年、総合病院 南生協病院の研修医になったばかりの杉田研介先生です。背景を少し説明させていただきます。現在ケアネットでは、全国の医学部、医科大学を通じて医学生が無料でCareNeTVを見ることができる「視聴パス」を提供しています。詳細はこちらをご覧いただければと思いますが、医学生が多数ある医師向けの番組の中から自分に合ったものを探すこと自体が容易ではありません。そこで杉田先生に「ケアネットのアンバサダー」として、個々の番組の医学生に役立つポイントや実際の活用法などを発信してもらっているのです。杉田先生とケアネットにつながりができたのは、昨年の「ケアネットまつり」(今年も9月21日、22日の2日間開催します!)。まだ医学部6年生だった昨年、「ケアネットまつり」で「視聴パス」のことを知った杉田さんは、臨床実習や卒業試験対策にCareNeTVを活用し始めたそうです。CareNeTVの有効な使い方を自分でいろいろ試してくれた彼こそその任にピッタリと、研修医になってからアンバサダーをお願いした次第です。その杉田先生が、アンバサダーとして最初に紹介した番組が「目からウロコ!Dr.古谷の実践!ザ・診察教室」。なぜこの番組を推してくれたのかは本人のSNS投稿を読んでもらうのが一番ですが、「初期研修医の先生方はもちろん、医学生の方々にもOSCE対策や実習対策として大いに役立つ内容」と太鼓判。Zoomでの定期ミーティングで「身体診察で知りたいことは、ほとんどこの番組の中にありました。内科のローテーションの間いつも見てましたよ」と熱っぽく語ってくれたのもうれしかったですね。「でも、古いよねー」と僕が尋ねると、「身体診察は基本的に変わりませんから、古さは関係ないです!」杉田先生の力も借りながら、これからも「時を越える名講義」を掘り起こして紹介していければと思います。ちなみに、アンバサダーも若干名密かに募集中ですので、われこそはという方はご連絡ください(研修医限定)。
いきなり言ってしまいます。今回取り上げるCareNeTV番組はコレ。古谷伸之先生の「目からウロコ!Dr.古谷の実践!ザ・診察教室」。2006年8月にケアネットDVDとして発売された“ふた昔前”の作品です。2ヵ月前のこのコラムでも、20年前の浅岡俊之先生の漢方番組のすばらしさをお伝えしましたが、昔の名講義で「今」勉強できるのは、膨大な動画コンテンツに瞬時にアクセスできるデジタル時代ならではですよね。しかし、今回この古谷先生の番組を掘り起こしたのは、実は僕でありません。今年、総合病院 南生協病院の研修医になったばかりの杉田研介先生です。背景を少し説明させていただきます。現在ケアネットでは、全国の医学部、医科大学を通じて医学生が無料でCareNeTVを見ることができる「視聴パス」を提供しています。詳細はこちらをご覧いただければと思いますが、医学生が多数ある医師向けの番組の中から自分に合ったものを探すこと自体が容易ではありません。そこで杉田先生に「ケアネットのアンバサダー」として、個々の番組の医学生に役立つポイントや実際の活用法などを発信してもらっているのです。杉田先生とケアネットにつながりができたのは、昨年の「ケアネットまつり」(今年も9月21日、22日の2日間開催します!)。まだ医学部6年生だった昨年、「ケアネットまつり」で「視聴パス」のことを知った杉田さんは、臨床実習や卒業試験対策にCareNeTVを活用し始めたそうです。CareNeTVの有効な使い方を自分でいろいろ試してくれた彼こそその任にピッタリと、研修医になってからアンバサダーをお願いした次第です。その杉田先生が、アンバサダーとして最初に紹介した番組が「目からウロコ!Dr.古谷の実践!ザ・診察教室」。なぜこの番組を推してくれたのかは本人のSNS投稿を読んでもらうのが一番ですが、「初期研修医の先生方はもちろん、医学生の方々にもOSCE対策や実習対策として大いに役立つ内容」と太鼓判。Zoomでの定期ミーティングで「身体診察で知りたいことは、ほとんどこの番組の中にありました。内科のローテーションの間いつも見てましたよ」と熱っぽく語ってくれたのもうれしかったですね。「でも、古いよねー」と僕が尋ねると、「身体診察は基本的に変わりませんから、古さは関係ないです!」杉田先生の力も借りながら、これからも「時を越える名講義」を掘り起こして紹介していければと思います。ちなみに、アンバサダーも若干名密かに募集中ですので、われこそはという方はご連絡ください(研修医限定)。 -
NASHの新薬とガイドラインと専門医試験 2024/07/21
 CareNeTVで臨床医学チャンネルを標榜し、臨床で働く先生方の「明日の仕事」がより高質に、より効率的になるようなコンテンツのあり様を入念に検討し、丁寧に制作しています。それが基本ではありますが、一方で、ここ数年先生方の「現実的なニーズ」がとても高いのが、専門医試験対策番組です。専門医の資格は、先生方のキャリアにおいて非常に重要であり、その試験を一発で確実に合格したいと考えるのは当然のこと。CareNeTVで微力ながらそのお手伝いをできればと、どのような形でサービス設計するのがよいか熟考し、実行に移しています。今年度は初の試みとして、「消化器病専門医試験パーフェクト対策」を企画しました。講師は公立豊岡病院の宮垣亜紀先生。こちらは動画コンテンツではなく、Zoomを使った双方向の少人数オンラインスクールで、7月26日に開講します。受験する先生がいたら、ぜひご紹介ください。ところで、今年に入って非アルコール性脂肪性肝炎、いわゆるNASHの新薬が初めて米国で承認されたのをご存じでしょうか?今年3月19日のCareNet.com「バイオの火曜日」の記事によると、その薬は米国Madrigal Pharmaceuticals社が開発したresmetirom(商品名:Rezdiffra)です。1日1回の経口服用薬で、NASH患者の肝臓で不調となる甲状腺ホルモン受容体β(THR-β)のアゴニスト。肝臓の線維化のステージがF2~F3の患者が適応となります。NASHは日本でも患者数が増えている疾患ですが、その治療薬は何か?と問われたら、「存在しない」というのがこれまでの答えでした。それが今は日本では承認されていないが、resmetiromという薬剤となります。ただし、NASHの新薬開発競争は肝臓の領域でホットな話題ではありますが、日本の専門医試験でresmetiromが問われることは今のところないはずです。もちろんNASHの治療について問われる可能性はあります。その際の正答の根拠となるのは、日本の標準治療つまり診療ガイドラインの記述ということになります。特効薬がないなかでNASHが実際に日本でどのように治療されているのか、どんな問題があるのかについてもケアネットで情報提供しています。2021年7月にライブ配信した「ガイドラインから学ぶNAFLD/NASHの診療ポイント」がそれです。ケアネットライブとして不定期で配信している「ガイドラインから学ぶ」シリーズは、さまざまな疾患の最新知見、日本におけるその時々の標準治療のキャッチアップに大変好評をいただいています。NASHの回のライブ講師は同じく宮垣先生。ガイドラインの最終改訂は2020年なので、内科専門医試験にも消化器病専門医試験にも対応できる内容です。もちろん本試験でNASHについて出題されるかはわかりませんが。医学は日進月歩で進歩し情報は絶えずアップデートされていきます。その意味で絶対的な不動の正解があるわけでなく、その目的によって情報の伝え方、届け方も変える必要があると思います。情報が溢れるなかでそれを最適化するのが、つまりところ私たちケアネットの役割なのではないかと感じる昨今です。
CareNeTVで臨床医学チャンネルを標榜し、臨床で働く先生方の「明日の仕事」がより高質に、より効率的になるようなコンテンツのあり様を入念に検討し、丁寧に制作しています。それが基本ではありますが、一方で、ここ数年先生方の「現実的なニーズ」がとても高いのが、専門医試験対策番組です。専門医の資格は、先生方のキャリアにおいて非常に重要であり、その試験を一発で確実に合格したいと考えるのは当然のこと。CareNeTVで微力ながらそのお手伝いをできればと、どのような形でサービス設計するのがよいか熟考し、実行に移しています。今年度は初の試みとして、「消化器病専門医試験パーフェクト対策」を企画しました。講師は公立豊岡病院の宮垣亜紀先生。こちらは動画コンテンツではなく、Zoomを使った双方向の少人数オンラインスクールで、7月26日に開講します。受験する先生がいたら、ぜひご紹介ください。ところで、今年に入って非アルコール性脂肪性肝炎、いわゆるNASHの新薬が初めて米国で承認されたのをご存じでしょうか?今年3月19日のCareNet.com「バイオの火曜日」の記事によると、その薬は米国Madrigal Pharmaceuticals社が開発したresmetirom(商品名:Rezdiffra)です。1日1回の経口服用薬で、NASH患者の肝臓で不調となる甲状腺ホルモン受容体β(THR-β)のアゴニスト。肝臓の線維化のステージがF2~F3の患者が適応となります。NASHは日本でも患者数が増えている疾患ですが、その治療薬は何か?と問われたら、「存在しない」というのがこれまでの答えでした。それが今は日本では承認されていないが、resmetiromという薬剤となります。ただし、NASHの新薬開発競争は肝臓の領域でホットな話題ではありますが、日本の専門医試験でresmetiromが問われることは今のところないはずです。もちろんNASHの治療について問われる可能性はあります。その際の正答の根拠となるのは、日本の標準治療つまり診療ガイドラインの記述ということになります。特効薬がないなかでNASHが実際に日本でどのように治療されているのか、どんな問題があるのかについてもケアネットで情報提供しています。2021年7月にライブ配信した「ガイドラインから学ぶNAFLD/NASHの診療ポイント」がそれです。ケアネットライブとして不定期で配信している「ガイドラインから学ぶ」シリーズは、さまざまな疾患の最新知見、日本におけるその時々の標準治療のキャッチアップに大変好評をいただいています。NASHの回のライブ講師は同じく宮垣先生。ガイドラインの最終改訂は2020年なので、内科専門医試験にも消化器病専門医試験にも対応できる内容です。もちろん本試験でNASHについて出題されるかはわかりませんが。医学は日進月歩で進歩し情報は絶えずアップデートされていきます。その意味で絶対的な不動の正解があるわけでなく、その目的によって情報の伝え方、届け方も変える必要があると思います。情報が溢れるなかでそれを最適化するのが、つまりところ私たちケアネットの役割なのではないかと感じる昨今です。 -
漢方の浅岡先生の20年前の名講義を聴けるのはCareNeTVだけ! 2024/06/23
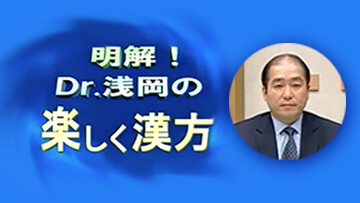 NHKの「時をかけるテレビ」という番組をご存じでしょうか? 放送開始から100年近くになるNHKが過去に制作・放送してきた番組から「今こそ見たい」作品を解説付きでオンエアするものです。映像は古く、時代背景も現代とは異なるのですが、純粋に今見ても面白い、いや今だからこそ面白いものが選りすぐられており、毎回楽しんでいます。プロデューサー目線でいうと、NHKの膨大なコンテンツのアーカイブがうらやましい限りです。かくいうCareNeTVも、医学教育動画という分野に限っていえば、日本有数の歴史があり、豊富なアーカイブを持っています。ケアネットの創業は1996年。当時はインターネットがまだ立ち上がったばかりで、医学教育番組を(なんと!)CS放送で配信する事業からスタートしました。今のCareNeTVに近い形態になったのは、2004年の「ケアネットDVD」から。当時はまだ動画をネットで見る環境ではありませんでした。逆に現在はDVDで動画を見る人は激減し、ネットでスマホでが当たり前になったのは周知のとおり。しかし、このようにメディア、デバイスが変遷していくなかでも、ケアネットの動画コンテンツ資産は連綿と蓄積されてきたのです。医学は進歩を続けているので古い番組はお薦めできないものが多いのですが、そんな中で今なお多くの方に視聴いただいているのが浅岡俊之先生の漢方番組です。最初の作品「明解!Dr.浅岡の楽しく漢方」(第1巻)のDVDが発売されたのは2004年7月。実に20年前ですが、漢方医学という性質上今見ても十分に実用的です。漢方関連のコンテンツに対するニーズは常にあるので、その後もいくつか番組をリリースしていますが、浅岡先生の講義は特別らしく、その評価は揺るがないと感じます。「15年ほど前に視聴していました。また繰り返し学習したいと思い、再視聴。わかりやすくて、役立つ内容で素晴らしいです」。2020年にこんなコメントが書き込まれています。そんな背景もあって、先日、久しぶりに浅岡先生に連絡し、新しい企画を打診したところ、教育・講演活動からはもう身を引いたとのこと。大変残念ですが、今では生で聴くことができない先生の名講義をいつでもどこでも視聴できるのがCareNeTVプレミアム会員の特権になりました。ところで、「明解!Dr.浅岡の楽しく漢方」はDVDで6枚、総講義時間は24時間を超えます。ほぼ大学の講義1コマ1年分。今のCareNeTVでは考えられない「超大作」です。このシリーズでしっかり学べば、日常診療に必要な漢方のかなりの部分まで習得できるのではないかと思います。
NHKの「時をかけるテレビ」という番組をご存じでしょうか? 放送開始から100年近くになるNHKが過去に制作・放送してきた番組から「今こそ見たい」作品を解説付きでオンエアするものです。映像は古く、時代背景も現代とは異なるのですが、純粋に今見ても面白い、いや今だからこそ面白いものが選りすぐられており、毎回楽しんでいます。プロデューサー目線でいうと、NHKの膨大なコンテンツのアーカイブがうらやましい限りです。かくいうCareNeTVも、医学教育動画という分野に限っていえば、日本有数の歴史があり、豊富なアーカイブを持っています。ケアネットの創業は1996年。当時はインターネットがまだ立ち上がったばかりで、医学教育番組を(なんと!)CS放送で配信する事業からスタートしました。今のCareNeTVに近い形態になったのは、2004年の「ケアネットDVD」から。当時はまだ動画をネットで見る環境ではありませんでした。逆に現在はDVDで動画を見る人は激減し、ネットでスマホでが当たり前になったのは周知のとおり。しかし、このようにメディア、デバイスが変遷していくなかでも、ケアネットの動画コンテンツ資産は連綿と蓄積されてきたのです。医学は進歩を続けているので古い番組はお薦めできないものが多いのですが、そんな中で今なお多くの方に視聴いただいているのが浅岡俊之先生の漢方番組です。最初の作品「明解!Dr.浅岡の楽しく漢方」(第1巻)のDVDが発売されたのは2004年7月。実に20年前ですが、漢方医学という性質上今見ても十分に実用的です。漢方関連のコンテンツに対するニーズは常にあるので、その後もいくつか番組をリリースしていますが、浅岡先生の講義は特別らしく、その評価は揺るがないと感じます。「15年ほど前に視聴していました。また繰り返し学習したいと思い、再視聴。わかりやすくて、役立つ内容で素晴らしいです」。2020年にこんなコメントが書き込まれています。そんな背景もあって、先日、久しぶりに浅岡先生に連絡し、新しい企画を打診したところ、教育・講演活動からはもう身を引いたとのこと。大変残念ですが、今では生で聴くことができない先生の名講義をいつでもどこでも視聴できるのがCareNeTVプレミアム会員の特権になりました。ところで、「明解!Dr.浅岡の楽しく漢方」はDVDで6枚、総講義時間は24時間を超えます。ほぼ大学の講義1コマ1年分。今のCareNeTVでは考えられない「超大作」です。このシリーズでしっかり学べば、日常診療に必要な漢方のかなりの部分まで習得できるのではないかと思います。 -
病理学を楽しく!医学生のころ苦痛だった講義をCareNeTVが作るとこうなる 2024/05/19
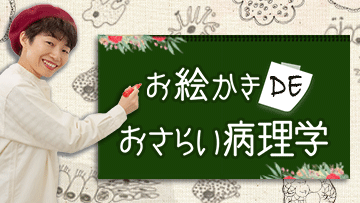 なんで大学生のころは、授業をさぼることばかり考えていたんだろう?「難しい入学試験をパスし高い授業料を払って、本当にもったいないことをしたなー」と社会人になってからよく後悔したものです。その分野の一流の先生の講義を生で聴けて、質問もできる。そんな貴重な機会をみすみす棒に振っていたのですから。「若かった」と言えばそれまでですが、それにしても…今この文章を読んでいただいているだろう多くの方と違い、僕は文系学生だったので、状況はかなり異なるとは思いますが、医学部での講義が「とても貴重だった」「もっとしっかり聴講しておけばよかった」と後年感じたことがある先生方も多いのではないでしょうか。CareNeTVは「臨床医学チャンネル」と標榜しているように、臨床医学の教育的な番組が大半を占めます。しかし、医学部でその手前に学ぶ「基礎医学」を扱ったコンテンツもあっていいのではないか?解剖学、生理学、病理学、薬理学等々…。番組企画会議で部員からそんな提案を聞いたとき(自分がそう感じているから)、そんなニーズも確かにあるかもしれないと思いました。臨床医として働き始めると、医学部で行われているような基礎医学の講義を聴く機会はそうそうないでしょうから。そんな発想から生まれた番組が「お絵かきDEおさらい病理学」です。CareNeTVの番組としては異色ですが、誕生にはそうした背景があったのです。実際に作品になるまでは紆余曲折があり、大学の講義のような感じではないかもしれませんが、「学生時代、病理や免疫学が苦手でしたが、改めて教科書を読んでみたくなりました」「とてもわかり易かったです。学生時代に聞きたかった」「復習できてよい」といった好意的な声を多数いただき、当初想定したニーズはやはり一定数あるということが確認できました。ところで、この番組にはもう1つ特徴があります。講師の小倉加奈子先生がイラストを描きながら病理の説明をしていくところです。基礎医学は、ともすれば小難しく退屈になりがちなので、先生の特技を生かしてCareNeTVらしい演出で仕上げています。実際に絵を描いているところを撮影されるというのは想像以上にハードルが高いことなのですが、小倉先生はプロのイラストレーターのように見事に対応してくれました。その姿を見て往年の水森亜土さんを思い出しました(わからない方のほうが多いですね。すいません)。他の分野でもこんな楽しい基礎医学の講義ができる先生がいるといいのですが…。われこそはという先生がおられましたら、ぜひご一報ください。
なんで大学生のころは、授業をさぼることばかり考えていたんだろう?「難しい入学試験をパスし高い授業料を払って、本当にもったいないことをしたなー」と社会人になってからよく後悔したものです。その分野の一流の先生の講義を生で聴けて、質問もできる。そんな貴重な機会をみすみす棒に振っていたのですから。「若かった」と言えばそれまでですが、それにしても…今この文章を読んでいただいているだろう多くの方と違い、僕は文系学生だったので、状況はかなり異なるとは思いますが、医学部での講義が「とても貴重だった」「もっとしっかり聴講しておけばよかった」と後年感じたことがある先生方も多いのではないでしょうか。CareNeTVは「臨床医学チャンネル」と標榜しているように、臨床医学の教育的な番組が大半を占めます。しかし、医学部でその手前に学ぶ「基礎医学」を扱ったコンテンツもあっていいのではないか?解剖学、生理学、病理学、薬理学等々…。番組企画会議で部員からそんな提案を聞いたとき(自分がそう感じているから)、そんなニーズも確かにあるかもしれないと思いました。臨床医として働き始めると、医学部で行われているような基礎医学の講義を聴く機会はそうそうないでしょうから。そんな発想から生まれた番組が「お絵かきDEおさらい病理学」です。CareNeTVの番組としては異色ですが、誕生にはそうした背景があったのです。実際に作品になるまでは紆余曲折があり、大学の講義のような感じではないかもしれませんが、「学生時代、病理や免疫学が苦手でしたが、改めて教科書を読んでみたくなりました」「とてもわかり易かったです。学生時代に聞きたかった」「復習できてよい」といった好意的な声を多数いただき、当初想定したニーズはやはり一定数あるということが確認できました。ところで、この番組にはもう1つ特徴があります。講師の小倉加奈子先生がイラストを描きながら病理の説明をしていくところです。基礎医学は、ともすれば小難しく退屈になりがちなので、先生の特技を生かしてCareNeTVらしい演出で仕上げています。実際に絵を描いているところを撮影されるというのは想像以上にハードルが高いことなのですが、小倉先生はプロのイラストレーターのように見事に対応してくれました。その姿を見て往年の水森亜土さんを思い出しました(わからない方のほうが多いですね。すいません)。他の分野でもこんな楽しい基礎医学の講義ができる先生がいるといいのですが…。われこそはという先生がおられましたら、ぜひご一報ください。 -
新しいエコーの使い方 肩こり、腰痛を治すハイドロリリースに触れてみる 2024/04/21
 CareNeTVでは、2500を超える臨床医学動画が見放題のCareNeTVプレミアムに加え、Zoomを活用し、講師の先生とオンラインで直接コミュニケーションしながら密度の濃い学びが得られるCareNeTVスクールも数多く企画しています。さまざまなスクールの中でいまや定番となっているのが、エコーの手技を学ぶスクールです。POCUS(Point of Care Ultra Sound)や心エコーなど、エコーのスクールも数種類ありますが、どれもスタジオに超音波診断装置を持ち込み、モデル患者に先生がプローブを当てて、そのエコー画像を遠隔の受講者にリアルタイムで映し出しながら生解説するのが大きな特徴です。一昔前と比べると、超音波診断装置の性能、UIは著しく向上し、臨床での用途は大きく広がっています。それにつれて、先生方がエコーを取り入れて診療をレベルアップさせたいという熱量が高まっていることを、エコースクールの人気を見るにつけ感じます。と、いきなりCareNeTVのエコースクールの話を延々としてしまいましたが、今回紹介したいのは「Dr.白石のLet‘sエコー 運動器編」というCareNeTV番組についてです。エコーで運動器を診るという発想は比較的新しく、実践している先生はまだ少数派だと思います。しかし、白石吉彦先生が第1回「外来超音波診療の実際」で紹介する外来診療でのエコーの使い方を見ると、肩こり、腰痛、肋骨骨折、膝関節穿刺、ばね指、痛風、粉瘤と実に多様。とくに運動器エコーが威力を発揮するのは、筋膜性疼痛症候群(MPS)です。MPSは、繰り返す動きや激しい運動、加齢などにより筋が炎症や血行不良を来した結果、筋肉を包む筋膜の癒着が起こり、骨や関節に異常はないのに痛みが生じる病態で、肩こりや腰痛の原因の多くがMPSだと考えられています。この癒着した筋膜などをエコーを用いて確認し、生理食塩水などを注入し筋膜を剥がすことで痛みを緩和するのがハイドロリリースという治療法。「Dr.白石のLet‘sエコー 運動器編」では、肩こり、腰臀部痛、五十肩のハイドロリリースの手技を見せ、エコー画像を提示しながら、詳細に指導しています。MPSとハイドロリリースをご存知ない方もいると思いますが、肩こり、腰痛という多くの患者が抱える悩みを解消できる可能性があり、注目されています。この番組は、ハイドロリリースの研究・普及を推進している一般社団法人 日本整形内科学研究会が監修しています。”整形内科”という言葉通り、整形外科だけでなく内科系のクリニックでも取り入れるところが出てきています。まずは動画で標準的な診断、治療法を知るだけでも価値があるのではないでしょうか。実は、これを実際に診療に取り入れてもらうためのCareNeTVスクールも検討しております。ご興味ありますか?
CareNeTVでは、2500を超える臨床医学動画が見放題のCareNeTVプレミアムに加え、Zoomを活用し、講師の先生とオンラインで直接コミュニケーションしながら密度の濃い学びが得られるCareNeTVスクールも数多く企画しています。さまざまなスクールの中でいまや定番となっているのが、エコーの手技を学ぶスクールです。POCUS(Point of Care Ultra Sound)や心エコーなど、エコーのスクールも数種類ありますが、どれもスタジオに超音波診断装置を持ち込み、モデル患者に先生がプローブを当てて、そのエコー画像を遠隔の受講者にリアルタイムで映し出しながら生解説するのが大きな特徴です。一昔前と比べると、超音波診断装置の性能、UIは著しく向上し、臨床での用途は大きく広がっています。それにつれて、先生方がエコーを取り入れて診療をレベルアップさせたいという熱量が高まっていることを、エコースクールの人気を見るにつけ感じます。と、いきなりCareNeTVのエコースクールの話を延々としてしまいましたが、今回紹介したいのは「Dr.白石のLet‘sエコー 運動器編」というCareNeTV番組についてです。エコーで運動器を診るという発想は比較的新しく、実践している先生はまだ少数派だと思います。しかし、白石吉彦先生が第1回「外来超音波診療の実際」で紹介する外来診療でのエコーの使い方を見ると、肩こり、腰痛、肋骨骨折、膝関節穿刺、ばね指、痛風、粉瘤と実に多様。とくに運動器エコーが威力を発揮するのは、筋膜性疼痛症候群(MPS)です。MPSは、繰り返す動きや激しい運動、加齢などにより筋が炎症や血行不良を来した結果、筋肉を包む筋膜の癒着が起こり、骨や関節に異常はないのに痛みが生じる病態で、肩こりや腰痛の原因の多くがMPSだと考えられています。この癒着した筋膜などをエコーを用いて確認し、生理食塩水などを注入し筋膜を剥がすことで痛みを緩和するのがハイドロリリースという治療法。「Dr.白石のLet‘sエコー 運動器編」では、肩こり、腰臀部痛、五十肩のハイドロリリースの手技を見せ、エコー画像を提示しながら、詳細に指導しています。MPSとハイドロリリースをご存知ない方もいると思いますが、肩こり、腰痛という多くの患者が抱える悩みを解消できる可能性があり、注目されています。この番組は、ハイドロリリースの研究・普及を推進している一般社団法人 日本整形内科学研究会が監修しています。”整形内科”という言葉通り、整形外科だけでなく内科系のクリニックでも取り入れるところが出てきています。まずは動画で標準的な診断、治療法を知るだけでも価値があるのではないでしょうか。実は、これを実際に診療に取り入れてもらうためのCareNeTVスクールも検討しております。ご興味ありますか? -
コロナ禍を乗り越えた!古さが新しいCareNeTVの看板番組で「しびれ」を学ぶ 2024/03/23
 「みなさん、お待たせしましたー!3年ぶりですよねー」冒頭こんなあいさつで始まるCareNeTVの番組があるんですが、何だかわかりますか?CareNeTVについて多少知っている方なら答えは1つしかありませんよね。そう、林寛之先生による「Dr.林の笑劇的救急問答」です。2005年から続く「Dr.林の笑劇的救急問答」は、CareNeTVの代名詞ともいえるシリーズ番組ですが、実は、15年目の2020年9月リリースのSeason16で止まっていました。その原因は言うまでもなくコロナ。この番組は、CareNeTVでは珍しく、撮影クルーが丸ごと東京から福井に赴き、福井大学医学部附属病院の一角をお借りし林先生と門下の先生方と撮影・収録しています。新型コロナパンデミックの間は当然、そんなことはできません。コロナ禍が長引く中、オンラインでの代替案などを幾度となく検討しましたが、納得できる方法が見つからぬまま、3年が経過したというわけです。今月、最新作Season17の全8回が配信スタートとなりました(ので、今CareNeTVに入会すれば一気見できます!)。コロナ前とまったく同じスタイル、テンションで、Dr.林ワールドをお楽しみいただけます。3年前のこのコラムでも書きましたが、「Dr.林の笑劇的救急問答」がすごいのは、番組のスタイルが20年前からまったく変わっていないことです。現役の若手医師、医療者による救急現場を模したベタな寸劇。後半は、その先生方に林先生がユーモアたっぷりの授業をします。笑いの取り方も不変で、どこか”昭和的”。しかし、それが今でもウケ続けているのです。林先生が本当にスゴいのは実はそこ。ウケ続けていることです。CareNeTVでは、視聴数とは別に部内でユーザー満足度を定期的に調査していますが、「Dr.林の笑劇的救急問答」の新作が出るたび、常に他の作品を圧倒的に凌駕する高い評価となります。昨年9月に開催した「ケアネットまつり」でも林先生が人気投票第1位を獲得。今、Z世代に80年代90年代の歌謡曲が人気だそうです。テレビドラマではバブル時代と現代のギャップを描いた「不適切にもほどがある!」が大ヒット中。案外、若い人々は古さに新しさを感じ、しびれるのかもしれません。ここで問題。「Dr.林の笑劇的救急問答 Season17」第1回「しびれ診断のかなめ」から。「半身のしびれ」を訴える患者に何を考えるか?選択肢は3つ。① 頭蓋内病変を示唆② 寝返りしないで側臥位で寝ていた③ 1985年優勝、日本一!正解と先生方のリアクションが気になる方は本編でご確認ください。
「みなさん、お待たせしましたー!3年ぶりですよねー」冒頭こんなあいさつで始まるCareNeTVの番組があるんですが、何だかわかりますか?CareNeTVについて多少知っている方なら答えは1つしかありませんよね。そう、林寛之先生による「Dr.林の笑劇的救急問答」です。2005年から続く「Dr.林の笑劇的救急問答」は、CareNeTVの代名詞ともいえるシリーズ番組ですが、実は、15年目の2020年9月リリースのSeason16で止まっていました。その原因は言うまでもなくコロナ。この番組は、CareNeTVでは珍しく、撮影クルーが丸ごと東京から福井に赴き、福井大学医学部附属病院の一角をお借りし林先生と門下の先生方と撮影・収録しています。新型コロナパンデミックの間は当然、そんなことはできません。コロナ禍が長引く中、オンラインでの代替案などを幾度となく検討しましたが、納得できる方法が見つからぬまま、3年が経過したというわけです。今月、最新作Season17の全8回が配信スタートとなりました(ので、今CareNeTVに入会すれば一気見できます!)。コロナ前とまったく同じスタイル、テンションで、Dr.林ワールドをお楽しみいただけます。3年前のこのコラムでも書きましたが、「Dr.林の笑劇的救急問答」がすごいのは、番組のスタイルが20年前からまったく変わっていないことです。現役の若手医師、医療者による救急現場を模したベタな寸劇。後半は、その先生方に林先生がユーモアたっぷりの授業をします。笑いの取り方も不変で、どこか”昭和的”。しかし、それが今でもウケ続けているのです。林先生が本当にスゴいのは実はそこ。ウケ続けていることです。CareNeTVでは、視聴数とは別に部内でユーザー満足度を定期的に調査していますが、「Dr.林の笑劇的救急問答」の新作が出るたび、常に他の作品を圧倒的に凌駕する高い評価となります。昨年9月に開催した「ケアネットまつり」でも林先生が人気投票第1位を獲得。今、Z世代に80年代90年代の歌謡曲が人気だそうです。テレビドラマではバブル時代と現代のギャップを描いた「不適切にもほどがある!」が大ヒット中。案外、若い人々は古さに新しさを感じ、しびれるのかもしれません。ここで問題。「Dr.林の笑劇的救急問答 Season17」第1回「しびれ診断のかなめ」から。「半身のしびれ」を訴える患者に何を考えるか?選択肢は3つ。① 頭蓋内病変を示唆② 寝返りしないで側臥位で寝ていた③ 1985年優勝、日本一!正解と先生方のリアクションが気になる方は本編でご確認ください。 -
Dr.香坂はジョブズだ!心電図講義でさえプレゼンテーションで魅了する 2024/02/24
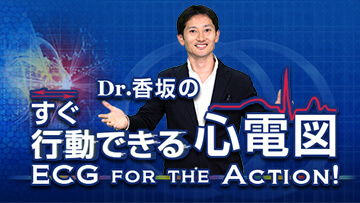 CareNeTVで取り上げている多様な臨床のテーマでとくに人気の高いものに心電図があります。数人の講師がさまざまな形で心電図の読み方をわかりすやく講義してくれています。それぞれに個性、特徴があり、自分の好みやレベルに合わせて選んで勉強していただければと思いますが、今日は、心電図番組としては全期間ランキングでトップの「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」のすごさを語らせてください。香坂先生は、優れた循環器臨床医であり、研究者であり、大学教員としては多くの後進を育てています。そのことは論を待ちません。しかし、僕が香坂先生が本当にすごいと思うのは、それら医師としての強固な土台のうえに圧倒的な「話力」が載っていることです。世の中には、いわゆる「話が上手い」人は少なからずいます。医師の中にも当然いますし、そうした先生はCareNeTVの講師陣に何人も見つけられるでしょう。あえて言うと、そうした「話が上手い」人たちの中でも香坂先生は傑出している、と僕は思います。例えば、故スティーブ・ジョブズ。伝説となった2005年のスタンフォード大学で行った卒業祝賀スピーチを、彼以外にできるでしょうか。言葉の選び方、声音、表情それらすべてを持って聴く者の心をつかみ、揺さぶり、強いメッセージを伝える。比肩するスピーカーはそうはいません。香坂先生のレクチャーを聴いていると、講義が上手い大学の先生の授業というより、ジョブズのスピーチを聞いているような気分になるのです。「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」の最終回で「カッコいい心電図の読み方」について彼は語ります。4枚の心電図を提示。心電図の波形の特徴から心臓の状態を仔細に解釈し、次々と一発診断してみせます。どうだ!これこそが「カッコいい心電図の読み方」だ…という話ではないのです。最後に推理小説なようなどんでん返しがあり、真に「カッコいい心電図の読み方」がどのようなものか視聴者の胸に刻んで講義が終わります。11分のレクチャーに情報が詰まっているだけでなく、キャッチーな導入があり、巧みなストーリー展開があり、意表をつくどんでん返しがあり、“腹落ち”するエンディングがある。見事です。確かな医学的知見にストーリーテラー、プレゼンターとしての才を兼ね備えたDr.香坂の「珠玉の講義」をぜひご堪能してください。
CareNeTVで取り上げている多様な臨床のテーマでとくに人気の高いものに心電図があります。数人の講師がさまざまな形で心電図の読み方をわかりすやく講義してくれています。それぞれに個性、特徴があり、自分の好みやレベルに合わせて選んで勉強していただければと思いますが、今日は、心電図番組としては全期間ランキングでトップの「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」のすごさを語らせてください。香坂先生は、優れた循環器臨床医であり、研究者であり、大学教員としては多くの後進を育てています。そのことは論を待ちません。しかし、僕が香坂先生が本当にすごいと思うのは、それら医師としての強固な土台のうえに圧倒的な「話力」が載っていることです。世の中には、いわゆる「話が上手い」人は少なからずいます。医師の中にも当然いますし、そうした先生はCareNeTVの講師陣に何人も見つけられるでしょう。あえて言うと、そうした「話が上手い」人たちの中でも香坂先生は傑出している、と僕は思います。例えば、故スティーブ・ジョブズ。伝説となった2005年のスタンフォード大学で行った卒業祝賀スピーチを、彼以外にできるでしょうか。言葉の選び方、声音、表情それらすべてを持って聴く者の心をつかみ、揺さぶり、強いメッセージを伝える。比肩するスピーカーはそうはいません。香坂先生のレクチャーを聴いていると、講義が上手い大学の先生の授業というより、ジョブズのスピーチを聞いているような気分になるのです。「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」の最終回で「カッコいい心電図の読み方」について彼は語ります。4枚の心電図を提示。心電図の波形の特徴から心臓の状態を仔細に解釈し、次々と一発診断してみせます。どうだ!これこそが「カッコいい心電図の読み方」だ…という話ではないのです。最後に推理小説なようなどんでん返しがあり、真に「カッコいい心電図の読み方」がどのようなものか視聴者の胸に刻んで講義が終わります。11分のレクチャーに情報が詰まっているだけでなく、キャッチーな導入があり、巧みなストーリー展開があり、意表をつくどんでん返しがあり、“腹落ち”するエンディングがある。見事です。確かな医学的知見にストーリーテラー、プレゼンターとしての才を兼ね備えたDr.香坂の「珠玉の講義」をぜひご堪能してください。