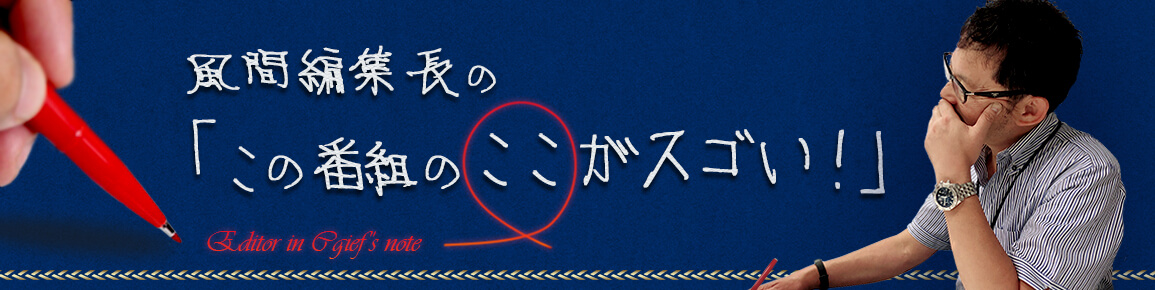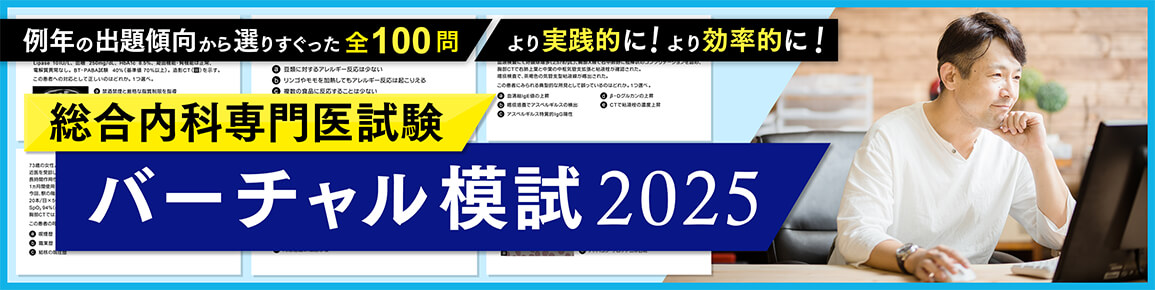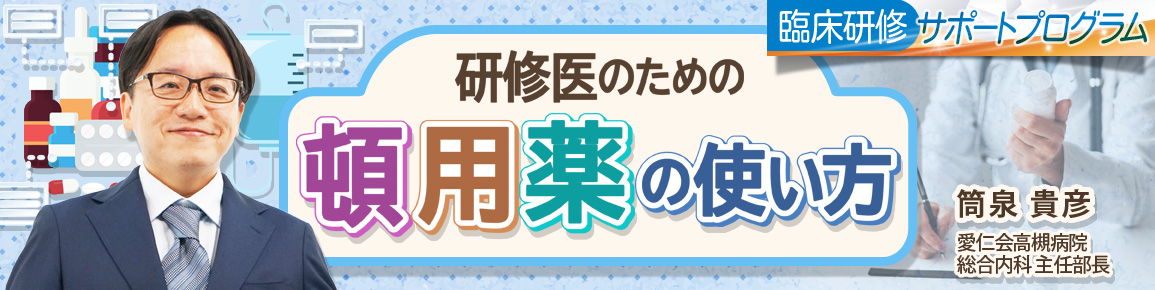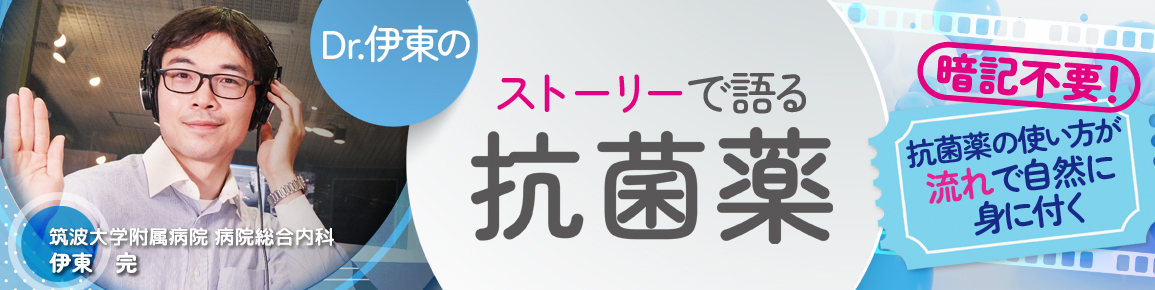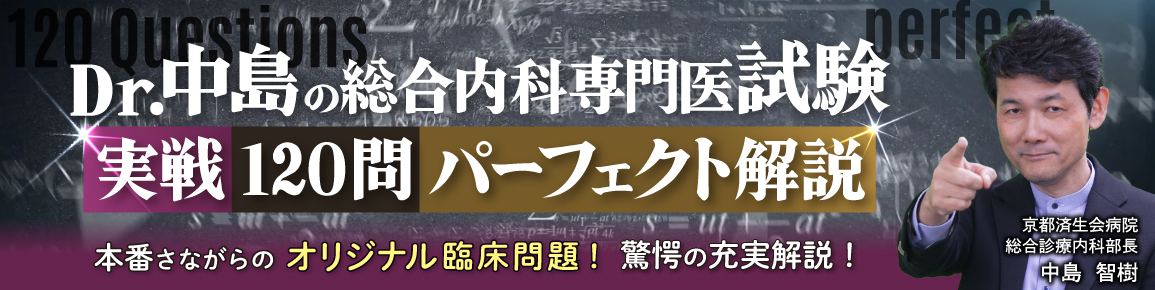僕は以前ある医学雑誌の編集長をしていました。紙の雑誌の編集長じゃなくなったのは2007年なので18年も前のこと。その雑誌自体ももうないので「昔話」として読んでください。
その雑誌で毎月どの記事がどのくらい読まれたか読者調査をしていました。読者はもちろんすべて医師です。いわばテレビの視聴率調査みたいなものですが、正直あまり良い数字ではありませんでした。
その中で相対的にもっともスコア(と当時呼んでいました)が良かったのが、クイズでした。練りに練った特集記事よりも、尖った企画記事よりも、連載よりもニュースよりもたいていクイズのスコアが一番高かった。
患者背景、主訴、時に検査データとともにX線写真やCT画像、心電図、皮膚所見などを提示し、読者に診断してもらう。奇数ページに一面ドーンと画像などが載っていて、裏の偶数ページに解答と解説がある。クイズといっても極めて医学的で教育的なものでした。
この手法は、インターネット時代になっても人気があるようです。いや、むしろ今はもっともコモンな医学教育の形の1つといえるかもしれません。たとえばNEJMのWebサイトでは、「IMAGE CHALLENGE」というコーナーで日替わりでそんな“クイズ”を掲載しています。先生方はその問題になんとなくチャレンジし、嬉々としてSNSに投稿したりしています。
変わったなあと思うと同時に変わらないなあと思います。
「Dr.金井のCTクイズ」は、つまるところ僕の雑誌時代の人気企画をそのまま動画化した番組です。想定通り視聴者からの評判はよく、CareNeTVの人気番組の1つになりました。
それはそれでよかったのですが、実は、僕の13年のCareNeTVでの動画制作の経験の中で、この番組ほど制作に時間がかかったものはありません。
「Dr.金井のCTクイズ 初級編」がリリースされたのは2021年4月ですが、僕が金井先生に最初にこの企画を提案しに行ったのは、メールを遡ると2018年6月です。企画提案から日の目を見るまで3年近くかかっています。
しかも、その時点から「初級編」「中級編」「上級編」を制作することが決まっており、構成も固めていました。しかし、その「上級編」の第1回がリリースされたのが今年の8月(スターウォーズじゃないんだから…)。
その間、コロナパンデミックが起こったなどさまざまな原因があるのですが、一番の問題は、最初ともかく画像データの扱い方がわかっていなかったこと。当時のシステム環境もありますが、大容量DICOMデータのどれがキー画像かわからないし、変換し動画化しようとしてスタックしたりと、作業が一向に進まない。また、アニメーションの女性医師キャラクターを作ってナレーターにしゃべらせたりと、演出も凝りすぎましたね。反省しています。
そんな裏話はさておき、「Dr.金井のCTクイズ 初級編」はリリースから5年を過ぎた今も、多くのCT画像初学者の若い先生方に見られています。今チェックしてみると、今月の視聴ランキングでも多くの新作の中で堂々の第12位!
医学画像クイズのニーズは今も昔不変なのです。