
Dr.國松とDr.ヤンデルの『また来たくなる外来』トーク ~コロナ禍でもうまくやる外来ノウハウ(全1回)
配信中の番組
Dr.國松とDr.ヤンデルの『また来たくなる外来』トーク プレミアム対象
-
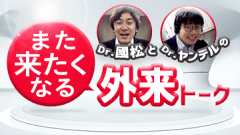
- 2020/07/08(水)公開
- 72分26秒
<無料公開は終了しました>
金原出版より発行されている國松淳和先生著『また来たくなる外来』をベースに、Dr.國松とDr.ヤンデルの奇才ドクター2人が、患者さんがまた来たいと思う外来診療に求められる医師の基本姿勢などを語り合います。
『また来たくなる外来』は、新型コロナ以前に出版されたもので、現在の状況を想定して書かれたわけではありませんが、患者さんに、質の高い、満足度の高い外来診療を提供するためのノウハウが満載で、医療機関が患者減に悩む今、とてもタイムリーな内容となっています。
医師、医療者の方々が患者さんと向き合っていくうえでのヒントが得られる対談です。
評価一覧
30代
勤務医
内科
専門性に特化した医師、現役の信念バリバリのまっすぐタイプな医師には見ても話が入らないかと思います。ある程度の熟練した医師には視聴おすすめです。
30代
勤務医
呼吸器内科
参考ならん
30代
勤務医
内科
色んな科、シチュエーションによって話が違ってくるのではないかと感じた。長い・・かな。
60代
開業医
整形外科
非常に役立つ
60代
勤務医
小児科
示唆に富む話ですね。
関連シリーズ
-
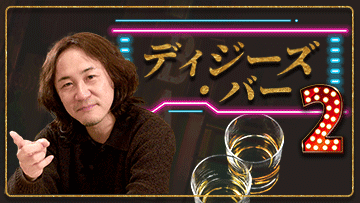
ディジーズ・バー2(全10回) 2022/11/30(水)~
「ディジーズ・バー」が2年ぶりにリニューアルオープンしました。 内科医・國松淳和と彼と親交の深い医師との間で、今回もさまざまな疾患の治療について腹を割った対話が繰り広げられます。
日々の臨床現場で出合うさまざまな内科疾患。診断はついてもガイドライン通りに処方すれば治るわけではない。ほかの医師は一つひとつ異なる症例にどのような治療戦略を立て、実際に治療しているんだろう?医師であれば誰しもそんな疑問を感じたことがあるでしょう。
コモンな内科疾患の治療のさじ加減、コロナ前後の臨床現場の変化など、スキルの高い医師同士が、同じ臨床医の目線で自由に語り合います。
尽きることのない奥深い臨床談義をグラス片手にお楽しみください。
第1回 市中肺炎(COVID-19含む)
第2回 梅毒
第3回 糖尿病の非薬物療法
第4回 アルコール・ニコチン依存
第5回 小児の解熱
第6回 起立性調節障害
第7回 かぜ(コロナ後どうしてる?)
第8回 偽痛風
第9回 高血圧症
第10回 脂質異常症 -
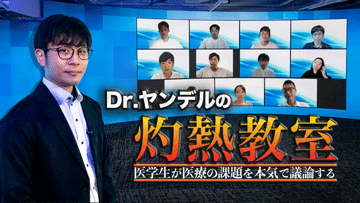
Dr.ヤンデルの灼熱教室(全3回) 2022/10/12(水)~
ハーバード大学教授 マイケル・サンデルによるあの番組の医療版がCareNeTVに! Twitterで病理医ヤンデル(@Dr_yandel)としてもおなじみの市原真先生のファシリテートのもと、現役医学生が現在のさまざまな医療の課題を大真面目に熱く討論します。
未来の日本の医療を担う医学生たちは、現在の医療の課題をどう考え、どうすれば解決できると考えているのか?本家サンデル顔負けのDr.ヤンデルの巧みな進行で、今どきの若者の思考、価値観を浮き彫りにし、ユニークな発想を引き出していきます。
さて、Dr.ヤンデル×フレッシュな10人の頭脳は、答えがない課題に解決の道筋を見つけることができるのでしょうか?
第1回 地域医療
第2回 感染症
第3回 医師の給与 -

ディジーズ・バー(全10回) 2021/03/03(水)~
都内某所にひっそりと佇む「ディジーズ・バー」。ここでは夜な夜な、内科医・國松淳和と彼と親交の深い医師との間でさまざまな疾患の治療について、腹を割った対話が繰り広げられる・・・
日々の臨床現場で出合うさまざまな内科疾患。診断はついてもガイドライン通りに処方すれば治るわけではない。
ほかの医師は一つひとつ異なる症例にどのような治療戦略を立て、実際に治療しているんだろう?医師であれば誰しもそんな疑問を感じたことがあるでしょう。
この番組では、コモンな内科疾患の治療のさじ加減について、スキルの高い医師同士が、同じ臨床医の目線で自由に語り合います。
今宵は、どんな医師が訪れ、どんな臨床談義に花が咲くのか・・・
※この番組は2020年1月~2月に収録したものです
第1回 機能性ディスペプシア(FD)
第2回 過敏性腸症候群(IBS)
第3回 誤嚥性肺炎1
第4回 誤嚥性肺炎2
第5回 高齢者の不定愁訴
第6回 困った精神神経症状
第7回 コモンな感染症
第8回 痛みを伴うコモンディジーズ
第9回 内科で診る不定愁訴
第10回 精神科に紹介すべき身体症状 -

Dr.國松とDr.ヤンデルの大真面目コロナトーク【2020年4月28日配信アーカイブ】(全1回) 2020/04/28(火)~
【無料公開中】
新型コロナウイルス感染拡大により政府から緊急事態宣言が出され、国民は外出などの行動を大きく制限される一方、テレビやSNSからの玉石混淆の情報にさらされ、精神的に不安定になる方も見受けられます。この環境下でいかに平常心を保って生きていくか。南多摩病院 総合内科の國松淳和先生と、Dr.ヤンデルこと札幌厚生病院病理診断科の市原真先生の2人の奇才ドクターが、國松先生が「CIAMS(シャムズ)」と名付けた“コロナ現象”を読み解き処方箋を示します。
ケアネットとメディカルノートの共同企画です。
/ でも無料でご覧いただけます
Dr.國松とDr.ヤンデルの大真面目コロナトーク -

国立国際医療研究センター総合診療科presents 内科インテンシブレビュー2017(全12回) 2017/04/12(水)~
2017年1月14~15日の2日間にわたって開催された集中型セミナー「国立国際医療研究センター総合診療科 presents内科インテンシブレビュー」。CareNeTV出演の講師も含めた、12医師の熱いレクチャーを一挙公開します。「学生・初期研修医向け」のレクチャーに飽きてしまった専門後期研修医、これを機に知識をアップデートしたいシニア医師、ちょっと背伸びしたい初期研修医の方々、国立国際医療研究センター病院総合診療科ほか有名講師による集中講義を堪能してください!
第1回 リンパ腫の臨床診断 “Internist's lymphoma”
第2回 パーキンソン病の話
第3回 大血管炎〜IgG4関連疾患も含めて〜
第4回 Young Doctor’s Case Report
第5回 感染症診療のロジック~常に丹念に病態を詰め切る~
第6回 呼吸器内科医から見た心不全
第7回 小腸疾患 Update 2017
第8回 NEJMへの道~2017 飛翔編~
第9回 陰性感情を考える
第10回 つつが虫病 シマからみる、シマでみる ~過去と現在、日本、沖縄、世界に眼をむけて~
第11回 低K血症をスッキリ理解する Keep It Simple, Stupid.
第12回 “元気で長生き”を維持するために 科学的根拠に基づくヘルスメンテナンス -

フィーバー國松の不明熱コンサルト(全8回) 2015/10/14(水)~
循環器、消化器、呼吸器…どんな臓器の専門医でも日々の専門診療のなかでなかなか原因が突き止められない「熱」に直面することがあります。そんな専門医が抱える不明熱を「熱」のスペシャリスト・フィーバー國松が徹底分析。各科で遭遇しやすいキホンの熱から、検査ではわからない困った熱まで、不明熱の鑑別方法、対処法を詳しく解説します。 国立国際医療研究センター病院で不明熱外来を担う國松淳和先生は、各科からさまざまな不明熱のコンサルトを受け、日々、その発熱の原因究明に挑んでいます。『フィーバー國松の不明熱コンサルト』で取り上げるのは、循環器、消化器、呼吸器、腎臓、血液、神経、膠原病、感染症の8領域。「熱」に自信を持って立ち向かえる!発熱診療の強力な手がかりをお届けします!
第1回 循環器内科「パパッとエコーでわからないもの」
第2回 消化器内科「内視鏡、やってみたけど」
第3回 呼吸器内科「肺は大丈夫だけど、苦しい」
第4回 腎臓内科「腎臓がやられているというだけで…」
第5回 血液内科「骨髄検査は正常です」
第6回 神経内科「答えは脳ではない」
第7回 膠原病内科「それでもスティル病とは言えない」
第8回 感染症内科「ほかに何があるでしょうか?」

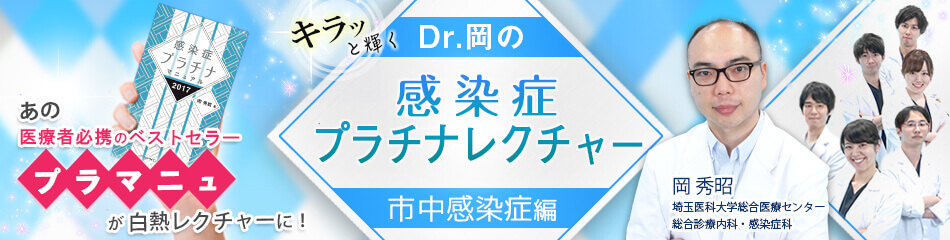
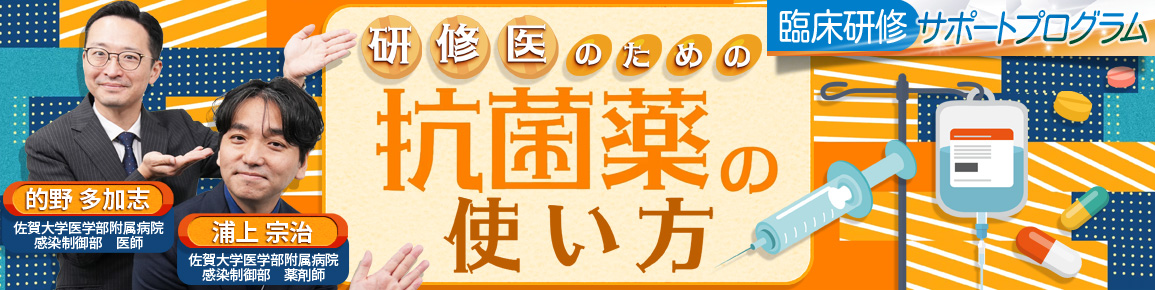




金原出版より発行されている國松淳和先生著『また来たくなる外来』をベースに、Dr.國松とDr.ヤンデルの奇才ドクター2人が、患者さんがまた来たいと思う外来診療に求められる医師の基本姿勢などを語り合います。 『また来たくなる外来』は、新型コロナ以前に出版されたもので、現在の状況を想定して書かれたわけではありませんが、患者さんに、質の高い、満足度の高い外来診療を提供するためのノウハウが満載で、医療機関が患者減に悩む今、とてもタイムリーな内容となっています。 医師、医療者の方々が患者さんと向き合っていくうえでのヒントが得られる対談です。