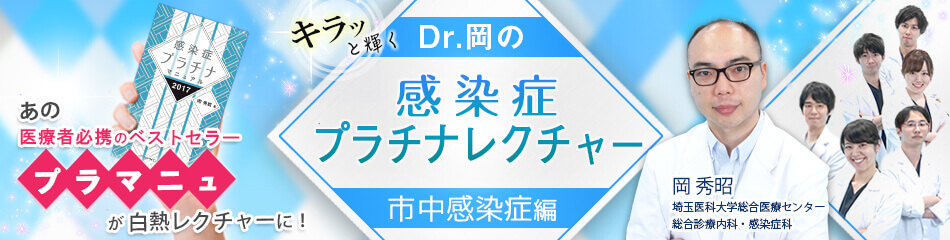外科の番組検索結果
-
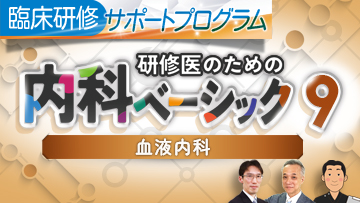 研修医のための内科ベーシック9 血液内科(全10回)第7回 白血球3 白血球減少症2023/04/01(土)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長白血球減少症の原因は、産生低下と破壊亢進の2つ。そのため、通常、問診や診察で簡単に判断できます。 すなわち白血球減少症では、鑑別よりも、マネジメントが問題となります。 その中でもとくに重要な発熱性好中球減少症について詳しく解説します。 Dr.田中和豊式フローチャートに沿って対応できるように理解を深めましょう。
研修医のための内科ベーシック9 血液内科(全10回)第7回 白血球3 白血球減少症2023/04/01(土)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長白血球減少症の原因は、産生低下と破壊亢進の2つ。そのため、通常、問診や診察で簡単に判断できます。 すなわち白血球減少症では、鑑別よりも、マネジメントが問題となります。 その中でもとくに重要な発熱性好中球減少症について詳しく解説します。 Dr.田中和豊式フローチャートに沿って対応できるように理解を深めましょう。
この番組のオリジナ... -
 脳血管内治療STANDARD(全10回)第9回 頭蓋内動脈狭窄症2020/05/31(日)公開 吉村 紳一 兵庫医科大学脳神経外科学講座 主任教授頭蓋内動脈高度狭窄症によって脳虚血発作を来した場合に、ステントを用いた血管拡張術が行われることがありますが、本治療は血圧低下や脂質低下などの積極的内科治療に対する優位性が証明されていません。このため、内科治療抵抗例などの限定的な状況で行われていることに注意してください。この回では、その治療の実際と注意点について解説します。
脳血管内治療STANDARD(全10回)第9回 頭蓋内動脈狭窄症2020/05/31(日)公開 吉村 紳一 兵庫医科大学脳神経外科学講座 主任教授頭蓋内動脈高度狭窄症によって脳虚血発作を来した場合に、ステントを用いた血管拡張術が行われることがありますが、本治療は血圧低下や脂質低下などの積極的内科治療に対する優位性が証明されていません。このため、内科治療抵抗例などの限定的な状況で行われていることに注意してください。この回では、その治療の実際と注意点について解説します。 -
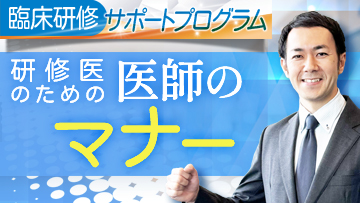 研修医のための医師のマナー(全10回)第7回 患者・家族との接し方2024/08/29(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科今回は患者や、その家族との接するときのマナーについて考えていきましょう。患者や家族の医療に対する満足度は、もちろん治療内容や、結果に大きく影響することは言うまでもありません。しかしながら、医師を含む医療スタッフの対応により、その満足度はプラスにもマイナスにも大きく変化するものであることを覚えておきましょう。
研修医のための医師のマナー(全10回)第7回 患者・家族との接し方2024/08/29(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科今回は患者や、その家族との接するときのマナーについて考えていきましょう。患者や家族の医療に対する満足度は、もちろん治療内容や、結果に大きく影響することは言うまでもありません。しかしながら、医師を含む医療スタッフの対応により、その満足度はプラスにもマイナスにも大きく変化するものであることを覚えておきましょう。 -
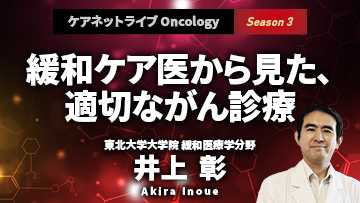 ケアネットライブOncology Season3(全6回)今こそ知っておきたいがん診療と糖尿病2024/07/31(水)公開 大橋 健 国立がん研究センター中央病院 総合内科糖尿病患者の約4割ががんで亡くなる時代――。
ケアネットライブOncology Season3(全6回)今こそ知っておきたいがん診療と糖尿病2024/07/31(水)公開 大橋 健 国立がん研究センター中央病院 総合内科糖尿病患者の約4割ががんで亡くなる時代――。
日本ではがん患者の約2割が糖尿病を併存し、糖尿病患者の約4割ががんで亡くなるなど両者の関係は切っても切れないものになっています。さらに、糖尿病患者は肝がん、膵がんなど、糖尿病に関わる臓器のがんに罹患する人の割合が高くなるといった特徴もあります。
国立がん研究センター... -
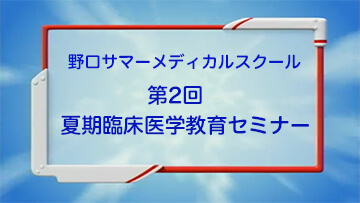 野口サマーメディカルスクール 第2回 夏期臨床医学教育セミナー(全8回)第3回 Case Study Sessions【外科】黄疸2011/11/22(火)公開 星 寿和 アイオワ大学 外科、腫瘍外科部門 助教授黄疸(Jaundics)は比較的まれな症状であるものの、その鑑別診断は多岐にわたり、詳細な病歴と身体所見、必要十分な血液、画像診断検査が正診に至る鍵である。このセッションでは病態生理に基づいた黄疸の鑑別診断、治療についてディスカッションを行う。 学習目的 1)主訴より鑑別診断考えながら必要な問診を行うことができる。 2)黄疸の鑑別を考えた診...
野口サマーメディカルスクール 第2回 夏期臨床医学教育セミナー(全8回)第3回 Case Study Sessions【外科】黄疸2011/11/22(火)公開 星 寿和 アイオワ大学 外科、腫瘍外科部門 助教授黄疸(Jaundics)は比較的まれな症状であるものの、その鑑別診断は多岐にわたり、詳細な病歴と身体所見、必要十分な血液、画像診断検査が正診に至る鍵である。このセッションでは病態生理に基づいた黄疸の鑑別診断、治療についてディスカッションを行う。 学習目的 1)主訴より鑑別診断考えながら必要な問診を行うことができる。 2)黄疸の鑑別を考えた診... -
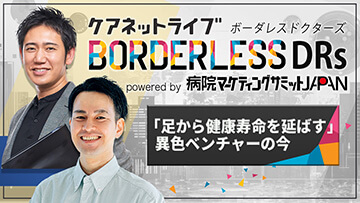 ケアネットライブBORDERLESS DRs powered by 病院マーケティングサミットJAPAN(全6回)第1回 途上国支援の現実と未来への挑戦2025/01/29(水)公開 竹田 陽介 病院マーケティングサミットJAPAN代表理事・カルチュラルエンジニア第1回は、医療にとどまらない“生きるための”途上国支援を続ける呼吸器外科医の大類隼人先生が登場。認定NPO法人Future Code理事長としてハイチ、バングラデシュ、ブルキナファソで人道支援活動を行う大類先生。日本で働く普通の臨床医は、なぜ途上国支援に目覚め、人生をかけるほどのめり込んでいったのか?その魅力と苦難に満ちた体験を生々しく語りま...
ケアネットライブBORDERLESS DRs powered by 病院マーケティングサミットJAPAN(全6回)第1回 途上国支援の現実と未来への挑戦2025/01/29(水)公開 竹田 陽介 病院マーケティングサミットJAPAN代表理事・カルチュラルエンジニア第1回は、医療にとどまらない“生きるための”途上国支援を続ける呼吸器外科医の大類隼人先生が登場。認定NPO法人Future Code理事長としてハイチ、バングラデシュ、ブルキナファソで人道支援活動を行う大類先生。日本で働く普通の臨床医は、なぜ途上国支援に目覚め、人生をかけるほどのめり込んでいったのか?その魅力と苦難に満ちた体験を生々しく語りま... -
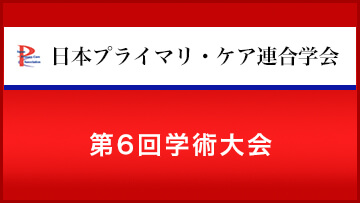 日本プライマリ・ケア連合学会 第6回 学術大会 (全12回)第12回 総合医に求められるスポーツ医学とは2015/11/18(水)公開 山本 明希 金沢医科大学医学部 病理学Ⅰ清川研究室スポーツ医学というと、整形外科医のイメージが強いですが、総合医が活躍すべき場面がたくさんあります。
日本プライマリ・ケア連合学会 第6回 学術大会 (全12回)第12回 総合医に求められるスポーツ医学とは2015/11/18(水)公開 山本 明希 金沢医科大学医学部 病理学Ⅰ清川研究室スポーツ医学というと、整形外科医のイメージが強いですが、総合医が活躍すべき場面がたくさんあります。
第6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会での本シンポジウムでは、水戸協同病院の小林裕幸先生、シムラ病院整形外科の池尻好聰先生、元オリンピック代表選手の為末大氏、金沢医科大学医学部の山本明希氏が、スポーツ医学において総合医に... -
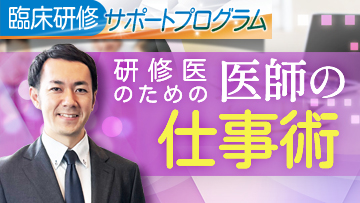 研修医のための医師の仕事術(全10回)第10回 生涯学習のすすめ2024/09/19(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科最終回は、生涯学習についてです。医学は常に進歩し続けています。5年前に習得した知識がすでに使えなくなっていることもまれではありません。そのため医師は、常に学習し続けていかなければならないのです。そんな生涯学習を続けるためのポイントをお教えします。ちょっとしたことを積み貸せ寝ることで、生涯学習を続けていくことができます。
研修医のための医師の仕事術(全10回)第10回 生涯学習のすすめ2024/09/19(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科最終回は、生涯学習についてです。医学は常に進歩し続けています。5年前に習得した知識がすでに使えなくなっていることもまれではありません。そのため医師は、常に学習し続けていかなければならないのです。そんな生涯学習を続けるためのポイントをお教えします。ちょっとしたことを積み貸せ寝ることで、生涯学習を続けていくことができます。 -
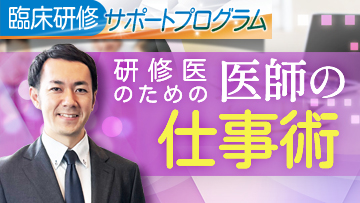 研修医のための医師の仕事術(全10回)第9回 将来のキャリア選択2024/09/19(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科自分の将来のキャリアについてどのように考えていますか?研修医として医師としての仕事を始めたことのより、学生時代に描いていたものと異なる選択肢が増えた人も多いのではないでしょうか。 専門科や、勤務先、海外留学や研究職などキャリアの選択肢は多種多様です。そんななか、どのようにキャリアを選択していくのか。そのために必要な考え方につ...
研修医のための医師の仕事術(全10回)第9回 将来のキャリア選択2024/09/19(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科自分の将来のキャリアについてどのように考えていますか?研修医として医師としての仕事を始めたことのより、学生時代に描いていたものと異なる選択肢が増えた人も多いのではないでしょうか。 専門科や、勤務先、海外留学や研究職などキャリアの選択肢は多種多様です。そんななか、どのようにキャリアを選択していくのか。そのために必要な考え方につ... -
 急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第6回 ガイディングカテーテルの誘導2021/10/06(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...主に大腿動脈からアプローチする場合のガイディングカテーテル誘導についてディスカッションします。 まず基本でありとても重要な点は「胸部のワーキングアングルを少し左側に振る」こと。そうすることで、動脈の分岐点が圧倒的に見えやすくなることは、図解で一目瞭然です。 そのほか、鋭角な血管の分岐点でガイディングカテーテルを上げていくとき...
急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第6回 ガイディングカテーテルの誘導2021/10/06(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...主に大腿動脈からアプローチする場合のガイディングカテーテル誘導についてディスカッションします。 まず基本でありとても重要な点は「胸部のワーキングアングルを少し左側に振る」こと。そうすることで、動脈の分岐点が圧倒的に見えやすくなることは、図解で一目瞭然です。 そのほか、鋭角な血管の分岐点でガイディングカテーテルを上げていくとき... -
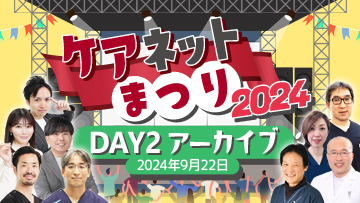 ケアネットまつり2024 DAY 2 アーカイブ【2024年9月22日】(全9回)7. Dr.増井の骨折ハンティングクイズ2024/09/30(月)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長増井 伸高先生(札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長)
ケアネットまつり2024 DAY 2 アーカイブ【2024年9月22日】(全9回)7. Dr.増井の骨折ハンティングクイズ2024/09/30(月)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長増井 伸高先生(札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長)
ハンティングシリーズでおなじみの増井伸高先生が今年は骨折読影クイズで登場! 非整形外科医が即座に判断できないビミョーな骨のX線を厳選し、クイズとして出題します。 出題されるX線画像を、骨折線をイメージしながら読影していきましょう。 解答提示後は、増井先生に... -
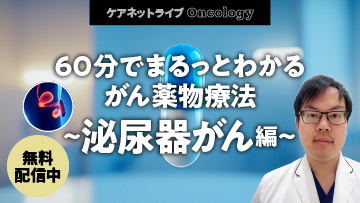 ケアネットライブOncology(全6回)60分でまるっとわかる がん薬物療法 ~乳がん編~2025/08/27(水)公開 能澤 一樹 名古屋市立大学 臨床研究戰略部 特任講師乳がんは診断時点で約9割が早期がんです。早期がんは、手術可能ながんとして、手術、抗がん剤治療などの薬物療法、放射線治療などを組みわせて行います。おおよそ10年の経過の中で再発をしなければ治癒に至りますが、残念ながら2~5割は再発し、薬物療法を中心とした治療を継続して行うことになります。
ケアネットライブOncology(全6回)60分でまるっとわかる がん薬物療法 ~乳がん編~2025/08/27(水)公開 能澤 一樹 名古屋市立大学 臨床研究戰略部 特任講師乳がんは診断時点で約9割が早期がんです。早期がんは、手術可能ながんとして、手術、抗がん剤治療などの薬物療法、放射線治療などを組みわせて行います。おおよそ10年の経過の中で再発をしなければ治癒に至りますが、残念ながら2~5割は再発し、薬物療法を中心とした治療を継続して行うことになります。
乳がんは近年薬剤の開発が目覚ましく... -
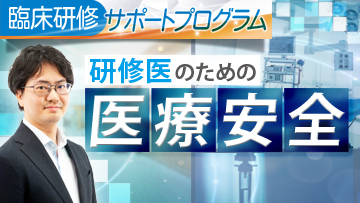 研修医のための医療安全(全10回)第2回 インシデントレポートの意義2024/07/04(木)公開 栗原 健 名古屋大学医学部附属病院 患者安全推進部 病院助教インシデントレポートを反省文や始末書だと思っていませんか? そうではありません!インシデントレポートは原則として無記名非公開。匿名性が保たれた、今後の事故を防ぐための重要な活動です。 今回は、医師がインシデントレポートを書くことのメリット、そして具体的な書き方のコツを解説します。
研修医のための医療安全(全10回)第2回 インシデントレポートの意義2024/07/04(木)公開 栗原 健 名古屋大学医学部附属病院 患者安全推進部 病院助教インシデントレポートを反省文や始末書だと思っていませんか? そうではありません!インシデントレポートは原則として無記名非公開。匿名性が保たれた、今後の事故を防ぐための重要な活動です。 今回は、医師がインシデントレポートを書くことのメリット、そして具体的な書き方のコツを解説します。 -
 急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第2回 M2閉塞へのアプローチ2021/07/21(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...M2閉塞における血栓回収療法は、複数のRCTのメタ解析やコホート研究で有効であったと報告されており、適応が広がりつつあります。しかし一方で、脳出血の発生率を上昇させるとの報告もあり、M2閉塞に血栓回収療法を行う際には安全性の確保が重要です。 M2閉塞をいかに安全に開通させるか、そのポイントとして挙げたPass回数、M1の屈曲度、血管径に合っ...
急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第2回 M2閉塞へのアプローチ2021/07/21(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...M2閉塞における血栓回収療法は、複数のRCTのメタ解析やコホート研究で有効であったと報告されており、適応が広がりつつあります。しかし一方で、脳出血の発生率を上昇させるとの報告もあり、M2閉塞に血栓回収療法を行う際には安全性の確保が重要です。 M2閉塞をいかに安全に開通させるか、そのポイントとして挙げたPass回数、M1の屈曲度、血管径に合っ... -
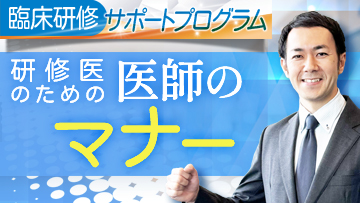 研修医のための医師のマナー(全10回)第9回 エレベーター・院内での歩き方2024/09/12(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科今回は病院内での行動について考えていきましょう。エレベーターやエスカレーターにのるとき、廊下を歩くとき、患者は常に医療者のことを見ています。忙しく周りを見る余裕がないこともあるかもしれませんが、そんなときこそ、ちょっとした気配りが大切です。どのようにふるまえばよいのかをしっかりと認識しておきましょう。
研修医のための医師のマナー(全10回)第9回 エレベーター・院内での歩き方2024/09/12(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科今回は病院内での行動について考えていきましょう。エレベーターやエスカレーターにのるとき、廊下を歩くとき、患者は常に医療者のことを見ています。忙しく周りを見る余裕がないこともあるかもしれませんが、そんなときこそ、ちょっとした気配りが大切です。どのようにふるまえばよいのかをしっかりと認識しておきましょう。 -
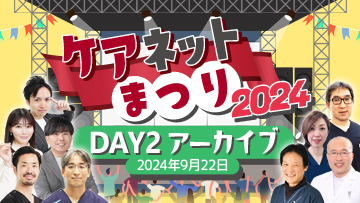 ケアネットまつり2024 DAY 2 アーカイブ【2024年9月22日】(全9回)1. 看護師集合!下痢から学ぶIn-Outとアセスメント2024/09/30(月)公開 青木 瑞智子 国立循環器病研究センター 診療看護師(NP)血管外科 / クリティカルケア認定看護師青木 瑞智子先生(済生会宇都宮病院 心臓血管外科 診療看護師 クリティカルケア認定看護師)
ケアネットまつり2024 DAY 2 アーカイブ【2024年9月22日】(全9回)1. 看護師集合!下痢から学ぶIn-Outとアセスメント2024/09/30(月)公開 青木 瑞智子 国立循環器病研究センター 診療看護師(NP)血管外科 / クリティカルケア認定看護師青木 瑞智子先生(済生会宇都宮病院 心臓血管外科 診療看護師 クリティカルケア認定看護師)
看護師にとってIn-Outは必須知識。だけど、多忙すぎる勤務のなかではアセスメントまでできずに、「終わらせなきゃいけないタスク」となってしまっていませんか? 今回は急性期だけでなく、在宅や一般病棟でもよく遭遇する「下痢」症例をベースに、体... -
 急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第3回 ADAPT:血栓吸引術2021/08/18(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...吸引カテーテルを血栓の近くまで挿入して血栓を直接吸引するこの術式では、ICA(内頸動脈)のサイフォン部と言われる折れ曲がった部位へのアプローチが困難でしたが、Penumbraカテーテルの導入によりかなり容易になりました。 血栓吸引術の強みは「血栓手前で勝負できる」ことと今井先生は語ります。その強みを最大限に活かすためにも、吸引カテーテル...
急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第3回 ADAPT:血栓吸引術2021/08/18(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...吸引カテーテルを血栓の近くまで挿入して血栓を直接吸引するこの術式では、ICA(内頸動脈)のサイフォン部と言われる折れ曲がった部位へのアプローチが困難でしたが、Penumbraカテーテルの導入によりかなり容易になりました。 血栓吸引術の強みは「血栓手前で勝負できる」ことと今井先生は語ります。その強みを最大限に活かすためにも、吸引カテーテル... -
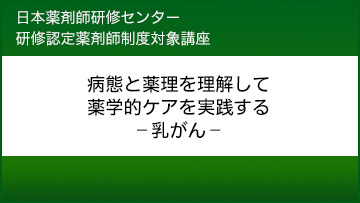 (JPEC研修) 病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-乳がん-(全4回)第3回 乳がん患者に対する保険薬局薬剤師の関わりについて2023/11/01(水)公開 下川 友香理 総合メディカル株式会社 執行役員/薬局事業本部 学術情報部長【日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度対象講座】
(JPEC研修) 病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-乳がん-(全4回)第3回 乳がん患者に対する保険薬局薬剤師の関わりについて2023/11/01(水)公開 下川 友香理 総合メディカル株式会社 執行役員/薬局事業本部 学術情報部長【日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度対象講座】
保険薬局クリニカルパス、薬局薬剤師ができること、模擬処方箋での実践について、総合メディカル株式会社の下川 友香里 氏が解説します。 -
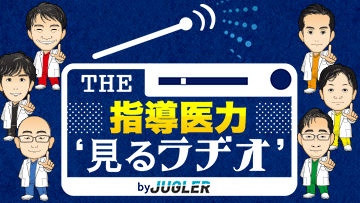 THE指導医力“見るラヂオ”by JUGLER(全12回)第5回 ブランディング2022/07/11(月)公開 和足 孝之 島根大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター新スタイルケアネットライブ「THE指導医力“見るラヂオ” by JUGLER」のアーカイブ配信です。 第5回は「ブランディング」。『JUGLERブック 若手指導医1年目の教科書』 では、Chapter16「ステークホルダーを見据えて組織の強みを最大化する!」 にあたるテーマです。ブランディング力とは何か、医療分野でのブランディングの重要性などについて体験談を...
THE指導医力“見るラヂオ”by JUGLER(全12回)第5回 ブランディング2022/07/11(月)公開 和足 孝之 島根大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター新スタイルケアネットライブ「THE指導医力“見るラヂオ” by JUGLER」のアーカイブ配信です。 第5回は「ブランディング」。『JUGLERブック 若手指導医1年目の教科書』 では、Chapter16「ステークホルダーを見据えて組織の強みを最大化する!」 にあたるテーマです。ブランディング力とは何か、医療分野でのブランディングの重要性などについて体験談を... -
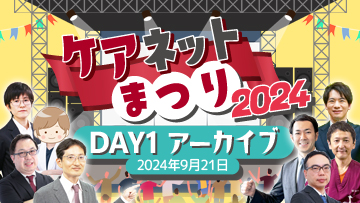 ケアネットまつり2024 DAY 1 アーカイブ【2024年9月21日】(全8回)3. 若手医師のためのマナーと仕事術2024/09/23(月)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科松尾 貴公先生(メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科)
ケアネットまつり2024 DAY 1 アーカイブ【2024年9月21日】(全8回)3. 若手医師のためのマナーと仕事術2024/09/23(月)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科松尾 貴公先生(メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科)
2024年4月にCareNeTVに「臨床研修サポートプログラム」がオープンしました。 臨床研修2年間で身につけるべき必要十分な知識・スキルをいつでも動画で学ぶことができるプログラムを取りそろえたものです。その中で「医師のマナー」、「仕事術」について解説した松尾貴公... -
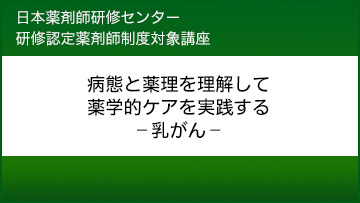 (JPEC研修) 病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-乳がん-(全4回)第4回 がんについての基礎知識、がん治療の学び方2023/11/01(水)公開 髙橋 郷 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 薬剤部【日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度対象講座】
(JPEC研修) 病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-乳がん-(全4回)第4回 がんについての基礎知識、がん治療の学び方2023/11/01(水)公開 髙橋 郷 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 薬剤部【日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度対象講座】
治療方針が決まるまでの流れ、ガイドラインの活用、ガイドラインの適応範囲について、国立国際医療研究センター国府台病院 薬剤部の高橋 郷 氏が解説します。 -
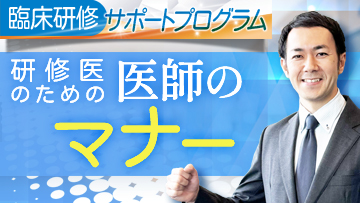 研修医のための医師のマナー(全10回)第8回 時間を守る2024/08/29(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科時間を守らないことで、自分自身や相手に対してどのようなマイナスな影響を与えるのかなどをしっかりと考え、時間を守ることの重要さについて一緒に考えていきましょう。 また別シリーズ“研修医のための医師の仕事術”において、時間管理術についても解説しています。合わせてご覧いただき、「時間を大切にする」ことをしっかりと考えてみてください。
研修医のための医師のマナー(全10回)第8回 時間を守る2024/08/29(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科時間を守らないことで、自分自身や相手に対してどのようなマイナスな影響を与えるのかなどをしっかりと考え、時間を守ることの重要さについて一緒に考えていきましょう。 また別シリーズ“研修医のための医師の仕事術”において、時間管理術についても解説しています。合わせてご覧いただき、「時間を大切にする」ことをしっかりと考えてみてください。 -
 急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第4回 ATBI:動脈硬化性病変2021/09/01(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...動脈硬化性病変は、狭窄部位の前後に多量の血栓が形成されるもの、 心原性塞栓が狭窄部位で引っ掛かるもの、さらには塞栓症のみの場合などがあり、 造影画像だけでは鑑別が難しく治療方針が立てづらい病変です。 血栓除去か、狭窄を広げる術式か、迷ったときには血栓回収術を優先したいという点は、今井先生も奥村先生も同意見。 塞栓症か狭窄...
急性脳梗塞・血栓回収療法マニアックトーク2(全6回)第4回 ATBI:動脈硬化性病変2021/09/01(水)公開 奥村 浩隆 佐々総合病院脳神経外科 脳神経血管内治療担当医 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科...動脈硬化性病変は、狭窄部位の前後に多量の血栓が形成されるもの、 心原性塞栓が狭窄部位で引っ掛かるもの、さらには塞栓症のみの場合などがあり、 造影画像だけでは鑑別が難しく治療方針が立てづらい病変です。 血栓除去か、狭窄を広げる術式か、迷ったときには血栓回収術を優先したいという点は、今井先生も奥村先生も同意見。 塞栓症か狭窄... -
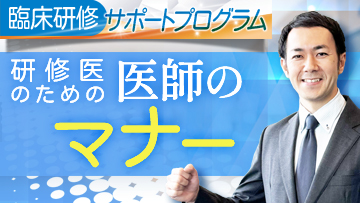 研修医のための医師のマナー(全10回)第10回 カンファレンス参加の心得2024/09/12(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科医師のマナー最終回は、カンファレンスに参加するときの心得について。カンファレンスは自分が直接経験していなくても、類似体験をすることのできる貴重な学習機会です。そのときの自分の行動が医師としての成長にかかわってくるということを知っておきましょう。そのうえで、どうすべきかを一緒に考えていきましょう。
研修医のための医師のマナー(全10回)第10回 カンファレンス参加の心得2024/09/12(木)公開 松尾 貴公 メイヨークリニック 感染症科/聖路加国際病院 感染症科医師のマナー最終回は、カンファレンスに参加するときの心得について。カンファレンスは自分が直接経験していなくても、類似体験をすることのできる貴重な学習機会です。そのときの自分の行動が医師としての成長にかかわってくるということを知っておきましょう。そのうえで、どうすべきかを一緒に考えていきましょう。