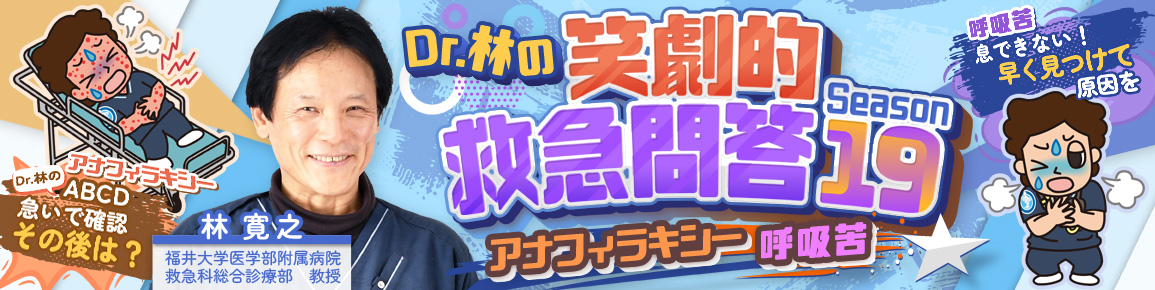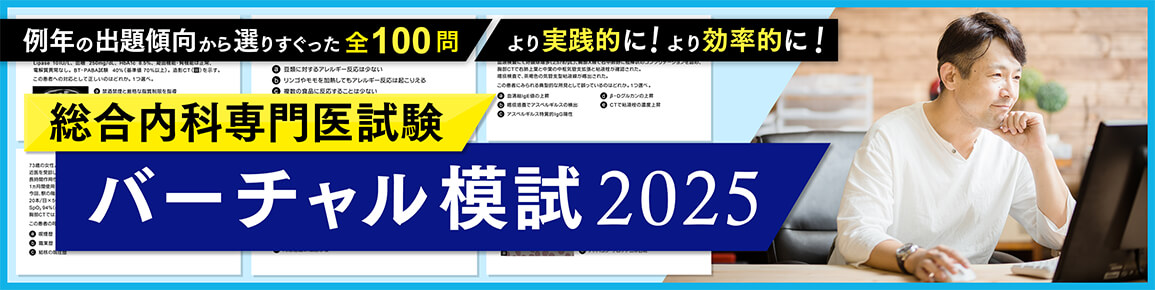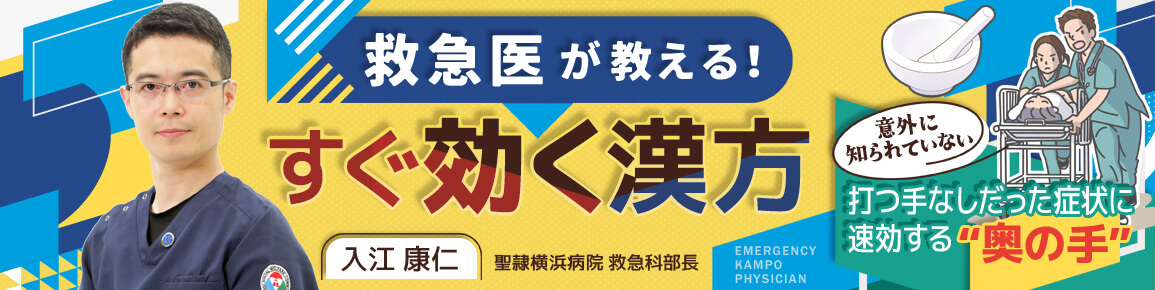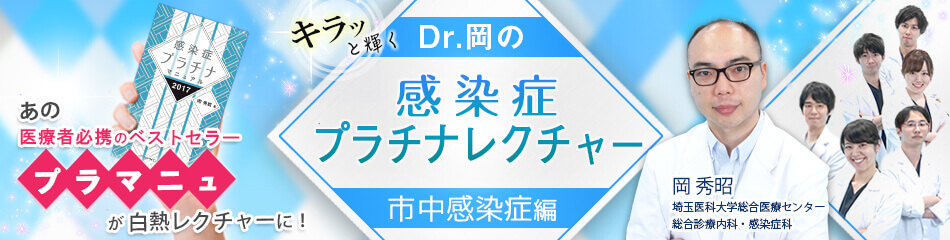講師情報:香坂 俊(こうさか しゅん)
各講師の出演しているシリーズを見ることができます。
香坂 俊(こうさか しゅん)
慶應義塾大学 循環器内科 准教授
慶應義塾大学卒業。1999年から10年ほど米国にて内科、循環器内科の臨床業務に従事。 2008年に帰国し、医学教育や臨床研究に携わる。 著書に『極論で語る循環器内科』(丸善出版)、『もしも心電図が小学校の必修科目だったら』(医学書院)、『循環器急性期診療』(MEDSI)、『みんなで解決!病棟のギモン 研修医のリアルな質問に答えます』(羊土社)ほか。

出演シリーズ
-
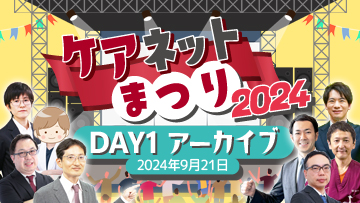
ケアネットまつり2024 DAY 1 アーカイブ【2024年9月21日】(全8回) 2024/09/30(月)~
『ケアネットまつり2024』は、2024年9月21日、22日に開催したオンラインLIVEイベントです。 臨床医学チャンネル「CareNeTV」のスター講師や各種メディアで人気の講師たちの講義を一度にご覧いただけます。研修医、医学生、看護師に向けたプログラムもたっぷりご用意。 レクチャー、クイズ、対談などバラエティ豊かな形式でお届けします。 LIVE配信を見逃してしまった方、もう一度見たい方、そして初めて見る方も、ケアネットならではの学びの価値と楽しさをぜひ体感してください。
※本シリーズは2024年9月21日(土)にオンラインにおいて公開収録されたものです。
1. 医学生お悩み相談ラヂオ おまつりVer.
2. ポチッと参加!第119回国試までのトリセツ
3. 若手医師のためのマナーと仕事術
4. Dr.岡の感染症プラチナレクチャー おまつりVer. ~感染症診療の大原則~
5. Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 おまつりVer.
6. 志水太郎のぶっつけ診断戦略2024
7. Dr.宮垣の消化器内視鏡クイズ
8. イワケン流 勤務医のタイムマネジメント術 -
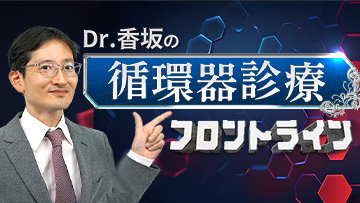
Dr.香坂の循環器診療フロントライン(全9回) 2024/05/30(木)~
2012年にリリースされた「Dr.香坂の循環器診療 最前線!」。当時の最新の診療方法を解説したこの番組から12年。この間に、循環器診療は大きく変わりました。診断や評価、薬の使い方などについて、新たなやり方が見出されており、かつ、新薬も次々と登場しています。数多くの臨床試験も実施され、常にアップデートされ続けている最新のエビデンスをDr.香坂が読み解き、そこから導き出される最善の治療方法を、的確に提示します。要点が刺さるDr.香坂らしいLogicalでありながら、Emotionalな講義。
取り上げる疾患は、急性/慢性心不全をはじめとして高血圧・高脂血症・不整脈・冠疾患・大動脈弁狭窄や僧帽弁逆流症など。また最新のデバイス治療についても触れていきます。
明日からの循環器診療をアップデートしませんか!
第1回 急性心不全(AHF)
第2回 慢性心不全(HF)
第3回 コラム 慢性心不全(HF)について
第4回 急性冠疾患(ACS)
第5回 慢性冠疾患(CCS)
第6回 大動脈弁狭窄(AS)・僧帽弁逆流症(MR)
第7回 高血圧・高脂血症
第8回 不整脈・デバイス治療
第9回 その他の話題 -
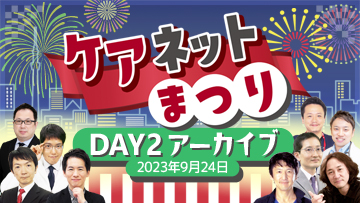
ケアネットまつり DAY 2 アーカイブ【2023年9月24日】(全9回) 2023/10/09(月)~
『ケアネットまつり』は、2023年9月23、24日に開催したオンラインLIVEイベントです。CareNeTVのオールスター講師陣をはじめ、各種メディアで人気の講師がこの日限定の臨床に役立つ講義を披露。レクチャー、クイズ、トークセッションなどバラエティ豊かな形式でお届けします。 LIVE配信を見逃してしまった方、もう一度見たい方、そして初めて見る方も、ケアネットらしさを凝縮したこのイベントの様子をぜひご体感ください。
※本シリーズは2023年9月24日(日)にオンラインにおいて公開収録されたものです。
1. その薬、患者さんは飲んでますか? -うつ病の理解とその診療-
2. 志水太郎のぶっつけ診断戦略
3. 医学生集合!国試までのトリセツ
4. ネッティー先生の読影技術が身につくCTクイズ -ルールを見つければ、画像診断が楽しくなる!-
5. 筒泉貴彦と山田悠史のTHE病棟管理“見るラヂオ”
6. Dr.香坂の循環器治療最前線 おまつりVer.
7. Dr.香坂とDr.岩田の医学教育の未来を本音で語り合う 生トークセッション
8. Dr.岩田の感染症診療の本質
9. Fever國松のコロナ禍で浮き彫りになったシン・不明熱「機能性高体温症」 -

研修医のための内科ベーシック2 循環器内科(全10回) 2023/04/01(土)~
研修医のための内科ベーシック2は循環器内科。遭遇頻度の高い疾患の病態・診断・治療、心電図や心音の基本などについてセレクトしました。短い時間で知りたい情報を得てもらうため、CareNeTVオリジナル番組の映像から、研修医に必要なところをピックアップして再編集。循環器内科を研修する際にお役立てください。
このシリーズで使用した番組のオリジナルはこちら
/ / / / /
第1回 動悸へのアプローチ
第2回 虚血性心疾患を疑うべき典型的胸痛
第3回 脚ブロックの心電図
第4回 ST上昇型心筋梗塞の心電図
第5回 5分で語る心房細動
第6回 心筋梗塞の心エコー所見
第7回 急性冠症候群
第8回 安定狭心症
第9回 心不全
第10回 心臓の解剖生理と心音の関係 -
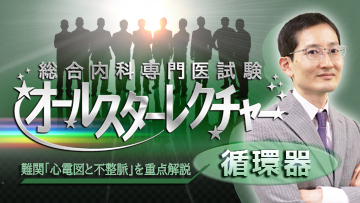
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 循環器(全8回) 2021/02/03(水)~
総合内科専門医試験対策レクチャーの決定版登場!総合内科専門医試験の受験者が一番苦労するのは、自分の専門外の最新トピックス。そこでこのシリーズでは、CareNeTV等で評価の高い内科各領域のトップクラスの専門医11名を招聘。各科専門医の視点で“出そうなトピック”を抽出し、1講義約20分で丁寧に解説します。キャッチアップが大変な近年のガイドラインの改訂や新規薬剤をしっかりカバー。2022年のアップデート情報を追加し、今年の試験対策としても万全です。
循環器については、慶應義塾大学循環器内科の香坂俊先生がレクチャーをします。薬剤とカテーテルインターベンションのどちらも進歩がめざましい循環器。心電図で疾患を素早く見極めるだけでなく、適切な治療を選ぶ力が問われます。
第1回 イントロダクション
第2回 急性冠症候群
第3回 安定狭心症
第4回 末梢動脈疾患・大動脈疾患
第5回 不整脈と心電図(1)
第6回 不整脈と心電図(2)
第7回 心不全・心筋症
第8回 アップデート2022 -

CADET12thセミナー 循環器内科のクスリの使い方(全3回) 2017/10/25(水)~
CADETとはCArDiovascular Education Team の略で香坂俊氏をはじめとする循環器若手医師による若手医師のためのセミナー。双方向式のディスカッションが大きな特徴です。 今回は、2016年10月29日に開催された第12回CADETセミナーの模様をお送りします。テーマは「循環器内科のクスリの使い方」。 循環器内科医の若きスペシャリストたちが、最新の知見を基に薬の使い方についてレクチャー&ディスカッション。 6つのテーマの中から、心不全急性期治療薬、心不全慢性期治療薬、抗不整脈薬の使い方をテーマにした演題をピックアップしました。
当動画を視聴するには が必要となります。
CADETの詳細は
第1回 心不全急性期のクスリ もう騙されません!
第2回 ここは日本! 心不全慢性期のクスリの使い方
第3回 今も必要?抗不整脈薬 -
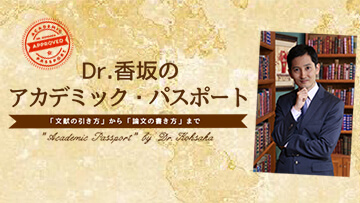
Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回) 2016/08/24(水)~
学術的知見を臨床に、臨床の知見を研究に生かす。そんなアカデミックな医師を目指す方のために、臨床の第一線で活躍しながら、臨床研究のスペシャリストでもあるDr.香坂こと香坂俊先生が道筋を指南します。 広い話題・狭い話題の調べ方、効率的な論文・研究の読み方、そして、学会発表や論文執筆のやり方をシンプルかつ明快にレクチャーします。 臨床が忙しい、現場主義という方に、見てほしい番組です。 さあ、アカデミック・ドクターへの第一歩を踏み出してください。
第1回 「失神の鑑別疾患を知りたい」 マニュアルや教科書の使い方を考える
第2回 「利尿薬の量を決めたい」 原著論文の使い方を考える
第3回 論文を効率的に読む
第4回 前向き研究を読む
第5回 後向き研究を読む
第6回 研究スタイルの使い分けの意味を知る
第7回 学会発表、論文執筆にチャレンジ -
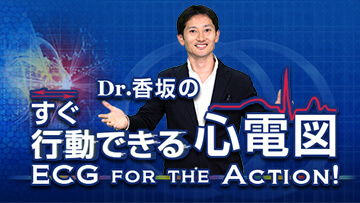
Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!(全12回) 2015/03/25(水)~
あのDr.香坂が帰ってきた!今回は循環器疾患の診断に不可欠な心電図について動画でレクチャーします。 心電図の目的は波形を読み取って、今心臓に何が起こっているかを把握することです。 波形が現れる根拠を知ることで次へのアクションにつなげることができます。 本番組は、「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」というタイトルのとおり、香坂俊先生のこだわりである、「読める」だけでなく次のアクションにつなげることに徹底フォーカス。 心電図に使われるか、使いこなすかはあなた次第です!!
第1回 左室肥大の真実
第2回 縁の下の力持ち 心房の心電図変化
第3回 脚ブロックを使いこなすには
第4回 外科医と内科医の心電図
第5回 心電図の本丸 STの上昇
第6回 ST低下はどこまで信用できる?
第7回 上室性頻拍(1) 心房粗動から紐解く不整脈へのアプローチ
第8回 上室性頻拍(2) 本当に必要か?AVRTとAVNRTの鑑別
第9回 なぜ心室から来る不整脈は怖いのか?VTとVFへの対応
第10回 5分で語る心房細動のエッセンス
第11回 心電図最後の山場 QT部分
第12回 声に出して読みたい心電図 -
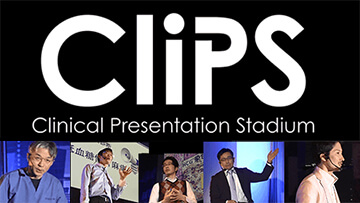
CliPS - Clinical Presentation Stadium - @TOKYO2013(全25回) 2013/08/28(水)~
『CliPS(Clinical Presentation Stadium)』は、限られた時間の中で、プレゼンター自身が経験した「とっておきの患者エピソード」や聞いた人が「きっと誰かに話したくなる」ような興味深い症例を、テイクホームメッセージを添えて伝える「症例の面白さ(学び)」と「語りの妙(プレゼンスキル)」を魅せるプレゼンテーション番組です。プレゼンターは、ケアネットでお馴染みの達人ドクターから若手医師や研修医まで、年齢も診療科も超えた多様なナレッジや価値観を、いくつものパールがつまったツイストの効いたストーリーに載せて競演します。さぁ、あなたも『CliPS』の世界で、学び、楽しんで下さい!
本シリーズは、2013年4月28日 首都医校コクーンホールB(東京都新宿区)において、公開収録されたものです。
突然の片麻痺、構音障害 【吉野鉄大】
幸運にも彼女は肺炎になった 【伊藤裕司】
診断の目利きになる 【山中克郎】
Good Morning, NY! 【岡田正人】
不明熱 【岸本暢将】
Ooops! I did it, again... 難しい呼吸困難の鑑別 【香坂俊】
Shock 【六反田諒】
外見の医療 【菅原康志】
What a Good case!【岡田正人】
首を動かすと電気が走る【山中克郎】
木を診て森も診る【遠井敬大】
なぜキズを縫うのか【菅原康志】
半年間にわたる間欠的な腹痛【小林健二】
高齢者高血圧管理におけるUnmet Medicak Needs: 『血圧変動』に対してどう考える?【飯島勝矢】
患者満足度 【岸本暢将】
ガイドラインって、そんなに大事ですか? 【香坂俊】
EBM or XBM?ーDecision making in clinical practiceー 【駒井好信】
原因不明を繰り返す発熱 【上原由紀】
脳卒中後の固定した麻痺 ―数年経過しても治療により改善するのか?― 【篠田雄一】
眼科での恐怖の糖尿病 【星合繁】
顔を赤くするのは、すれてない証拠? 【国枝武重】
失神恐るるに足らず? 【藤原玲子】
背部痛で救急搬送された82歳男性 【杉原正子】
免疫不全の患者さんが歩いてきた 【井村春樹】
初発痙攣にて搬送された 22歳女性 痙攣の鑑別に難渋した1例 【福井早矢人】 -
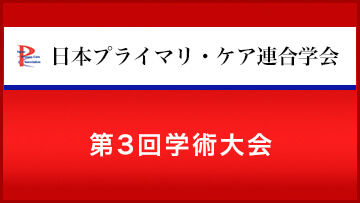
日本プライマリ・ケア連合学会 第3回 学術大会(全11回) 2012/11/28(水)~
「プライマリ・ケアによるパラダイム・シフト-更なる前進への第一歩-」、今回の学術大会のテーマです。 テーマに掲げられた“第一歩”。 これは<人から押されたような、確信もなく一体感のない“第一歩”>であるのか、或いは、<私たち自身が団結し、確実で力強い“第一歩”を踏み出す>のか・・・。後者を目指せば、日本の未来の医療へ、進化を導くきっかけとなるのではないでしょうか。 テーマに掲げられた“パラダイム・シフト”。 これは正に、私たち自身、一人一人に内在する諸問題を、大きな目標の前では、ある意味“妥協”し得るという、成熟した転換が出来るかどうかにかかっていると考えたものです。 プライマリ・ケア現場での諸問題の改革は、日本の医療にとって大きなパラダイム・シフトになるでしょう。 第3回目となる学術大会、今回、CareNeTVでは以下のテーマについてお届けします。 在宅医療/漢方/心電図/教育カンファレンス/耳鼻科/ワクチン/家庭医に必要な経営学
シンポジウム4 診療所のネットワークで支える在宅医療-機能強化型在宅支援診療所のモデル的事例の普及に向けて-
大会長の挨拶
教育講演7 プライマリ・ケアで一生使える耳鼻科診療
教育講演2 心電図がプライマリ・ケアで輝くとき
シンポジウム1 卒前教育でプライマリ・ケアをどう教えるか
シンポジウム10 日本リハビリテーション医学会との連携シンポジウム「在宅における食・排泄・睡眠」
シンポジウム6 経験を学びに変える、効果的な教育カンファレンスのあり方
ランチョンセミナー1 冷え症・肩こり・めまい・倦怠感・食欲不振やその他の不定愁訴に漢方を使おう!
教育講演1 プライマリケアにおける肺炎診療のPearls & Pitfalls
教育講演11 「ワクチンについて、これだけは知っておきたい!-保護者、医療者からよくある質問を中心に、あなたの疑問に答えます-」
シンポジウム14 これからの家庭医・総合診療医に必要な経営能力とは -
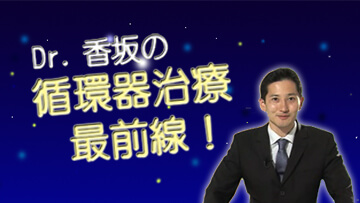
Dr.香坂の循環器診療 最前線!(全12回) 2012/02/22(水)~
様々な検査や治療方法がからんでくる循環器は一見複雑ですが、 派手な所見や手技に目を奪われず、その患者さんにとって一番大事なポイントを押さえましょう。 また、豊富なエビデンスとリサーチをもとに、その解釈や臨床の現場への活用にも話題を広げていきます。
第1回心房細動はどこを治療する?
第2回 徹底的にエビデンスにこだわった狭心症の診断と治療
第3回 心不全は見た目ではない
第4回 急性期の不整脈治療
第5回 動脈硬化の予防~血圧とコレステロール、数値の先にあるもの
第6回 心内膜炎を身近に考える
第7回 見逃したくない胸部疾患 ~急性冠症候群? 大動脈解離? 肺血栓塞栓症?
第8回 弁膜症…その雑音がホンモノだったら?
第9回 心原性ショックのパラダイム・シフト
第10回 忘れられがちな心臓疾患…心膜疾患と右室
第11回 この方、手術しても大丈夫?周術期管理の真髄
第12回 みんなの心エコー -
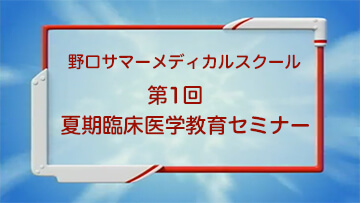
野口サマーメディカルスクール 第1回 夏期臨床医学教育セミナー(全7回) 2012/02/08(水)~
日米の医学教育を経験している各科米国専門認定医が講師となり、米国の教育病院で「Morning Report」という形式で定着している少人数で行うディスカッションにより臨床における Problem oriented solvingと Critical thinkingの訓練・実践を実際の臨床例から学びます。
具体的には、患者から如何にして重要な情報を得て、その情報から患者の病態を推理し、病態を証明するために必要な臨床検査の必然性を説明するか、またその上で如何に正しい診断・治療に導いていくかというアプローチです。このとき非常に重要視されるのが、医師による正確な病歴(History)および身体所見(Physical)の獲得と、それらを基にした病態生理の推理です。この能力が臨床医の「基本中の基本」として尊重されています。そして患者の訴える症状や身体所見が、推理された病態から全て説明できるかという点に関して、いろいろな方面から多くの厳しい質問が出され、さらに議論がなされます。
第1回 津田 武セッション Pediatrics
第2回 香坂 俊セッション Cardiology
第3回 町 淳二セッション General Surgery
第4回 岸本 暢将セッション Rheumatology
第5回 八重樫 牧人セッション Pulmonary
第6回 高部 和明セッション General Surgery
第7回 Educational Lecture「Medical Education and Training-Change,Can We Do It?-Suggestion to Japan!!-」 -

聖路加GENERAL<循環器内科>(全4回) 2011/07/27(水)~
リスクが高い循環器疾患。胸痛、呼吸困難など、他の疾患でも見られる症状から、最初に除外しなければなりません。的確な問診をして、心電図を読み、心雑音を聞き分けて、心エコーを見てその疾患を見極めていく。アメリカでも活躍された経験豊富な香坂先生が、わかりやすく指導してくださいます
第1回 階段がつらいのは歳のせい?
第2回 夜間の呼吸困難は花粉症のせい?
第3回 心雑音と言われたのですが元気なんです
第4回 ためらってはいけないCAB