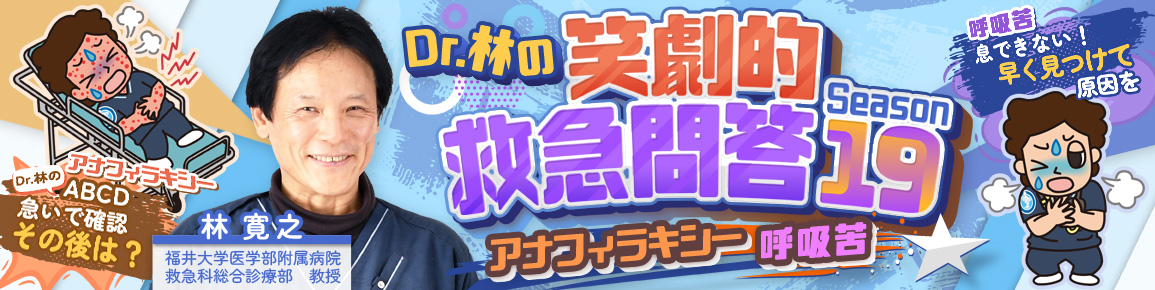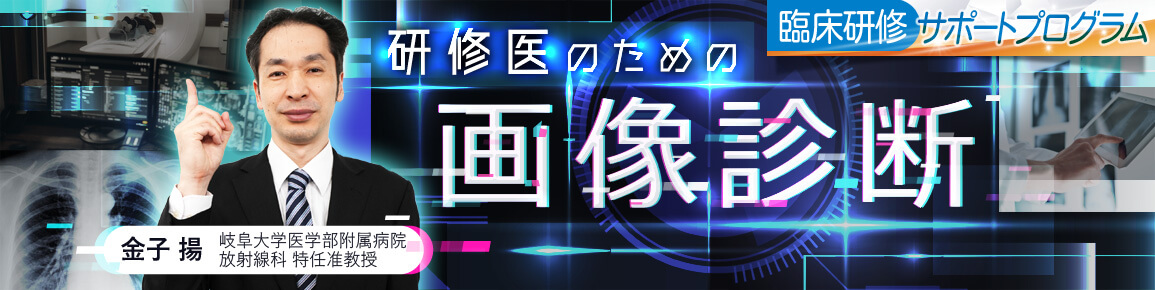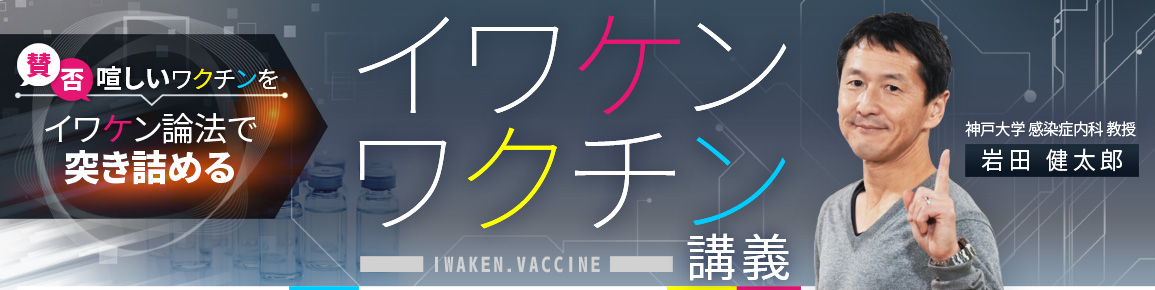眼科の番組検索結果
-
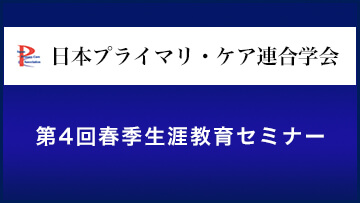 日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 春季生涯教育セミナー(全4回)WS9 Generalistのための眼底鏡・耳鏡の使い方-正しい診方で確実な所見をー2012/08/08(水)公開 鈴木 富雄 大阪医科大学附属病院 総合診療科 科長日常診療の中で、患者が眼や耳の症状を訴えることがよくあります。
日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 春季生涯教育セミナー(全4回)WS9 Generalistのための眼底鏡・耳鏡の使い方-正しい診方で確実な所見をー2012/08/08(水)公開 鈴木 富雄 大阪医科大学附属病院 総合診療科 科長日常診療の中で、患者が眼や耳の症状を訴えることがよくあります。
糖尿病や高血圧などの慢性疾患でも、眼底所見の評価は非常に重要です。
そんな時、皆さん方は、どうされていますか?
眼科や耳鼻科に紹介が必要な場合もありますが、その場合でも、最初に主治医がまず一通りの診察を試み、患者に起こっていることの可能性を説明した上... -
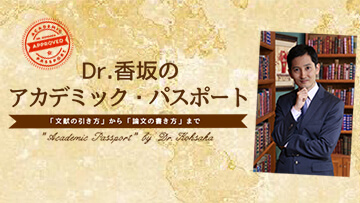 Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第1回 「失神の鑑別疾患を知りたい」 マニュアルや教科書の使い方を考える2016/08/24(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「失神の鑑別疾患を知りたい!」と相談に訪れます。 教科書、マニュアル、ガイドライン・・・・いろいろなものがあって何をどう調べればいいのかわからなくなったようです。 そんな広い話題を調べるにはどうすればいいのか、Dr.香坂がお教えします。
Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第1回 「失神の鑑別疾患を知りたい」 マニュアルや教科書の使い方を考える2016/08/24(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「失神の鑑別疾患を知りたい!」と相談に訪れます。 教科書、マニュアル、ガイドライン・・・・いろいろなものがあって何をどう調べればいいのかわからなくなったようです。 そんな広い話題を調べるにはどうすればいいのか、Dr.香坂がお教えします。 -
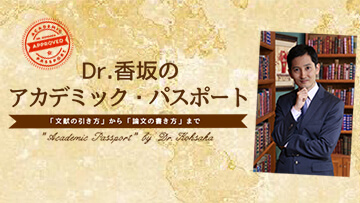 Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第2回 「利尿薬の量を決めたい」 原著論文の使い方を考える2016/09/14(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「利尿薬の量を決めるのに、何を見ればいいですか!」と相談に訪れます。 前回の広い話題のときにでた「マニュアル」や「ガイドライン」などもみたようですが・・・なかなか決められません。 簡単過ぎる「マニュアル」、そして長過ぎる「ガイドライン」。 こんな狭い話題を調べるのにち...
Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第2回 「利尿薬の量を決めたい」 原著論文の使い方を考える2016/09/14(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「利尿薬の量を決めるのに、何を見ればいいですか!」と相談に訪れます。 前回の広い話題のときにでた「マニュアル」や「ガイドライン」などもみたようですが・・・なかなか決められません。 簡単過ぎる「マニュアル」、そして長過ぎる「ガイドライン」。 こんな狭い話題を調べるのにち... -
 志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第1回 なぜ今、診断戦略か?2017/09/13(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長若手Dr.の支持を集める診断学の「ニューバイブル」を映像化! 「診断」というものを独自のアプローチで捉え直した書として注目された「診断戦略」(医学書院)。 医師が無意識的に行っていた診断に至る思考プロセスを言語化することで、意識的に、効率的にその精度を向上させることができる、まさに診断学イノベーション! 本番組では『診断戦略』の...
志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第1回 なぜ今、診断戦略か?2017/09/13(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長若手Dr.の支持を集める診断学の「ニューバイブル」を映像化! 「診断」というものを独自のアプローチで捉え直した書として注目された「診断戦略」(医学書院)。 医師が無意識的に行っていた診断に至る思考プロセスを言語化することで、意識的に、効率的にその精度を向上させることができる、まさに診断学イノベーション! 本番組では『診断戦略』の... -
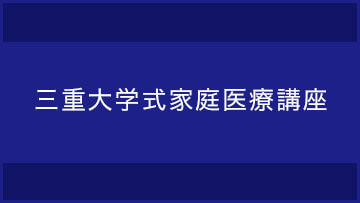 三重大学式家庭医療講座(全1回)第1回 ぜひとも知っておきたいプライマリ・ケアで遭遇するアレルギー疾患2013/03/27(水)公開 竹村 洋典 三重大学大学院 医学系研究科 臨床医学系講座家庭医療学分野花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など、日常診療でよく遭遇するアレルギー疾患を取り上げます。致死的疾患ではありませんが、慢性化しやすく、治療・根治には正しい知識が不可欠です。 皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科など複数の科に関わることも多く、診断に悩まれる先生も多いかと思います。 本講演では、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜...
三重大学式家庭医療講座(全1回)第1回 ぜひとも知っておきたいプライマリ・ケアで遭遇するアレルギー疾患2013/03/27(水)公開 竹村 洋典 三重大学大学院 医学系研究科 臨床医学系講座家庭医療学分野花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など、日常診療でよく遭遇するアレルギー疾患を取り上げます。致死的疾患ではありませんが、慢性化しやすく、治療・根治には正しい知識が不可欠です。 皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科など複数の科に関わることも多く、診断に悩まれる先生も多いかと思います。 本講演では、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜... -
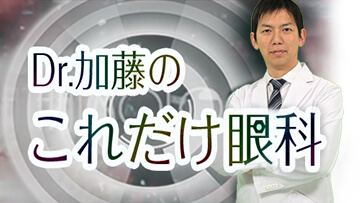 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第1回 「眼底所見」はこれだけ2016/03/16(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第1回は先生方からリクエストの多い眼底所見について取り上げます。 前半は最近の眼底検査機器とその特徴、後半は眼底所見のポイントについて糖尿病や高血圧などの内科疾患も含めて紹介します。 眼底所見、これだけ知っておけば非専門医の標準レベル突破です。
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第1回 「眼底所見」はこれだけ2016/03/16(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第1回は先生方からリクエストの多い眼底所見について取り上げます。 前半は最近の眼底検査機器とその特徴、後半は眼底所見のポイントについて糖尿病や高血圧などの内科疾患も含めて紹介します。 眼底所見、これだけ知っておけば非専門医の標準レベル突破です。 -
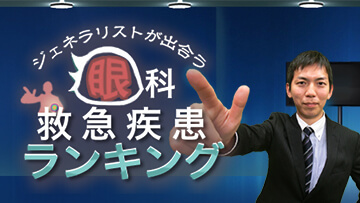 ジェネラリストが出合う眼科救急疾患ランキング!(全6回)第1回 初期治療が重要な救急疾患!2015/01/21(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授プライマリケア医が眼科症状を有する患者さんに遭遇した時に大切なことは、救急疾患の見極めです。眼科救急疾患の中で、最も重症度が高いのが失明リスクの伴う疾患です。 今回お届けする眼科救急疾患の症例は、「19時30分頃突然左眼が見えなくなり、おかしいと思い直ぐに来院した65歳男性」、「実験中に塩酸が目に入り、すぐに洗浄したが、痛みの続く20...
ジェネラリストが出合う眼科救急疾患ランキング!(全6回)第1回 初期治療が重要な救急疾患!2015/01/21(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授プライマリケア医が眼科症状を有する患者さんに遭遇した時に大切なことは、救急疾患の見極めです。眼科救急疾患の中で、最も重症度が高いのが失明リスクの伴う疾患です。 今回お届けする眼科救急疾患の症例は、「19時30分頃突然左眼が見えなくなり、おかしいと思い直ぐに来院した65歳男性」、「実験中に塩酸が目に入り、すぐに洗浄したが、痛みの続く20... -
 Dr.小松のとことん病歴ゼミ(全6回)第1回 肩こりで帰してはいけない頸部痛2018/03/28(水)公開 小松 孝行 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科診断に直結する病歴聴取のスキルを鍛える新番組スタート! 診断に際して、検査値や画像所見を重視して病歴聴取を軽視してはいませんか。病歴こそがもっとも重要な診断材料であり、それだけで8割方の診断はつくといわれます。しかし、Onsetの時期や発症様式などの重要な情報を得られるかは、医師の問診技術にかかっています。 この番組では講師である...
Dr.小松のとことん病歴ゼミ(全6回)第1回 肩こりで帰してはいけない頸部痛2018/03/28(水)公開 小松 孝行 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科診断に直結する病歴聴取のスキルを鍛える新番組スタート! 診断に際して、検査値や画像所見を重視して病歴聴取を軽視してはいませんか。病歴こそがもっとも重要な診断材料であり、それだけで8割方の診断はつくといわれます。しかし、Onsetの時期や発症様式などの重要な情報を得られるかは、医師の問診技術にかかっています。 この番組では講師である... -
 志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第2回 2つの思考プロセス2017/10/04(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断戦略の世界へようこそ。 医師が操る直観的思考と分析的思考。この思考パターンの見える化こそが、診断の精度をアップするための第1歩。診断の思考プロセスを意識することで、自身の診断能力を鍛えることができるんです。 今回の「志水太郎の診断戦略エッセンス」は実際の症例の診断のなかで、ひらめきである直観的思考と分析的思考による推論に挑...
志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第2回 2つの思考プロセス2017/10/04(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断戦略の世界へようこそ。 医師が操る直観的思考と分析的思考。この思考パターンの見える化こそが、診断の精度をアップするための第1歩。診断の思考プロセスを意識することで、自身の診断能力を鍛えることができるんです。 今回の「志水太郎の診断戦略エッセンス」は実際の症例の診断のなかで、ひらめきである直観的思考と分析的思考による推論に挑... -
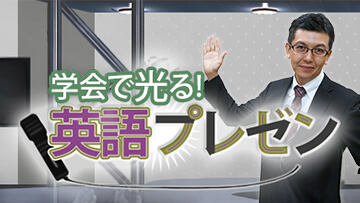 学会で光る!英語プレゼン(全8回)第1回 英語プレゼンに必要なチカラとは?2015/07/08(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会での英語プレゼンテーションには、ライブでメッセージ伝達できる、意見交換から人とのつながりが生まれる、など英語論文とは違う効果があります。今回は、英語プレゼンの効果、英語プレゼン力とは、どうしたら英語プレゼン力は上がるのか、について紹介します。
学会で光る!英語プレゼン(全8回)第1回 英語プレゼンに必要なチカラとは?2015/07/08(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会での英語プレゼンテーションには、ライブでメッセージ伝達できる、意見交換から人とのつながりが生まれる、など英語論文とは違う効果があります。今回は、英語プレゼンの効果、英語プレゼン力とは、どうしたら英語プレゼン力は上がるのか、について紹介します。 -
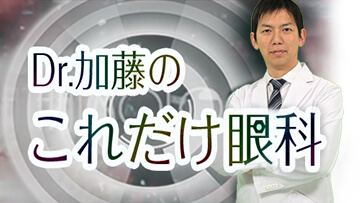 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第3回 「緑内障」はこれだけ2016/04/27(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第3回は高齢疾患である緑内障。先生の患者さんにも大勢いらっしゃるのではないでしょうか?緑内障は症状が現れるころには、すでに中期以降に進行しているため、プライマリケア医による早期発見・治療はとても重要です。 番組では、緑内障の眼底所見、頭痛や悪心嘔吐など身体症状を呈する緑内障発作の初期対応、また、抗コリン薬...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第3回 「緑内障」はこれだけ2016/04/27(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第3回は高齢疾患である緑内障。先生の患者さんにも大勢いらっしゃるのではないでしょうか?緑内障は症状が現れるころには、すでに中期以降に進行しているため、プライマリケア医による早期発見・治療はとても重要です。 番組では、緑内障の眼底所見、頭痛や悪心嘔吐など身体症状を呈する緑内障発作の初期対応、また、抗コリン薬... -
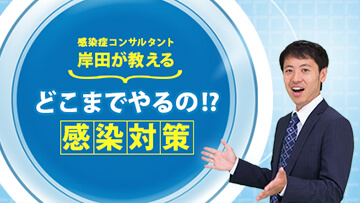 感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第2回 多剤耐性菌って何?2016/01/06(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師MRSAはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌すなわちメチシリンに耐性であるということが明確ですが、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネトバクターなどの多剤耐性菌の“多剤”とはどのようなことを示すのかご存知ですか?複数の抗菌薬に耐性があることなのでしょうか?これからさまざまな微生物の感染対策に進む前に、定義を確認しおきましょう。 対策のためにも...
感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第2回 多剤耐性菌って何?2016/01/06(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師MRSAはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌すなわちメチシリンに耐性であるということが明確ですが、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネトバクターなどの多剤耐性菌の“多剤”とはどのようなことを示すのかご存知ですか?複数の抗菌薬に耐性があることなのでしょうか?これからさまざまな微生物の感染対策に進む前に、定義を確認しおきましょう。 対策のためにも... -
 志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第1回 隠された病変(The Hidden Lesion)2018/09/19(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving...
志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第1回 隠された病変(The Hidden Lesion)2018/09/19(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving... -
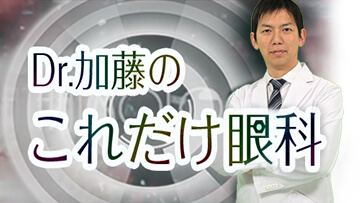 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第2回 「糖尿病網膜症」はこれだけ2016/03/30(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第2回は糖尿病患者の約2割が罹患しているといわれる糖尿病網膜症。緑内障に次いで失明原因の第2位です。 糖尿病網膜症は糖尿病罹患5~10年で発症率が高まると言われていますが、中期以上に進行しないと自覚症状が現れない厄介な合併症です。 番組では、網膜症の進行度、症状と所見などの基本知識、発症予防のための血糖管理、眼...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第2回 「糖尿病網膜症」はこれだけ2016/03/30(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第2回は糖尿病患者の約2割が罹患しているといわれる糖尿病網膜症。緑内障に次いで失明原因の第2位です。 糖尿病網膜症は糖尿病罹患5~10年で発症率が高まると言われていますが、中期以上に進行しないと自覚症状が現れない厄介な合併症です。 番組では、網膜症の進行度、症状と所見などの基本知識、発症予防のための血糖管理、眼... -
 志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第3回 診断力をどう鍛えるか?2017/10/25(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断力は、直観的思考の洗練に加え、活用できる分析的思考の種類がどれだけあるかがカギ。分析的思考のための具体的なツールであるアルゴリズム、ベイズの定理、スコアリングシステム、フレームワーク。このなかで自分なりの手堅い戦略の型を持っておくことが鑑別診断を進める際の高い機動力に繋がります。 番組内では志水太郎先生が日常的に使うフレ...
志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第3回 診断力をどう鍛えるか?2017/10/25(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断力は、直観的思考の洗練に加え、活用できる分析的思考の種類がどれだけあるかがカギ。分析的思考のための具体的なツールであるアルゴリズム、ベイズの定理、スコアリングシステム、フレームワーク。このなかで自分なりの手堅い戦略の型を持っておくことが鑑別診断を進める際の高い機動力に繋がります。 番組内では志水太郎先生が日常的に使うフレ... -
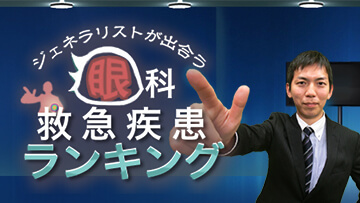 ジェネラリストが出合う眼科救急疾患ランキング!(全6回)第2回 診断が予後を左右する救急疾患!2015/01/28(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授失明と同等に注意したいのが、初期治療によっては後遺症のリスクを伴う眼科救急疾患です。 今回お届けする眼科救急疾患の症例は、「昨夜から右眼が見にくく、右の頭が痛い。気分も悪く2回嘔吐している76歳女性」、「4日前から左目に黒いものが見え、昨日から下のほうに膜がかった感じだが、多忙で眼科受診できなかった61歳男性」の2本。 病歴のどこに着...
ジェネラリストが出合う眼科救急疾患ランキング!(全6回)第2回 診断が予後を左右する救急疾患!2015/01/28(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授失明と同等に注意したいのが、初期治療によっては後遺症のリスクを伴う眼科救急疾患です。 今回お届けする眼科救急疾患の症例は、「昨夜から右眼が見にくく、右の頭が痛い。気分も悪く2回嘔吐している76歳女性」、「4日前から左目に黒いものが見え、昨日から下のほうに膜がかった感じだが、多忙で眼科受診できなかった61歳男性」の2本。 病歴のどこに着... -
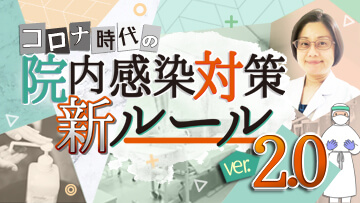 コロナ時代の院内感染対策・新ルール Ver.2.0(全1回)コロナ時代の院内感染対策・新ルールVer.2.02021/01/29(金)公開 坂本 史衣 板橋中央総合病院 院長補佐 感染対策相談支援事務所 所長聖路加国際病院 感染管理担当の坂本 史衣先生による、コロナ禍における院内感染対策ケアネットライブ第2弾。
コロナ時代の院内感染対策・新ルール Ver.2.0(全1回)コロナ時代の院内感染対策・新ルールVer.2.02021/01/29(金)公開 坂本 史衣 板橋中央総合病院 院長補佐 感染対策相談支援事務所 所長聖路加国際病院 感染管理担当の坂本 史衣先生による、コロナ禍における院内感染対策ケアネットライブ第2弾。
この半年間で、新型コロナウイルスに関し、さまざまなことがわかってきました。今回のライブでは、明らかになった情報や蓄積されたデータを踏まえて、院内感染対策で重点的に気を付けるポイント、実践した結果大いに有効だった対策などを... -
 志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第4回 診断の型のイノベーション2017/11/15(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長知れば使いたくなる新しい診断戦略を伝授します。 鑑別診断という答えをどう追い詰めて明らかにするか。診断力をアップする鍵は、これまでとはまったく異なるアプローチかもしれません。今回の「志水太郎の診断戦略エッセンス」は、直観と分析の合わせ技「Pivot&Cluster」や、疾患群の網を重ねていく「Mesh Layers」など、今日からの診断の質が変わる...
志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第4回 診断の型のイノベーション2017/11/15(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長知れば使いたくなる新しい診断戦略を伝授します。 鑑別診断という答えをどう追い詰めて明らかにするか。診断力をアップする鍵は、これまでとはまったく異なるアプローチかもしれません。今回の「志水太郎の診断戦略エッセンス」は、直観と分析の合わせ技「Pivot&Cluster」や、疾患群の網を重ねていく「Mesh Layers」など、今日からの診断の質が変わる... -
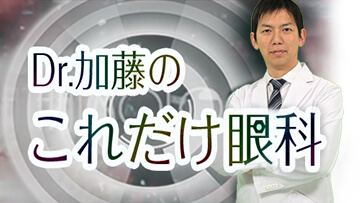 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第6回 「結膜炎」はこれだけ2016/07/13(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授結膜炎は白目(結膜)に炎症が生じる非常にコモンな眼科疾患です。 また、プライマリケア医でも十分治療できる疾患だと言われています。 番組では結膜炎の3つのタイプ、ウイルス性、アレルギー性、細菌性の特徴と簡単な見分け方、さらに目の充血と出血の違いも紹介します。 結膜炎、これだけ知っておけば非専門医の標準レベル突破
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第6回 「結膜炎」はこれだけ2016/07/13(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授結膜炎は白目(結膜)に炎症が生じる非常にコモンな眼科疾患です。 また、プライマリケア医でも十分治療できる疾患だと言われています。 番組では結膜炎の3つのタイプ、ウイルス性、アレルギー性、細菌性の特徴と簡単な見分け方、さらに目の充血と出血の違いも紹介します。 結膜炎、これだけ知っておけば非専門医の標準レベル突破 -
 志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第5回 病歴の技法2017/12/06(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長検査値、画像、身体所見―医師は様々な情報から診断を導き出す。その中でもとくに重要な意味を持つのは病歴聴取。 志水太郎先生が日々の問診で大切にしているのは”4つのC”と"BEOアプローチ”。診断戦略の前提となる質の高い病歴の技法を伝授します。
志水太郎の診断戦略エッセンス(全7回)第5回 病歴の技法2017/12/06(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長検査値、画像、身体所見―医師は様々な情報から診断を導き出す。その中でもとくに重要な意味を持つのは病歴聴取。 志水太郎先生が日々の問診で大切にしているのは”4つのC”と"BEOアプローチ”。診断戦略の前提となる質の高い病歴の技法を伝授します。 -
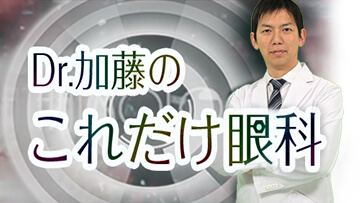 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第7回 「眼科コモンディジーズ」はこれだけ2016/08/17(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授非眼科医が出合う眼科疾患の80%以上はまぶた、角膜、結膜などの前眼部疾患です。 つまり、前眼部診察のポイントを押さえておけば、日常診療でのほとんどの眼科疾患に対応できることになります。 番組では、プライマリケア医への眼科教育に積極的に取り組む加藤浩晃先生が、上眼瞼翻転などプライマリケアでの簡単な前眼部診察や、麦粒腫、ドライアイ、...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第7回 「眼科コモンディジーズ」はこれだけ2016/08/17(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授非眼科医が出合う眼科疾患の80%以上はまぶた、角膜、結膜などの前眼部疾患です。 つまり、前眼部診察のポイントを押さえておけば、日常診療でのほとんどの眼科疾患に対応できることになります。 番組では、プライマリケア医への眼科教育に積極的に取り組む加藤浩晃先生が、上眼瞼翻転などプライマリケアでの簡単な前眼部診察や、麦粒腫、ドライアイ、... -
 Dr.小松のとことん病歴ゼミ(全6回)第2回 パニック障害の再発?それとも…2018/04/18(水)公開 小松 孝行 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科診断に直結する病歴の聴取スキルを鍛える病歴ゼミ。 今回、小松孝行先生はパニック障害の既往のある女性に扮します。患者が解釈モデルを持っている場合、そのバイアスに引っ張られずに、冷静に情報を引き出していくことが病歴聴取では重要です。以前のパニック障害の症状とどこが似ていて、どこが違うのか、会話の流れのなかで巧みに探っていきましょ...
Dr.小松のとことん病歴ゼミ(全6回)第2回 パニック障害の再発?それとも…2018/04/18(水)公開 小松 孝行 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科診断に直結する病歴の聴取スキルを鍛える病歴ゼミ。 今回、小松孝行先生はパニック障害の既往のある女性に扮します。患者が解釈モデルを持っている場合、そのバイアスに引っ張られずに、冷静に情報を引き出していくことが病歴聴取では重要です。以前のパニック障害の症状とどこが似ていて、どこが違うのか、会話の流れのなかで巧みに探っていきましょ... -
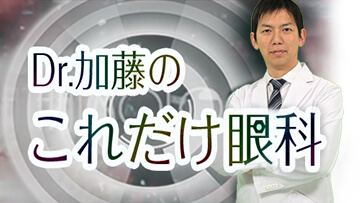 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第4回 「白内障」はこれだけ2016/05/18(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第4回は高齢化とともに増加する白内障。患者さんから白内障について質問されることもあるのではないでしょうか? 白内障は眼科の代表的疾患ですが、加齢だけでなく、糖尿病、ステロイドが原因となることもあります。また、転倒リスクや死亡率も上昇するとも相関するなど眼科以外の診療科とも関連の深い疾患です。 番組では、白...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第4回 「白内障」はこれだけ2016/05/18(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第4回は高齢化とともに増加する白内障。患者さんから白内障について質問されることもあるのではないでしょうか? 白内障は眼科の代表的疾患ですが、加齢だけでなく、糖尿病、ステロイドが原因となることもあります。また、転倒リスクや死亡率も上昇するとも相関するなど眼科以外の診療科とも関連の深い疾患です。 番組では、白... -
 志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第2回 一周回って確診に(Circling Back for the Diagnosis)2018/10/24(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving...
志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第2回 一周回って確診に(Circling Back for the Diagnosis)2018/10/24(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving...