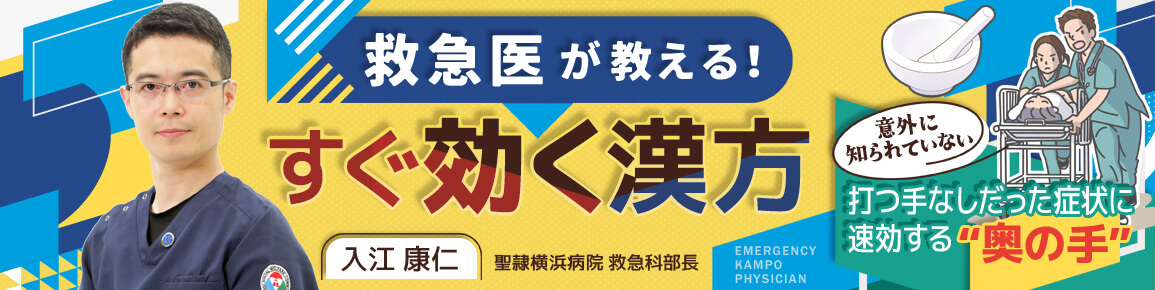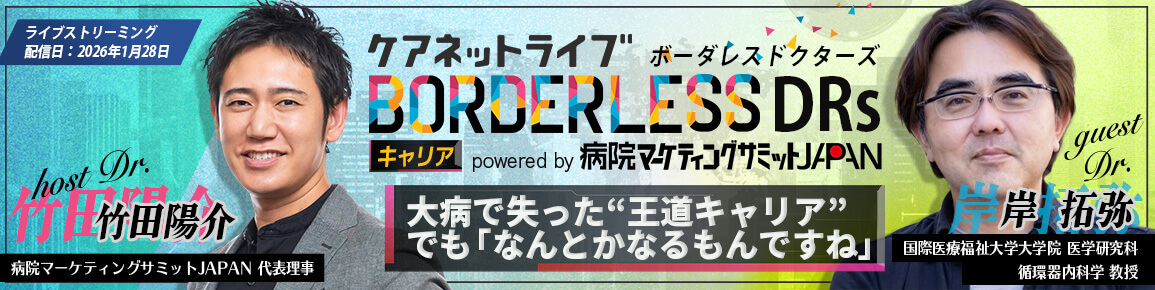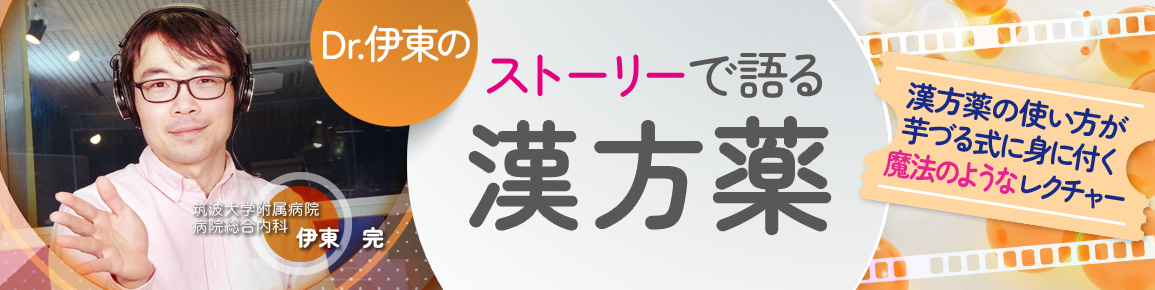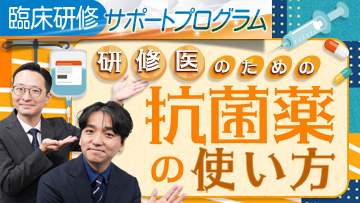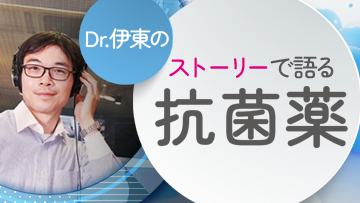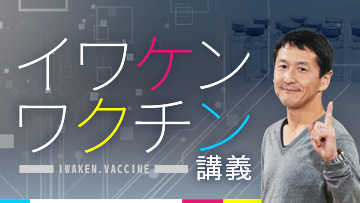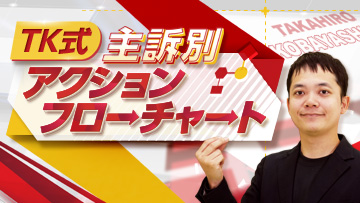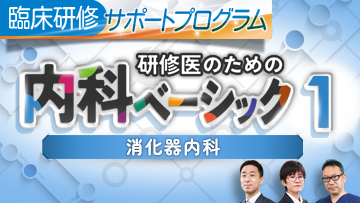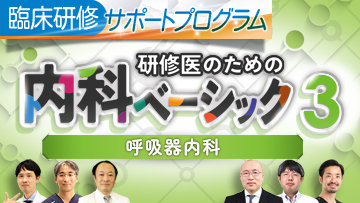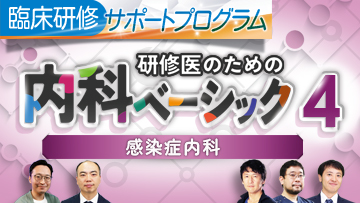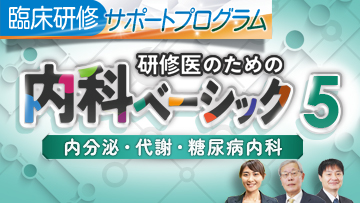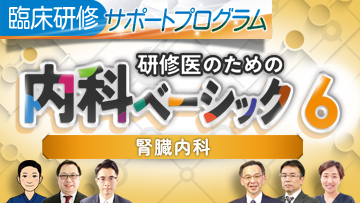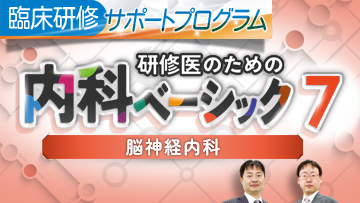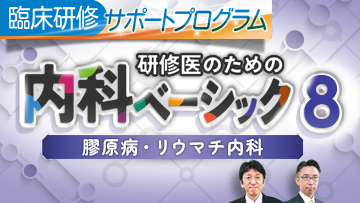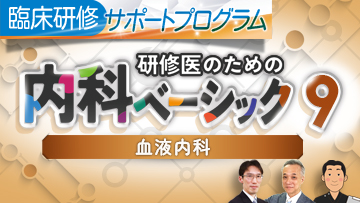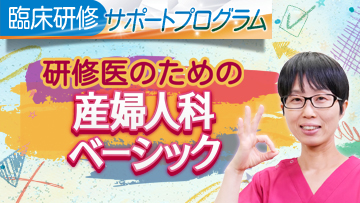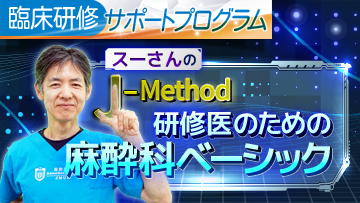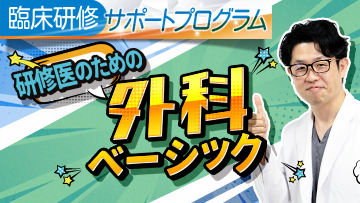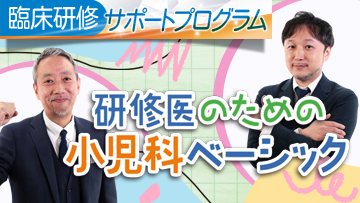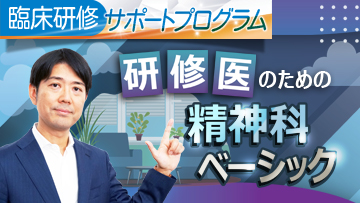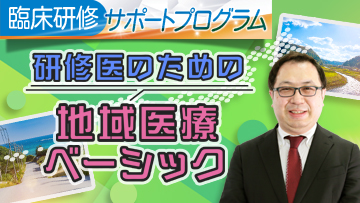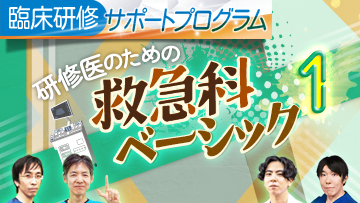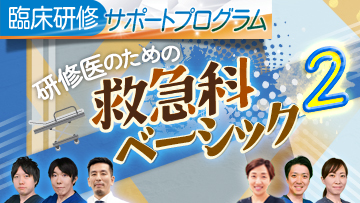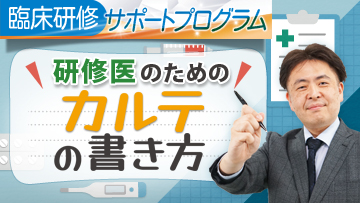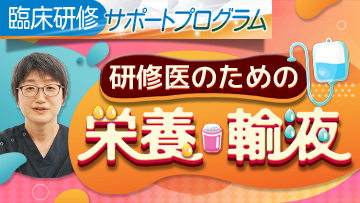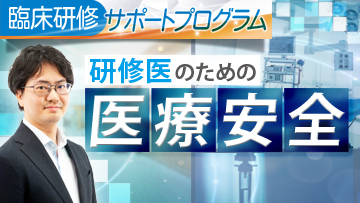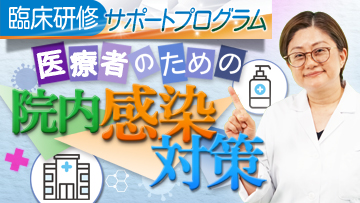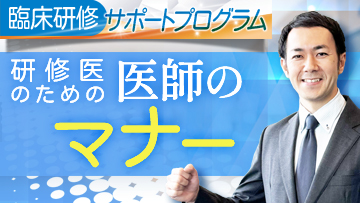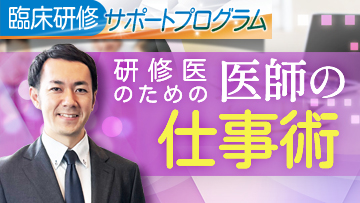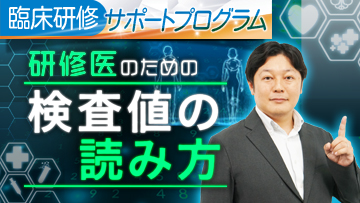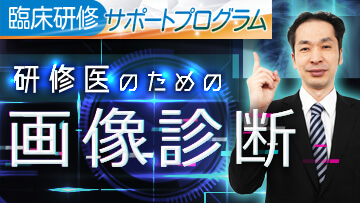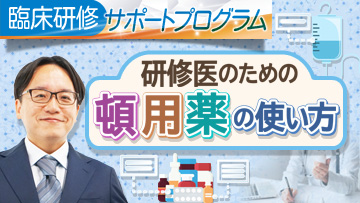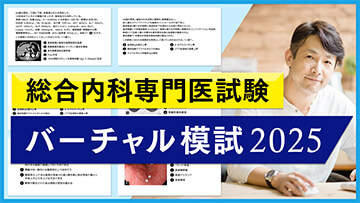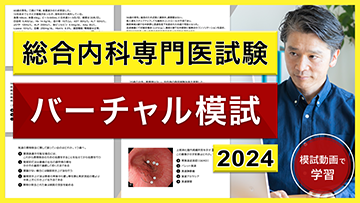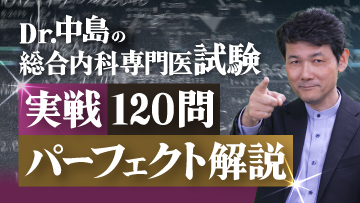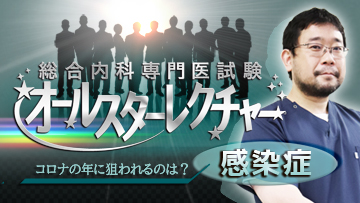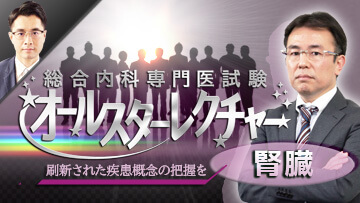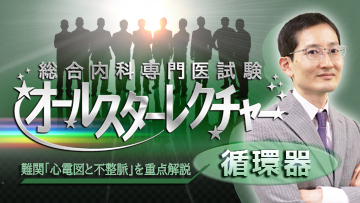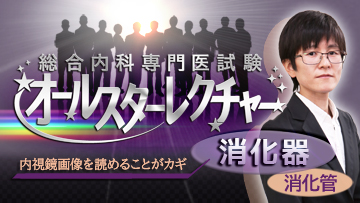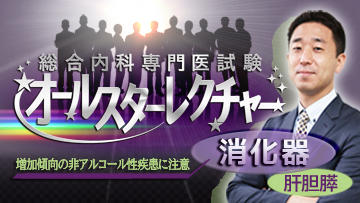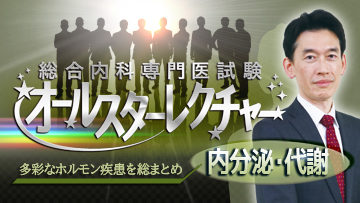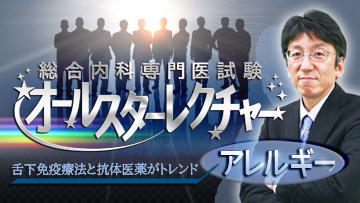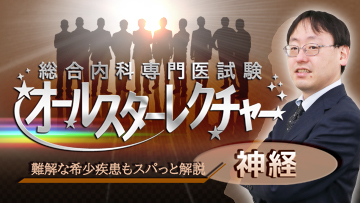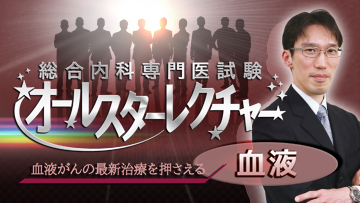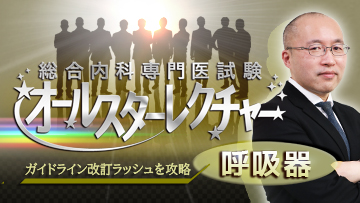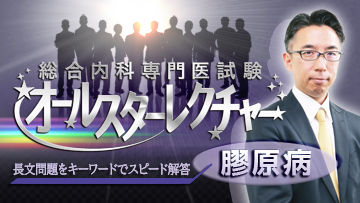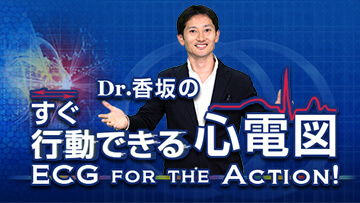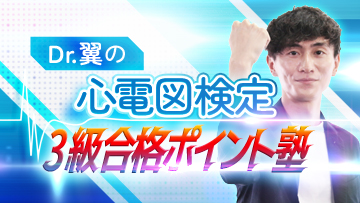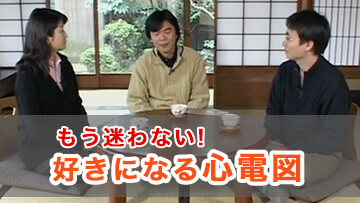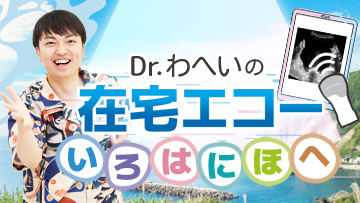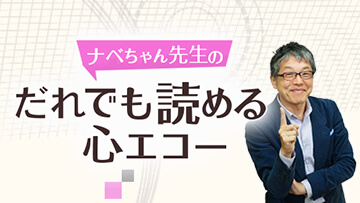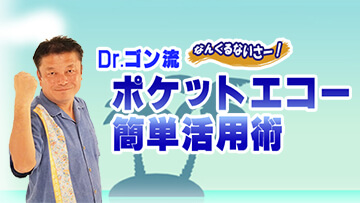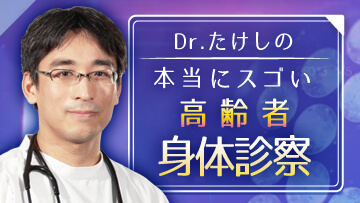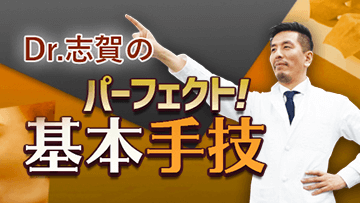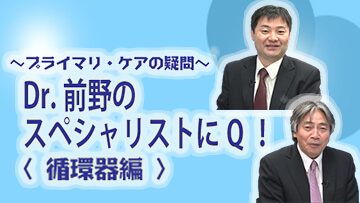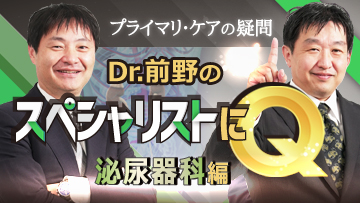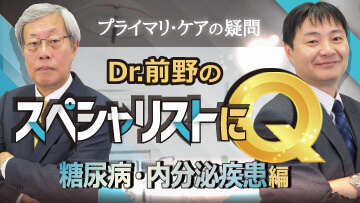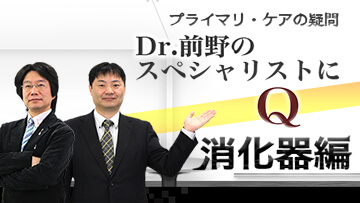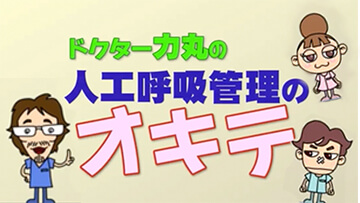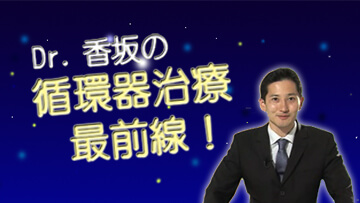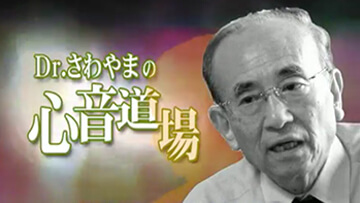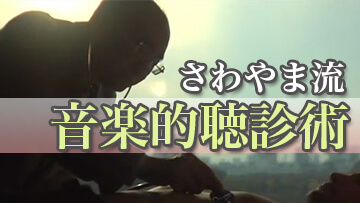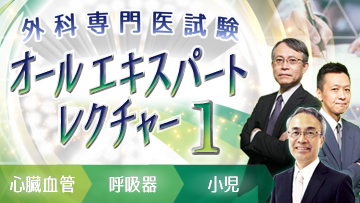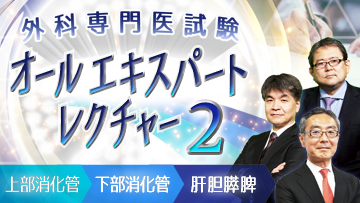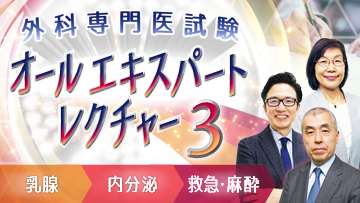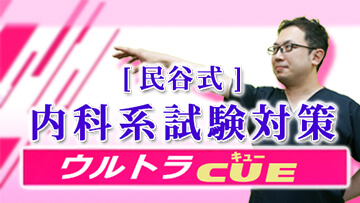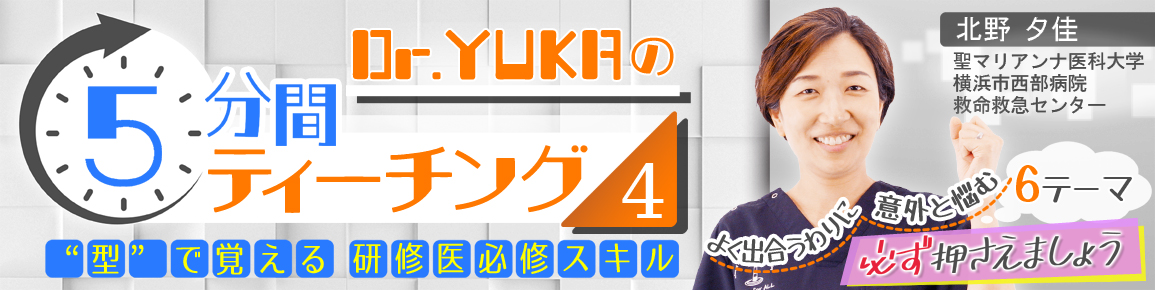-
- 2026/02/05(木)公開

Dr.ヒデキのプライマリ心不全 AtoD(全10回)
第6回 検査・画像評価
-
- 2026/02/05(木)公開
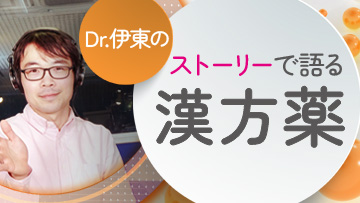
Dr.伊東のストーリーで語る漢方薬(全13回)
第11回 四君子湯:気虚に対する処方
-
- 2026/01/29(木)公開
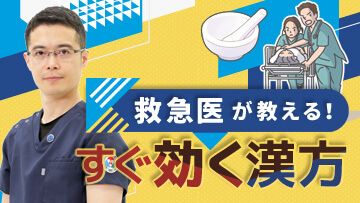
救急医が教える!すぐ効く漢方(全11回)
第11回 破傷風
-
- 2026/01/29(木)公開

Dr.Junの人工呼吸管理スピードマスター(全12回)
第9回 人工呼吸器離脱の考え方
-
- 2026/01/28(水)公開
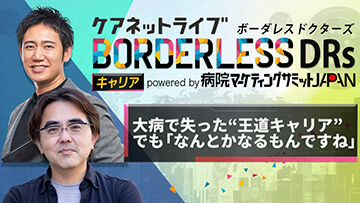
ケアネットライブBORDERLESS DRs キャリア powered by 病院マーケティングサミットJAPAN(全6回)
第1回 大病で失った“王道キャリア” でも「なんとかなるもんですね」
-
- 2026/01/26(月)公開
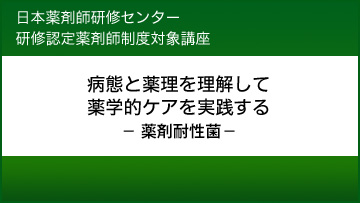
(JPEC研修) 病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-薬剤耐性菌-(全3回)
第1回 薬剤耐性(AMR)対策について~薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)をふまえて~
-
- 2026/01/22(木)公開

Dr.田中和豊の血液検査指南 臓器不全編(全15回)
第5回 循環不全1 ショック
-
- 2026/01/22(木)公開

知らないと困る!男性更年期障害(全6回)
第4回 男性更年期障害の予防
-
- 2026/01/22(木)公開

Dr.金井のCTクイズ 上級編(全12回)
第8回 腹部:微細な所見を拾ってthin sliceやwindow調整で診断に
-
- 2026/01/21(水)公開
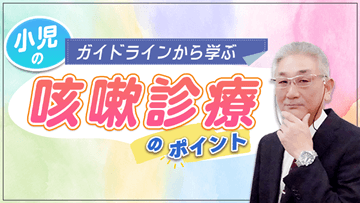
ガイドラインから学ぶ小児の咳嗽診療のポイント(全2回)
前編 小児の咳嗽の分類と診断
-
- 2026/01/15(木)公開
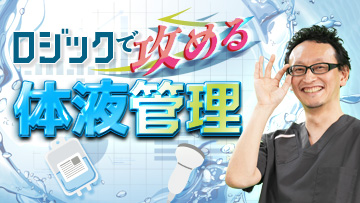
ロジックで攻める体液管理(全10回)
第10回 腎代替療法 後編
-
- 2026/01/08(木)公開
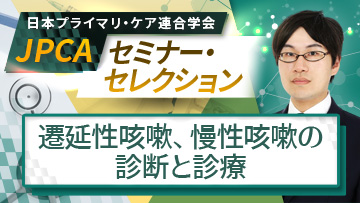
JPCAセミナー・セレクション(全12回)
遷延性咳嗽、慢性咳嗽の診断と診療
-
- 2026/01/08(木)公開
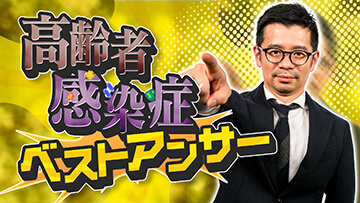
高齢者感染症ベストアンサー(全8回)
第8回 予防対策
-
- 2025/12/25(木)公開
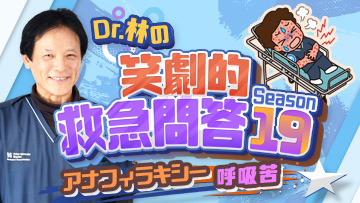
Dr.林の笑劇的救急問答 Season19(全8回)
第8回 呼吸苦4:検査だけでは気付けない!
-
- 2025/12/24(水)公開
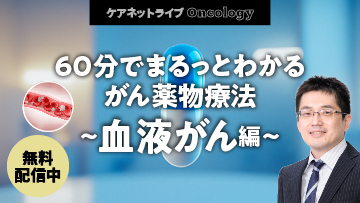
ケアネットライブOncology(全6回)
60分でまるっとわかる がん薬物療法 ~血液がん編~
臨床研修サポートプログラム
総合内科専門医試験試験対策
画像・心電図をちゃんと読める医者になる
風間編集長の「この番組のここがスゴイ!」
-
食は喜び。「口から食べさせる」技術が詰まった一本
 全国民が外出を自粛し、Stay homeに励んだ結果、新型コロナウイルス感染の第1波が収束に向かいつつあります。かく言う僕もこの1ヵ月はほぼ在宅勤務で、この原稿も家で書いています。 外に出られない、人と会えない、というのはつらいものです。日々の楽しみと言えば、食事くらい。こういう状況になると、食というのは、人間のQOLにとって本当に重要なものだと改めて痛感します。 そんなことを考えていると、6年前の1つの番組を思い出しました。『Dr.野原のナルホド!摂食・嚥下障害マネジメント ~キュアからケアへ~』。患者さんに、口からものを食べてもらうことの大切さを力説する野原幹司先生に当時いたく共感したのを覚えています。 急性期治療中のため、あるいは誤嚥性肺炎防止のため、医師が患者さんに経口摂取を禁じるケースは多々あります。もちろん、それは致し方ないことです。しかし、認知症や寝たきりの高齢者が一度、経管栄養や胃瘻になってしまうと、一切経口摂取できないものとみなされ、口から食べさせる努力を医療者がやめてしまう。そして、さらに廃用が進み、完全に経口摂取できなくなってしまうという実態があることを野原先生は憂います。 端的に言うと「少しでも口から食べられる限り、少しでも口から食べさせろ」というのが野原先生の一貫した主張です。なぜなら、食べることは人生の喜びそのものだからです。 「胃瘻イコール禁食ではない」(胃瘻から経口摂取に戻せることもあるし、胃瘻が造設されていても口から食べてもよい)。 「誤嚥してもいいじゃないか」(誤嚥性肺炎を恐れるあまり経口摂取を無闇に禁じるより、誤嚥しても肺炎にならない方法を考えるべき)。といったメッセージには、ドキッとする医療者も多いのではないでしょうか。 もちろん番組には、高齢者が口から食べることによって生じる誤嚥性肺炎のリスクを最大限軽減するための知識、ノウハウが満載です。医療者がこの番組を通して気づき、学び、経管栄養、中心静脈栄養、胃瘻が常態化して食べることを忘れてしまったお年寄りが一人でもその喜びをまた味わうことができたら、野原先生も本望だと思います。 さて、この原稿を書き終えたので今日の仕事は終わりです。今夜は何を食べようかなー?
全国民が外出を自粛し、Stay homeに励んだ結果、新型コロナウイルス感染の第1波が収束に向かいつつあります。かく言う僕もこの1ヵ月はほぼ在宅勤務で、この原稿も家で書いています。 外に出られない、人と会えない、というのはつらいものです。日々の楽しみと言えば、食事くらい。こういう状況になると、食というのは、人間のQOLにとって本当に重要なものだと改めて痛感します。 そんなことを考えていると、6年前の1つの番組を思い出しました。『Dr.野原のナルホド!摂食・嚥下障害マネジメント ~キュアからケアへ~』。患者さんに、口からものを食べてもらうことの大切さを力説する野原幹司先生に当時いたく共感したのを覚えています。 急性期治療中のため、あるいは誤嚥性肺炎防止のため、医師が患者さんに経口摂取を禁じるケースは多々あります。もちろん、それは致し方ないことです。しかし、認知症や寝たきりの高齢者が一度、経管栄養や胃瘻になってしまうと、一切経口摂取できないものとみなされ、口から食べさせる努力を医療者がやめてしまう。そして、さらに廃用が進み、完全に経口摂取できなくなってしまうという実態があることを野原先生は憂います。 端的に言うと「少しでも口から食べられる限り、少しでも口から食べさせろ」というのが野原先生の一貫した主張です。なぜなら、食べることは人生の喜びそのものだからです。 「胃瘻イコール禁食ではない」(胃瘻から経口摂取に戻せることもあるし、胃瘻が造設されていても口から食べてもよい)。 「誤嚥してもいいじゃないか」(誤嚥性肺炎を恐れるあまり経口摂取を無闇に禁じるより、誤嚥しても肺炎にならない方法を考えるべき)。といったメッセージには、ドキッとする医療者も多いのではないでしょうか。 もちろん番組には、高齢者が口から食べることによって生じる誤嚥性肺炎のリスクを最大限軽減するための知識、ノウハウが満載です。医療者がこの番組を通して気づき、学び、経管栄養、中心静脈栄養、胃瘻が常態化して食べることを忘れてしまったお年寄りが一人でもその喜びをまた味わうことができたら、野原先生も本望だと思います。 さて、この原稿を書き終えたので今日の仕事は終わりです。今夜は何を食べようかなー? -
「京都にスゴい医者がいるらしい」日本中の内科医が唸ったEBM診断学
 「京都の洛和会丸太町病院の上田先生というのはスゴいらしいよ」 僕は職業柄、常に優れた臨床医探しのアンテナを張るようにしています。今から7、8年前でしょうか?その頃、とくにCareNeTVの新しいスター講師を探していて、ことあるごとに、いろいろな先生方に「どこかに、いい先生、いないですかねー?」と尋ねていましたが、そんな中で上田剛士先生の噂を聞きつけました。 ほぼ時を同じくして、医学書院から「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」が発刊。今や内科医の定番とも言える同書ですが、発刊当時は、その異次元のクオリティーに、日本中の“心ある内科医”が驚愕したものです。 今Amazonのレビューをのぞいても、「今更改めて言うほどでもないが・・・この本は神です」「成書の知識が、どんどん繋がって、現場で役立つ知識に変わっていくよう」といった絶賛コメントが並んでいます。 ともかく一度お目にかかりたいと、なんとかアポイントを取りつけ、暑い夏の京都を訪れたのが2014年。 面会前、僕が頭の中に描いていたのが、当時テレビで流行っていた「ドクターG」をいわば普遍化した番組。ドクターGでは、実際の症例を用いて、さまざまな症状から、1つの診断という答えを絞り込んでいくわけですが、僕のアイデアは、外来でよく遭遇する症候から、およそ考えうる疾患を網羅できないか、というものでした。 「外来で出合う8割の症候をカバーしたいと考えているんですが…」 初対面の僕のざっくりとしたお願いに上田先生は、少し間を置くと、「できると思いますよ」と、さらりとおっしゃいました。あの冷徹な趣きで。 それが結実したのが『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断』です。3シリーズで、主要20症候をカバー。とことんエビデンスに立脚した上田先生ならではの精緻なアプローチで、今やCareNeTV屈指の人気番組になりました。 番組タイトルも当時のテレビ番組「たけしの本当は怖い家庭の医学」をもじったものです。僕が案出したわけではなく、番組にも出演している若い先生の「『たけしの本当にスゴい臨床医学』でいいんじゃないっすか?」という収録の合間の何気ない一言を拝借しました。 ぜひご覧ください。本当にスゴいですから。『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断』『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2』『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断3』
「京都の洛和会丸太町病院の上田先生というのはスゴいらしいよ」 僕は職業柄、常に優れた臨床医探しのアンテナを張るようにしています。今から7、8年前でしょうか?その頃、とくにCareNeTVの新しいスター講師を探していて、ことあるごとに、いろいろな先生方に「どこかに、いい先生、いないですかねー?」と尋ねていましたが、そんな中で上田剛士先生の噂を聞きつけました。 ほぼ時を同じくして、医学書院から「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」が発刊。今や内科医の定番とも言える同書ですが、発刊当時は、その異次元のクオリティーに、日本中の“心ある内科医”が驚愕したものです。 今Amazonのレビューをのぞいても、「今更改めて言うほどでもないが・・・この本は神です」「成書の知識が、どんどん繋がって、現場で役立つ知識に変わっていくよう」といった絶賛コメントが並んでいます。 ともかく一度お目にかかりたいと、なんとかアポイントを取りつけ、暑い夏の京都を訪れたのが2014年。 面会前、僕が頭の中に描いていたのが、当時テレビで流行っていた「ドクターG」をいわば普遍化した番組。ドクターGでは、実際の症例を用いて、さまざまな症状から、1つの診断という答えを絞り込んでいくわけですが、僕のアイデアは、外来でよく遭遇する症候から、およそ考えうる疾患を網羅できないか、というものでした。 「外来で出合う8割の症候をカバーしたいと考えているんですが…」 初対面の僕のざっくりとしたお願いに上田先生は、少し間を置くと、「できると思いますよ」と、さらりとおっしゃいました。あの冷徹な趣きで。 それが結実したのが『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断』です。3シリーズで、主要20症候をカバー。とことんエビデンスに立脚した上田先生ならではの精緻なアプローチで、今やCareNeTV屈指の人気番組になりました。 番組タイトルも当時のテレビ番組「たけしの本当は怖い家庭の医学」をもじったものです。僕が案出したわけではなく、番組にも出演している若い先生の「『たけしの本当にスゴい臨床医学』でいいんじゃないっすか?」という収録の合間の何気ない一言を拝借しました。 ぜひご覧ください。本当にスゴいですから。『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断』『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2』『Dr.たけしの本当にスゴい症候診断3』
2026/02/12(木)配信(次回)
お知らせ
-
2026/01/15(木)
【お知らせ】
CareNeTVにおける「日本薬剤師研修センター(JPEC) / ビデオ・オン・デマンド(VOD)研修」は、2026年3月末をもって終了いたします。
終了後は、コンテンツの視聴およびメモの確認ができなくなります。 必要な情報につきましては、お手数ですが、お手元にお控えくださいますようお願い申し上げます。
公益財団法人日本薬剤師研修センター(JPEC)認定薬剤師の単位取得をご希望の方は、JPECホームページをご確認ください。 -
2026/01/01(木)
【決済システムメンテナンスのお知らせ】
2026年1月度は以下の日程で決済システムのメンテナンスを実施いたします。当該時間帯は、クレジットカードの決済処理やカード情報の変更ができませんのでご注意ください。
■ 1月 9日(金) 2:00 - 5:00
■ 1月13日(火) 0:00 - 6:00
■ 1月16日(金) 2:00 - 5:00
■ 1月19日(月) 2:00 - 5:00
■ 1月26日(月) 2:00 - 5:00
■ 1月27日(火) 0:00 - 6:00
※三井住友カードをご利用の方は、以下の日程でエラーが発生する場合がありますので、
この時間を避けるか、エラーとなった場合は時間をおいてから再度実行してください。
■ 1月 6日 (火) 22:00 - 1月 7日 (水) 2:00
■ 1月 7日 (水) 3:00 - 7:00
■ 1月13日 (火) 22:00 - 1月14日 (水) 2:00
■ 1月14日 (水) 3:00 - 7:00
■ 1月20日 (火) 22:00 - 1月21日 (水) 2:00
■ 1月21日 (水) 3:00 - 7:00
■ 1月27日 (火) 22:00 - 1月28日 (水) 2:00
■ 1月28日 (水) 3:00 - 7:00
※終了時刻は、メンテナンスの状況によって前後する可能性がございます。
なお、プレミアム会員、および購入済み番組のCareNeTVサイト視聴に関しましては、通常通りご利用いただけます。 -
2025/12/25(木)
【ケアネットカスタマーセンター年末年始の対応について】
年末年始におけるケアネットカスタマーセンターの営業に関しまして、下記のとおりご案内申し上げます。
ーーーーー
休業期間:2025年 12月27日(土)~ 2026年 1月4日(日)
年末営業終了日時:2025年 12月26日(金)14時
年始営業開始日時:2026年 1月 5日(月)10時
ーーーーー
なお、休業期間中のお問い合わせフォームやメールでのお問い合わせにつきましては、年始営業開始より順次対応させていただきます。
また、お問い合わせ状況により、返信までにお日にちをいただく可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。
ご利用中の皆さまにはご不便をお掛けしますが、なにとぞ、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご確認ください。