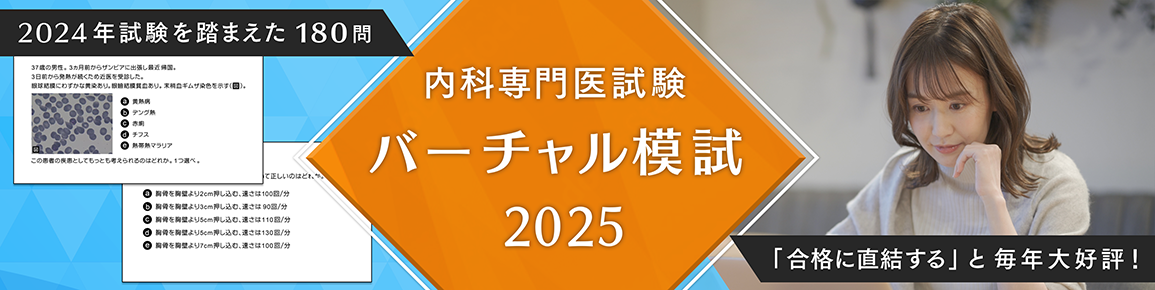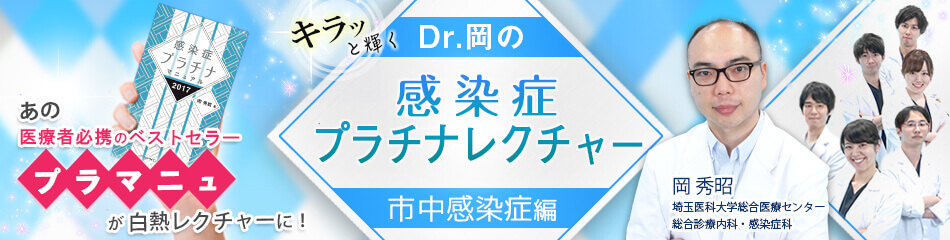歯科の番組検索結果
-
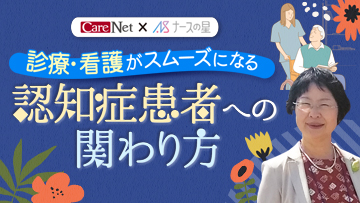 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方(全2回)前編 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方2023/12/20(水)公開 内田 陽子 群馬大学大学院保健学研究科 教授認知症患者に治療やケアを拒否されたとき、対応の仕方に頭を悩ませたことがある人は多いのではないでしょうか。今回は群馬大学大学院保健学研究科の内田陽子先生が認知症患者への関わり方について講義します。医療者にとって悩みの種であるBPSDですが、その出現には方程式があります。認知症の中核症状やBPSDを理解し、関わり方を変えることで、治療や...
診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方(全2回)前編 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方2023/12/20(水)公開 内田 陽子 群馬大学大学院保健学研究科 教授認知症患者に治療やケアを拒否されたとき、対応の仕方に頭を悩ませたことがある人は多いのではないでしょうか。今回は群馬大学大学院保健学研究科の内田陽子先生が認知症患者への関わり方について講義します。医療者にとって悩みの種であるBPSDですが、その出現には方程式があります。認知症の中核症状やBPSDを理解し、関わり方を変えることで、治療や... -
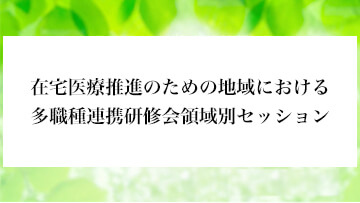 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第18回 【リハビリ1】在宅でのリハビリテーションの取り組み方2014/04/23(水)公開 堀田 富士子 東京都リハビリテーション病院地域リハビリテーション科 科長在宅リハビリテーションの主な対象疾患・障害を紹介し、脳卒中、がん、認知症などを例にリハビリテーションの目的と各ステージにおけるアプローチ法などを解説します。リハビリテーションとは、患者さんの“障害”をマネジメントすること。例えば「片麻痺」の患者さんでは、脳損傷を解決することが目標ではありません。片麻痺という“障害”を理解し、手足...
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第18回 【リハビリ1】在宅でのリハビリテーションの取り組み方2014/04/23(水)公開 堀田 富士子 東京都リハビリテーション病院地域リハビリテーション科 科長在宅リハビリテーションの主な対象疾患・障害を紹介し、脳卒中、がん、認知症などを例にリハビリテーションの目的と各ステージにおけるアプローチ法などを解説します。リハビリテーションとは、患者さんの“障害”をマネジメントすること。例えば「片麻痺」の患者さんでは、脳損傷を解決することが目標ではありません。片麻痺という“障害”を理解し、手足... -
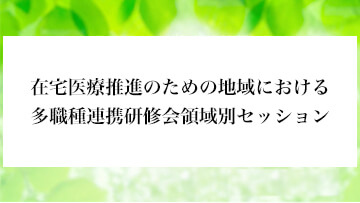 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第7回 【摂食嚥下・口腔ケア3】栄養摂取方法2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部嚥下障害の患者は病院よりも在宅や施設で療養する方が多く、地域で多職種連携によるサポートケアが必須となります。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第7回 【摂食嚥下・口腔ケア3】栄養摂取方法2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部嚥下障害の患者は病院よりも在宅や施設で療養する方が多く、地域で多職種連携によるサポートケアが必須となります。
本セッションでは、症例をもとに患者に適した栄養摂取方法を多職種グループでディスカッションし考えていきます。
【事例】74歳男性。主訴はムセる。食べこぼす。脳梗塞後、食事中のムセがでる。1ヵ月前に肺炎のため2週間入... -
 北米式☆プレゼンテーション上達ライブ(全3回)第3回 より良い Oral Presentation とは!?<後編>2010/11/19(金)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授あなたは身体所見/検査所見/アセスメント・プランをオーラルプレゼンテーションする際、だらだらと長くなっていませんか? 今回は強調すべき点&省くべき点を、それぞれのステップで整理し、的確かつ簡潔に伝えるためのポイントを一気に解説します。 また、聴き手の心をしっかりと掴んで離さない秘訣も紹介! 重要なのは“言葉”だけではありません。...
北米式☆プレゼンテーション上達ライブ(全3回)第3回 より良い Oral Presentation とは!?<後編>2010/11/19(金)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授あなたは身体所見/検査所見/アセスメント・プランをオーラルプレゼンテーションする際、だらだらと長くなっていませんか? 今回は強調すべき点&省くべき点を、それぞれのステップで整理し、的確かつ簡潔に伝えるためのポイントを一気に解説します。 また、聴き手の心をしっかりと掴んで離さない秘訣も紹介! 重要なのは“言葉”だけではありません。... -
 Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第6回 Chest Pain - History and Examination2024/02/08(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic今回は、胸痛を訴える患者が来院。どうやら以前もあった症状のようです。さてこの患者さん、英語でどのように問診しますか?OPQRSTの聞き方は?日本語にはズキズキ、チクチクなど痛みを表す言葉がたくさんありますが、英語にはそれほど多くの表現はありません。ネイティブが普段からよく使うワードを中心に紹介します。
Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第6回 Chest Pain - History and Examination2024/02/08(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic今回は、胸痛を訴える患者が来院。どうやら以前もあった症状のようです。さてこの患者さん、英語でどのように問診しますか?OPQRSTの聞き方は?日本語にはズキズキ、チクチクなど痛みを表す言葉がたくさんありますが、英語にはそれほど多くの表現はありません。ネイティブが普段からよく使うワードを中心に紹介します。 -
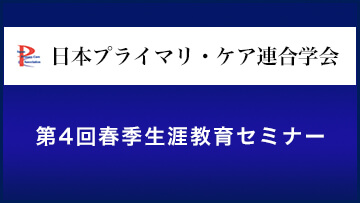 日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 春季生涯教育セミナー(全4回)WS7 子供の事故を防ぐ知恵と子育て支援2012/09/12(水)公開 山中 龍宏 緑園こどもクリニック 院長事故(accident)は“予測ができない”ものである。
日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 春季生涯教育セミナー(全4回)WS7 子供の事故を防ぐ知恵と子育て支援2012/09/12(水)公開 山中 龍宏 緑園こどもクリニック 院長事故(accident)は“予測ができない”ものである。
しかし、果たして子供の事故は“予測ができない”のでしょうか。
山中龍宏先生曰く「子供の事故は“予測もできる”し“予防もできる”。“事故(accident)”ではなく“傷害(injury)”である」。
同じような事故が繰り返される子供の事故は、現代社会の事故に対する意識を変えなくては止めるこ... -
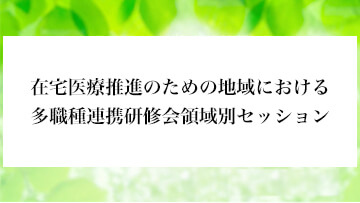 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第6回 【摂食嚥下・口腔ケア2】口腔ケア2013/12/11(水)公開 山口 朱見 あおぞら診療所在宅療養患者で特に口腔ケアが必要な方は、セルフケアが困難な方、肺炎を繰り返す方、的確にものごとを伝えることが出来ない認知症の方、終末期の方です。本セッションでは、このような患者さんの口腔内を例に、どの様な状態があり、何に着目し、口腔ケアをすべきか、口腔機能の基本と維持について解説します。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第6回 【摂食嚥下・口腔ケア2】口腔ケア2013/12/11(水)公開 山口 朱見 あおぞら診療所在宅療養患者で特に口腔ケアが必要な方は、セルフケアが困難な方、肺炎を繰り返す方、的確にものごとを伝えることが出来ない認知症の方、終末期の方です。本セッションでは、このような患者さんの口腔内を例に、どの様な状態があり、何に着目し、口腔ケアをすべきか、口腔機能の基本と維持について解説します。 -
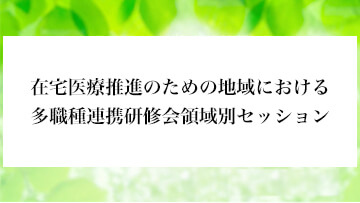 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第9回 【摂食嚥下・口腔ケア5】嚥下リハビリテーション2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第7回の事例検討1を題材に、今度はこの患者の嚥下リハビリーテーションのプランを多職種グループで考えていきます。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第9回 【摂食嚥下・口腔ケア5】嚥下リハビリテーション2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第7回の事例検討1を題材に、今度はこの患者の嚥下リハビリーテーションのプランを多職種グループで考えていきます。
注意すべきは誤嚥性肺炎を予防すること。
さて、多職種連携でどんなプランが出てくるでしょうか。 -
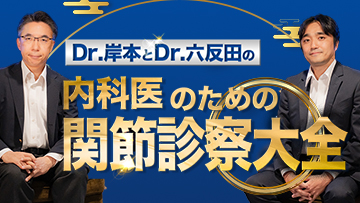 Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第8回 腰・股関節の診察2025/04/10(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授今回は、股関節診察と腰痛に焦点を当てます。アメリカリウマチ学会が提案するコアセットには内科医が診る関節として「腰」は含まれませんが、腰痛を訴える患者の中には、実は股関節に異常がある場合や、その逆も多く見られ、腰痛・股関節痛の両者を同時に疑う必要があります。また、腰痛患者には重大な疾患が潜む可能性があるため、診察時に警戒すべきR...
Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第8回 腰・股関節の診察2025/04/10(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授今回は、股関節診察と腰痛に焦点を当てます。アメリカリウマチ学会が提案するコアセットには内科医が診る関節として「腰」は含まれませんが、腰痛を訴える患者の中には、実は股関節に異常がある場合や、その逆も多く見られ、腰痛・股関節痛の両者を同時に疑う必要があります。また、腰痛患者には重大な疾患が潜む可能性があるため、診察時に警戒すべきR... -
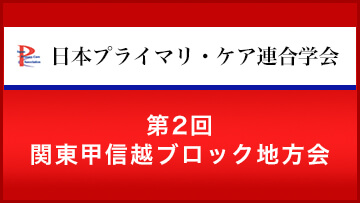 日本プライマリ・ケア連合学会 第2回 関東甲信越ブロック地方会(全3回)地域における糖尿病のケア2014/02/26(水)公開 伊藤 澄信 東京医療センター 総合内科糖尿病は、新薬や治療法、HbA1cの基準値の変化など、常に最新の知識やエビデンスが必要とされます。また患者さんも増加の一途であり医師だけでなく多職種連携で診ることが大切です。
日本プライマリ・ケア連合学会 第2回 関東甲信越ブロック地方会(全3回)地域における糖尿病のケア2014/02/26(水)公開 伊藤 澄信 東京医療センター 総合内科糖尿病は、新薬や治療法、HbA1cの基準値の変化など、常に最新の知識やエビデンスが必要とされます。また患者さんも増加の一途であり医師だけでなく多職種連携で診ることが大切です。
本講演では、西東京の地域連携で実践されている、DPP-4阻害薬を中心とした経口血糖降下薬の活用法、糖尿病ケアにおける管理栄養士の役割など、最新の糖尿病ケアモ... -
 Dr.名郷のコモンディジーズ常識のウソ(全14回)第7回 101人目の患者 ~EBMの常識のウソ~2005/01/20(木)公開 池田 正行 長崎大学 医師薬学総合研究科 教授Evidence-based medicineという言葉がEBMと略されるようになって、急速にその言葉だけは浸透しました。反面、言葉に本来含まれていた概念の一部分のみにスポットが当てられ、臨床現場には熱狂と失望、対立や批判などがもたらされました。多くの人がEBMについて抱くイメージとは、“大規模臨床試験に基づく論文など外部の客観的情報から臨床判断を行う”と...
Dr.名郷のコモンディジーズ常識のウソ(全14回)第7回 101人目の患者 ~EBMの常識のウソ~2005/01/20(木)公開 池田 正行 長崎大学 医師薬学総合研究科 教授Evidence-based medicineという言葉がEBMと略されるようになって、急速にその言葉だけは浸透しました。反面、言葉に本来含まれていた概念の一部分のみにスポットが当てられ、臨床現場には熱狂と失望、対立や批判などがもたらされました。多くの人がEBMについて抱くイメージとは、“大規模臨床試験に基づく論文など外部の客観的情報から臨床判断を行う”と... -
 Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第8回 Abdominal Pain - History and Examination2024/03/14(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic今回は、消化器症状のある患者が来院。“I feel sick.”は直訳すると「体調が悪い」という意味ですが、患者が伝えたいのは違う主訴かもしれません。便に関する表現は、日本語のうんち、お通じのように、英語にもいくつか使い分けがあります。単語の選び方と問診で使いやすいフレーズを学びましょう。ロールプレイでは、ブルンベルグ徴候、マーフィー徴候...
Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第8回 Abdominal Pain - History and Examination2024/03/14(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic今回は、消化器症状のある患者が来院。“I feel sick.”は直訳すると「体調が悪い」という意味ですが、患者が伝えたいのは違う主訴かもしれません。便に関する表現は、日本語のうんち、お通じのように、英語にもいくつか使い分けがあります。単語の選び方と問診で使いやすいフレーズを学びましょう。ロールプレイでは、ブルンベルグ徴候、マーフィー徴候... -
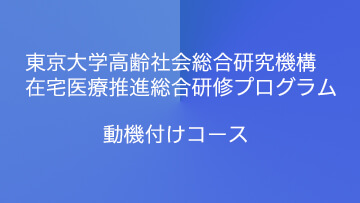 東京大学高齢社会総合研究機構 在宅医療推進総合研修プログラム 動機付けコース(全13回)第11回 在宅療養を支える医療・介護資源2012/08/08(水)公開 川越 正平 あおぞら診療所 院長在宅医療を実施する上で多職種連携はかかせません。
東京大学高齢社会総合研究機構 在宅医療推進総合研修プログラム 動機付けコース(全13回)第11回 在宅療養を支える医療・介護資源2012/08/08(水)公開 川越 正平 あおぞら診療所 院長在宅医療を実施する上で多職種連携はかかせません。
しかし、連携するためには地域にどのくらい在宅医療に対応できる医療・介護資源があるのか把握しておくことが必要です。
今回の「在宅医療推進総合研修プログラム」の本セッションでは柏市を例に挙げ、全国平均や近隣の地域と比べてどのくらい資源が充実しているのか、また地域のどのあた... -
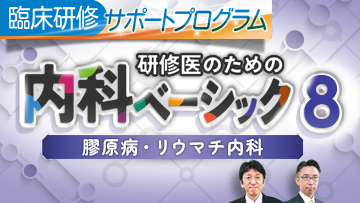 研修医のための内科ベーシック8 膠原病・リウマチ内科(全10回)第3回 全身性エリテマトーデス2023/04/01(土)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授全身性エリテマトーデスを発症するのはほとんどが女性で、多彩な症状を呈します。免疫の基本から解説しているので、全身性エリテマトーデスを調べる補体検査・抗体検査の解釈が身に付きます。
研修医のための内科ベーシック8 膠原病・リウマチ内科(全10回)第3回 全身性エリテマトーデス2023/04/01(土)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授全身性エリテマトーデスを発症するのはほとんどが女性で、多彩な症状を呈します。免疫の基本から解説しているので、全身性エリテマトーデスを調べる補体検査・抗体検査の解釈が身に付きます。
この番組のオリジナルは「総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病」です。 -
 Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第7回 Chest Pain - Diagnosis and Treatment2024/02/22(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic前回に続き、胸痛患者の診断と治療について。心筋梗塞は教科書的には“Myocardial Infarction”ですが、これは患者にはなじみのない言葉。疾患名や治療法・薬剤など、循環器内科でよく使う単語を中心に、患者に伝わる言い方を紹介します。手術や処置内容を言葉だけで患者に説明するのは、母国語でも難しいもの。レニック先生だったらどうするか、ロールプ...
Dr.レニックの演じる!臨床英会話(全10回)第7回 Chest Pain - Diagnosis and Treatment2024/02/22(木)公開 レニック ニコラス Tokyo Medical and Surgical Clinic前回に続き、胸痛患者の診断と治療について。心筋梗塞は教科書的には“Myocardial Infarction”ですが、これは患者にはなじみのない言葉。疾患名や治療法・薬剤など、循環器内科でよく使う単語を中心に、患者に伝わる言い方を紹介します。手術や処置内容を言葉だけで患者に説明するのは、母国語でも難しいもの。レニック先生だったらどうするか、ロールプ... -
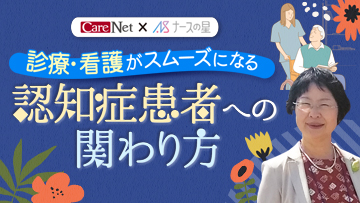 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方(全2回)後編 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方2023/12/20(水)公開 内田 陽子 群馬大学大学院保健学研究科 教授後編では、「認知症患者の関わりの原則」を具体例を交えながら紹介。個人レベルですぐに取り組める言葉がけなど、現場で役立つノウハウをお届けします。
診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方(全2回)後編 診療・看護がスムーズになる 認知症患者への関わり方2023/12/20(水)公開 内田 陽子 群馬大学大学院保健学研究科 教授後編では、「認知症患者の関わりの原則」を具体例を交えながら紹介。個人レベルですぐに取り組める言葉がけなど、現場で役立つノウハウをお届けします。 -
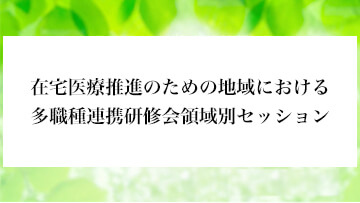 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第10回 【摂食嚥下・口腔ケア6】嚥下リハビリテーション62013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第9回の事例検討2のディスカッションをふまえ、講師の野原幹司先生が誤嚥性肺炎を予防することを念頭に、口腔ケア、嚥下リハビリテーション、薬剤変更、ワクチン利用、呼吸リハビリテーションなどを解説していきます。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第10回 【摂食嚥下・口腔ケア6】嚥下リハビリテーション62013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第9回の事例検討2のディスカッションをふまえ、講師の野原幹司先生が誤嚥性肺炎を予防することを念頭に、口腔ケア、嚥下リハビリテーション、薬剤変更、ワクチン利用、呼吸リハビリテーションなどを解説していきます。 -
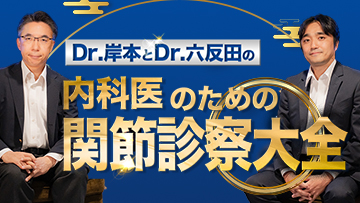 Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第9回 足(首)・足趾関節の診察2025/05/08(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授第9回は各関節の診察の最後のパートとなる、足関節(足首と足趾)を解説します。腱付着部炎、関節炎、整形外科的疾患を正確に見分けるには、複雑な解剖理解が不可欠です。岸本先生と六反田先生が、図解を交えて足関節の構造を丁寧に解説。続いて視診・可動域・触診の手技を動画で実演し、実践的なポイントを2人のエキスパートの診察から学べます。自信...
Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第9回 足(首)・足趾関節の診察2025/05/08(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授第9回は各関節の診察の最後のパートとなる、足関節(足首と足趾)を解説します。腱付着部炎、関節炎、整形外科的疾患を正確に見分けるには、複雑な解剖理解が不可欠です。岸本先生と六反田先生が、図解を交えて足関節の構造を丁寧に解説。続いて視診・可動域・触診の手技を動画で実演し、実践的なポイントを2人のエキスパートの診察から学べます。自信... -
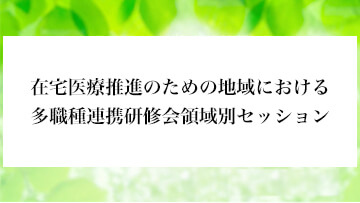 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第8回 【摂食嚥下・口腔ケア4】栄養摂取方法2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第7回の事例検討1を題材に、講師の野原幹司先生が解説していきます。在宅での主な栄養摂取方法は経口摂取、経管栄養、栄養静脈などがあげられます。それぞれのメリットとデメリットを考えながら、この患者さんに適した栄養摂取方法を導きます。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第8回 【摂食嚥下・口腔ケア4】栄養摂取方法2013/12/11(水)公開 野原 幹司 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部第7回の事例検討1を題材に、講師の野原幹司先生が解説していきます。在宅での主な栄養摂取方法は経口摂取、経管栄養、栄養静脈などがあげられます。それぞれのメリットとデメリットを考えながら、この患者さんに適した栄養摂取方法を導きます。 -
 Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第20回 経口キノロン系抗菌薬 52024/06/20(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表今回がキノロン系抗菌薬に関連した最後のレクチャーです。口腔・歯科領域感染症について、キノロン系投与の是非を含め、その全体像と具体的な抗菌薬処方のノウハウ・注意点を詳しく解説。キノロン系抗菌薬のまとめとして添付文書適応症と臨床的適応症とを対比しながらその使い方を整理します。加えて、消化器感染症の起炎菌にキノロン耐性が増加してい...
Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第20回 経口キノロン系抗菌薬 52024/06/20(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表今回がキノロン系抗菌薬に関連した最後のレクチャーです。口腔・歯科領域感染症について、キノロン系投与の是非を含め、その全体像と具体的な抗菌薬処方のノウハウ・注意点を詳しく解説。キノロン系抗菌薬のまとめとして添付文書適応症と臨床的適応症とを対比しながらその使い方を整理します。加えて、消化器感染症の起炎菌にキノロン耐性が増加してい... -
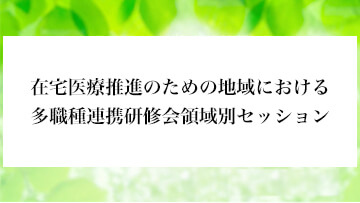 在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第12回 【栄養2】在宅での栄養管理の基本2014/01/08(水)公開 小野沢 滋 北里大学病院 患者支援センター部 副部長在宅療養中の高齢者の約3割は低栄養と言われており、栄養管理による状況改善が求められます。
在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会 領域別セッション(全15回)第12回 【栄養2】在宅での栄養管理の基本2014/01/08(水)公開 小野沢 滋 北里大学病院 患者支援センター部 副部長在宅療養中の高齢者の約3割は低栄養と言われており、栄養管理による状況改善が求められます。
本セッションでは、事例をもとにBMIや体重減少率の計算と栄養状況の評価を行い、在宅医療の多職種連携による介入方法をディスカッションします。
【事例】74歳男性。脳梗塞後、食事中にムセがではじめ、1カ月前に誤嚥性疑いの肺炎のため2週間入院... -
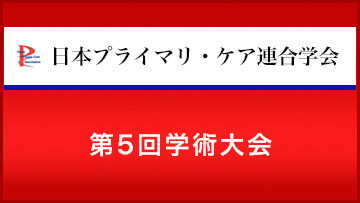 日本プライマリ・ケア連合学会 第5回 学術大会 (全12回)第8回 予防接種を考える -予防接種の実際と地域啓発活動-2014/08/27(水)公開 守屋 章成 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻 熱帯医学コース(...開業医の先生方は、子供を診る機会が多く予防接種をすることも増えているかと思います。 そのような状況のなか、お母さん達にどのように個別のプランを提示してあげていますか。 また今後、多くの人にワクチンを打って欲しいと願っていても、どのように啓発すべきか、頭を悩ませてはいませんか。 外来小児科研究会の中心的なメンバーとして活動され...
日本プライマリ・ケア連合学会 第5回 学術大会 (全12回)第8回 予防接種を考える -予防接種の実際と地域啓発活動-2014/08/27(水)公開 守屋 章成 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻 熱帯医学コース(...開業医の先生方は、子供を診る機会が多く予防接種をすることも増えているかと思います。 そのような状況のなか、お母さん達にどのように個別のプランを提示してあげていますか。 また今後、多くの人にワクチンを打って欲しいと願っていても、どのように啓発すべきか、頭を悩ませてはいませんか。 外来小児科研究会の中心的なメンバーとして活動され... -
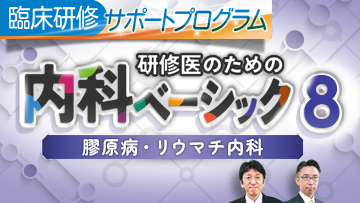 研修医のための内科ベーシック8 膠原病・リウマチ内科(全10回)第2回 ベーチェット病2023/04/01(土)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授20~30代に多いベーチェット病。まずは口内炎の鑑別診断から解説。口内炎・ざ瘡様皮疹などさまざまな所見を示すベーチェット病を実際の所見写真を確認しながら学習を進めることができます。
研修医のための内科ベーシック8 膠原病・リウマチ内科(全10回)第2回 ベーチェット病2023/04/01(土)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授20~30代に多いベーチェット病。まずは口内炎の鑑別診断から解説。口内炎・ざ瘡様皮疹などさまざまな所見を示すベーチェット病を実際の所見写真を確認しながら学習を進めることができます。
この番組のオリジナルは「総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病」です。 -
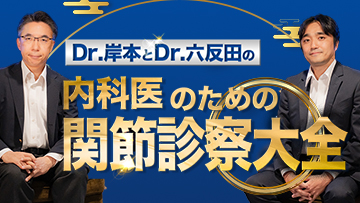 Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第7回 肘・顎・胸鎖・肩鎖関節の診察2025/03/20(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授第7回では、関節リウマチ病変の症状が現れやすい肘、顎、胸鎖、肩鎖関節を解説します。関節リウマチを疑うとともに、胸鎖・肩鎖関節では感染性疾患、肘関節ではテニス肘やゴルフ肘、顎関節では関節症など、頻出する疾患との鑑別も押さえます。さらに、各関節の解剖を踏まえた上で、岸本先生と六反田先生による視診・可動域(ROM)・触診の手技をレクチ...
Dr.岸本とDr.六反田の内科医のための関節診察大全(全10回)第7回 肘・顎・胸鎖・肩鎖関節の診察2025/03/20(木)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授第7回では、関節リウマチ病変の症状が現れやすい肘、顎、胸鎖、肩鎖関節を解説します。関節リウマチを疑うとともに、胸鎖・肩鎖関節では感染性疾患、肘関節ではテニス肘やゴルフ肘、顎関節では関節症など、頻出する疾患との鑑別も押さえます。さらに、各関節の解剖を踏まえた上で、岸本先生と六反田先生による視診・可動域(ROM)・触診の手技をレクチ...