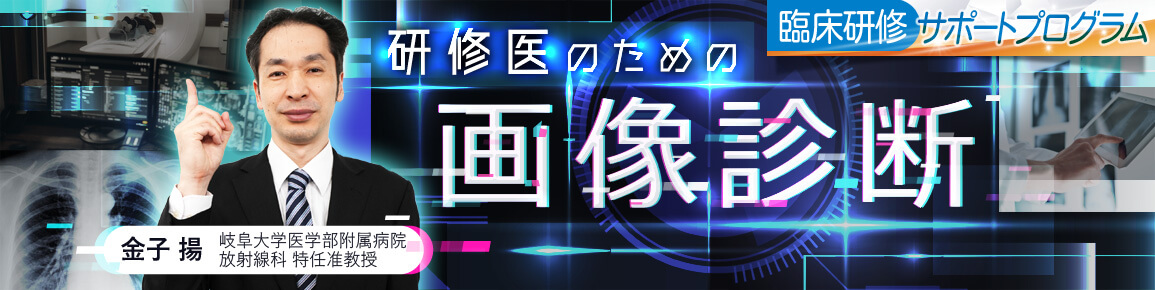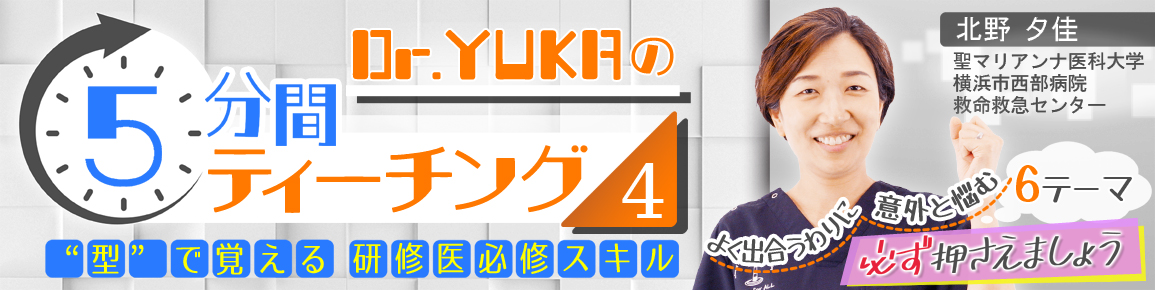在宅医療の番組検索結果
-
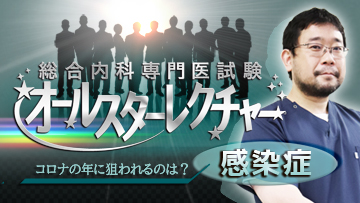 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第2回 新型コロナワクチン2021/04/07(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授国内で2021年2月下旬より医療者への先行接種が開始されたワクチン。新型コロナワクチンに採用された新しいプラットフォームであるmRNA2ワクチンについて、その原理を解説。非常に高い確率の発症予防効果ならびに重症化予防効果が証明されています。報告されている副反応や、アレルギーのある人に接種した場合のアナフィラキシーの頻度について、データ...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第2回 新型コロナワクチン2021/04/07(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授国内で2021年2月下旬より医療者への先行接種が開始されたワクチン。新型コロナワクチンに採用された新しいプラットフォームであるmRNA2ワクチンについて、その原理を解説。非常に高い確率の発症予防効果ならびに重症化予防効果が証明されています。報告されている副反応や、アレルギーのある人に接種した場合のアナフィラキシーの頻度について、データ... -
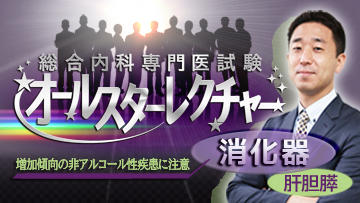 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第4回 肝硬変2021/06/30(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師肝硬変の主な原因は、これまではC型肝炎でしたが、直接型抗ウイルス薬(DAA)の進歩により減少が予想されており、対してNASHの割合が増加傾向です。特徴的な身体所見を確認します。診断と予後予測には肝線維化を評価。肝硬変は低栄養や低血糖に陥りやすく、死亡率増加や各種合併症につながります。合併症となる食道静脈瘤、肝性脳症、腹水、特発性細菌...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第4回 肝硬変2021/06/30(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師肝硬変の主な原因は、これまではC型肝炎でしたが、直接型抗ウイルス薬(DAA)の進歩により減少が予想されており、対してNASHの割合が増加傾向です。特徴的な身体所見を確認します。診断と予後予測には肝線維化を評価。肝硬変は低栄養や低血糖に陥りやすく、死亡率増加や各種合併症につながります。合併症となる食道静脈瘤、肝性脳症、腹水、特発性細菌... -
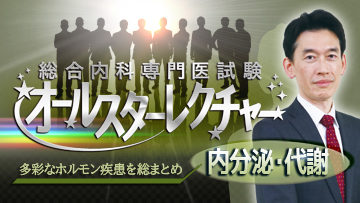 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 内分泌・代謝(全7回)第5回 代謝性疾患2020/11/18(水)公開 能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長総合内科専門医試験対策「内分泌・代謝」の第5回は、代謝性疾患について解説します。脂質異常症の診断基準は、LDL-C、HDL-C、中性脂肪を数値別にチェック。総コレステロールから善玉コレステロールを除いた”non-HDL-C”という新たな指標が注目されています。幼少期から動脈硬化性疾患を起こす原発性高コレステロール血症の治療には、PCSK-9阻害薬が近年...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 内分泌・代謝(全7回)第5回 代謝性疾患2020/11/18(水)公開 能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長総合内科専門医試験対策「内分泌・代謝」の第5回は、代謝性疾患について解説します。脂質異常症の診断基準は、LDL-C、HDL-C、中性脂肪を数値別にチェック。総コレステロールから善玉コレステロールを除いた”non-HDL-C”という新たな指標が注目されています。幼少期から動脈硬化性疾患を起こす原発性高コレステロール血症の治療には、PCSK-9阻害薬が近年... -
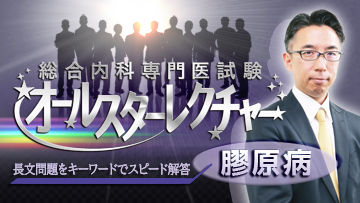 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第5回 大型血管炎2021/08/04(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授血管炎のうち大型血管炎に分類される高安動脈炎と巨細胞性動脈炎について岸本暢將先生が解説します。小型血管炎に比べて症状が出にくい大型血管炎。間欠性跛行や大動脈解離など深刻な症状が起きる前に見つけるには、不明熱、倦怠感、体重減少、関節痛などの症状で疑うことが重要です。高安動脈炎の9割が女性、発症年齢は20歳前後がピーク。X線、CT、MRI...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第5回 大型血管炎2021/08/04(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授血管炎のうち大型血管炎に分類される高安動脈炎と巨細胞性動脈炎について岸本暢將先生が解説します。小型血管炎に比べて症状が出にくい大型血管炎。間欠性跛行や大動脈解離など深刻な症状が起きる前に見つけるには、不明熱、倦怠感、体重減少、関節痛などの症状で疑うことが重要です。高安動脈炎の9割が女性、発症年齢は20歳前後がピーク。X線、CT、MRI... -
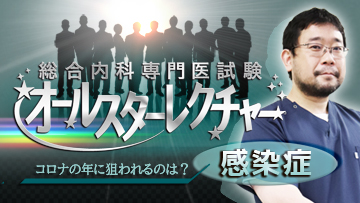 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第3回 マダニ媒介感染症2021/05/12(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授マダニ媒介感染症は、まず媒介者となるダニの生息分布域を確認。ライム病、ツツガムシ病、日本紅斑熱、SFTSなどの各種マダニ媒介感染症は、国内の流行地域が異なり、同じ県内でも微妙な地域差があります。輸入感染症の側面もあり、海外渡航歴も診断の手がかりに。症状には共通する特徴が多く見られますが、流行時期、潜伏期や刺し口の違いなどに注目し...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第3回 マダニ媒介感染症2021/05/12(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授マダニ媒介感染症は、まず媒介者となるダニの生息分布域を確認。ライム病、ツツガムシ病、日本紅斑熱、SFTSなどの各種マダニ媒介感染症は、国内の流行地域が異なり、同じ県内でも微妙な地域差があります。輸入感染症の側面もあり、海外渡航歴も診断の手がかりに。症状には共通する特徴が多く見られますが、流行時期、潜伏期や刺し口の違いなどに注目し... -
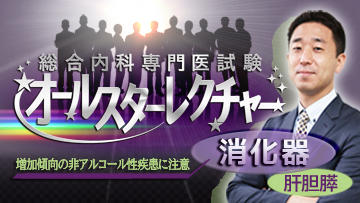 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第3回 自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎2021/06/16(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師自己免疫性肝炎AIHは中年以降の女性に好発する肝疾患で、約30%に慢性甲状腺炎やシェーグレン症候群といった他の自己免疫性疾患を合併。AIHの10~20%に原発性胆汁性胆管炎PBCを合併したオーバーラップ症候群がみられます。PBCも中年以降の女性に好発し、他の自己免疫性疾患と合併する場合があります。ともに無症状から非特異的な症状が多く、診断のポ...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第3回 自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎2021/06/16(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師自己免疫性肝炎AIHは中年以降の女性に好発する肝疾患で、約30%に慢性甲状腺炎やシェーグレン症候群といった他の自己免疫性疾患を合併。AIHの10~20%に原発性胆汁性胆管炎PBCを合併したオーバーラップ症候群がみられます。PBCも中年以降の女性に好発し、他の自己免疫性疾患と合併する場合があります。ともに無症状から非特異的な症状が多く、診断のポ... -
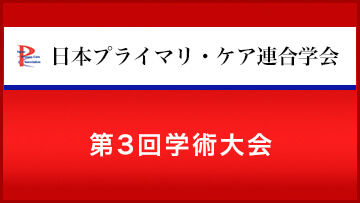 日本プライマリ・ケア連合学会 第3回 学術大会(全11回)教育講演2 心電図がプライマリ・ケアで輝くとき2012/11/28(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授心電図が苦手。「V1 の S 波と V5/6 の R 波を足して 35mm 以上で左室肥大」とか、「再分極には4種類のカリウムイオンチャネルが関与している」という、非常に細かい「六法全書」のようなイメージが肌に合わないとおっしゃる方は少なくありません。しかし、まるで受験勉強のような定義の詰め込みは、心電図がスクリーニングとして多く用いられるプラ...
日本プライマリ・ケア連合学会 第3回 学術大会(全11回)教育講演2 心電図がプライマリ・ケアで輝くとき2012/11/28(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授心電図が苦手。「V1 の S 波と V5/6 の R 波を足して 35mm 以上で左室肥大」とか、「再分極には4種類のカリウムイオンチャネルが関与している」という、非常に細かい「六法全書」のようなイメージが肌に合わないとおっしゃる方は少なくありません。しかし、まるで受験勉強のような定義の詰め込みは、心電図がスクリーニングとして多く用いられるプラ... -
 透析患者を診る前に1時間で詰め込む透析管理の基礎知識(全7回)第2回 血液透析のシステムと原理を理解する2017/05/17(水)公開 櫻田 勉 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 病院教授/大学病院腎臓・高血圧内科副部長/大学病...血液透析の原理、理解していますか? 第2回の「透析管理の基礎知識」では透析装置の基本構成と原理について解説します。透析中どんなことが行われているかがわかれば、より自信を持って透析管理ができるはずです。透析患者を診る前にまず、血液透析のシステムをしっかり頭に入れておきましょう。
透析患者を診る前に1時間で詰め込む透析管理の基礎知識(全7回)第2回 血液透析のシステムと原理を理解する2017/05/17(水)公開 櫻田 勉 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 病院教授/大学病院腎臓・高血圧内科副部長/大学病...血液透析の原理、理解していますか? 第2回の「透析管理の基礎知識」では透析装置の基本構成と原理について解説します。透析中どんなことが行われているかがわかれば、より自信を持って透析管理ができるはずです。透析患者を診る前にまず、血液透析のシステムをしっかり頭に入れておきましょう。 -
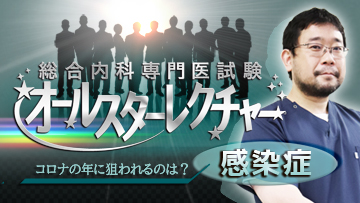 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第5回 発熱と発疹を伴う感染症2021/06/09(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授麻疹と風疹はどう鑑別するのか、症例から診断のポイントを解説。発疹の性状だけで鑑別するのは非常に難しく、ワクチン接種歴、罹患歴が極めて重要。髄膜炎菌感染症、リケッチア症、毒素性ショック症候群、アナフィラキシー、感染性心内膜炎といったショックを伴う皮疹では、診断の決め手となるキーワードを確認します。発熱・皮疹は輸入感染症の可能性...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第5回 発熱と発疹を伴う感染症2021/06/09(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授麻疹と風疹はどう鑑別するのか、症例から診断のポイントを解説。発疹の性状だけで鑑別するのは非常に難しく、ワクチン接種歴、罹患歴が極めて重要。髄膜炎菌感染症、リケッチア症、毒素性ショック症候群、アナフィラキシー、感染性心内膜炎といったショックを伴う皮疹では、診断の決め手となるキーワードを確認します。発熱・皮疹は輸入感染症の可能性... -
 透析患者を診る前に1時間で詰め込む透析管理の基礎知識(全7回)第3回 透析処方の実際2017/05/24(水)公開 櫻田 勉 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 病院教授/大学病院腎臓・高血圧内科副部長/大学病...透析室で受け取る「血液浄化記録」は完璧に理解できていますか? 良好な透析を行うためには、患者によってさまざまな設定を適切に行わなければなりません。その1つひとつの設定が患者の予後に関わります。たとえば、“高齢者の透析時間は短い”というのは、患者の予後を悪化させる是正すべき事実です。水分制限の計算方法など、患者ごとに考えなければな...
透析患者を診る前に1時間で詰め込む透析管理の基礎知識(全7回)第3回 透析処方の実際2017/05/24(水)公開 櫻田 勉 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 病院教授/大学病院腎臓・高血圧内科副部長/大学病...透析室で受け取る「血液浄化記録」は完璧に理解できていますか? 良好な透析を行うためには、患者によってさまざまな設定を適切に行わなければなりません。その1つひとつの設定が患者の予後に関わります。たとえば、“高齢者の透析時間は短い”というのは、患者の予後を悪化させる是正すべき事実です。水分制限の計算方法など、患者ごとに考えなければな... -
 岡田正人のアナフィラキシーLIVE コロナワクチン特講(全1回)岡田正人のアナフィラキシーLIVE コロナワクチン特講2021/05/26(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長※2021年5月19日時点の情報に基いた、2021年5月26日にライブストリーミング配信した講義であることをご留意のうえ、ご覧ください。
岡田正人のアナフィラキシーLIVE コロナワクチン特講(全1回)岡田正人のアナフィラキシーLIVE コロナワクチン特講2021/05/26(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長※2021年5月19日時点の情報に基いた、2021年5月26日にライブストリーミング配信した講義であることをご留意のうえ、ご覧ください。
日本でのコロナワクチン接種は医療者から高齢者へと進み、政府は7月末までの高齢者の接種完了を目指しています。 ワクチン接種の際に最も気を付けなければならないのは、言うまでもなくアナフィラキシーで、アレル... -
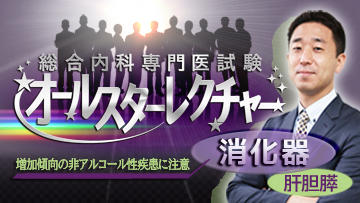 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第5回 急性胆嚢炎・胆管炎2021/07/14(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師急性胆嚢炎と急性胆管炎を比較しながら解説します。まず原因に胆石性の有無を確認することが重要。無石胆嚢炎は、症状は胆石性胆嚢炎と同じですが、外傷、心臓手術後、敗血症など高ストレス下で発症し、重症化しやすく死亡率が高いため、早期発見・早期治療が必須。急性胆嚢炎の画像診断は、腹部エコーが第1選択。診断基準となる数値を押さえます。急性...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第5回 急性胆嚢炎・胆管炎2021/07/14(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師急性胆嚢炎と急性胆管炎を比較しながら解説します。まず原因に胆石性の有無を確認することが重要。無石胆嚢炎は、症状は胆石性胆嚢炎と同じですが、外傷、心臓手術後、敗血症など高ストレス下で発症し、重症化しやすく死亡率が高いため、早期発見・早期治療が必須。急性胆嚢炎の画像診断は、腹部エコーが第1選択。診断基準となる数値を押さえます。急性... -
 明日からできるインスリン導入ABC(全6回)第2回 ココで見極め!インスリン導入の指標は4つ2015/12/02(水)公開 三澤 美和 大阪医科大学附属病院 総合診療科今回はインスリン導入の指標を4つに分けて、導入を考慮すべき患者さんの見分け方をレクチャーします。 インスリン抵抗性やインスリン分泌能などについて、参考にすべき検査数値もはっきりと提示。 反対にインスリンを使わないほうがよい場合や専門医に相談すべき症例も紹介します。
明日からできるインスリン導入ABC(全6回)第2回 ココで見極め!インスリン導入の指標は4つ2015/12/02(水)公開 三澤 美和 大阪医科大学附属病院 総合診療科今回はインスリン導入の指標を4つに分けて、導入を考慮すべき患者さんの見分け方をレクチャーします。 インスリン抵抗性やインスリン分泌能などについて、参考にすべき検査数値もはっきりと提示。 反対にインスリンを使わないほうがよい場合や専門医に相談すべき症例も紹介します。 -
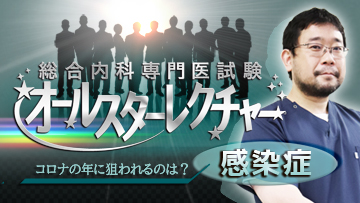 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第4回 血液培養2021/05/26(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授菌血症を疑ったときに行う血液培養。ガタガタと震える悪寒戦慄があると菌血症を疑うポイント。細菌性髄膜炎、腎盂腎炎、感染性心内膜炎といった、菌血症の頻度が高い感染症を知っておきましょう。血培は基本的に2セット採取します。コンタミネーションしやすい菌なのか、しにくい菌なのか、検出された菌の種類も判断の指標となります。血培で検出された...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第4回 血液培養2021/05/26(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授菌血症を疑ったときに行う血液培養。ガタガタと震える悪寒戦慄があると菌血症を疑うポイント。細菌性髄膜炎、腎盂腎炎、感染性心内膜炎といった、菌血症の頻度が高い感染症を知っておきましょう。血培は基本的に2セット採取します。コンタミネーションしやすい菌なのか、しにくい菌なのか、検出された菌の種類も判断の指標となります。血培で検出された... -
 明日からできるインスリン導入ABC(全6回)第3回 さあ実践!導入レジメンと口説き方2015/12/09(水)公開 三澤 美和 大阪医科大学附属病院 総合診療科インスリンを導入したほうがよい患者さんを見つけたら、次は実践です。 今回はズバリ、初めはこれだけでOKという持効型1回注射(BOT)から、強化療法までのレジメンを伝授! そして、インスリンに抵抗感を持つ患者さんにどんな説明をしたらよいのかも取り上げます。 三澤先生をはじめとした日本プライマリ・ケア学会糖尿病委員会メンバーの経験に基...
明日からできるインスリン導入ABC(全6回)第3回 さあ実践!導入レジメンと口説き方2015/12/09(水)公開 三澤 美和 大阪医科大学附属病院 総合診療科インスリンを導入したほうがよい患者さんを見つけたら、次は実践です。 今回はズバリ、初めはこれだけでOKという持効型1回注射(BOT)から、強化療法までのレジメンを伝授! そして、インスリンに抵抗感を持つ患者さんにどんな説明をしたらよいのかも取り上げます。 三澤先生をはじめとした日本プライマリ・ケア学会糖尿病委員会メンバーの経験に基... -
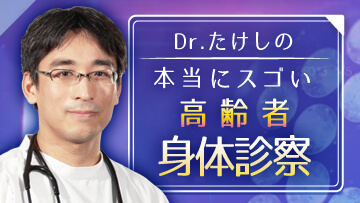 Dr.たけしの本当にスゴい高齢者身体診察(全6回)第4回 肺の診察2019/02/06(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長今回は、COPDを中心に肺の診察方法について解説します。 肺の診察と言えば聴診のイメージが強いですが、それだけではありません。さまざまな身体診察法を実技を交えて、しっかりとお教えします。
Dr.たけしの本当にスゴい高齢者身体診察(全6回)第4回 肺の診察2019/02/06(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長今回は、COPDを中心に肺の診察方法について解説します。 肺の診察と言えば聴診のイメージが強いですが、それだけではありません。さまざまな身体診察法を実技を交えて、しっかりとお教えします。
患者が呼吸困難で救急で運ばれてきた場合、COPDと心不全との鑑別が重要です。この鑑別が瞬時に行うことができるよう、各々の身体所見の取り方を理解し... -
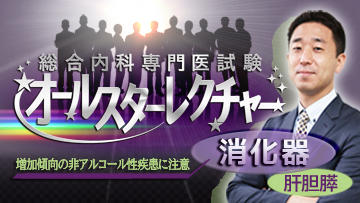 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第6回 急性膵炎2021/07/28(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師急性膵炎の2大原因はアルコールと胆石。強い腹痛を伴う疾患で、約7割が心窩部痛です。重症度診断のスコアとともに、重症垂炎を除外するためのHAPSというスコアも有用です。発症早期の多量輸液が死亡率を下げるため重要。治療については、抗菌薬や蛋白分解酵素阻害薬の有効性について、最新の見解を整理します。膵周囲の液体貯留の定義である「改訂Atlan...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第6回 急性膵炎2021/07/28(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師急性膵炎の2大原因はアルコールと胆石。強い腹痛を伴う疾患で、約7割が心窩部痛です。重症度診断のスコアとともに、重症垂炎を除外するためのHAPSというスコアも有用です。発症早期の多量輸液が死亡率を下げるため重要。治療については、抗菌薬や蛋白分解酵素阻害薬の有効性について、最新の見解を整理します。膵周囲の液体貯留の定義である「改訂Atlan... -
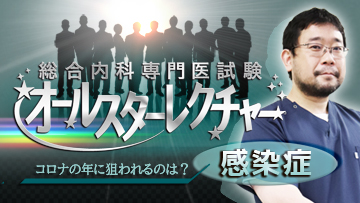 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第6回 性感染症2021/06/23(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授性感染症を疑った場合、性交渉歴を聞く上で大事な“5P”を確認。感染リスクの高い行為を聞き逃さないようにします。近年増加傾向にある梅毒は、発疹の性状がさまざまで、神経梅毒による認知症など多彩な症状が特徴。病期によって治療内容が異なります。性感染症を診断した場合、他の性感染症の合併リスクも高く、スクリーニング検査やパートナーの診断治...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 感染症(全7回)第6回 性感染症2021/06/23(水)公開 忽那 賢志 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授性感染症を疑った場合、性交渉歴を聞く上で大事な“5P”を確認。感染リスクの高い行為を聞き逃さないようにします。近年増加傾向にある梅毒は、発疹の性状がさまざまで、神経梅毒による認知症など多彩な症状が特徴。病期によって治療内容が異なります。性感染症を診断した場合、他の性感染症の合併リスクも高く、スクリーニング検査やパートナーの診断治... -
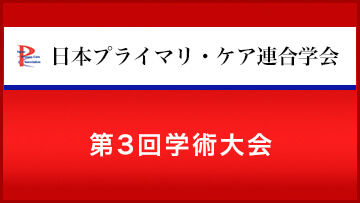 日本プライマリ・ケア連合学会 第3回 学術大会(全11回)教育講演7 プライマリ・ケアで一生使える耳鼻科診療2012/10/24(水)公開 高橋 優二 長崎大学病院 へき地病院再生支援・教育機構最近、家庭医療や ER 領域のセミナーで、耳鏡の使い方のワークショップ等が頻繁に開催されており、プライマリ・ケアにおける耳鼻咽喉科診療への関心が高まっています。本講演では、一生使えることを目標に下記3つの観点から話します。 1)頻度の多い耳疾患 2)緊急性の高い疾患、 3)プライマリ・ケア医が知っておくべき、耳鼻科医では通常知...
日本プライマリ・ケア連合学会 第3回 学術大会(全11回)教育講演7 プライマリ・ケアで一生使える耳鼻科診療2012/10/24(水)公開 高橋 優二 長崎大学病院 へき地病院再生支援・教育機構最近、家庭医療や ER 領域のセミナーで、耳鏡の使い方のワークショップ等が頻繁に開催されており、プライマリ・ケアにおける耳鼻咽喉科診療への関心が高まっています。本講演では、一生使えることを目標に下記3つの観点から話します。 1)頻度の多い耳疾患 2)緊急性の高い疾患、 3)プライマリ・ケア医が知っておくべき、耳鼻科医では通常知... -
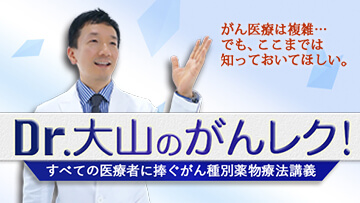 Dr.大山のがんレク! すべての医療者に捧ぐがん種別薬物療法講義(全15回)第1回 がん総論2017/02/01(水)公開 大山 優 亀田総合病院 腫瘍内科 部長「2人に1人はがんになる」時代。すべての医療者に捧ぐがん種別薬物療法講義「がんレク!」 第1回はその基本中の基本である「がん総論」。がん治療で使用される用語や指標、治療方法とその進め方をコンパクトに解説。さらに、注目を集める免疫療法をはじめ、医療のプロとして今必ず知っておくべきがんにまつわる知識をまとめました。
Dr.大山のがんレク! すべての医療者に捧ぐがん種別薬物療法講義(全15回)第1回 がん総論2017/02/01(水)公開 大山 優 亀田総合病院 腫瘍内科 部長「2人に1人はがんになる」時代。すべての医療者に捧ぐがん種別薬物療法講義「がんレク!」 第1回はその基本中の基本である「がん総論」。がん治療で使用される用語や指標、治療方法とその進め方をコンパクトに解説。さらに、注目を集める免疫療法をはじめ、医療のプロとして今必ず知っておくべきがんにまつわる知識をまとめました。 -
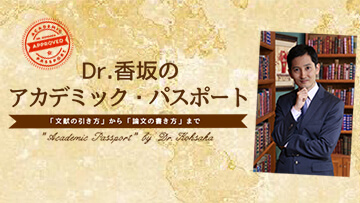 Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第1回 「失神の鑑別疾患を知りたい」 マニュアルや教科書の使い方を考える2016/08/24(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「失神の鑑別疾患を知りたい!」と相談に訪れます。 教科書、マニュアル、ガイドライン・・・・いろいろなものがあって何をどう調べればいいのかわからなくなったようです。 そんな広い話題を調べるにはどうすればいいのか、Dr.香坂がお教えします。
Dr.香坂のアカデミック・パスポート 「文献の引き方」から「論文の書き方」まで(全7回)第1回 「失神の鑑別疾患を知りたい」 マニュアルや教科書の使い方を考える2016/08/24(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授香坂俊先生の研究室にアカデミック・ドクターを目指す1人の医師が「失神の鑑別疾患を知りたい!」と相談に訪れます。 教科書、マニュアル、ガイドライン・・・・いろいろなものがあって何をどう調べればいいのかわからなくなったようです。 そんな広い話題を調べるにはどうすればいいのか、Dr.香坂がお教えします。 -
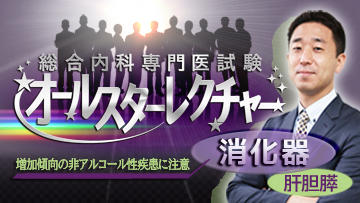 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第7回 慢性膵炎 IPMN2021/08/11(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師慢性膵炎の原因はアルコールが68%を占めています。飲酒と喫煙がリスク因子で、原因が不明瞭な場合は遺伝子検査の対象になります。試験で出題されやすい画像診断では、膵石・石灰化、主膵管不整拡張といった所見が重要。無症状で偶発的に見つかることが多い膵管内乳頭粘液性腫瘍IPMN。画像診断はMRCPが第1選択。浸潤がんや悪性所見を見落とさないように...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 消化器(肝胆膵)(全9回)第7回 慢性膵炎 IPMN2021/08/11(水)公開 山田 徹 東京科学大学 総合診療医学分野 講師慢性膵炎の原因はアルコールが68%を占めています。飲酒と喫煙がリスク因子で、原因が不明瞭な場合は遺伝子検査の対象になります。試験で出題されやすい画像診断では、膵石・石灰化、主膵管不整拡張といった所見が重要。無症状で偶発的に見つかることが多い膵管内乳頭粘液性腫瘍IPMN。画像診断はMRCPが第1選択。浸潤がんや悪性所見を見落とさないように... -
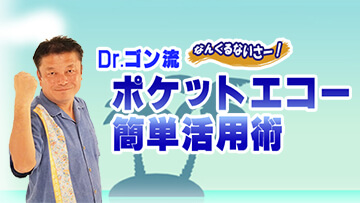 Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第1回 心臓へのアプローチと評価2014/02/12(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所心臓を胸骨左縁と心尖部からアプローチする方法について、プローブの実演とエコー画像の2画面を用いてわかりやすく解説します。ポケットエコーは肋間などの狭い窓から体内を観察するのに適しています。その特徴を生かした泰川恵吾先生流のアプローチ方法・ポイントは必見です。 さらに心エコー像評価の基本となる左室機能、弁膜疾患、右心系の評価方法...
Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第1回 心臓へのアプローチと評価2014/02/12(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所心臓を胸骨左縁と心尖部からアプローチする方法について、プローブの実演とエコー画像の2画面を用いてわかりやすく解説します。ポケットエコーは肋間などの狭い窓から体内を観察するのに適しています。その特徴を生かした泰川恵吾先生流のアプローチ方法・ポイントは必見です。 さらに心エコー像評価の基本となる左室機能、弁膜疾患、右心系の評価方法... -
 Dr.金井のCTクイズ 初級編(全12回)第8回 多彩な腹痛症例を画像で見分ける2021/11/10(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長腹痛はさまざまな原因疾患が疑われます。今回は消化管に関する疾患から複数のクイズを出題し、多彩な腹痛症例の鑑別に挑戦。似た症状のそれぞれの疾患について特徴的な画像所見を確認し、腹部CTの読影に強くなります。
Dr.金井のCTクイズ 初級編(全12回)第8回 多彩な腹痛症例を画像で見分ける2021/11/10(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長腹痛はさまざまな原因疾患が疑われます。今回は消化管に関する疾患から複数のクイズを出題し、多彩な腹痛症例の鑑別に挑戦。似た症状のそれぞれの疾患について特徴的な画像所見を確認し、腹部CTの読影に強くなります。