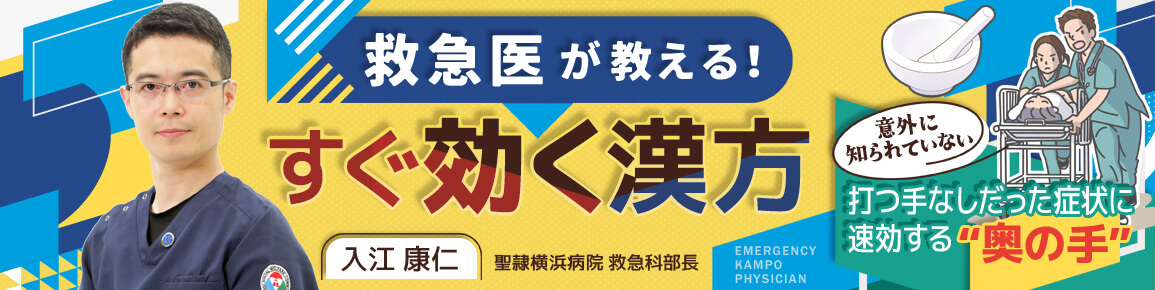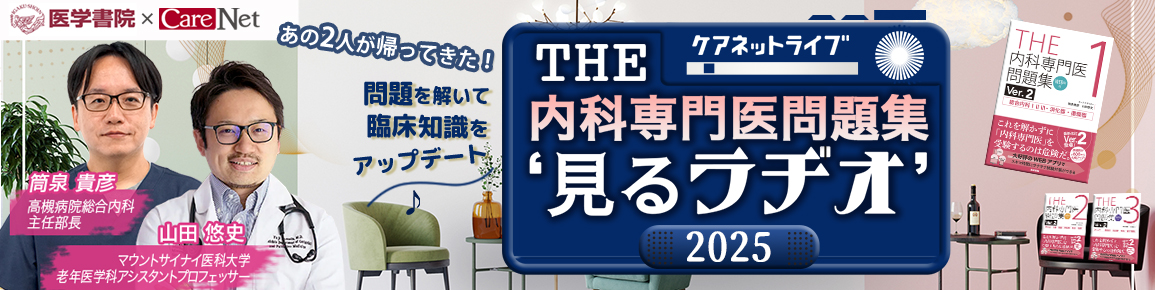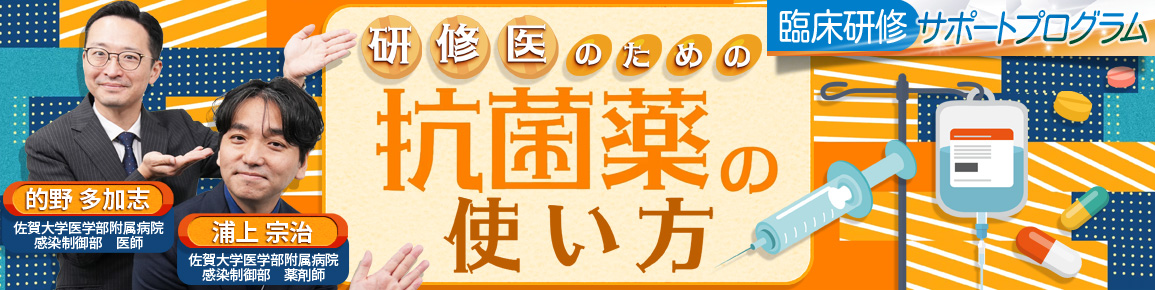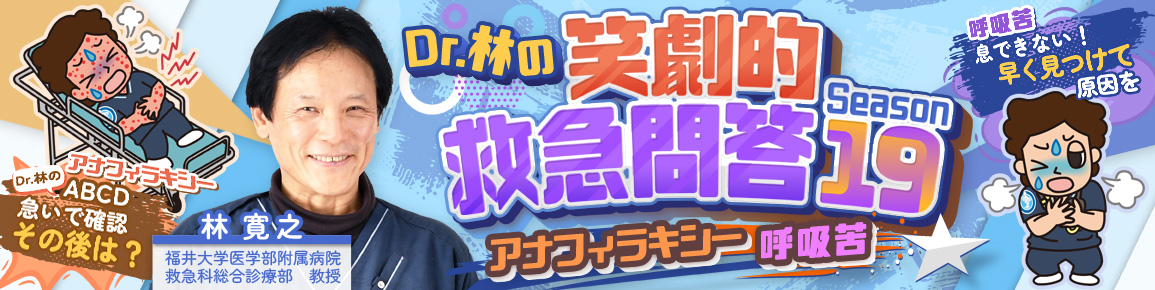救急科の番組検索結果
-
![Dr.林の笑劇的救急問答 [Season5] | 第4回 さ、さ、酸素!~気管支喘息~ Dr.林の笑劇的救急問答 [Season5] | 第4回 さ、さ、酸素!~気管支喘息~]( /movie/v_image/series/thumbnail/278_20181107105659.jpg) Dr.林の笑劇的救急問答 [Season5] (全4回)第4回 さ、さ、酸素!~気管支喘息~2009/12/18(金)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授気管支喘息は非常によくある疾患で、夜間外来などにも老若男女を問わず来院します。重症の患者さんが徒歩で来院することも決して珍しくありません。また「吸入で改善するだろう」などと甘く見ていると吸入薬が効かなかったり、来院後にみるみる具合が悪くなっていくケースもあります。そんなとき、次の一手はどうするか?さまざまな戦術を林寛之先生が披...
Dr.林の笑劇的救急問答 [Season5] (全4回)第4回 さ、さ、酸素!~気管支喘息~2009/12/18(金)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授気管支喘息は非常によくある疾患で、夜間外来などにも老若男女を問わず来院します。重症の患者さんが徒歩で来院することも決して珍しくありません。また「吸入で改善するだろう」などと甘く見ていると吸入薬が効かなかったり、来院後にみるみる具合が悪くなっていくケースもあります。そんなとき、次の一手はどうするか?さまざまな戦術を林寛之先生が披... -
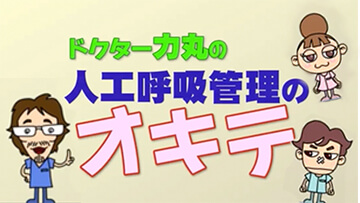 ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ(全14回)第9回 気道内圧波形に異常あり! …呼吸仕事量過多を見極める(2)2012/04/25(水)公開 古川 力丸 医療法人弘仁会 板倉病院 救急診療部呼吸仕事量過多の原因は、人工呼吸器の気道内圧波形から、「気道抵抗の上昇」、「コンプライアンスの低下」、「呼吸回数の増加」の3つのいずれかであることがわかります。では、それぞれに、どのような対応をすればいいのでしょう。原因となる疾患、病態はたくさんあって覚えるのは大変ですが、分類して考えれば難しくありません。人工呼吸器を使いこ...
ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ(全14回)第9回 気道内圧波形に異常あり! …呼吸仕事量過多を見極める(2)2012/04/25(水)公開 古川 力丸 医療法人弘仁会 板倉病院 救急診療部呼吸仕事量過多の原因は、人工呼吸器の気道内圧波形から、「気道抵抗の上昇」、「コンプライアンスの低下」、「呼吸回数の増加」の3つのいずれかであることがわかります。では、それぞれに、どのような対応をすればいいのでしょう。原因となる疾患、病態はたくさんあって覚えるのは大変ですが、分類して考えれば難しくありません。人工呼吸器を使いこ... -
 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第3回 呼吸困難へのアプローチ2015/02/25(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長呼吸困難の原因は、心疾患と肺疾患が大きく占めていますが、それ以外でも、貧血、心因性などのさまざまな原因があります。まずはキーワードから原因疾患を探っていきましょう。 そして、原因疾患の中でも重要度の高い、“心不全”と“慢性閉塞性肺疾患(COPD)”について取り上げ、詳しく見ていきます。 これらの診断に必要な身体所見は何か?そしてその...
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第3回 呼吸困難へのアプローチ2015/02/25(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長呼吸困難の原因は、心疾患と肺疾患が大きく占めていますが、それ以外でも、貧血、心因性などのさまざまな原因があります。まずはキーワードから原因疾患を探っていきましょう。 そして、原因疾患の中でも重要度の高い、“心不全”と“慢性閉塞性肺疾患(COPD)”について取り上げ、詳しく見ていきます。 これらの診断に必要な身体所見は何か?そしてその... -
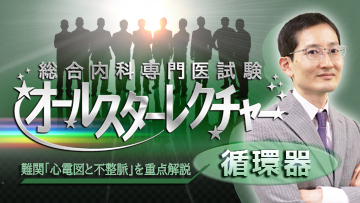 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 循環器(全8回)第5回 不整脈と心電図(1)2021/03/31(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授総合内科専門医試験の循環器の試験領域での最大の山場となる不整脈。今回は頻脈性の上室性不整脈のポイントを押さえます。不整脈はマクロリエントリー型とミクロリエントリー型に分類。発作性上室性頻拍(PSVT)は薬でコントロール。ただし、WPW症候群合併時の対応は異なるので要注意。PSVTと心房粗動(AF)は、アブレーションの奏効率も非常に良好です...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 循環器(全8回)第5回 不整脈と心電図(1)2021/03/31(水)公開 香坂 俊 慶應義塾大学 循環器内科 准教授総合内科専門医試験の循環器の試験領域での最大の山場となる不整脈。今回は頻脈性の上室性不整脈のポイントを押さえます。不整脈はマクロリエントリー型とミクロリエントリー型に分類。発作性上室性頻拍(PSVT)は薬でコントロール。ただし、WPW症候群合併時の対応は異なるので要注意。PSVTと心房粗動(AF)は、アブレーションの奏効率も非常に良好です... -
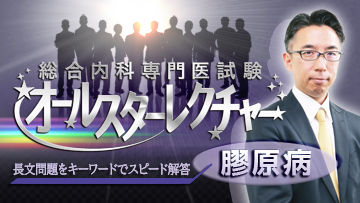 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第3回 全身性エリテマトーデス シェーグレン症候群2021/07/07(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授リンパ球に関わる獲得免疫系の疾患を取り上げます。全身性エリテマトーデスSLEを発症するのはほとんどが女性で、多彩な症状を呈します。血小板数、白血球数、赤血球数の低下、CH50、C3、C4の低下が非常に特徴的な所見です。疾患と関連する抗核抗体も総合内科専門医試験に出やすいポイント。ループス腎炎はSLEに起因する糸球体腎炎です。口腔乾燥やドラ...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第3回 全身性エリテマトーデス シェーグレン症候群2021/07/07(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授リンパ球に関わる獲得免疫系の疾患を取り上げます。全身性エリテマトーデスSLEを発症するのはほとんどが女性で、多彩な症状を呈します。血小板数、白血球数、赤血球数の低下、CH50、C3、C4の低下が非常に特徴的な所見です。疾患と関連する抗核抗体も総合内科専門医試験に出やすいポイント。ループス腎炎はSLEに起因する糸球体腎炎です。口腔乾燥やドラ... -
 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第4回 失神へのアプローチ2015/03/18(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長失神とは脳血流の低下によって起こる一過性意識消失発作のことで、まずはてんかんなどと区別することから始めましょう。そして予後から考え、脳血管障害、心原性、起立性低血圧、薬剤性、神経介在性の順に鑑別を行なっていきます。失神の原因を導き出すために考慮すべき検査をそれぞれの原因ごとに提示していきます。でも結局は病歴と身体診察に勝る検...
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第4回 失神へのアプローチ2015/03/18(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長失神とは脳血流の低下によって起こる一過性意識消失発作のことで、まずはてんかんなどと区別することから始めましょう。そして予後から考え、脳血管障害、心原性、起立性低血圧、薬剤性、神経介在性の順に鑑別を行なっていきます。失神の原因を導き出すために考慮すべき検査をそれぞれの原因ごとに提示していきます。でも結局は病歴と身体診察に勝る検... -
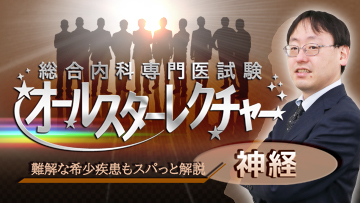 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 神経(全7回)第1回 脳卒中 超急性期2020/08/05(水)公開 井口 正寛 沖縄県立中部病院 脳神経内科総合内科専門医試験対策「神経」の第1回のテーマは、超急性期の脳卒中。近年では血栓溶解療法や血管内治療が推奨されています。rt-PA静注血栓溶解療法は有効性のエビデンスが蓄積され、脳卒中の発症から治療可能な時間が延長されています。MRIの画像所見を評価スケールに照らし合わせて適応を判断することが重要です。脳卒中の血管内治療は、ステントリ...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 神経(全7回)第1回 脳卒中 超急性期2020/08/05(水)公開 井口 正寛 沖縄県立中部病院 脳神経内科総合内科専門医試験対策「神経」の第1回のテーマは、超急性期の脳卒中。近年では血栓溶解療法や血管内治療が推奨されています。rt-PA静注血栓溶解療法は有効性のエビデンスが蓄積され、脳卒中の発症から治療可能な時間が延長されています。MRIの画像所見を評価スケールに照らし合わせて適応を判断することが重要です。脳卒中の血管内治療は、ステントリ... -
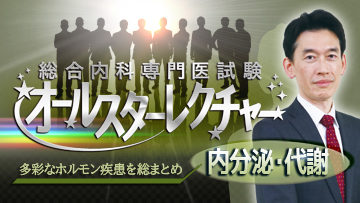 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 内分泌・代謝(全7回)第3回 下垂体疾患 副甲状腺疾患 骨粗鬆症2020/09/30(水)公開 能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長総合内科専門医試験対策「内分泌・代謝」の第3回は、下垂体疾患・副甲状腺疾患・骨粗鬆症について解説します。さまざまなホルモンを分泌する下垂体。初めにホルモンの種類と全身の標的器官を押さえます。下垂体ホルモンの過剰分泌や分泌低下によって引き起こされる各疾患も要チェック。副甲状腺ホルモン疾患の鑑別には、カルシウムとリンの値に注目しま...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 内分泌・代謝(全7回)第3回 下垂体疾患 副甲状腺疾患 骨粗鬆症2020/09/30(水)公開 能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長総合内科専門医試験対策「内分泌・代謝」の第3回は、下垂体疾患・副甲状腺疾患・骨粗鬆症について解説します。さまざまなホルモンを分泌する下垂体。初めにホルモンの種類と全身の標的器官を押さえます。下垂体ホルモンの過剰分泌や分泌低下によって引き起こされる各疾患も要チェック。副甲状腺ホルモン疾患の鑑別には、カルシウムとリンの値に注目しま... -
 Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第1回 不整脈心電図のルーチンワーク2021/05/12(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長見るべきところが多すぎて、確定診断が容易ではない不整脈の心電図。苦手な人も多いのではないでしょうか。では、どのように見ていくのでしょうか。そうです。実は確定診断にこだわる必要はありません。マネジメントに必要な情報を読み取ればよいのです。そのために、まずは、不整脈心電図に出会ったときに行うべきルーチンワークを確認しましょう。実...
Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第1回 不整脈心電図のルーチンワーク2021/05/12(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長見るべきところが多すぎて、確定診断が容易ではない不整脈の心電図。苦手な人も多いのではないでしょうか。では、どのように見ていくのでしょうか。そうです。実は確定診断にこだわる必要はありません。マネジメントに必要な情報を読み取ればよいのです。そのために、まずは、不整脈心電図に出会ったときに行うべきルーチンワークを確認しましょう。実... -
 Dr.金井のCTクイズ 初級編(全12回)第1回 頭部メジャー疾患の「非典型例」を押さえる2021/04/21(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長患者さんは、2〜3日前から続く頭痛で来院した女性。主訴と頭部CTから、原因疾患を突き止めます。メジャーな疾患では典型例だけでなく、非典型例の特徴も押さえておくことがポイントです。
Dr.金井のCTクイズ 初級編(全12回)第1回 頭部メジャー疾患の「非典型例」を押さえる2021/04/21(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長患者さんは、2〜3日前から続く頭痛で来院した女性。主訴と頭部CTから、原因疾患を突き止めます。メジャーな疾患では典型例だけでなく、非典型例の特徴も押さえておくことがポイントです。 -
![Dr.林の笑劇的救急問答 [Season8] | 第2回 外傷基本のABC(後編) CASE2:外傷性出血ショック!高所から転落したロシア人男性 Dr.林の笑劇的救急問答 [Season8] | 第2回 外傷基本のABC(後編) CASE2:外傷性出血ショック!高所から転落したロシア人男性]( /movie/v_image/series/thumbnail/92_20181107103649.jpg) Dr.林の笑劇的救急問答 [Season8](全8回)第2回 外傷基本のABC(後編) CASE2:外傷性出血ショック!高所から転落したロシア人男性2012/07/25(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授外傷診療を行ううえでの基本操作(ABC)後編。外傷性の出血性ショックに対する処置の方法を学びます。 【症例2】ロシア人男性。港に寄港している船の船員で港での作業中に高さ約6mから転落した。バイタルサインは血圧100/80mmHg、脈拍100/m、SpO2は酸素投与下で92%。エコーでは腹腔内出血(+)、肺挫傷(+)、不安定骨盤骨折(ー)。研修医は2Lから...
Dr.林の笑劇的救急問答 [Season8](全8回)第2回 外傷基本のABC(後編) CASE2:外傷性出血ショック!高所から転落したロシア人男性2012/07/25(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授外傷診療を行ううえでの基本操作(ABC)後編。外傷性の出血性ショックに対する処置の方法を学びます。 【症例2】ロシア人男性。港に寄港している船の船員で港での作業中に高さ約6mから転落した。バイタルサインは血圧100/80mmHg、脈拍100/m、SpO2は酸素投与下で92%。エコーでは腹腔内出血(+)、肺挫傷(+)、不安定骨盤骨折(ー)。研修医は2Lから... -
 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第5回 発熱へのアプローチ2015/04/08(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長発熱はもっともコモンな症候ですが、原因が多岐にわたり、対応には膨大な知識が必要となります。今回はその中から、とくに“すぐに対応しなければならない発熱”、“不明熱”をピックアップして解説します。 原因を絞り込むためには、どんな材料が必要なのか。症状、検査、病歴など、さまざまな切り口から整理していきましょう。
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断(全6回)第5回 発熱へのアプローチ2015/04/08(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長発熱はもっともコモンな症候ですが、原因が多岐にわたり、対応には膨大な知識が必要となります。今回はその中から、とくに“すぐに対応しなければならない発熱”、“不明熱”をピックアップして解説します。 原因を絞り込むためには、どんな材料が必要なのか。症状、検査、病歴など、さまざまな切り口から整理していきましょう。 -
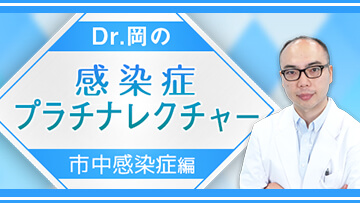 Dr.岡の感染症プラチナレクチャー 市中感染症編(全11回)第9回 感染性心内膜炎2018/07/18(水)公開 岡 秀昭 埼玉医科大学総合医療センター 総合診療内科・感染症科 教授感染性心内膜炎(IE)は最も見逃されやすい感染症の中の1つです。 なぜ見逃してしまうのか、見逃さないためのポイントは? そして、IEと診断したときにやるべきこととは? 実臨床に即した内容をシンプルに、かつわかりやすく解説します。
Dr.岡の感染症プラチナレクチャー 市中感染症編(全11回)第9回 感染性心内膜炎2018/07/18(水)公開 岡 秀昭 埼玉医科大学総合医療センター 総合診療内科・感染症科 教授感染性心内膜炎(IE)は最も見逃されやすい感染症の中の1つです。 なぜ見逃してしまうのか、見逃さないためのポイントは? そして、IEと診断したときにやるべきこととは? 実臨床に即した内容をシンプルに、かつわかりやすく解説します。 -
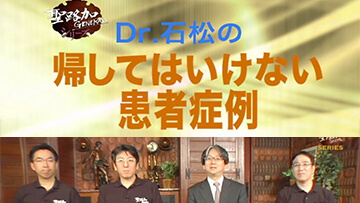 聖路加GENERAL<Dr.石松の帰してはいけない患者症例>(全8回)第1回 頭痛篇(1)2012/09/12(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:石松 伸一 氏
聖路加GENERAL<Dr.石松の帰してはいけない患者症例>(全8回)第1回 頭痛篇(1)2012/09/12(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:石松 伸一 氏
さまざまな症状で救急に来る患者さん。最も重要なのは、緊急性の判断です。緊急性の高い疾患を見逃して、帰してしまうようなことだけは避けなければなりません。問診、身体所見、必要な検査を迅速に行い、疾患の鑑別を行いますが、判断の難しいケース、ときには緊急性なしと判断されてしまう場合もあります。 今回は、頭... -
![Dr.林の笑劇的救急問答 [Season7] | 第6回 ACLS Upgrade 2010 CASE2 78歳男性 Dr.林の笑劇的救急問答 [Season7] | 第6回 ACLS Upgrade 2010 CASE2 78歳男性]( /movie/v_image/series/thumbnail/27_20181107113224.jpg) Dr.林の笑劇的救急問答 [Season7](全8回)第6回 ACLS Upgrade 2010 CASE2 78歳男性2011/09/14(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授心肺蘇生が必要な心静止の症例をガイドライン2010に則ってDr.林こと林寛之先生が解説、更にプラスアルファの知識を身につけACLSの達人を目指す後編! 【症例2】78歳男性。自宅のトイレで倒れ孫が連れてきたが待合室で意識消失した。顔面蒼白で意識呼吸ともに(-)、PEAで心肺蘇生を開始する。駆けつけたDr.林の指導のもとチームの合言葉は「さるも聴...
Dr.林の笑劇的救急問答 [Season7](全8回)第6回 ACLS Upgrade 2010 CASE2 78歳男性2011/09/14(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授心肺蘇生が必要な心静止の症例をガイドライン2010に則ってDr.林こと林寛之先生が解説、更にプラスアルファの知識を身につけACLSの達人を目指す後編! 【症例2】78歳男性。自宅のトイレで倒れ孫が連れてきたが待合室で意識消失した。顔面蒼白で意識呼吸ともに(-)、PEAで心肺蘇生を開始する。駆けつけたDr.林の指導のもとチームの合言葉は「さるも聴... -
 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2(全6回)第4回 しびれへのアプローチ2015/11/04(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長しびれは診療する機会が多く、かつ鑑別疾患が多岐にわたり、診断に苦慮することも多い症候です。 今回は、末梢神経障害に絞って解説します。 末梢神経障害は、単神経障害、多発単神経障害、多発神経障害に分類されます。その中でも、とくに高頻度で、原因疾患が100以上もある“ややこしい”多発神経障害を中心に取り扱います。 診断に必要なのは「系統...
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2(全6回)第4回 しびれへのアプローチ2015/11/04(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長しびれは診療する機会が多く、かつ鑑別疾患が多岐にわたり、診断に苦慮することも多い症候です。 今回は、末梢神経障害に絞って解説します。 末梢神経障害は、単神経障害、多発単神経障害、多発神経障害に分類されます。その中でも、とくに高頻度で、原因疾患が100以上もある“ややこしい”多発神経障害を中心に取り扱います。 診断に必要なのは「系統... -
![Dr.林の笑劇的救急問答 [Season10] 胸痛編 | 第1回 急性心筋梗塞1 「胸がキュンキュンする80歳女性」 Dr.林の笑劇的救急問答 [Season10] 胸痛編 | 第1回 急性心筋梗塞1 「胸がキュンキュンする80歳女性」]( /movie/v_image/series/thumbnail/157_20181108110805.jpg) Dr.林の笑劇的救急問答 [Season10] 胸痛編(全4回)第1回 急性心筋梗塞1 「胸がキュンキュンする80歳女性」2014/09/10(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回のお題は急性心筋梗塞。 救急や臨床の現場で最も見落としたくない疾患の1つ。しかし、心筋梗塞は「非典型例こそ典型」と言われるほど、非典型例が当たり前です。 胸痛だけに着目していたら、見落としてしまうことも・・・。胸痛のない心筋梗塞は22~35%もあります。 心筋梗塞の診断のPitfallsやDr.林のNERD、30cmの法則など、林寛之先生の覚え...
Dr.林の笑劇的救急問答 [Season10] 胸痛編(全4回)第1回 急性心筋梗塞1 「胸がキュンキュンする80歳女性」2014/09/10(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回のお題は急性心筋梗塞。 救急や臨床の現場で最も見落としたくない疾患の1つ。しかし、心筋梗塞は「非典型例こそ典型」と言われるほど、非典型例が当たり前です。 胸痛だけに着目していたら、見落としてしまうことも・・・。胸痛のない心筋梗塞は22~35%もあります。 心筋梗塞の診断のPitfallsやDr.林のNERD、30cmの法則など、林寛之先生の覚え... -
 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2(全6回)第2回 頭痛へのアプローチ2015/09/23(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長第2回は頭痛へのアプローチです。 頭痛の原因はなんと194にも分類されます。(国際頭痛分類) 実際にはすべてを鑑別するというのは非常に困難ですので、この番組では、よくある原因や見落としてはいけない疾患に絞って詳しく解説します。 見落としてはならない2次性頭痛、片頭痛と緊張型頭痛の鑑別が難しい1次性頭痛。 それぞれ、原因の鑑別に必要...
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断2(全6回)第2回 頭痛へのアプローチ2015/09/23(水)公開 上田 剛士 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 部長第2回は頭痛へのアプローチです。 頭痛の原因はなんと194にも分類されます。(国際頭痛分類) 実際にはすべてを鑑別するというのは非常に困難ですので、この番組では、よくある原因や見落としてはいけない疾患に絞って詳しく解説します。 見落としてはならない2次性頭痛、片頭痛と緊張型頭痛の鑑別が難しい1次性頭痛。 それぞれ、原因の鑑別に必要... -
 救急エコー最速RUSH!(全6回)第4回 TANK(1)2017/03/15(水)公開 瀬良 誠 福井県立病院 救命救急センター 医長PUMPに続いて、RUSH Exam.の3つのコンポーネントのうちの1つ「TANK」についてみていきます。 TANKのメインは、“FAST”。体腔内に液体貯留がないかどうかの検索を行います。 でも、もちろん、ただのFASTではなく、Step Beyond FAST! TANKの見るべきビューとそれぞれの施行ポイント、そしてその所見の取りかたをしっかりとマスターしましょう!
救急エコー最速RUSH!(全6回)第4回 TANK(1)2017/03/15(水)公開 瀬良 誠 福井県立病院 救命救急センター 医長PUMPに続いて、RUSH Exam.の3つのコンポーネントのうちの1つ「TANK」についてみていきます。 TANKのメインは、“FAST”。体腔内に液体貯留がないかどうかの検索を行います。 でも、もちろん、ただのFASTではなく、Step Beyond FAST! TANKの見るべきビューとそれぞれの施行ポイント、そしてその所見の取りかたをしっかりとマスターしましょう! -
![Dr.林の笑劇的救急問答[Season14] | 第2回 意識障害2 目は口ほどにモノを言う Dr.林の笑劇的救急問答[Season14] | 第2回 意識障害2 目は口ほどにモノを言う]( /movie/v_image/series/thumbnail/282_20181113114808.jpg) Dr.林の笑劇的救急問答[Season14](全8回)第2回 意識障害2 目は口ほどにモノを言う2018/12/12(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授意識障害は系統立てて、診ていくことが重要です。それらをしっかりと把握しておきましょう。また、今回の「笑劇的救急問答」では、 JCSやGCSの意識レベルの判定をどうやって行うのか、Dr.林ならではの例を挙げて、しっかりとお教えします。これでもう、判断に迷うことはありません!
Dr.林の笑劇的救急問答[Season14](全8回)第2回 意識障害2 目は口ほどにモノを言う2018/12/12(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授意識障害は系統立てて、診ていくことが重要です。それらをしっかりと把握しておきましょう。また、今回の「笑劇的救急問答」では、 JCSやGCSの意識レベルの判定をどうやって行うのか、Dr.林ならではの例を挙げて、しっかりとお教えします。これでもう、判断に迷うことはありません! -
 Dr.林の笑劇的救急問答【Season12】(全8回)第2回 Step Beyond ACLS 心肺蘇生ガイドライン2015 Part2!2016/06/29(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授「院内で倒れ、死戦期呼吸を呈する56歳男性」今回のDr.林の笑劇的救急問答は 前回に引き続き、林寛之先生が心肺蘇生ガイドライン2015の変更のポイントを中心に解説します。 心臓カテーテルの適応、蘇生後の体温管理療法や酸素投与、そしてアドレナリン投与など これまで救急の現場で当たり前に行われてきたことが大きく変わっています! 一つひとつエビ...
Dr.林の笑劇的救急問答【Season12】(全8回)第2回 Step Beyond ACLS 心肺蘇生ガイドライン2015 Part2!2016/06/29(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授「院内で倒れ、死戦期呼吸を呈する56歳男性」今回のDr.林の笑劇的救急問答は 前回に引き続き、林寛之先生が心肺蘇生ガイドライン2015の変更のポイントを中心に解説します。 心臓カテーテルの適応、蘇生後の体温管理療法や酸素投与、そしてアドレナリン投与など これまで救急の現場で当たり前に行われてきたことが大きく変わっています! 一つひとつエビ... -
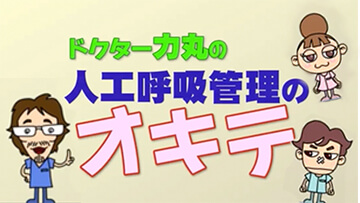 ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ(全14回)コラム3 初期設定総まとめ2012/05/23(水)公開 古川 力丸 医療法人弘仁会 板倉病院 救急診療部前回までの学習で、基本的な知識は習得できたはず。でも、いざ、人工呼吸器を設定するとなると腰が引けちゃいますよね。そこで、今回は、人工呼吸器の初期設定から、その後の調整までの流れをわかりやすく解説。これだけ覚えておけば、人工呼吸管理がすぐに始められます。
ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ(全14回)コラム3 初期設定総まとめ2012/05/23(水)公開 古川 力丸 医療法人弘仁会 板倉病院 救急診療部前回までの学習で、基本的な知識は習得できたはず。でも、いざ、人工呼吸器を設定するとなると腰が引けちゃいますよね。そこで、今回は、人工呼吸器の初期設定から、その後の調整までの流れをわかりやすく解説。これだけ覚えておけば、人工呼吸管理がすぐに始められます。 -
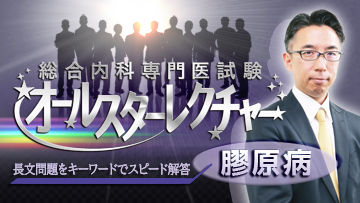 総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第4回 全身性強皮症 混合性結合組織疾患 皮膚筋炎・多発性筋炎2021/07/21(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授皮膚や内臓が硬化、線維化する全身性強皮症SSc。限局皮膚型とびまん皮膚型に分けられ、手指にレイノー現象がみられます。抗体の種類によって合併する臓器障害が異なる点が総合内科専門医試験試験でもよく問われます。混合性結合組織疾患MCTDの診断のポイントは、抗U1-RNP抗体と肺高血圧症。皮膚筋炎・多発性筋炎PM/DMでは、悪性腫瘍と急速進行性の間質...
総合内科専門医試験オールスターレクチャー 膠原病(全7回)第4回 全身性強皮症 混合性結合組織疾患 皮膚筋炎・多発性筋炎2021/07/21(水)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授皮膚や内臓が硬化、線維化する全身性強皮症SSc。限局皮膚型とびまん皮膚型に分けられ、手指にレイノー現象がみられます。抗体の種類によって合併する臓器障害が異なる点が総合内科専門医試験試験でもよく問われます。混合性結合組織疾患MCTDの診断のポイントは、抗U1-RNP抗体と肺高血圧症。皮膚筋炎・多発性筋炎PM/DMでは、悪性腫瘍と急速進行性の間質... -
 Dr.林の笑劇的救急問答 Season15(全8回)第3回 身じろぎできない腹痛!急性腹症?2019/11/06(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回の腹痛のテーマは「急性腹症」、主に腹膜炎について取り上げます。急性腹症は、いかに早く診断し、治療するかの時間との勝負です。 腹痛患者のそれぞれの状態や疾患による痛がり方、腹膜刺激症状の出方、身体診察の仕方など、なぜそうなのかの理由も含めて林寛之先生がしっかりとお教えします。これであなたも急性腹症に強くなれるはず。そうすれ...
Dr.林の笑劇的救急問答 Season15(全8回)第3回 身じろぎできない腹痛!急性腹症?2019/11/06(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回の腹痛のテーマは「急性腹症」、主に腹膜炎について取り上げます。急性腹症は、いかに早く診断し、治療するかの時間との勝負です。 腹痛患者のそれぞれの状態や疾患による痛がり方、腹膜刺激症状の出方、身体診察の仕方など、なぜそうなのかの理由も含めて林寛之先生がしっかりとお教えします。これであなたも急性腹症に強くなれるはず。そうすれ...