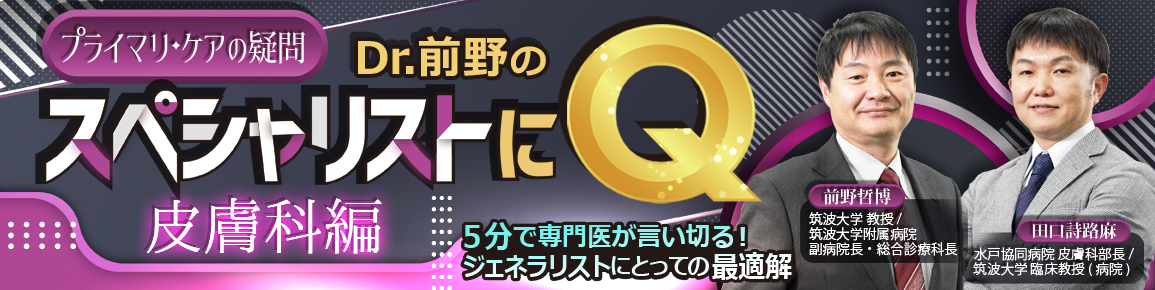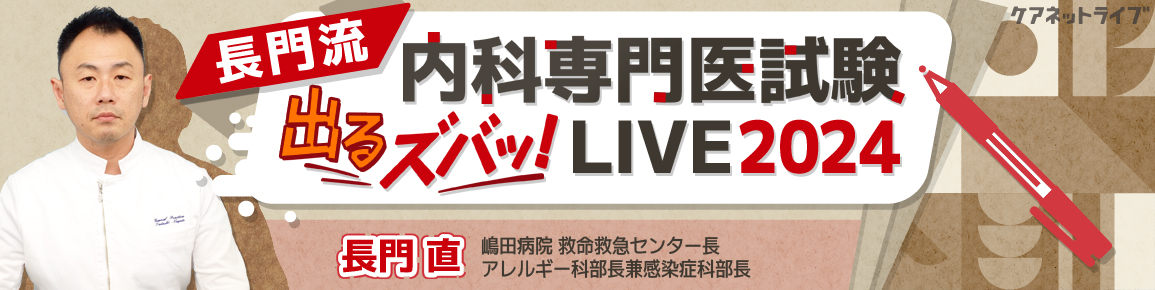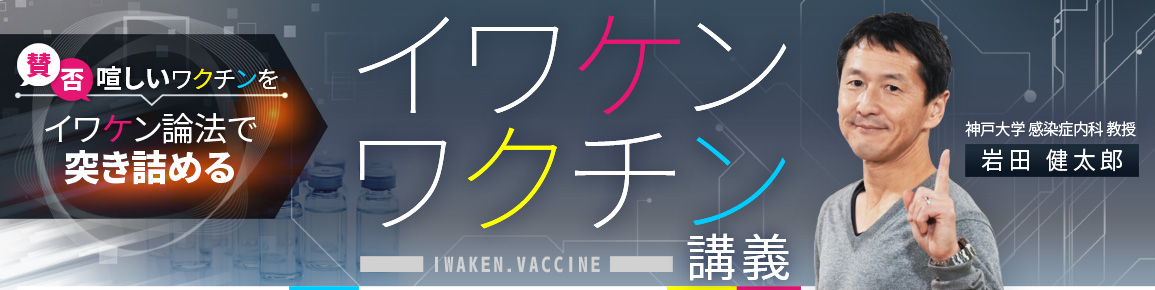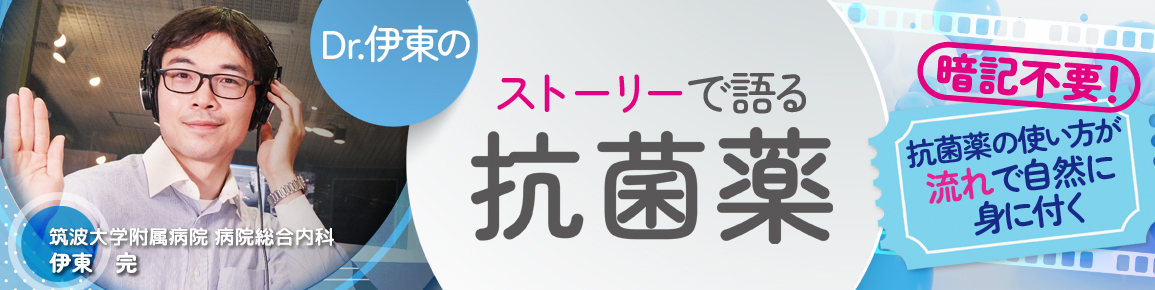番組検索結果
-
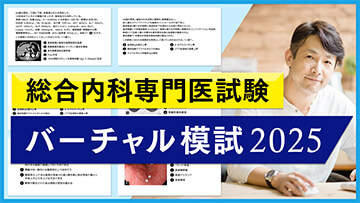 総合内科専門医試験 バーチャル模試2025(全5回)第3回 第41~60問2025/09/25(木)公開 ケアネット総合内科専門医試験対策チーム ケアネット第3回は、総合内科専門医試験バーチャル模試2025の第41~60問です。
総合内科専門医試験 バーチャル模試2025(全5回)第3回 第41~60問2025/09/25(木)公開 ケアネット総合内科専門医試験対策チーム ケアネット第3回は、総合内科専門医試験バーチャル模試2025の第41~60問です。 -
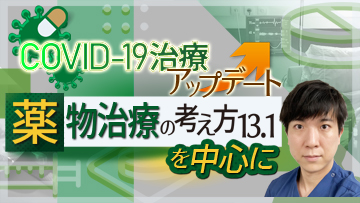 COVID-19治療アップデート「薬物治療の考え方13.1」を中心に (全1回)COVID-19治療アップデート「薬物治療の考え方13.1」を中心に2022/04/13(水)公開 黒田 浩一 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 副医長※4月7日時点の情報であることをご留意のうえご覧ください。
COVID-19治療アップデート「薬物治療の考え方13.1」を中心に (全1回)COVID-19治療アップデート「薬物治療の考え方13.1」を中心に2022/04/13(水)公開 黒田 浩一 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 副医長※4月7日時点の情報であることをご留意のうえご覧ください。
感染症学会は、COVID-19治療薬の使い方の指針として「COVID-19に対する薬物治療の考え方」をまとめ、公開しています。この指針は常にアップデートされており、現在は、2月18日公開の13.1版が最新版です。 今回、日本感染症学会 COVID-19 治療薬タスクフォースメンバーであり、かつ最前線... -
 サルコペニアを防ぐ臨床栄養学(全6回)第1回 栄養管理の基本2021/11/17(水)公開 吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター長、リハビリテーション科副...医学部でも現場でも栄養療法を体系的に学ぶ機会はありませんが、疾患治療と栄養療法を組み合わせることで、治療効果を最大限に引き出すことが可能です。まずは、患者さんの栄養状態を評価し、低栄養・サルコペニアを早期に発見しましょう。第1回では、実際の栄養管理の流れや栄養指標の種類や特徴、診断方法を解説します。
サルコペニアを防ぐ臨床栄養学(全6回)第1回 栄養管理の基本2021/11/17(水)公開 吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター長、リハビリテーション科副...医学部でも現場でも栄養療法を体系的に学ぶ機会はありませんが、疾患治療と栄養療法を組み合わせることで、治療効果を最大限に引き出すことが可能です。まずは、患者さんの栄養状態を評価し、低栄養・サルコペニアを早期に発見しましょう。第1回では、実際の栄養管理の流れや栄養指標の種類や特徴、診断方法を解説します。 -
 一発診断(全15回)第12回 両手足のむくみ・かゆみと膝関節痛の26歳女性2019/10/02(水)公開 宮田 靖志 愛知医科大学 地域総合診療医学寄附講座・教授 医学教育センター・副センター長 プライマ...今回は、「両手足のむくみ・かゆみと膝関節痛の26歳女性」と「部活中に胸痛・呼吸苦が出現した15歳男性」の2症例を取り上げます。さまざまな鑑別疾患が想起されますが、どこが診断の決め手となるのか。そして、その治療についても解説します。 さあ、あなたの一発診断は?
一発診断(全15回)第12回 両手足のむくみ・かゆみと膝関節痛の26歳女性2019/10/02(水)公開 宮田 靖志 愛知医科大学 地域総合診療医学寄附講座・教授 医学教育センター・副センター長 プライマ...今回は、「両手足のむくみ・かゆみと膝関節痛の26歳女性」と「部活中に胸痛・呼吸苦が出現した15歳男性」の2症例を取り上げます。さまざまな鑑別疾患が想起されますが、どこが診断の決め手となるのか。そして、その治療についても解説します。 さあ、あなたの一発診断は? -
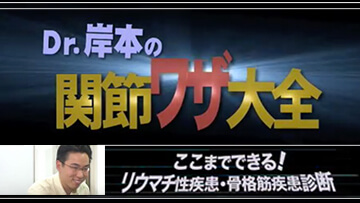 Dr.岸本の関節ワザ大全(全10回)第9回 身体診察のコツ4膝・足2008/05/23(金)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授体の全体重がかかる膝は、老若男女問わず特に痛めやすい箇所です。しかし一概に「膝が痛い」と言っても原因はさまざま。膝関節の他、いろいろな腱や靭帯、半月体、滑液包のうち、どこに障害があるのか見極めることが診断の第一歩です。また、足を診るときは手と同様に患部関節の分布が重要です。これを押さえておくと難しかった診断が一目でついてしま...
Dr.岸本の関節ワザ大全(全10回)第9回 身体診察のコツ4膝・足2008/05/23(金)公開 岸本 暢將 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 准教授体の全体重がかかる膝は、老若男女問わず特に痛めやすい箇所です。しかし一概に「膝が痛い」と言っても原因はさまざま。膝関節の他、いろいろな腱や靭帯、半月体、滑液包のうち、どこに障害があるのか見極めることが診断の第一歩です。また、足を診るときは手と同様に患部関節の分布が重要です。これを押さえておくと難しかった診断が一目でついてしま... -
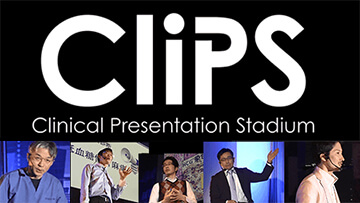 CliPS - Clinical Presentation Stadium - @TOKYO2013(全25回)Shock 【六反田諒】2013/08/28(水)公開 六反田 諒 亀田総合病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 部長とびきり印象的なショックの症例を紹介します。イタリアンレストランに勤務されている61歳の男性で、主訴は「気分が悪い」、それ以外はまったく症状がありません。血圧66/42 mmHg、脈拍114/minとショック状態ですが、熱はなく、サチュレーションも正常です。不思議なことに、過去20年間、毎年1回ずつ同様の症状に陥ると言います。さて、この患者さんは...
CliPS - Clinical Presentation Stadium - @TOKYO2013(全25回)Shock 【六反田諒】2013/08/28(水)公開 六反田 諒 亀田総合病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 部長とびきり印象的なショックの症例を紹介します。イタリアンレストランに勤務されている61歳の男性で、主訴は「気分が悪い」、それ以外はまったく症状がありません。血圧66/42 mmHg、脈拍114/minとショック状態ですが、熱はなく、サチュレーションも正常です。不思議なことに、過去20年間、毎年1回ずつ同様の症状に陥ると言います。さて、この患者さんは... -
 聖路加GENERAL<呼吸器内科> (全8回)第5回 慢性の咳には まずCXRから CASE1 62歳男性2012/02/08(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:仁多 寅彦氏(聖路加国際病院呼吸器内科)
聖路加GENERAL<呼吸器内科> (全8回)第5回 慢性の咳には まずCXRから CASE1 62歳男性2012/02/08(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:仁多 寅彦氏(聖路加国際病院呼吸器内科)
今回は、慢性咳嗽の症例です。15本/日の喫煙を40年間続けてきた62歳の男性。咳嗽の出現をきっかけに救急室を受診し、気管支炎の疑いで抗菌薬を処方されましたが、改善しませんでした。その後、抗菌薬を変えたところ、効果があったかにみえましたが、またすぐに咳嗽が再燃してしまいました。こ... -
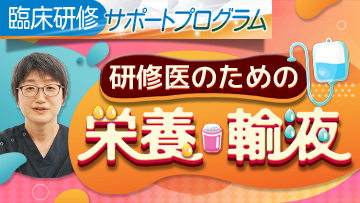 研修医のための栄養・輸液(全10回)第6回 輸液の常識2024/07/25(木)公開 伊在井 淳子 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 救急外科科長 NST委員会委員長今回から輸液の話題に入っていきます。知らないと困る基本的知識から。輸液の目的は大きく2つ、体液管理と栄養補給です。細胞外液補充液と維持輸液がそれぞれ血管内に入った後どう分布するのかを理解すれば、目的に応じてどちらを選択すべきか簡単に判断できます。
研修医のための栄養・輸液(全10回)第6回 輸液の常識2024/07/25(木)公開 伊在井 淳子 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 救急外科科長 NST委員会委員長今回から輸液の話題に入っていきます。知らないと困る基本的知識から。輸液の目的は大きく2つ、体液管理と栄養補給です。細胞外液補充液と維持輸液がそれぞれ血管内に入った後どう分布するのかを理解すれば、目的に応じてどちらを選択すべきか簡単に判断できます。 -
 総合内科専門医試験対策 “苦手”科目をクイック復習 2016(全5回)第5回 神経2016/08/03(水)公開 民谷 健太郎 ケアネット プログラムディレクター / 救急科専門医「総合内科専門医試験対策」第5回は神経。プライマリの現場でもよく出くわすcommonな疾患を取り扱っていますが、試験で混乱しないためのヒントが満載です。神経領域では、似たような疾患名でも扱う薬剤や検査が全く異なります。薬理作用を理解して、きちんと整理することが総合内科専門医試験攻略の近道です。
総合内科専門医試験対策 “苦手”科目をクイック復習 2016(全5回)第5回 神経2016/08/03(水)公開 民谷 健太郎 ケアネット プログラムディレクター / 救急科専門医「総合内科専門医試験対策」第5回は神経。プライマリの現場でもよく出くわすcommonな疾患を取り扱っていますが、試験で混乱しないためのヒントが満載です。神経領域では、似たような疾患名でも扱う薬剤や検査が全く異なります。薬理作用を理解して、きちんと整理することが総合内科専門医試験攻略の近道です。 -
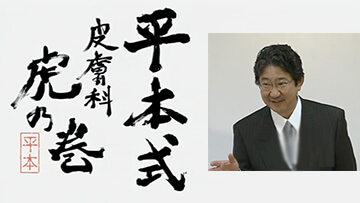 平本式 皮膚科虎の巻(全8回)第5回 因・機・疹、遠・近・考の極意を知れ!その12004/07/01(木)公開 平本 力 石岡・平本皮膚科医院 院長/自治医科大学 非常勤講師上巻(第4回まで)の講義で、湿疹と、それに紛らわしい疾患に対応できるようになったのではないでしょうか。しかし、皮膚科疾患には湿疹だけでなくさまざまなものがあります。皮膚科が苦手という先生方の理由の多くは『診断名がわからない』こと。教科書の写真と見比べてもはっきりしないし、どこに注目して診たらいいのかわからない。そんな疑問と格闘し...
平本式 皮膚科虎の巻(全8回)第5回 因・機・疹、遠・近・考の極意を知れ!その12004/07/01(木)公開 平本 力 石岡・平本皮膚科医院 院長/自治医科大学 非常勤講師上巻(第4回まで)の講義で、湿疹と、それに紛らわしい疾患に対応できるようになったのではないでしょうか。しかし、皮膚科疾患には湿疹だけでなくさまざまなものがあります。皮膚科が苦手という先生方の理由の多くは『診断名がわからない』こと。教科書の写真と見比べてもはっきりしないし、どこに注目して診たらいいのかわからない。そんな疑問と格闘し... -
 Dr.長尾の胸部X線クイズ 上級編(全6回)第3回 肺紋理が濃く見える、その理由は?2018/08/22(水)公開 長尾 大志 島根大学医学部地域医療教育学講座 教授 <br>島根大学医学部附属病院 総合診療医センター/病...胸部X線で肺紋理が濃く見えるとき、どんな疾患を疑いますか?今回の2問を読み解く鍵は、肺紋理。なぜこの線が見えるのか原理から理解していれば、パっと鑑別を挙げられます。 胸部X線写真の読影に欠かせない重要な肺紋理の読み方を解説するとともに、鑑別に活かすポイントを伝授します。
Dr.長尾の胸部X線クイズ 上級編(全6回)第3回 肺紋理が濃く見える、その理由は?2018/08/22(水)公開 長尾 大志 島根大学医学部地域医療教育学講座 教授 <br>島根大学医学部附属病院 総合診療医センター/病...胸部X線で肺紋理が濃く見えるとき、どんな疾患を疑いますか?今回の2問を読み解く鍵は、肺紋理。なぜこの線が見えるのか原理から理解していれば、パっと鑑別を挙げられます。 胸部X線写真の読影に欠かせない重要な肺紋理の読み方を解説するとともに、鑑別に活かすポイントを伝授します。 -
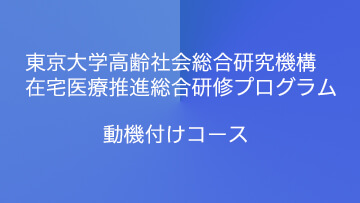 東京大学高齢社会総合研究機構 在宅医療推進総合研修プログラム 動機付けコース(全13回)第1回 21世紀前半の社会と医療、在宅医の果たすべき役割2012/06/27(水)公開 辻 哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授2025年に75歳以上人口のピークを迎える日本において、大都市圏では未曾有の高齢化が見込まれており、特に千葉県、埼玉県、神奈川県で顕著となっています。
東京大学高齢社会総合研究機構 在宅医療推進総合研修プログラム 動機付けコース(全13回)第1回 21世紀前半の社会と医療、在宅医の果たすべき役割2012/06/27(水)公開 辻 哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授2025年に75歳以上人口のピークを迎える日本において、大都市圏では未曾有の高齢化が見込まれており、特に千葉県、埼玉県、神奈川県で顕著となっています。
この見込みが何を示唆しているかと言えば、大都市圏で認知症高齢者と、一人暮らしないし夫婦暮らし高齢者が激増するということです。
では、このような高齢者を支えるにはどうすればい... -
![カスガ先生の精神科入門[負けるが勝ち!] | 第2回 うつ病に関する必要最小限の知識 カスガ先生の精神科入門[負けるが勝ち!] | 第2回 うつ病に関する必要最小限の知識]( /movie/v_image/series/thumbnail/55_20181107105457.jpg) カスガ先生の精神科入門[負けるが勝ち!](全4回)第2回 うつ病に関する必要最小限の知識2008/02/29(金)公開 春日 武彦 東京未来大学教授 / 心療内科病院・楽山精神科の医師でなくとも、うつ病を併発した(あるいは、その疑いがある)患者を診る機会は少なくないことでしょう。今回は、現代の流行病とも言うべき、この「うつ病」に関する、医師であれば必ず知っておかなければならない「必要最小限の」知識を春日武彦先生が凝縮してお届けします。 もちろん視聴者の皆様も、この疾患についてのひととおりの知識は...
カスガ先生の精神科入門[負けるが勝ち!](全4回)第2回 うつ病に関する必要最小限の知識2008/02/29(金)公開 春日 武彦 東京未来大学教授 / 心療内科病院・楽山精神科の医師でなくとも、うつ病を併発した(あるいは、その疑いがある)患者を診る機会は少なくないことでしょう。今回は、現代の流行病とも言うべき、この「うつ病」に関する、医師であれば必ず知っておかなければならない「必要最小限の」知識を春日武彦先生が凝縮してお届けします。 もちろん視聴者の皆様も、この疾患についてのひととおりの知識は... -
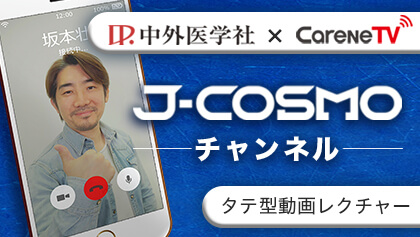 J-COSMOチャンネル(全6回)第1回【坂本壮】心停止対応のキモはこれだ【病棟急変ただいま対応中!】2019/04/10(水)公開 坂本 壮 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 救急救命科医長/ 臨床研修センター副センター長第1回は、『J-COSMO』編集主幹の坂本壮先生が「心停止対応のGolden rule」をレクチャーします。数ある心停止評価スケールに必ず共通するバイタルサインは?胸骨圧迫は実は「●●」が大切!本当に心停止全例に対処が必要か?坂本先生が考える心停止対応の最重要ポイント3つに絞って、臨床で身に付けたスキルとパッションを惜しみなくお伝えします。
J-COSMOチャンネル(全6回)第1回【坂本壮】心停止対応のキモはこれだ【病棟急変ただいま対応中!】2019/04/10(水)公開 坂本 壮 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 救急救命科医長/ 臨床研修センター副センター長第1回は、『J-COSMO』編集主幹の坂本壮先生が「心停止対応のGolden rule」をレクチャーします。数ある心停止評価スケールに必ず共通するバイタルサインは?胸骨圧迫は実は「●●」が大切!本当に心停止全例に対処が必要か?坂本先生が考える心停止対応の最重要ポイント3つに絞って、臨床で身に付けたスキルとパッションを惜しみなくお伝えします。 -
 聖路加GENERAL<内分泌疾患>(全6回)第4回 糖尿病の悪化だと思ったら…2011/04/18(月)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:出雲 博子氏 人間ドックにおいて、糖尿病の疑いということで精査を勧められていた68歳の男性。 肥満も家族歴もないことから受診していませんでしたが、急な体重減少をきっかけに初めて検査を受けたところ、A1Cが13.7%と、急激に上昇していることが判明。 高血糖の要因は、I型II型糖尿病以外にも、膵炎、膵がん、ヘモクロマトーシス、Cush...
聖路加GENERAL<内分泌疾患>(全6回)第4回 糖尿病の悪化だと思ったら…2011/04/18(月)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:出雲 博子氏 人間ドックにおいて、糖尿病の疑いということで精査を勧められていた68歳の男性。 肥満も家族歴もないことから受診していませんでしたが、急な体重減少をきっかけに初めて検査を受けたところ、A1Cが13.7%と、急激に上昇していることが判明。 高血糖の要因は、I型II型糖尿病以外にも、膵炎、膵がん、ヘモクロマトーシス、Cush... -
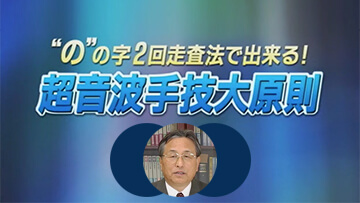 “の”の字2回走査法で出来る!超音波手技大原則(全11回)第8回 膀胱・前立腺、婦人科の基本走査と症例2007/03/30(金)公開 杉山 髙 医療法人社団 綾和会 浜松南病院 画像診断部顧問腹部エコーでの「膀胱・前立腺」および「子宮・卵巣」検査は、適度な膀胱容量で検査を行うことが大切です。膀胱・前立腺検査は、縦断走査、横断走査により膀胱・前立腺の描出から消失を繰り返し行います。腫瘍と血腫との鑑別や結石の動きなど、体位変換も適宜取り入れ、リアルタイムで観察します。前立腺では、大きさ、内部エコー像に注目します。前立...
“の”の字2回走査法で出来る!超音波手技大原則(全11回)第8回 膀胱・前立腺、婦人科の基本走査と症例2007/03/30(金)公開 杉山 髙 医療法人社団 綾和会 浜松南病院 画像診断部顧問腹部エコーでの「膀胱・前立腺」および「子宮・卵巣」検査は、適度な膀胱容量で検査を行うことが大切です。膀胱・前立腺検査は、縦断走査、横断走査により膀胱・前立腺の描出から消失を繰り返し行います。腫瘍と血腫との鑑別や結石の動きなど、体位変換も適宜取り入れ、リアルタイムで観察します。前立腺では、大きさ、内部エコー像に注目します。前立... -
 Dr.水野のうたう♪心音レクチャー(全7回)第7回 聴診手技の勘所2017/03/08(水)公開 水野 篤 聖路加国際病院 循環器内科/医療の質管理室最終回は実際の聴診手技のポイントをレクチャー。基本を押さえて正しく心音を聴けるようになりましょう!
Dr.水野のうたう♪心音レクチャー(全7回)第7回 聴診手技の勘所2017/03/08(水)公開 水野 篤 聖路加国際病院 循環器内科/医療の質管理室最終回は実際の聴診手技のポイントをレクチャー。基本を押さえて正しく心音を聴けるようになりましょう! -
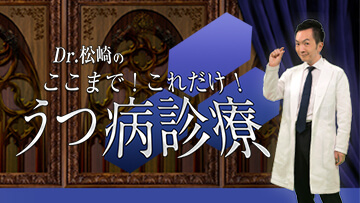 Dr.松崎のここまで!これだけ!うつ病診療(全8回)第2回 うつ病の「原因」を探索する2015/09/30(水)公開 松崎 朝樹 筑波大学精神神経科 講師うつ病になりやすい性格は本当にあるのでしょうか。離婚や死別などストレスになる出来事があった場合の抑うつはうつ病ではないのでしょうか。 今回は混乱しやすい、うつ病の「原因」についてレクチャーします。さらにうつ病と適応障害の違いも解説。この内容を知っておくだけで格段に診断をしやすくなること間違いありません!
Dr.松崎のここまで!これだけ!うつ病診療(全8回)第2回 うつ病の「原因」を探索する2015/09/30(水)公開 松崎 朝樹 筑波大学精神神経科 講師うつ病になりやすい性格は本当にあるのでしょうか。離婚や死別などストレスになる出来事があった場合の抑うつはうつ病ではないのでしょうか。 今回は混乱しやすい、うつ病の「原因」についてレクチャーします。さらにうつ病と適応障害の違いも解説。この内容を知っておくだけで格段に診断をしやすくなること間違いありません! -
 Dr.金井のCTクイズ 中級編(全12回)第1回 頭部:見た目は派手だがそれだけではない2022/12/21(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長第1問は頭部から。 3日前から左上肢麻痺、構音障害があるとのことで家族に連れられて受診した62歳男性。神経所見が認められるため、頭部CTを撮影しました。 画像を確認してみましょう。あれ、見た目は派手な画像で、簡単に読影できる…。いえいえ、それだけではありませんよ。
Dr.金井のCTクイズ 中級編(全12回)第1回 頭部:見た目は派手だがそれだけではない2022/12/21(水)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長第1問は頭部から。 3日前から左上肢麻痺、構音障害があるとのことで家族に連れられて受診した62歳男性。神経所見が認められるため、頭部CTを撮影しました。 画像を確認してみましょう。あれ、見た目は派手な画像で、簡単に読影できる…。いえいえ、それだけではありませんよ。 -
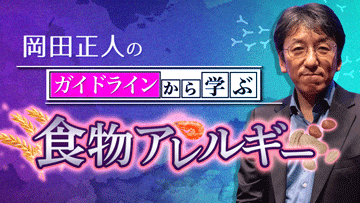 岡田正人のガイドラインから学ぶ食物アレルギー(全1回)岡田正人のガイドラインから学ぶ食物アレルギー2022/09/14(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長ガイドラインから学ぶシリーズに岡田正人氏が登壇!
岡田正人のガイドラインから学ぶ食物アレルギー(全1回)岡田正人のガイドラインから学ぶ食物アレルギー2022/09/14(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長ガイドラインから学ぶシリーズに岡田正人氏が登壇!
世界標準のアレルギー診療を知り尽くした岡田先生が、食物アレルギー診療ガイドライン2021について解説します。 疫学の変化から、食物依存性運動誘発アナフィラキシーや、新しくガイドラインに追加された「成人の食物アレルギー」まで幅広く紹介。 pork-cat症候群やbird-egg症候群、納豆アレ... -
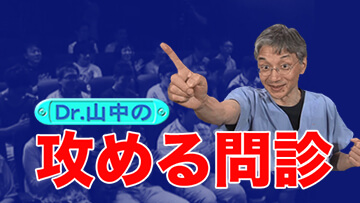 Dr.山中の攻める問診(全13回)第13回 攻める身体所見2014/05/28(水)公開 山中 克郎 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 特任教授/ 諏訪中央病院 看護専門学校 ...最終回は趣向をかえて、鑑別診断を導き出すための“山中克郎流”身体診察を披露。手の診察で貧血の程度や栄養状態を推定し、膠原病の可能性を探ります。頸部の診察で頸静脈波を的確に診るポイント、推定中心静脈圧から心不全を疑うなど、身体に臓器位置をペイントしながら、リアルに楽しく解説。また、苦手な方が多い心雑音の聴取では、聴診器で、AS(大...
Dr.山中の攻める問診(全13回)第13回 攻める身体所見2014/05/28(水)公開 山中 克郎 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 特任教授/ 諏訪中央病院 看護専門学校 ...最終回は趣向をかえて、鑑別診断を導き出すための“山中克郎流”身体診察を披露。手の診察で貧血の程度や栄養状態を推定し、膠原病の可能性を探ります。頸部の診察で頸静脈波を的確に診るポイント、推定中心静脈圧から心不全を疑うなど、身体に臓器位置をペイントしながら、リアルに楽しく解説。また、苦手な方が多い心雑音の聴取では、聴診器で、AS(大... -
 一発診断(全15回)第15回 体動で悪化する右胸の痛みを訴える50歳男性2019/11/27(水)公開 宮田 靖志 愛知医科大学 地域総合診療医学寄附講座・教授 医学教育センター・副センター長 プライマ...最終回となる今回は、「嘔気・嘔吐と太もものしびれを訴える84歳女性」と「体動で悪化する右胸の痛みを訴える50歳男性」の2症例を一発診断。いずれの症例も身体診察がポイントでとなります。あなたはどのような問診と診察で、この患者を診断できるのか! さあ、一発診断してみてください!
一発診断(全15回)第15回 体動で悪化する右胸の痛みを訴える50歳男性2019/11/27(水)公開 宮田 靖志 愛知医科大学 地域総合診療医学寄附講座・教授 医学教育センター・副センター長 プライマ...最終回となる今回は、「嘔気・嘔吐と太もものしびれを訴える84歳女性」と「体動で悪化する右胸の痛みを訴える50歳男性」の2症例を一発診断。いずれの症例も身体診察がポイントでとなります。あなたはどのような問診と診察で、この患者を診断できるのか! さあ、一発診断してみてください! -
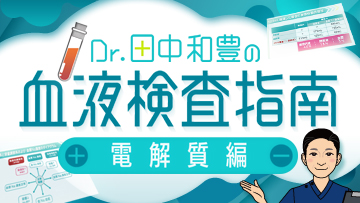 Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第5回 総論5:酸塩基平衡の歴史2021/11/03(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第5回は「酸塩基平衡の歴史」です。1884年に初めて化学上、「酸塩基」が定義されました。その後、生体における酸塩基平衡はCopenhagenアプローチ、Bostonアプローチ、Stewartアプローチなどさまざまな理論が展開されてきました。それはどのような考え方から生まれたのか、そしてその議論の決着は?
Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第5回 総論5:酸塩基平衡の歴史2021/11/03(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第5回は「酸塩基平衡の歴史」です。1884年に初めて化学上、「酸塩基」が定義されました。その後、生体における酸塩基平衡はCopenhagenアプローチ、Bostonアプローチ、Stewartアプローチなどさまざまな理論が展開されてきました。それはどのような考え方から生まれたのか、そしてその議論の決着は?
Dr.田中... -
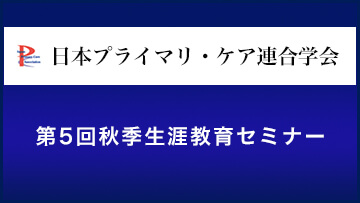 日本プライマリ・ケア連合学会 第5回 秋季生涯教育セミナー(全8回)WS13 ジェネラリスト・ウィメンズヘルス・シリーズ(1)月経と性感染症 ~産婦人科につなぐ境界線はどこか~2013/03/13(水)公開 寺岡 英美 弓削メディカルクリニックWomen's Health というと苦手意識をもっていませんか?産婦人科の知識がないとダメだから?内診台がないと診療できないから?そんなことはありません。 普段の診療の中で、ちょっと視点を変えるだけで診療の幅がとても広がります。または、潜在化しがちなWomen's Health に関するニーズにこたえるチャンスにも・・・。そんなエッセンスを、月経と...
日本プライマリ・ケア連合学会 第5回 秋季生涯教育セミナー(全8回)WS13 ジェネラリスト・ウィメンズヘルス・シリーズ(1)月経と性感染症 ~産婦人科につなぐ境界線はどこか~2013/03/13(水)公開 寺岡 英美 弓削メディカルクリニックWomen's Health というと苦手意識をもっていませんか?産婦人科の知識がないとダメだから?内診台がないと診療できないから?そんなことはありません。 普段の診療の中で、ちょっと視点を変えるだけで診療の幅がとても広がります。または、潜在化しがちなWomen's Health に関するニーズにこたえるチャンスにも・・・。そんなエッセンスを、月経と...