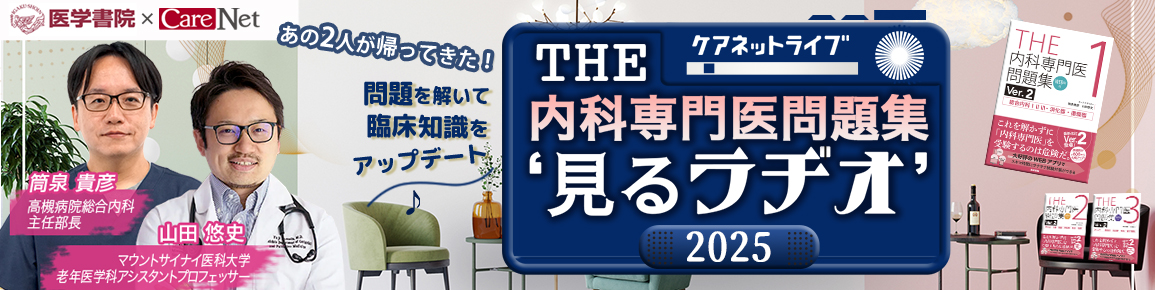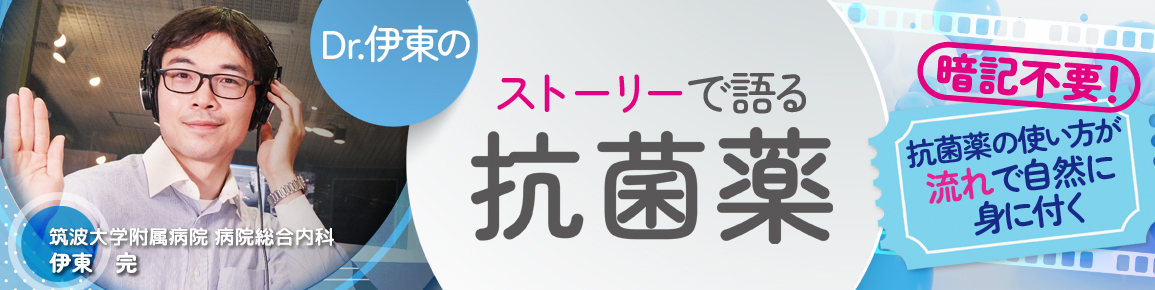外科の番組検索結果
-
 Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第5回 Obesity and Cancer.2015/04/01(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授今回紹介する論文は「Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults.」 Krishnan Bhaskaran, et al. Lancet. 2014;384(9945);755-765. 【PMID:25129328】 肥満とがんの関係についてです。 イギリス人1千万人以上の情報が集積されたデータベース「Clinical Practice Research Da...
Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第5回 Obesity and Cancer.2015/04/01(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授今回紹介する論文は「Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults.」 Krishnan Bhaskaran, et al. Lancet. 2014;384(9945);755-765. 【PMID:25129328】 肥満とがんの関係についてです。 イギリス人1千万人以上の情報が集積されたデータベース「Clinical Practice Research Da... -
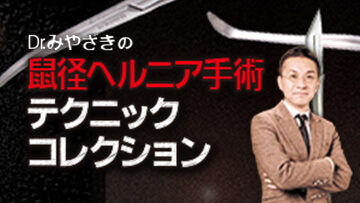 Dr.みやざきの鼠径ヘルニア手術テクニックコレクション(全12回)第4回 鼠径部ヘルニア手術の術前・術後管理2014/08/06(水)公開 宮崎 恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 院長鼠径ヘルニア手術は嵌頓例以外は手術の緊急性はありません。無理に患者さんへ手術を薦めず、患者さん自信が、手術を決意するまで待つことが大切です。 さて、いざ手術となった場合、鼠径ヘルニア修復術の術前と術後の管理はどうすればよいのでしょうか? 実は、鼠径ヘルニア手術の術前には特別な管理はほとんど不要です。Dr.みやざき曰く「抗凝固薬...
Dr.みやざきの鼠径ヘルニア手術テクニックコレクション(全12回)第4回 鼠径部ヘルニア手術の術前・術後管理2014/08/06(水)公開 宮崎 恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 院長鼠径ヘルニア手術は嵌頓例以外は手術の緊急性はありません。無理に患者さんへ手術を薦めず、患者さん自信が、手術を決意するまで待つことが大切です。 さて、いざ手術となった場合、鼠径ヘルニア修復術の術前と術後の管理はどうすればよいのでしょうか? 実は、鼠径ヘルニア手術の術前には特別な管理はほとんど不要です。Dr.みやざき曰く「抗凝固薬... -
 国立国際医療研究センター総合診療科presents 内科インテンシブレビュー2017(全12回)第9回 陰性感情を考える2017/07/05(水)公開 加藤 温 国立国際医療研究センター病院 総合診療科/精神科「この患者さん苦手だな…」 アルコール依存や、ボーダー患者、はたまた普通の患者に対しても、「嫌だな」という感情はどんな医師でも起こりうるものです。そんな陰性感情はどう対処するべきかを、国立国際医療研究センター病院 総合診療科/精神科の加藤温先生が精神科医の視点でレクチャーします。陥りやすい危ないケースからの回避方法や、明日から...
国立国際医療研究センター総合診療科presents 内科インテンシブレビュー2017(全12回)第9回 陰性感情を考える2017/07/05(水)公開 加藤 温 国立国際医療研究センター病院 総合診療科/精神科「この患者さん苦手だな…」 アルコール依存や、ボーダー患者、はたまた普通の患者に対しても、「嫌だな」という感情はどんな医師でも起こりうるものです。そんな陰性感情はどう対処するべきかを、国立国際医療研究センター病院 総合診療科/精神科の加藤温先生が精神科医の視点でレクチャーします。陥りやすい危ないケースからの回避方法や、明日から... -
 Dr.金井のCTクイズ 中級編(全12回)第8回 腹部:原因探しは左右を比べて念入りに2023/12/21(木)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長腹痛・嘔吐で受診した痩せ型の54歳女性。経産婦で、右股関節脱臼の既往があります。問診、身体診察により、腸閉塞が疑われました。第7回と同様、腸閉塞の原因を探索するために、腹部CTを撮像しました。 さて、原因は一体何なのでしょうか。ポイントとしては、痩せた高齢経産婦の腸閉塞であるということです。念入りに確認してみてください。
Dr.金井のCTクイズ 中級編(全12回)第8回 腹部:原因探しは左右を比べて念入りに2023/12/21(木)公開 金井 信恭 元東京北医療センター 救急科科長腹痛・嘔吐で受診した痩せ型の54歳女性。経産婦で、右股関節脱臼の既往があります。問診、身体診察により、腸閉塞が疑われました。第7回と同様、腸閉塞の原因を探索するために、腹部CTを撮像しました。 さて、原因は一体何なのでしょうか。ポイントとしては、痩せた高齢経産婦の腸閉塞であるということです。念入りに確認してみてください。 -
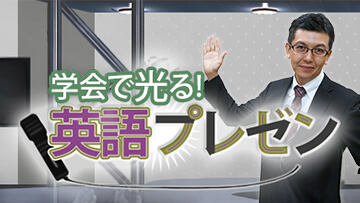 学会で光る!英語プレゼン(全8回)第4回 図表中心にわかりやすく メソッド・リザルトの示し方2015/07/29(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会プレゼンのメインはメソッドとリザルトの紹介です。このメソッドとリザルト、情報量が多いだけに英語プレゼンではわかりにくくなってしまうことがあります。しかし、スライドタイトルや図表の用い方で、わかりやすく伝えることができます。今回は学会での英語プレゼンにおけるリザルト・メソッドの説明テクニックを実例を示しながら紹介します。
学会で光る!英語プレゼン(全8回)第4回 図表中心にわかりやすく メソッド・リザルトの示し方2015/07/29(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会プレゼンのメインはメソッドとリザルトの紹介です。このメソッドとリザルト、情報量が多いだけに英語プレゼンではわかりにくくなってしまうことがあります。しかし、スライドタイトルや図表の用い方で、わかりやすく伝えることができます。今回は学会での英語プレゼンにおけるリザルト・メソッドの説明テクニックを実例を示しながら紹介します。 -
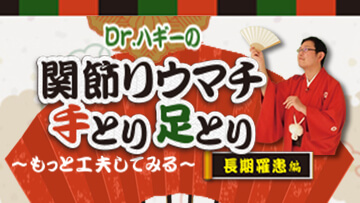 Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~もっと工夫してみる~ <長期罹患編>(全7回)第2回 慢性的な痛みへの対応2014/10/22(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(血液・リウマチ)関節が痛いと訴える患者さんに、漫然とNSAIDsやステロイドを投与していませんか?NSAIDsやステロイドは即効性に優れていますが、効きめがあるからといって長期間使用すると重篤な副作用をもたらすリスクが高まります。萩野昇先生が推奨するのは、「可能な限りステロイドは減量し、NSAIDsの連用は避ける」ことです。そのために実践しているさまざまな工...
Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~もっと工夫してみる~ <長期罹患編>(全7回)第2回 慢性的な痛みへの対応2014/10/22(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(血液・リウマチ)関節が痛いと訴える患者さんに、漫然とNSAIDsやステロイドを投与していませんか?NSAIDsやステロイドは即効性に優れていますが、効きめがあるからといって長期間使用すると重篤な副作用をもたらすリスクが高まります。萩野昇先生が推奨するのは、「可能な限りステロイドは減量し、NSAIDsの連用は避ける」ことです。そのために実践しているさまざまな工... -
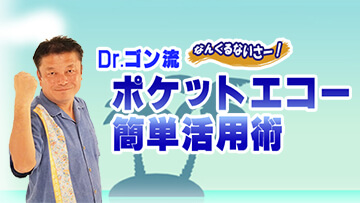 Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第8回 在宅医療でのポケットエコー活用法2014/05/28(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所最終回は泰川恵吾先生の訪問診療に密着します。患者さんに対するエコー検査についての説明、ご家族への検査準備のお願い、検査の実施、そして結果の説明。在宅医療の現場でどのようにポケットエコーを使い役立てるのか?第7回までに学んだポケットエコーのテクニックを、ゴン先生のように、ぜひ臨床現場で生かしてください。
Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第8回 在宅医療でのポケットエコー活用法2014/05/28(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所最終回は泰川恵吾先生の訪問診療に密着します。患者さんに対するエコー検査についての説明、ご家族への検査準備のお願い、検査の実施、そして結果の説明。在宅医療の現場でどのようにポケットエコーを使い役立てるのか?第7回までに学んだポケットエコーのテクニックを、ゴン先生のように、ぜひ臨床現場で生かしてください。 -
 Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第7回 Lower GI Bleeding2015/05/13(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授今回紹介する論文は「Lower GI bleeding risk of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and antiplatelet drug use alone and the effect of combined therapy.」 Naoyoshi Nagata, et al. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Dec;80(6);1124-1131. 【PMID:25088922】 NSAIDsや抗血小板薬の単独および併用使用による下部消化管出血のリスクについ...
Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第7回 Lower GI Bleeding2015/05/13(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授今回紹介する論文は「Lower GI bleeding risk of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and antiplatelet drug use alone and the effect of combined therapy.」 Naoyoshi Nagata, et al. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Dec;80(6);1124-1131. 【PMID:25088922】 NSAIDsや抗血小板薬の単独および併用使用による下部消化管出血のリスクについ... -
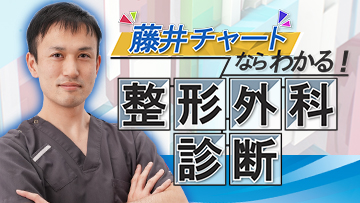 藤井チャートならわかる!整形外科診断(全8回)第8回 足関節痛2021/10/20(水)公開 藤井 達也 医療法人社団 晃山会 松江病院 整形外科子どもの運動会で受傷した37歳女性患者を例に、足関節痛の診断フローをみていきます。 足関節の診断でも問診は重要です。ぶつけたのかひねったのかといった病歴聴取のポイントを解説します。外傷/非外傷いずれでも鑑別の決め手になる触診は、外側・内側・足背・足底と部位ごとに解説、実演します。
藤井チャートならわかる!整形外科診断(全8回)第8回 足関節痛2021/10/20(水)公開 藤井 達也 医療法人社団 晃山会 松江病院 整形外科子どもの運動会で受傷した37歳女性患者を例に、足関節痛の診断フローをみていきます。 足関節の診断でも問診は重要です。ぶつけたのかひねったのかといった病歴聴取のポイントを解説します。外傷/非外傷いずれでも鑑別の決め手になる触診は、外側・内側・足背・足底と部位ごとに解説、実演します。 -
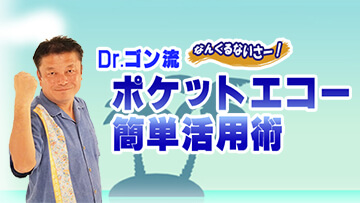 Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第7回 医学的管理・処置への活用法2014/05/14(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所胃瘻の管理やドレナージの処置をする際にもポケットエコーは有用です。すでに習った左肋骨弓下走査で胃瘻交換後のカテーテルの位置や形状を確認したり、ドレナージ可能箇所をエコーでチェックすることができます。手軽に使えるポケットエコーを活用し、より安全・正確な処置を学んでください。
Dr.ゴン流ポケットエコー簡単活用術(全8回)第7回 医学的管理・処置への活用法2014/05/14(水)公開 泰川 恵吾 医療法人鳥伝白川会 理事長 ドクターゴン診療所胃瘻の管理やドレナージの処置をする際にもポケットエコーは有用です。すでに習った左肋骨弓下走査で胃瘻交換後のカテーテルの位置や形状を確認したり、ドレナージ可能箇所をエコーでチェックすることができます。手軽に使えるポケットエコーを活用し、より安全・正確な処置を学んでください。 -
 Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第16回 経口キノロン系抗菌薬 12024/04/25(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表わが国で承認されている経口キノロン系抗菌薬は約10種類ありますが、Dr.RIKIによればそのうち本当に押さえるべきなのは2つだけです。外来診療においてどのような場合にキノロン系抗菌薬を処方すべきか。開発の歴史・バイオアベイラビリティ・薬剤感受性データなどを踏まえて具体的に詳しく解説します。新しい抗菌薬適正使用支援加算とも関係するWHOのAW...
Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第16回 経口キノロン系抗菌薬 12024/04/25(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表わが国で承認されている経口キノロン系抗菌薬は約10種類ありますが、Dr.RIKIによればそのうち本当に押さえるべきなのは2つだけです。外来診療においてどのような場合にキノロン系抗菌薬を処方すべきか。開発の歴史・バイオアベイラビリティ・薬剤感受性データなどを踏まえて具体的に詳しく解説します。新しい抗菌薬適正使用支援加算とも関係するWHOのAW... -
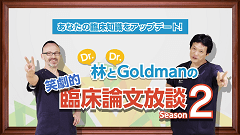 Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談 Season2(全6回)第5回 小児の鈍的頭部外傷にCT検査はどこまで必要?2016/06/29(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授林寛之先生Ran Goldman先生が、今回取り上げる文献は「PIsolated linear skull fractures in children with blunt head trauma. Powell EC, et al. Pediatrics. 2015 Apr;135(4);e851-e857.」【PMID:25780067】です。 小児の鈍的頭部外傷に関する研究です。 被ばくとコスト、さらには鎮静の問題から小児のCT検査は常に議論されています。 頭蓋...
Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談 Season2(全6回)第5回 小児の鈍的頭部外傷にCT検査はどこまで必要?2016/06/29(水)公開 Ran D. Goldman ブリティッシュコロンビア大学 救急部 教授林寛之先生Ran Goldman先生が、今回取り上げる文献は「PIsolated linear skull fractures in children with blunt head trauma. Powell EC, et al. Pediatrics. 2015 Apr;135(4);e851-e857.」【PMID:25780067】です。 小児の鈍的頭部外傷に関する研究です。 被ばくとコスト、さらには鎮静の問題から小児のCT検査は常に議論されています。 頭蓋... -
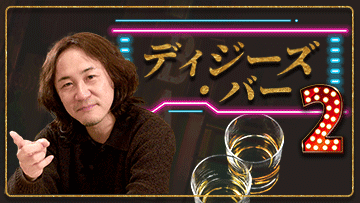 ディジーズ・バー2(全10回)第8回 偽痛風2023/11/16(木)公開 國松 淳和 南多摩病院 総合内科・膠原病内科 部長前回に引き続き北和也先生をゲストに迎え、偽痛風について細部まで語り合います。
ディジーズ・バー2(全10回)第8回 偽痛風2023/11/16(木)公開 國松 淳和 南多摩病院 総合内科・膠原病内科 部長前回に引き続き北和也先生をゲストに迎え、偽痛風について細部まで語り合います。
80代以上の在宅・入院患者に発症することの多い偽痛風。必ずしもガイドライン通りではない治療薬の使い分けやその匙加減で2人の処方感が見事に一致。そのほか、検査の必要性から軸関節の偽痛風の治療まで、実臨床で気になる論点をとことんディスカッションします。 -
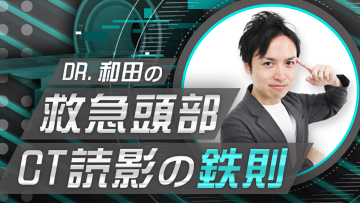 Dr.和田の救急頭部CT読影の鉄則(全9回)第7回 意識障害の原因を探れ!2024/12/12(木)公開 和田 武 帝京大学医学部放射線科学講座/放射線診断専門医・IVR専門医今回の症例は意識障害。画像所見自体は明確ですが問題はその原因です。普段はあまりお目にかからない疾患でも勘所が頭に入っていれば単純CTでも診断することができます。そのポイントをDr.和田に学んでください。適応となる鉄則は「(5) 脳血管を観察する」です。
Dr.和田の救急頭部CT読影の鉄則(全9回)第7回 意識障害の原因を探れ!2024/12/12(木)公開 和田 武 帝京大学医学部放射線科学講座/放射線診断専門医・IVR専門医今回の症例は意識障害。画像所見自体は明確ですが問題はその原因です。普段はあまりお目にかからない疾患でも勘所が頭に入っていれば単純CTでも診断することができます。そのポイントをDr.和田に学んでください。適応となる鉄則は「(5) 脳血管を観察する」です。 -
 志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第4回 眠れる巨人(A Sleeping Giant)2019/01/16(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving...
志水太郎の診断戦略ケーススタディ(全4回)第4回 眠れる巨人(A Sleeping Giant)2019/01/16(水)公開 志水 太郎 獨協医科大学総合診療医学主任教授 総合診療科診療部長診断のメカニズムを解き明かした名著「診断戦略」。そこで示された戦術や技法を、臨床でどのように使えば効率的かつ正確な診断が行えるのか。志水太郎先生がNEJMの症例を題材にケーススタディ形式で解説します。難症例を前に、直観的思考はどうひらめくのか、どのタイミングでどんな鑑別のクラスターを開くのか。今回はNEJMのClinical Problem-Solving... -
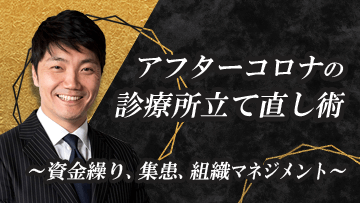 アフターコロナの診療所立て直し術 ~資金繰り、集患、組織マネジメント~(全1回)アフターコロナの診療所立て直し術 ~資金繰り、集患、組織マネジメント~2020/06/02(火)公開 裵 英洙 ハイズ株式会社 代表取締役社長、医師、医学博士、経営学修士 (MD、Ph.D、MBA)<無料公開は終了しました>
アフターコロナの診療所立て直し術 ~資金繰り、集患、組織マネジメント~(全1回)アフターコロナの診療所立て直し術 ~資金繰り、集患、組織マネジメント~2020/06/02(火)公開 裵 英洙 ハイズ株式会社 代表取締役社長、医師、医学博士、経営学修士 (MD、Ph.D、MBA)<無料公開は終了しました>
※2020年5月29日時点での情報に基づいた6月2日配信の講義であることをご留意のうえ、ご視聴ください。
新型コロナウイルス感染症は収束に向かいつつありますが、診療所の経営者は疲弊した組織のマネジメントや患者の受診控え後の集患など、悩みが尽きないのではないでしょうか。
今回の「アフターコロナの診... -
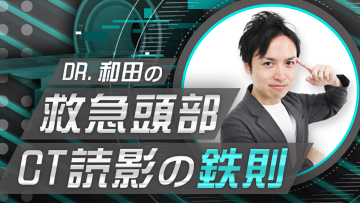 Dr.和田の救急頭部CT読影の鉄則(全9回)第6回 頭部外傷での見落としを防げ!2024/11/21(木)公開 和田 武 帝京大学医学部放射線科学講座/放射線診断専門医・IVR専門医今回は頭部打撲の症例です。適応となる鉄則は「(1) MPRを活用して観察する」。頭蓋内出血の14%は軸位断像では描出されないとする報告もあります。冠状断を始めとするMPRを活用した観察術をDr.和田に学び、見落としのない読影法を身に付けましょう。
Dr.和田の救急頭部CT読影の鉄則(全9回)第6回 頭部外傷での見落としを防げ!2024/11/21(木)公開 和田 武 帝京大学医学部放射線科学講座/放射線診断専門医・IVR専門医今回は頭部打撲の症例です。適応となる鉄則は「(1) MPRを活用して観察する」。頭蓋内出血の14%は軸位断像では描出されないとする報告もあります。冠状断を始めとするMPRを活用した観察術をDr.和田に学び、見落としのない読影法を身に付けましょう。 -
 Dr.飯島の在宅整形(全7回)第6回 在宅リウマチ2020/01/29(水)公開 飯島 治 亀戸大島クリニック 院長最新のリウマチ治療と異なり、在宅で必要なのはすでに関節が変形している患者のQOLを向上させる治療です。ステロイドの用量調節はもちろん、簡単な運動リハビリや生活上の工夫など、実際に数多くのリウマチ患者さんを診てきた飯島治先生ならではの在宅診療ノウハウを惜しみなく伝授します。
Dr.飯島の在宅整形(全7回)第6回 在宅リウマチ2020/01/29(水)公開 飯島 治 亀戸大島クリニック 院長最新のリウマチ治療と異なり、在宅で必要なのはすでに関節が変形している患者のQOLを向上させる治療です。ステロイドの用量調節はもちろん、簡単な運動リハビリや生活上の工夫など、実際に数多くのリウマチ患者さんを診てきた飯島治先生ならではの在宅診療ノウハウを惜しみなく伝授します。 -
 サルコペニアを防ぐ臨床栄養学(全6回)第5回 嚥下障害2022/01/19(水)公開 吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター長、リハビリテーション科副...嚥下障害は脳卒中や神経変性疾患だけでなく、サルコペニアによっても起こります。その場合はサルコペニアの治療や運動によって改善することが可能なため、サルコペニアの可能性を念頭に置き、嚥下障害の原因を探ることが必要です。第5回では、サルコペニアの嚥下障害の診断や治療、食事の問題点などを解説します。
サルコペニアを防ぐ臨床栄養学(全6回)第5回 嚥下障害2022/01/19(水)公開 吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター長、リハビリテーション科副...嚥下障害は脳卒中や神経変性疾患だけでなく、サルコペニアによっても起こります。その場合はサルコペニアの治療や運動によって改善することが可能なため、サルコペニアの可能性を念頭に置き、嚥下障害の原因を探ることが必要です。第5回では、サルコペニアの嚥下障害の診断や治療、食事の問題点などを解説します。 -
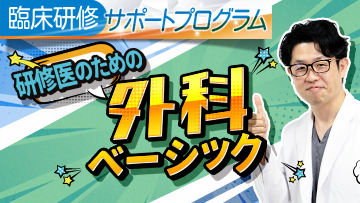 研修医のための外科ベーシック(全10回)第9回 周術期管理2024/04/04(木)公開 本間 崇浩 聖マリアンナ医科大学 呼吸器外科 講師第9回では、外科研修に不可欠な周術期管理の重要な知識を解説します。良い手術の背後には、良い周術期管理が必要不可欠です。発熱、感染、出血、疼痛、ドレーンの管理方法を詳しく説明し、周術期管理の要点を丁寧にレクチャーします。とくに重要なのは、検査結果だけでなく、患者の声にも注意を払い、多角的な視点から総合的に判断すること。本番組を手...
研修医のための外科ベーシック(全10回)第9回 周術期管理2024/04/04(木)公開 本間 崇浩 聖マリアンナ医科大学 呼吸器外科 講師第9回では、外科研修に不可欠な周術期管理の重要な知識を解説します。良い手術の背後には、良い周術期管理が必要不可欠です。発熱、感染、出血、疼痛、ドレーンの管理方法を詳しく説明し、周術期管理の要点を丁寧にレクチャーします。とくに重要なのは、検査結果だけでなく、患者の声にも注意を払い、多角的な視点から総合的に判断すること。本番組を手... -
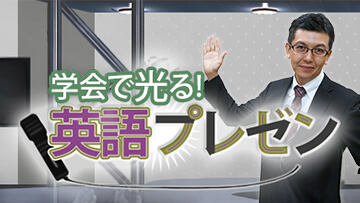 学会で光る!英語プレゼン(全8回)第7回 日本人苦手度No.1! 質疑応答を生き残れ2015/08/19(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会で英語プレゼンは大成功、でも質疑応答で大崩壊。こんな痛ましい光景、日本人スピーカーの発表では珍しくありません。英語プレゼンにおいて、日本人スピーカーの最大の壁は何といっても質疑応答です。今回は、英語プレゼン後の質疑応答を切り抜ける実践テクニックを実例を佐藤雅昭先生が紹介します。
学会で光る!英語プレゼン(全8回)第7回 日本人苦手度No.1! 質疑応答を生き残れ2015/08/19(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会で英語プレゼンは大成功、でも質疑応答で大崩壊。こんな痛ましい光景、日本人スピーカーの発表では珍しくありません。英語プレゼンにおいて、日本人スピーカーの最大の壁は何といっても質疑応答です。今回は、英語プレゼン後の質疑応答を切り抜ける実践テクニックを実例を佐藤雅昭先生が紹介します。 -
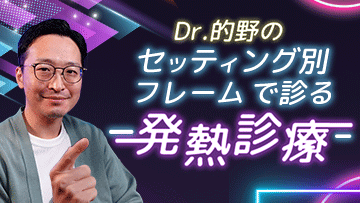 Dr.的野のセッティング別フレームで診る発熱診療(全6回)第4回 救急×発熱2023/08/24(木)公開 的野 多加志 佐賀大学医学部附属病院 感染制御部 特任准教授/飯塚病院 感染症科 顧問第4回は救急外来のセッティングです。救急の現場では重症度・緊急度が高いか、つまり、入院させる必要があるかどうかを正しく見極めることが肝心。
Dr.的野のセッティング別フレームで診る発熱診療(全6回)第4回 救急×発熱2023/08/24(木)公開 的野 多加志 佐賀大学医学部附属病院 感染制御部 特任准教授/飯塚病院 感染症科 顧問第4回は救急外来のセッティングです。救急の現場では重症度・緊急度が高いか、つまり、入院させる必要があるかどうかを正しく見極めることが肝心。
そのためにはまず、重症度が低いかぜ症候群を知り、かぜかそれ以外の疾患かを判断することから始めます。さらに、発熱に伴う症状を整理し、正しい診断に近づくための知識を詳しく解説します。 -
 脳血管内治療STANDARD(全10回)第4回 穿刺とガイディングカテーテル2020/05/31(日)公開 吉村 紳一 兵庫医科大学脳神経外科学講座 主任教授脳血管内治療を開始する最初のステップが、動脈の穿刺とシースの留置、そしてガイディングカテーテルの誘導です。治療方法、また治療対象によって穿刺の部位やシースの太さ、ガイディングカテーテルの種類などが異なりますが、この回では吉村紳一先生が代表的な脳血管内治療における機器と操作法について紹介します。
脳血管内治療STANDARD(全10回)第4回 穿刺とガイディングカテーテル2020/05/31(日)公開 吉村 紳一 兵庫医科大学脳神経外科学講座 主任教授脳血管内治療を開始する最初のステップが、動脈の穿刺とシースの留置、そしてガイディングカテーテルの誘導です。治療方法、また治療対象によって穿刺の部位やシースの太さ、ガイディングカテーテルの種類などが異なりますが、この回では吉村紳一先生が代表的な脳血管内治療における機器と操作法について紹介します。 -
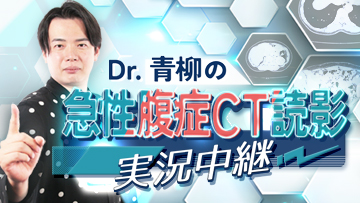 Dr.青柳の急性腹症CT読影 実況中継(全9回)第5回 腫大している臓器の評価2024/12/12(木)公開 青柳 泰史 放射線科専門医主訴は発熱と腹痛。その原因となっている、ある臓器に生じた結石や腫大に着目できるかが診断のポイントとなります。また今回の症例紹介では性別は伏せられていますが、画像を追っていけばそれも一目瞭然。画像を通じて性別特有の病態とその原因疾患を特定する画像診断医ならではの視点にも注目です。
Dr.青柳の急性腹症CT読影 実況中継(全9回)第5回 腫大している臓器の評価2024/12/12(木)公開 青柳 泰史 放射線科専門医主訴は発熱と腹痛。その原因となっている、ある臓器に生じた結石や腫大に着目できるかが診断のポイントとなります。また今回の症例紹介では性別は伏せられていますが、画像を追っていけばそれも一目瞭然。画像を通じて性別特有の病態とその原因疾患を特定する画像診断医ならではの視点にも注目です。