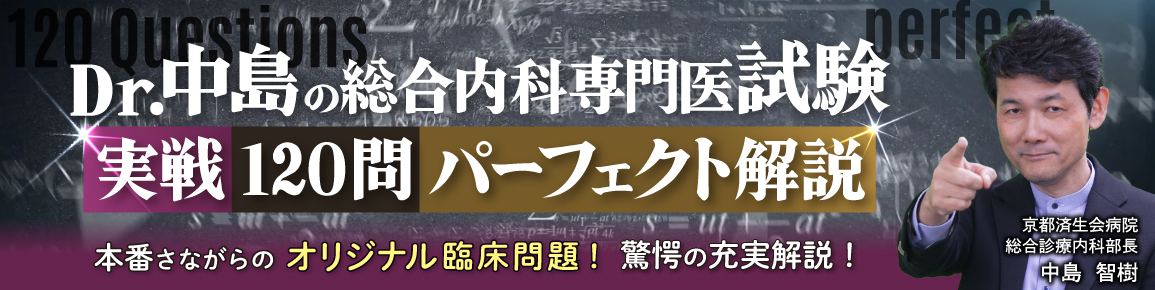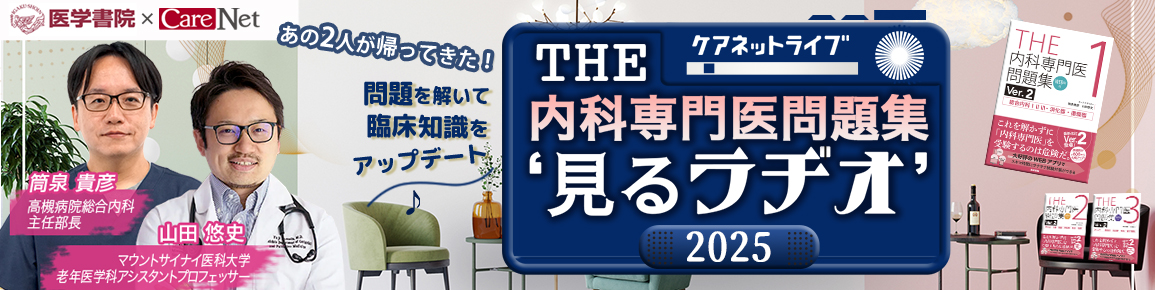内科の番組検索結果
-
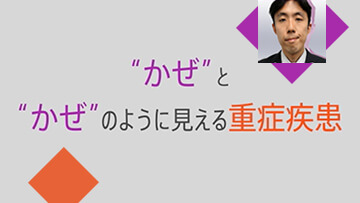 “かぜ”と“かぜ”のように見える重症疾患(全13回)第6回 column2 プロカルシトニンの使い方2011/07/13(水)公開 山本 舜悟 京都大学医学部附属病院 臨床研究・教育研修部最近話題のプロカルシトニン。新しい指標としてさまざまな議論がなされていますが、今現在の臨床ではどのように使えるのでしょうか?診療の現場での実際の使い道を解説します。
“かぜ”と“かぜ”のように見える重症疾患(全13回)第6回 column2 プロカルシトニンの使い方2011/07/13(水)公開 山本 舜悟 京都大学医学部附属病院 臨床研究・教育研修部最近話題のプロカルシトニン。新しい指標としてさまざまな議論がなされていますが、今現在の臨床ではどのように使えるのでしょうか?診療の現場での実際の使い道を解説します。 -
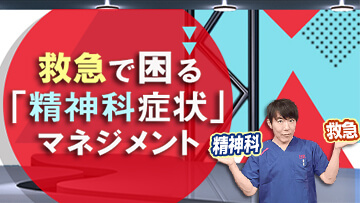 救急で困る「精神科症状」マネジメント(全5回)第1回 精神科診断の基本を知る2017/11/29(水)公開 久村 正樹 埼玉医科大学総合医療センター 救急科(ER)精神科医として、救急医として両方の現場を熟知する久村正樹先生が、精神科診断の基本からしっかりと解説します。精神科診断のプロセスは外因→内因→心因の順番で検索していくことが基本です。 性格や環境から考えることのないようにしましょう。診断の優先順位付けをしていますので、その順番に診察していくことで、落ち着いて対応できます。
救急で困る「精神科症状」マネジメント(全5回)第1回 精神科診断の基本を知る2017/11/29(水)公開 久村 正樹 埼玉医科大学総合医療センター 救急科(ER)精神科医として、救急医として両方の現場を熟知する久村正樹先生が、精神科診断の基本からしっかりと解説します。精神科診断のプロセスは外因→内因→心因の順番で検索していくことが基本です。 性格や環境から考えることのないようにしましょう。診断の優先順位付けをしていますので、その順番に診察していくことで、落ち着いて対応できます。 -
 岡田正人のアレルギーLIVE(全8回)第4回 鼻炎2019/10/30(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長今回の「岡田正人のアレルギーLIVE」はアレルギー性鼻炎についてです。 アレルギー性鼻炎は、鼻漏、鼻閉、かゆみ、結膜炎などさまざまな症状があります。 実は、出る症状(とくに鼻漏と鼻閉)によって、処方する薬が異なってきます。 患者の症状に合わせた治療薬と処方方法についてそれぞれの薬の特徴も踏まえ、詳しくわかりやすく解説します。 ま...
岡田正人のアレルギーLIVE(全8回)第4回 鼻炎2019/10/30(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長今回の「岡田正人のアレルギーLIVE」はアレルギー性鼻炎についてです。 アレルギー性鼻炎は、鼻漏、鼻閉、かゆみ、結膜炎などさまざまな症状があります。 実は、出る症状(とくに鼻漏と鼻閉)によって、処方する薬が異なってきます。 患者の症状に合わせた治療薬と処方方法についてそれぞれの薬の特徴も踏まえ、詳しくわかりやすく解説します。 ま... -
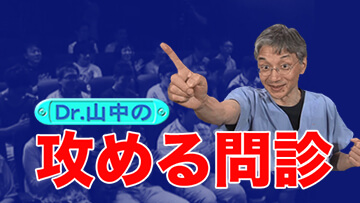 Dr.山中の攻める問診(全13回)第10回 めまい ~朝からめまい~2014/02/12(水)公開 山中 克郎 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 特任教授/ 諏訪中央病院 看護専門学校 ...79歳女性。朝突然、フワ~っとするめまいを発症。最初はトイレまで歩けたが、直ぐに歩くことも困難になる。上胸部に違和感があり、左下肢腫脹がある。既往歴に10年前に子宮癌あり。放射線療法をおこなった。2ヶ月前に心筋梗塞。この患者さんの診断は何だったのでしょうか?病歴や身体所見、検査所見のどこにキーワードがあり、どの様に攻める問診を行っ...
Dr.山中の攻める問診(全13回)第10回 めまい ~朝からめまい~2014/02/12(水)公開 山中 克郎 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 特任教授/ 諏訪中央病院 看護専門学校 ...79歳女性。朝突然、フワ~っとするめまいを発症。最初はトイレまで歩けたが、直ぐに歩くことも困難になる。上胸部に違和感があり、左下肢腫脹がある。既往歴に10年前に子宮癌あり。放射線療法をおこなった。2ヶ月前に心筋梗塞。この患者さんの診断は何だったのでしょうか?病歴や身体所見、検査所見のどこにキーワードがあり、どの様に攻める問診を行っ... -
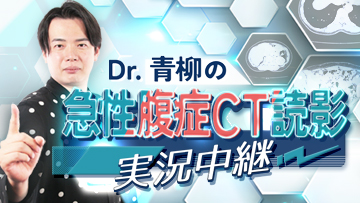 Dr.青柳の急性腹症CT読影 実況中継(全9回)第1回 急性腹症の鑑別疾患2024/09/19(木)公開 青柳 泰史 放射線科専門医初回は急性腹症の鑑別疾患について海外の文献も踏まえて整理します。コモンな疾患から希少な疾患まで、腹痛患者を診る際に想起すべき疾患について確認しましょう。
Dr.青柳の急性腹症CT読影 実況中継(全9回)第1回 急性腹症の鑑別疾患2024/09/19(木)公開 青柳 泰史 放射線科専門医初回は急性腹症の鑑別疾患について海外の文献も踏まえて整理します。コモンな疾患から希少な疾患まで、腹痛患者を診る際に想起すべき疾患について確認しましょう。 -
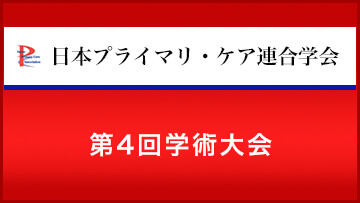 日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 学術大会(全14回)痛みとしびれの診断学2013/11/27(水)公開 生坂 政臣 千葉大学 名誉教授/生坂医院 副院長痛みとしびれは外来初診診療者の主訴の4割を占める重要な症状です。
日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 学術大会(全14回)痛みとしびれの診断学2013/11/27(水)公開 生坂 政臣 千葉大学 名誉教授/生坂医院 副院長痛みとしびれは外来初診診療者の主訴の4割を占める重要な症状です。
いずれも患者さんの主観的な症状であり、身体診察や一般検査で異常を認めないことも多く、病態を理解した上での病歴聴取が診断の鍵となります。
本講義は、生坂政臣先生が聴講者に実際の症例の鑑別を出題しながら、痛みとしびれの病態と鑑別アプローチ法を解説します。 -
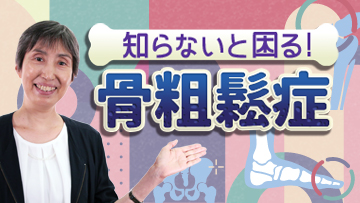 知らないと困る!骨粗鬆症(全7回)第5回 薬物療法2024/03/07(木)公開 千葉 優子 東京都健康長寿医療センター 臨床検査科部長骨粗鬆症治療薬には数多くの種類があり、投与経路や投与頻度もさまざま。骨形成促進作用と骨吸収抑制作用の両方を併せ持つ新薬も登場しています。代表的な薬剤の作用と特徴を押さえ、個々の患者に合った薬剤選択と長期的な治療方針の立て方について学びましょう。
知らないと困る!骨粗鬆症(全7回)第5回 薬物療法2024/03/07(木)公開 千葉 優子 東京都健康長寿医療センター 臨床検査科部長骨粗鬆症治療薬には数多くの種類があり、投与経路や投与頻度もさまざま。骨形成促進作用と骨吸収抑制作用の両方を併せ持つ新薬も登場しています。代表的な薬剤の作用と特徴を押さえ、個々の患者に合った薬剤選択と長期的な治療方針の立て方について学びましょう。 -
 Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~まずは触ってみる~ <早期介入編>(全6回)第1回 関節リウマチ診療の現在2014/07/02(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(リウマチ)准教授プライマリ・ケア医にとってはとっつきにくいイメージのある関節リウマチ。しかし近年、治療法が格段に進歩し、今では早期発見・介入し寛解を目指すのが常識となっています。この世界的な新しい関節リウマチ治療方針がTreat to Target(T2T)。その鍵を握っているのは、プライマリ・ケア医です。早期介入編第1回は「関節リウマチ診療の現在」と題して、...
Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~まずは触ってみる~ <早期介入編>(全6回)第1回 関節リウマチ診療の現在2014/07/02(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(リウマチ)准教授プライマリ・ケア医にとってはとっつきにくいイメージのある関節リウマチ。しかし近年、治療法が格段に進歩し、今では早期発見・介入し寛解を目指すのが常識となっています。この世界的な新しい関節リウマチ治療方針がTreat to Target(T2T)。その鍵を握っているのは、プライマリ・ケア医です。早期介入編第1回は「関節リウマチ診療の現在」と題して、... -
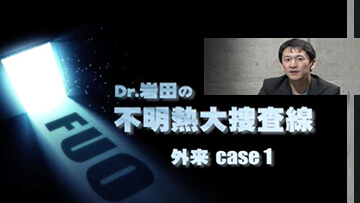 Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線(全13回)第3回 外来 case3 ―90歳女性・・8年間繰り返す発熱―2009/10/23(金)公開 岩田 健太郎 神戸大学 感染症内科 教授外来での不明熱、今回の「Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線」の症例は「8年間繰り返す発熱」です。不明熱を得意とする西垂水和隆先生にとっても記憶に残る症例です。 外来で見る不明熱の多くは、医師のちょっとした思い込み、あるいは病歴や身体診察の軽視により、単純な疾患が見逃されることによって起こります。それは医師の技量や熱意にかかわらず、どん...
Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線(全13回)第3回 外来 case3 ―90歳女性・・8年間繰り返す発熱―2009/10/23(金)公開 岩田 健太郎 神戸大学 感染症内科 教授外来での不明熱、今回の「Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線」の症例は「8年間繰り返す発熱」です。不明熱を得意とする西垂水和隆先生にとっても記憶に残る症例です。 外来で見る不明熱の多くは、医師のちょっとした思い込み、あるいは病歴や身体診察の軽視により、単純な疾患が見逃されることによって起こります。それは医師の技量や熱意にかかわらず、どん... -
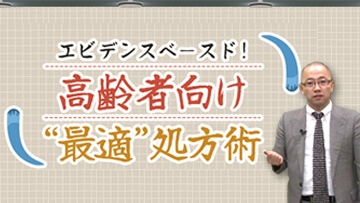 エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第5回 抗凝固薬2016/05/11(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科「転倒リスクのある高齢者に抗凝固治療は行うべきではない!?」はたしてそうでしょうか? 血栓予防効果と出血リスク。どちらをとるかは、高齢者の抗凝固療法における永遠のテーマといえるでしょう。 今回は、”抗凝固薬の真のベネフィット”はどの程度か?という昔ながらの疑問から、NOACとワルファリンはどちらが良いのか?といった最近の疑問まで、...
エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第5回 抗凝固薬2016/05/11(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科「転倒リスクのある高齢者に抗凝固治療は行うべきではない!?」はたしてそうでしょうか? 血栓予防効果と出血リスク。どちらをとるかは、高齢者の抗凝固療法における永遠のテーマといえるでしょう。 今回は、”抗凝固薬の真のベネフィット”はどの程度か?という昔ながらの疑問から、NOACとワルファリンはどちらが良いのか?といった最近の疑問まで、... -
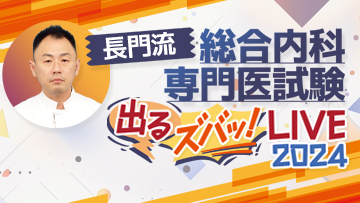 長門流 総合内科専門医試験「出るズバッ!LIVE」2024(全13回)第7回 代謝2024/09/18(水)公開 長門 直 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 呼吸器内科・アレルギー科部長第7回は「代謝」です。この分野は比較的オーソドックスな出題傾向ですが、内科専門医試験に比べて細かな知識が問われます。本ライブでそのポイントを押さえましょう。
長門流 総合内科専門医試験「出るズバッ!LIVE」2024(全13回)第7回 代謝2024/09/18(水)公開 長門 直 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 呼吸器内科・アレルギー科部長第7回は「代謝」です。この分野は比較的オーソドックスな出題傾向ですが、内科専門医試験に比べて細かな知識が問われます。本ライブでそのポイントを押さえましょう。
※ライブストリーミング配信日:2024年9月18日 -
 コロナワクチン緊急対談 接種済在米医師とワクチンエキスパートが近未来を見通す(全1回)コロナワクチン緊急対談 接種済在米医師とワクチンエキスパートが近未来を見通す2021/01/13(水)公開 守屋 章成 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻 熱帯医学コース(...コロナワクチン接種済みの米国・ワシントンD.C.の病院に勤務する米国感染症専門医でもある安川康介氏とワクチンエキスパートの守屋章成氏との緊急対談。米国での新型コロナウイルスの感染状況とワクチン接種の実態などを安川氏が生々しくシェア。守屋氏はファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンの効果、リスクなどを論文ベースで冷徹に比較検...
コロナワクチン緊急対談 接種済在米医師とワクチンエキスパートが近未来を見通す(全1回)コロナワクチン緊急対談 接種済在米医師とワクチンエキスパートが近未来を見通す2021/01/13(水)公開 守屋 章成 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻 熱帯医学コース(...コロナワクチン接種済みの米国・ワシントンD.C.の病院に勤務する米国感染症専門医でもある安川康介氏とワクチンエキスパートの守屋章成氏との緊急対談。米国での新型コロナウイルスの感染状況とワクチン接種の実態などを安川氏が生々しくシェア。守屋氏はファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンの効果、リスクなどを論文ベースで冷徹に比較検... -
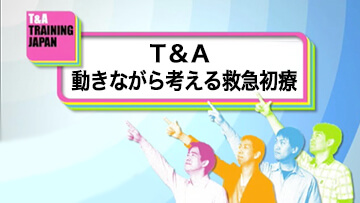 T&A 動きながら考える救急初療(全5回)第1回 診療所での救急初療―軽症にみえる重症患者を見極めろ!―2009/08/21(金)公開 齊藤 裕之 山口大学医学部附属病院 総合診療部・臨床教育センター、MD、MBA病院設定と違い診療所では発症から間もない患者が典型的な症状を呈さずに来院します。まずは“救急初療ユニバーサルアルゴリズム”を3部構成で紹介します。デモンストレーションでは診療所での動き方をダイナミックに解説。T&A動きながら考える救急初療で、軽症にみえる重症患者を見極めよう!
T&A 動きながら考える救急初療(全5回)第1回 診療所での救急初療―軽症にみえる重症患者を見極めろ!―2009/08/21(金)公開 齊藤 裕之 山口大学医学部附属病院 総合診療部・臨床教育センター、MD、MBA病院設定と違い診療所では発症から間もない患者が典型的な症状を呈さずに来院します。まずは“救急初療ユニバーサルアルゴリズム”を3部構成で紹介します。デモンストレーションでは診療所での動き方をダイナミックに解説。T&A動きながら考える救急初療で、軽症にみえる重症患者を見極めよう! -
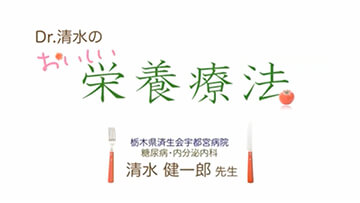 Dr.清水のおいしい栄養療法(全11回)第9回 末梢静脈栄養の考え方(1)2012/11/28(水)公開 清水 健一郎 医師/ウェブサイト「ランドマップ研究室」点滴による栄養補給は、使い方を間違えると筋肉を崩壊させ、ADLの低下を招いてしまいます。 ブドウ糖だけの栄養がダメな理由とは・・? 脂肪乳剤を点滴しないと、たった2週間で大変なことに・・? 病気が治った時すぐに退院できる“体”を作っておくためには、末梢静脈栄養の中身をどのように組み立てたら良いのか。 「考え方(1)」では、4つの構成要素の...
Dr.清水のおいしい栄養療法(全11回)第9回 末梢静脈栄養の考え方(1)2012/11/28(水)公開 清水 健一郎 医師/ウェブサイト「ランドマップ研究室」点滴による栄養補給は、使い方を間違えると筋肉を崩壊させ、ADLの低下を招いてしまいます。 ブドウ糖だけの栄養がダメな理由とは・・? 脂肪乳剤を点滴しないと、たった2週間で大変なことに・・? 病気が治った時すぐに退院できる“体”を作っておくためには、末梢静脈栄養の中身をどのように組み立てたら良いのか。 「考え方(1)」では、4つの構成要素の... -
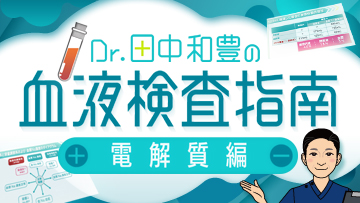 Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第10回 各論3:K(カリウム)2022/01/26(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」各論の第3回はK(カリウム)についてみていきます。 Kの基準値を覚えておくことは重要です。Kの値を見て、すぐに行動に移す必要があるからです。 とくに高K血症は、電解質異常の中で一番緊急性が高いので、まずは治療を行います。慌てずにしっかりと対応できるよう、やるべきことを確認しておきましょう。 低N...
Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第10回 各論3:K(カリウム)2022/01/26(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」各論の第3回はK(カリウム)についてみていきます。 Kの基準値を覚えておくことは重要です。Kの値を見て、すぐに行動に移す必要があるからです。 とくに高K血症は、電解質異常の中で一番緊急性が高いので、まずは治療を行います。慌てずにしっかりと対応できるよう、やるべきことを確認しておきましょう。 低N... -
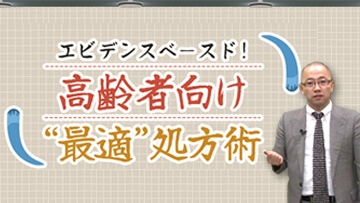 エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第6回 ベンゾジアゼピン2016/05/18(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科不眠を訴えるお年寄りの患者さんに、「あまり薬に頼るのは良くないんですけどね」と言いつつ、ベンゾジアゼピンを処方していませんか? ベンゾジアゼピンの高齢者の不眠に対する効果はどの程度か?転倒リスクは?継続使用による認知症発症リスクは? 今まで問題点が指摘されることが多かったこの薬剤について、エビデンスを基に具体的に解説します...
エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第6回 ベンゾジアゼピン2016/05/18(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科不眠を訴えるお年寄りの患者さんに、「あまり薬に頼るのは良くないんですけどね」と言いつつ、ベンゾジアゼピンを処方していませんか? ベンゾジアゼピンの高齢者の不眠に対する効果はどの程度か?転倒リスクは?継続使用による認知症発症リスクは? 今まで問題点が指摘されることが多かったこの薬剤について、エビデンスを基に具体的に解説します... -
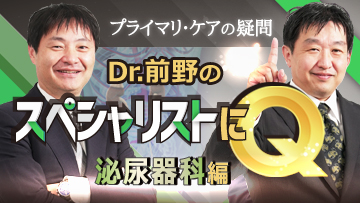 プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!【泌尿器科編】(全19回)第3回 血尿前編:肉眼的血尿2023/01/12(木)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長プライマリケアで肉眼的血尿に出合ったときに最も多い原因は炎症。とくに青壮年ではある感染症を疑って調べることが重要です。発熱や膀胱刺激症状がないからといって除外することができないこの原因を見つけるためのヒントを伝授します。
プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!【泌尿器科編】(全19回)第3回 血尿前編:肉眼的血尿2023/01/12(木)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長プライマリケアで肉眼的血尿に出合ったときに最も多い原因は炎症。とくに青壮年ではある感染症を疑って調べることが重要です。発熱や膀胱刺激症状がないからといって除外することができないこの原因を見つけるためのヒントを伝授します。 -
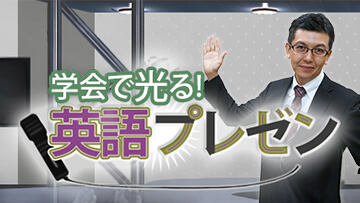 学会で光る!英語プレゼン(全8回)第1回 英語プレゼンに必要なチカラとは?2015/07/08(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会での英語プレゼンテーションには、ライブでメッセージ伝達できる、意見交換から人とのつながりが生まれる、など英語論文とは違う効果があります。今回は、英語プレゼンの効果、英語プレゼン力とは、どうしたら英語プレゼン力は上がるのか、について紹介します。
学会で光る!英語プレゼン(全8回)第1回 英語プレゼンに必要なチカラとは?2015/07/08(水)公開 佐藤 雅昭 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師学会での英語プレゼンテーションには、ライブでメッセージ伝達できる、意見交換から人とのつながりが生まれる、など英語論文とは違う効果があります。今回は、英語プレゼンの効果、英語プレゼン力とは、どうしたら英語プレゼン力は上がるのか、について紹介します。 -
 Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第10回 所見のない失神心電図2021/11/24(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編もいよいよ最終回! 今回はこのシリーズの第1回~第9回で学んだ心電図のいずれにも該当する所見がない心電図が登場。さあ、あなたならどう判断しますか? 初回心電図で心原性と診断できるのはわずか5%未満。心電図以外でも方法があるのか?しっかりと確認してください!
Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第10回 所見のない失神心電図2021/11/24(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編もいよいよ最終回! 今回はこのシリーズの第1回~第9回で学んだ心電図のいずれにも該当する所見がない心電図が登場。さあ、あなたならどう判断しますか? 初回心電図で心原性と診断できるのはわずか5%未満。心電図以外でも方法があるのか?しっかりと確認してください! -
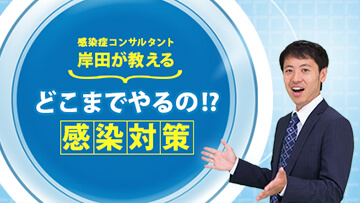 感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第3回 感染対策の基本はMRSA2016/01/27(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師なんといっても感染対策の基本はMRSAです。 最近ではMRSAに関する報道もなく、MRSAに慣れっこになっていませんか? でも実は日本の医療機関で検出される黄色ブドウ球菌に占めるMRSAの割合はなんと50%!まだまだ高いのが現状です。 そのMRSAを抑えることができれば、院内感染を“ゼロ”に近づけていくことも可能です。 MRSAの感染対策について理想論...
感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第3回 感染対策の基本はMRSA2016/01/27(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師なんといっても感染対策の基本はMRSAです。 最近ではMRSAに関する報道もなく、MRSAに慣れっこになっていませんか? でも実は日本の医療機関で検出される黄色ブドウ球菌に占めるMRSAの割合はなんと50%!まだまだ高いのが現状です。 そのMRSAを抑えることができれば、院内感染を“ゼロ”に近づけていくことも可能です。 MRSAの感染対策について理想論... -
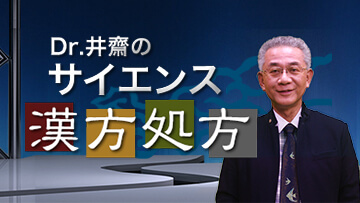 Dr.井齋のサイエンス漢方処方(全5回)第1回 なぜサイエンス漢方処方なのか?2014/12/03(水)公開 井齋 偉矢 日高徳洲会病院 院長基本的に1成分で構成され、対処療法に有用な西洋薬と異なり、漢方薬は複数の生薬で構成され、生薬それぞれが作用を刺激しあうことで、さまざまな効用を発揮します。第1回の「Dr.井齋のサイエンス漢方処方」では、漢方薬の開発過程や成分形態、効能などを西洋薬と比較しながら、サイエンス漢方処方の基本的な考え方を解説します。
Dr.井齋のサイエンス漢方処方(全5回)第1回 なぜサイエンス漢方処方なのか?2014/12/03(水)公開 井齋 偉矢 日高徳洲会病院 院長基本的に1成分で構成され、対処療法に有用な西洋薬と異なり、漢方薬は複数の生薬で構成され、生薬それぞれが作用を刺激しあうことで、さまざまな効用を発揮します。第1回の「Dr.井齋のサイエンス漢方処方」では、漢方薬の開発過程や成分形態、効能などを西洋薬と比較しながら、サイエンス漢方処方の基本的な考え方を解説します。 -
 産婦人科医ユミの頼られる「女性のミカタ」(全8回)第3回 何が怖い?妊婦の急変2014/07/09(水)公開 池田 裕美枝 産婦人科医 / NPO法人女性医療ネットワーク 副理事長妊婦が急な腹痛を訴えて産婦人科以外に受診したとき、どう対応したら良いでしょうか?重要なポイントになるのが、妊娠にまつわる腹痛なのか、そうではないのかの見極めです。 今回は、ただちに産婦人科へコンサルトすべき緊急疾患と、その鑑別方法について解説します。 冒頭のスキットでは、ユミ先生こと池田裕美枝先生扮する妊婦が腹痛を訴えて受診...
産婦人科医ユミの頼られる「女性のミカタ」(全8回)第3回 何が怖い?妊婦の急変2014/07/09(水)公開 池田 裕美枝 産婦人科医 / NPO法人女性医療ネットワーク 副理事長妊婦が急な腹痛を訴えて産婦人科以外に受診したとき、どう対応したら良いでしょうか?重要なポイントになるのが、妊娠にまつわる腹痛なのか、そうではないのかの見極めです。 今回は、ただちに産婦人科へコンサルトすべき緊急疾患と、その鑑別方法について解説します。 冒頭のスキットでは、ユミ先生こと池田裕美枝先生扮する妊婦が腹痛を訴えて受診... -
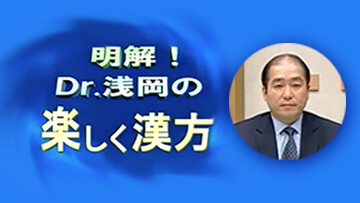 明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第3回 カゼに葛根湯が効かない?2004/07/15(木)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長今回はカゼについての漢方治療のお話です。カゼは非常に一般的な疾患であり「カゼのひき始めに葛根湯」はよく用いられる言葉ですが、そもそも「ひき始め」って一体いつまでなんでしょうか?そして、葛根湯を使っても全く効かなかった、そんな経験はないでしょうか。本シリーズ第1回「東洋医学の特徴」で学習した東洋医学的な診断方法「証」、そして「証」を使った...
明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第3回 カゼに葛根湯が効かない?2004/07/15(木)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長今回はカゼについての漢方治療のお話です。カゼは非常に一般的な疾患であり「カゼのひき始めに葛根湯」はよく用いられる言葉ですが、そもそも「ひき始め」って一体いつまでなんでしょうか?そして、葛根湯を使っても全く効かなかった、そんな経験はないでしょうか。本シリーズ第1回「東洋医学の特徴」で学習した東洋医学的な診断方法「証」、そして「証」を使った... -
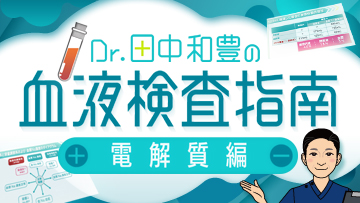 Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第6回 総論6:酸塩基平衡障害の評価方法2021/11/24(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第6回は、酸塩基平衡の評価方法について確認していきましょう。前回で紹介したいくつかの評価方法の中でも、医師国家試験や内科専門医試験に出題されるのはBoston Approachによる酸塩基平衡の評価方法です。ですので、まずはこの評価方法を身に付けていきましょう。
Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第6回 総論6:酸塩基平衡障害の評価方法2021/11/24(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第6回は、酸塩基平衡の評価方法について確認していきましょう。前回で紹介したいくつかの評価方法の中でも、医師国家試験や内科専門医試験に出題されるのはBoston Approachによる酸塩基平衡の評価方法です。ですので、まずはこの評価方法を身に付けていきましょう。
Dr.田中和豊考案の、人体の酸塩基平衡...