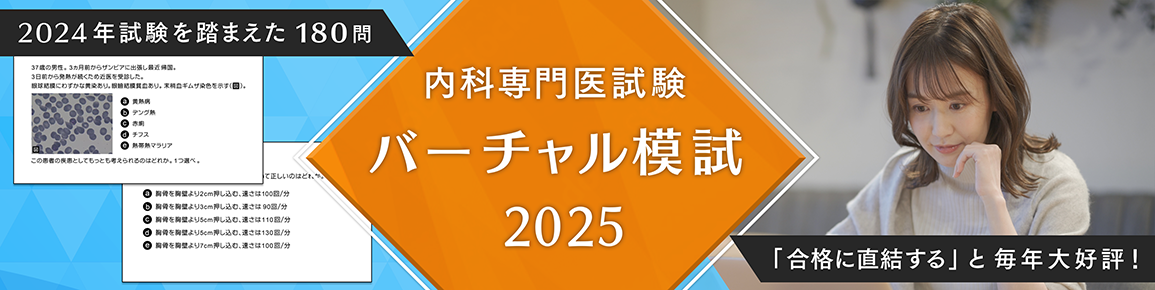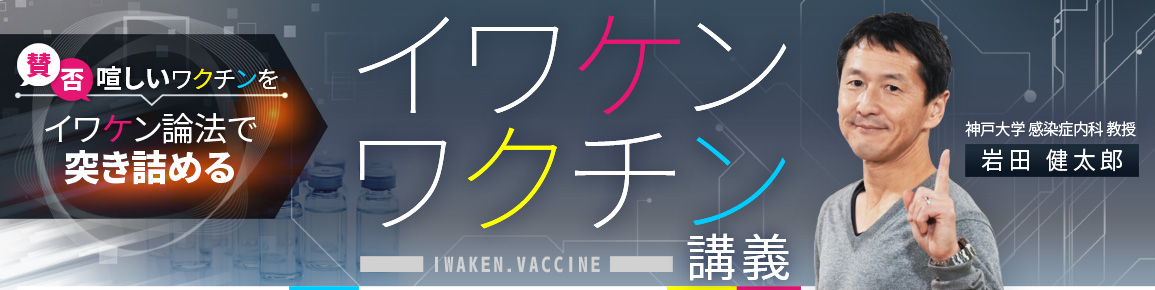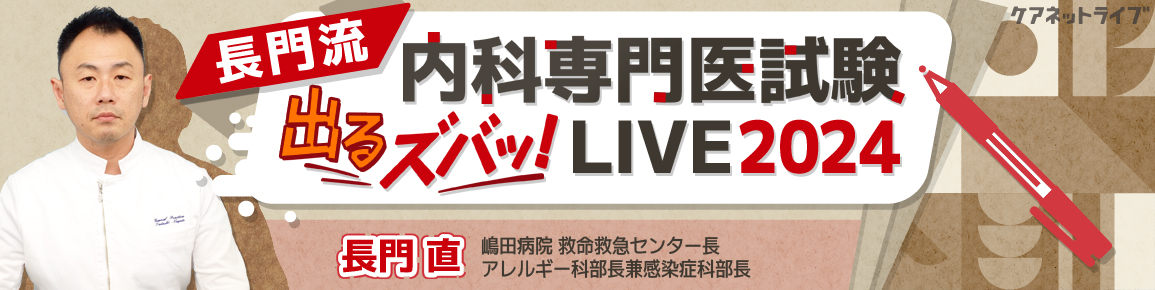番組検索結果
-
 Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第10回 所見のない失神心電図2021/11/24(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編もいよいよ最終回! 今回はこのシリーズの第1回~第9回で学んだ心電図のいずれにも該当する所見がない心電図が登場。さあ、あなたならどう判断しますか? 初回心電図で心原性と診断できるのはわずか5%未満。心電図以外でも方法があるのか?しっかりと確認してください!
Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回)第10回 所見のない失神心電図2021/11/24(水)公開 増井 伸高 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 副センター長・国際医療支援室室長Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編もいよいよ最終回! 今回はこのシリーズの第1回~第9回で学んだ心電図のいずれにも該当する所見がない心電図が登場。さあ、あなたならどう判断しますか? 初回心電図で心原性と診断できるのはわずか5%未満。心電図以外でも方法があるのか?しっかりと確認してください! -
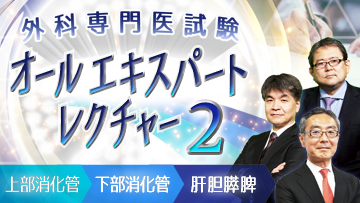 外科専門医試験 オールエキスパートレクチャー2(全11回)第1回 上部消化管12022/06/22(水)公開 深川 剛生 帝京大学医学部外科学講座教授上部消化管は帝京大学外科教授 深川剛生先生が4回にわたって講義します。 まずは外科専門医試験の過去問の分析から。その中でも重要な項目である食道の解剖と食道癌を中心に解説します。
外科専門医試験 オールエキスパートレクチャー2(全11回)第1回 上部消化管12022/06/22(水)公開 深川 剛生 帝京大学医学部外科学講座教授上部消化管は帝京大学外科教授 深川剛生先生が4回にわたって講義します。 まずは外科専門医試験の過去問の分析から。その中でも重要な項目である食道の解剖と食道癌を中心に解説します。 -
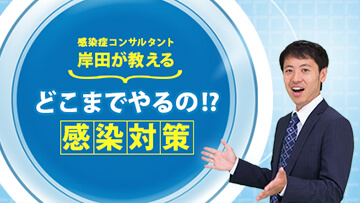 感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第3回 感染対策の基本はMRSA2016/01/27(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師なんといっても感染対策の基本はMRSAです。 最近ではMRSAに関する報道もなく、MRSAに慣れっこになっていませんか? でも実は日本の医療機関で検出される黄色ブドウ球菌に占めるMRSAの割合はなんと50%!まだまだ高いのが現状です。 そのMRSAを抑えることができれば、院内感染を“ゼロ”に近づけていくことも可能です。 MRSAの感染対策について理想論...
感染症コンサルタント岸田が教える どこまでやるの!?感染対策(全9回)第3回 感染対策の基本はMRSA2016/01/27(水)公開 岸田 直樹 一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 ・ 医師なんといっても感染対策の基本はMRSAです。 最近ではMRSAに関する報道もなく、MRSAに慣れっこになっていませんか? でも実は日本の医療機関で検出される黄色ブドウ球菌に占めるMRSAの割合はなんと50%!まだまだ高いのが現状です。 そのMRSAを抑えることができれば、院内感染を“ゼロ”に近づけていくことも可能です。 MRSAの感染対策について理想論... -
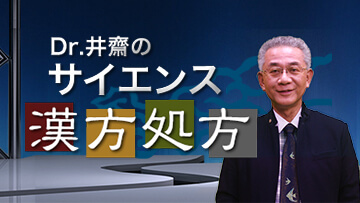 Dr.井齋のサイエンス漢方処方(全5回)第1回 なぜサイエンス漢方処方なのか?2014/12/03(水)公開 井齋 偉矢 日高徳洲会病院 院長基本的に1成分で構成され、対処療法に有用な西洋薬と異なり、漢方薬は複数の生薬で構成され、生薬それぞれが作用を刺激しあうことで、さまざまな効用を発揮します。第1回の「Dr.井齋のサイエンス漢方処方」では、漢方薬の開発過程や成分形態、効能などを西洋薬と比較しながら、サイエンス漢方処方の基本的な考え方を解説します。
Dr.井齋のサイエンス漢方処方(全5回)第1回 なぜサイエンス漢方処方なのか?2014/12/03(水)公開 井齋 偉矢 日高徳洲会病院 院長基本的に1成分で構成され、対処療法に有用な西洋薬と異なり、漢方薬は複数の生薬で構成され、生薬それぞれが作用を刺激しあうことで、さまざまな効用を発揮します。第1回の「Dr.井齋のサイエンス漢方処方」では、漢方薬の開発過程や成分形態、効能などを西洋薬と比較しながら、サイエンス漢方処方の基本的な考え方を解説します。 -
 産婦人科医ユミの頼られる「女性のミカタ」(全8回)第3回 何が怖い?妊婦の急変2014/07/09(水)公開 池田 裕美枝 産婦人科医 / NPO法人女性医療ネットワーク 副理事長妊婦が急な腹痛を訴えて産婦人科以外に受診したとき、どう対応したら良いでしょうか?重要なポイントになるのが、妊娠にまつわる腹痛なのか、そうではないのかの見極めです。 今回は、ただちに産婦人科へコンサルトすべき緊急疾患と、その鑑別方法について解説します。 冒頭のスキットでは、ユミ先生こと池田裕美枝先生扮する妊婦が腹痛を訴えて受診...
産婦人科医ユミの頼られる「女性のミカタ」(全8回)第3回 何が怖い?妊婦の急変2014/07/09(水)公開 池田 裕美枝 産婦人科医 / NPO法人女性医療ネットワーク 副理事長妊婦が急な腹痛を訴えて産婦人科以外に受診したとき、どう対応したら良いでしょうか?重要なポイントになるのが、妊娠にまつわる腹痛なのか、そうではないのかの見極めです。 今回は、ただちに産婦人科へコンサルトすべき緊急疾患と、その鑑別方法について解説します。 冒頭のスキットでは、ユミ先生こと池田裕美枝先生扮する妊婦が腹痛を訴えて受診... -
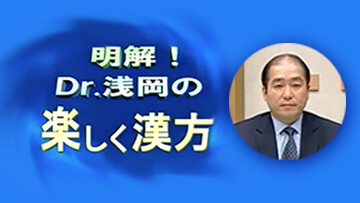 明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第3回 カゼに葛根湯が効かない?2004/07/15(木)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長今回はカゼについての漢方治療のお話です。カゼは非常に一般的な疾患であり「カゼのひき始めに葛根湯」はよく用いられる言葉ですが、そもそも「ひき始め」って一体いつまでなんでしょうか?そして、葛根湯を使っても全く効かなかった、そんな経験はないでしょうか。本シリーズ第1回「東洋医学の特徴」で学習した東洋医学的な診断方法「証」、そして「証」を使った...
明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第3回 カゼに葛根湯が効かない?2004/07/15(木)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長今回はカゼについての漢方治療のお話です。カゼは非常に一般的な疾患であり「カゼのひき始めに葛根湯」はよく用いられる言葉ですが、そもそも「ひき始め」って一体いつまでなんでしょうか?そして、葛根湯を使っても全く効かなかった、そんな経験はないでしょうか。本シリーズ第1回「東洋医学の特徴」で学習した東洋医学的な診断方法「証」、そして「証」を使った... -
 Dr.松田のフローチャート皮膚診断(全7回)第4回 真皮の病変(1) 蕁麻疹の鑑別と中毒疹の考え方2023/03/16(木)公開 松田 光弘 皮膚科専門医、アレルギー専門医ここからは表面がツルツルの紅斑=真皮・皮下組織の病変について学びます。まずは原因が真皮にあるか皮下組織にあるかですが、その見分け方は超カンタン。松田先生の解説を聞けばその理由も含めてすぐに理解できるでしょう。また、今回のお話しの中心である蕁麻疹と中毒疹(薬疹・感染症・膠原病)には膨大な鑑別診断がありますが、フローチャートに沿...
Dr.松田のフローチャート皮膚診断(全7回)第4回 真皮の病変(1) 蕁麻疹の鑑別と中毒疹の考え方2023/03/16(木)公開 松田 光弘 皮膚科専門医、アレルギー専門医ここからは表面がツルツルの紅斑=真皮・皮下組織の病変について学びます。まずは原因が真皮にあるか皮下組織にあるかですが、その見分け方は超カンタン。松田先生の解説を聞けばその理由も含めてすぐに理解できるでしょう。また、今回のお話しの中心である蕁麻疹と中毒疹(薬疹・感染症・膠原病)には膨大な鑑別診断がありますが、フローチャートに沿... -
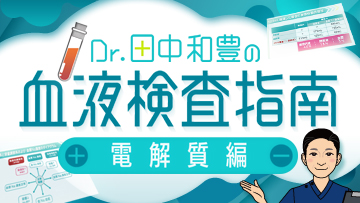 Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第6回 総論6:酸塩基平衡障害の評価方法2021/11/24(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第6回は、酸塩基平衡の評価方法について確認していきましょう。前回で紹介したいくつかの評価方法の中でも、医師国家試験や内科専門医試験に出題されるのはBoston Approachによる酸塩基平衡の評価方法です。ですので、まずはこの評価方法を身に付けていきましょう。
Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(全12回)第6回 総論6:酸塩基平衡障害の評価方法2021/11/24(水)公開 田中 和豊 済生会福岡総合病院 総合診療部 主任部長/臨床教育部部長Dr.田中和豊の血液検査指南「電解質編」の第6回は、酸塩基平衡の評価方法について確認していきましょう。前回で紹介したいくつかの評価方法の中でも、医師国家試験や内科専門医試験に出題されるのはBoston Approachによる酸塩基平衡の評価方法です。ですので、まずはこの評価方法を身に付けていきましょう。
Dr.田中和豊考案の、人体の酸塩基平衡... -
 内科専門医試験 バーチャル模試2025(全9回)第8回 第141~160問2025/04/17(木)公開 ケアネット内科試験問題作成チーム ケアネット第8回は、内科専門医試験バーチャル模試2025の第141~160問です。
内科専門医試験 バーチャル模試2025(全9回)第8回 第141~160問2025/04/17(木)公開 ケアネット内科試験問題作成チーム ケアネット第8回は、内科専門医試験バーチャル模試2025の第141~160問です。 -
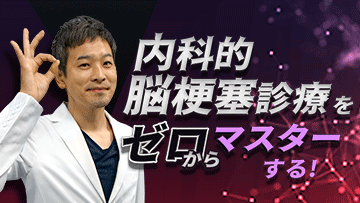 内科的脳梗塞診療をゼロからマスターする!(全6回)第3回 内科的脳梗塞の急性期治療2024/05/23(木)公開 山本大介 湘南鎌倉総合病院 脳神経内科第3回では、急性期の治療に焦点を当てます。病型分類と重症度などから、急性期において適切な治療薬の選択方法やタイミングを詳説します。また、ガイドラインの要点ついてもポイントを押さえて解説。番組の最後にまとめとして症例を提示し、自身で急性期治療を適切に行えるかをを確認ができます。この番組を通じて、脳梗塞の「内科的」急性期治療をマス...
内科的脳梗塞診療をゼロからマスターする!(全6回)第3回 内科的脳梗塞の急性期治療2024/05/23(木)公開 山本大介 湘南鎌倉総合病院 脳神経内科第3回では、急性期の治療に焦点を当てます。病型分類と重症度などから、急性期において適切な治療薬の選択方法やタイミングを詳説します。また、ガイドラインの要点ついてもポイントを押さえて解説。番組の最後にまとめとして症例を提示し、自身で急性期治療を適切に行えるかをを確認ができます。この番組を通じて、脳梗塞の「内科的」急性期治療をマス... -
 Dr.岩田の感染症アップグレード-外来シリーズ-(全7回)第5回 気分はトラベル!楽しい旅行医学2006/12/15(金)公開 岩田 健太郎 神戸大学 感染症内科 教授感染症というと、難しい疾患や細菌の名前、ややこしい治療法など“頭が痛くなることばかり”と言う方も多いと思いますが、そんな中、楽しくできる感染症学が「旅行医学」です。大学で教えてくれることはなく、日本ではまだ未熟な分野ですが、日本人の行動範囲がどんどん世界に広がり、昔と違い発展途上国に旅行する人も飛躍的に増えているため、ますます重...
Dr.岩田の感染症アップグレード-外来シリーズ-(全7回)第5回 気分はトラベル!楽しい旅行医学2006/12/15(金)公開 岩田 健太郎 神戸大学 感染症内科 教授感染症というと、難しい疾患や細菌の名前、ややこしい治療法など“頭が痛くなることばかり”と言う方も多いと思いますが、そんな中、楽しくできる感染症学が「旅行医学」です。大学で教えてくれることはなく、日本ではまだ未熟な分野ですが、日本人の行動範囲がどんどん世界に広がり、昔と違い発展途上国に旅行する人も飛躍的に増えているため、ますます重... -
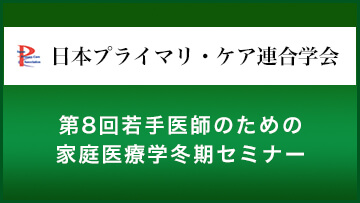 日本プライマリ・ケア連合学会 第8回 若手医師のための家庭医療学冬期セミナー(全3回)WS15 ジェネラリストのための産婦人科医療2013/05/08(水)公開 加藤 一朗 隠岐病院妊婦さんへの処方、女性の腹痛などで困ったことはありませんか?
日本プライマリ・ケア連合学会 第8回 若手医師のための家庭医療学冬期セミナー(全3回)WS15 ジェネラリストのための産婦人科医療2013/05/08(水)公開 加藤 一朗 隠岐病院妊婦さんへの処方、女性の腹痛などで困ったことはありませんか?
すぐに産婦人科専門医にコンサルトしていませんか?
妊婦さんの12%は鎮痛剤を服用、9%は喘息など慢性疾患の薬を服用しています。
一方妊娠の2%以上に先天奇形のベビーが生まれますがその半数以上は原因不明、1/4は遺伝子異常ですが、薬に関係しているものは2%といわ... -
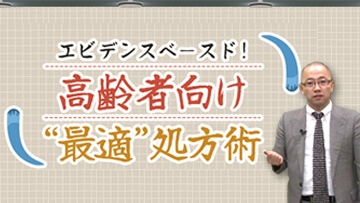 エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第7回 糖尿病治療薬2016/05/25(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科高齢の糖尿病患者さん。「血糖コントロールは良好だけと、低血糖は大丈夫かな?」と思いつつ処方していませんか? ご存じのとおり、高齢の糖尿病患者に対する厳格な血糖コントロールは、良好なアウトカムを示していません。しかし、緩徐なコントロールでは合併症が心配です。 一体、どの程度の目標値にコントロールすれば良いのでしょうか? 今回は、海...
エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第7回 糖尿病治療薬2016/05/25(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科高齢の糖尿病患者さん。「血糖コントロールは良好だけと、低血糖は大丈夫かな?」と思いつつ処方していませんか? ご存じのとおり、高齢の糖尿病患者に対する厳格な血糖コントロールは、良好なアウトカムを示していません。しかし、緩徐なコントロールでは合併症が心配です。 一体、どの程度の目標値にコントロールすれば良いのでしょうか? 今回は、海... -
 聖路加GENERAL<腫瘍内科学>(全2回)第2回 Oncologic emergenciesとがん性疼痛管理について2011/07/13(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:大山 優 氏
聖路加GENERAL<腫瘍内科学>(全2回)第2回 Oncologic emergenciesとがん性疼痛管理について2011/07/13(水)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:大山 優 氏
がんは慢性疾患のひとつと捉えられますが、救急処置が必要な「Oncologic emergencies」という病態があります。たとえばSAIDH は、肺がんなど、がん自体に起因するほかプラチナ系のシスプラチンなどの治療薬が原因となることもあります。また、がんの既往がある患者に脊髄圧迫による疼痛や高カルシウム血症などが発症した場合... -
 Dr.林の笑劇的救急問答 Season17(全8回)第4回 しびれに対する身体診察って2023/11/16(木)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回のしびれは「頸椎性神経根症」がテーマ。しびれに対する神経所見の身体診察について解説します。診断するには、しっかりとデルマトームを理解しそのしびれの原因がどこにあるのかを見極めること。Dr.林が体を張ったデモンストレーションで覚え方を伝授します。単なる語呂合わせでなく、楽しさと覚えやすさを追求するのがDr.林ならでは。一緒にやっ...
Dr.林の笑劇的救急問答 Season17(全8回)第4回 しびれに対する身体診察って2023/11/16(木)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回のしびれは「頸椎性神経根症」がテーマ。しびれに対する神経所見の身体診察について解説します。診断するには、しっかりとデルマトームを理解しそのしびれの原因がどこにあるのかを見極めること。Dr.林が体を張ったデモンストレーションで覚え方を伝授します。単なる語呂合わせでなく、楽しさと覚えやすさを追求するのがDr.林ならでは。一緒にやっ... -
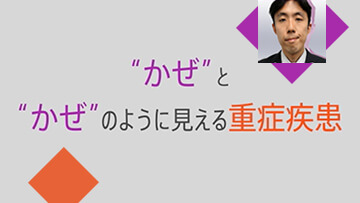 “かぜ”と“かぜ”のように見える重症疾患(全13回)第5回 column1 悪寒戦慄とCRP2011/07/13(水)公開 山本 舜悟 京都大学医学部附属病院 臨床研究・教育研修部たいていの血液検査で測られているCRP。感度や特異度はそれほど高いわけでなく、場合によっては計測自体に意味がないこともあります。しかし、使いようによっては思わぬピットフォールを避ける武器にもなります。悪寒戦慄と合わせて、CRPの使い方を覚えましょう。
“かぜ”と“かぜ”のように見える重症疾患(全13回)第5回 column1 悪寒戦慄とCRP2011/07/13(水)公開 山本 舜悟 京都大学医学部附属病院 臨床研究・教育研修部たいていの血液検査で測られているCRP。感度や特異度はそれほど高いわけでなく、場合によっては計測自体に意味がないこともあります。しかし、使いようによっては思わぬピットフォールを避ける武器にもなります。悪寒戦慄と合わせて、CRPの使い方を覚えましょう。 -
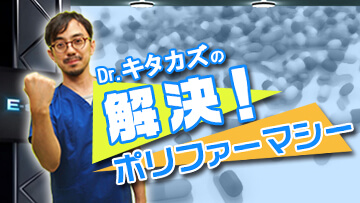 Dr.キタカズの解決!ポリファーマシー(全6回)第2回 最も気を付けるべき薬剤はコレだ2016/11/16(水)公開 北 和也 医療法人やわらぎ会 やわらぎクリニック 院長数ヵ月単位で衰弱していく80歳代男性患者。高齢のためと思っていた症状が実は薬剤性だった!今回はそんな事例を通して、日常臨床で頻繁に処方されるものの、薬物有害事象を起こしやすい薬剤について解説します。その症状が薬剤性だと気付くために、誰でも知ってるあの格言が役に立ちます。どう使うのかぜひ番組をご覧ください。
Dr.キタカズの解決!ポリファーマシー(全6回)第2回 最も気を付けるべき薬剤はコレだ2016/11/16(水)公開 北 和也 医療法人やわらぎ会 やわらぎクリニック 院長数ヵ月単位で衰弱していく80歳代男性患者。高齢のためと思っていた症状が実は薬剤性だった!今回はそんな事例を通して、日常臨床で頻繁に処方されるものの、薬物有害事象を起こしやすい薬剤について解説します。その症状が薬剤性だと気付くために、誰でも知ってるあの格言が役に立ちます。どう使うのかぜひ番組をご覧ください。 -
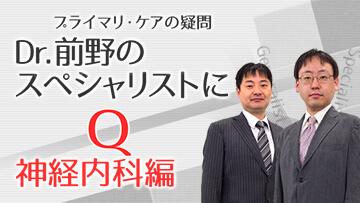 プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!(神経内科編)(全16回)第15回 【しびれ】紹介すべきか経過観察かを見分ける2016/10/12(水)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長しびれはよくある訴えですが、稀にすぐに専門医に紹介すべき例が隠れています。 この両者を見分ける条件を伝授。原因部位を3つに分類して数多い鑑別疾患をクリアに整理します。 日頃から診る機会の多い中でも、レッドフラッグを見落とさず発見するワザを身に付けてください。
プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!(神経内科編)(全16回)第15回 【しびれ】紹介すべきか経過観察かを見分ける2016/10/12(水)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長しびれはよくある訴えですが、稀にすぐに専門医に紹介すべき例が隠れています。 この両者を見分ける条件を伝授。原因部位を3つに分類して数多い鑑別疾患をクリアに整理します。 日頃から診る機会の多い中でも、レッドフラッグを見落とさず発見するワザを身に付けてください。 -
 ERで闘うための手技(全8回)第4回 動脈穿刺2020/11/04(水)公開 久村 正樹 埼玉医科大学総合医療センター 救急科(ER)難易度が高い動脈穿刺は、ショックなどの重症患者の管理には欠かせない手技です。 この回では、第1選択である橈骨動脈での穿刺方法について学びます。 講義では橈骨動脈での動脈路確保の前に必ず行うアレンテストの手順、シミュレーターを用いた手技動画では、穿刺法と貫通法をそれぞれイラストを交えて詳しく解説していきます。
ERで闘うための手技(全8回)第4回 動脈穿刺2020/11/04(水)公開 久村 正樹 埼玉医科大学総合医療センター 救急科(ER)難易度が高い動脈穿刺は、ショックなどの重症患者の管理には欠かせない手技です。 この回では、第1選択である橈骨動脈での穿刺方法について学びます。 講義では橈骨動脈での動脈路確保の前に必ず行うアレンテストの手順、シミュレーターを用いた手技動画では、穿刺法と貫通法をそれぞれイラストを交えて詳しく解説していきます。 -
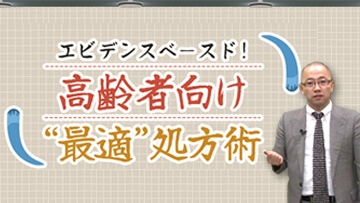 エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第2回 高齢者総合機能評価(CGA)2016/04/13(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科高齢者診療では、病気だけに焦点を当ててもQOL向上にはつながりません。 QOLを構成するさまざまな要素を評価し、個々の患者に最適な介入を決めることが必要です。 今回は、高齢患者診療の基本第2弾 高齢患者のQOLをシンプルかつ網羅的に評価できる国際的指標「高齢者総合機能評価(CGA)」について関口健二先生が解説します。
エビデンスベースド!高齢者向け“最適”処方術(全7回)第2回 高齢者総合機能評価(CGA)2016/04/13(水)公開 関口 健二 信州大学医学部附属病院/市立大町総合病院 総合診療科高齢者診療では、病気だけに焦点を当ててもQOL向上にはつながりません。 QOLを構成するさまざまな要素を評価し、個々の患者に最適な介入を決めることが必要です。 今回は、高齢患者診療の基本第2弾 高齢患者のQOLをシンプルかつ網羅的に評価できる国際的指標「高齢者総合機能評価(CGA)」について関口健二先生が解説します。 -
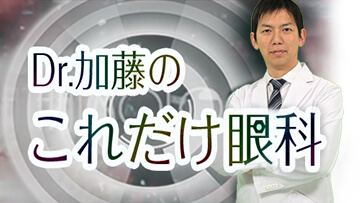 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第3回 「緑内障」はこれだけ2016/04/27(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第3回は高齢疾患である緑内障。先生の患者さんにも大勢いらっしゃるのではないでしょうか?緑内障は症状が現れるころには、すでに中期以降に進行しているため、プライマリケア医による早期発見・治療はとても重要です。 番組では、緑内障の眼底所見、頭痛や悪心嘔吐など身体症状を呈する緑内障発作の初期対応、また、抗コリン薬...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第3回 「緑内障」はこれだけ2016/04/27(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授Dr.加藤のこれだけ眼科、第3回は高齢疾患である緑内障。先生の患者さんにも大勢いらっしゃるのではないでしょうか?緑内障は症状が現れるころには、すでに中期以降に進行しているため、プライマリケア医による早期発見・治療はとても重要です。 番組では、緑内障の眼底所見、頭痛や悪心嘔吐など身体症状を呈する緑内障発作の初期対応、また、抗コリン薬... -
 聖路加GENERAL<内分泌疾患>(全6回)第5回 ただ風邪といっても2011/05/23(月)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:出雲 博子氏 もともと健康な21歳の女子大生。 発熱、咽頭痛など、感染症の症状を呈したため近医で受診しました。数種類の抗菌薬を処方されましたが改善せず、ついには意識低下で救急コールとなりました。 糖尿病の既往のある78歳の男性。 家族が訪ねて行ったら、すでに意識がなく倒れていました。 いずれも意識障害が出る危険な状態です...
聖路加GENERAL<内分泌疾患>(全6回)第5回 ただ風邪といっても2011/05/23(月)公開 岡田 正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 部長・センター長黒帯師範:出雲 博子氏 もともと健康な21歳の女子大生。 発熱、咽頭痛など、感染症の症状を呈したため近医で受診しました。数種類の抗菌薬を処方されましたが改善せず、ついには意識低下で救急コールとなりました。 糖尿病の既往のある78歳の男性。 家族が訪ねて行ったら、すでに意識がなく倒れていました。 いずれも意識障害が出る危険な状態です... -
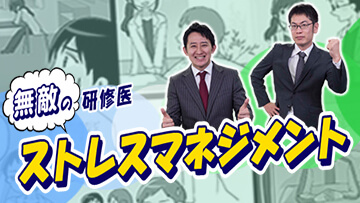 無敵の研修医ストレスマネジメント(全7回)第1回 デキレジほどうつになりやすい!?2017/01/25(水)公開 鈴木 瞬 SNCメンタルヘルス・産業医事務所代表初期臨床研修に臨む医師1年生の皆さんも知っての通り、研修期間は過酷そのもの。約3割の研修医がうつを経験する厳しいストレス環境で、充実した研修生活を送るための必須スキルが、「ストレスマネジメント」です! できるだけ早い段階でこのスキルを身に付けておけば、研修期間だけでなくこれからの長い医師人生が快適になること間違いありません。第1...
無敵の研修医ストレスマネジメント(全7回)第1回 デキレジほどうつになりやすい!?2017/01/25(水)公開 鈴木 瞬 SNCメンタルヘルス・産業医事務所代表初期臨床研修に臨む医師1年生の皆さんも知っての通り、研修期間は過酷そのもの。約3割の研修医がうつを経験する厳しいストレス環境で、充実した研修生活を送るための必須スキルが、「ストレスマネジメント」です! できるだけ早い段階でこのスキルを身に付けておけば、研修期間だけでなくこれからの長い医師人生が快適になること間違いありません。第1... -
 認定内科医試験完全対策 総合内科専門医ベーシック(全13回)第13回 総合内科/救急2016/06/08(水)公開 長門 直 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 呼吸器内科・アレルギー科部長最終回の総合内科/救急は、認定内科医試験では出題数は少ないですが、とくに確率統計に関する計算は毎年のように出題されているので必ず得点できるようにしておきましょう。 また、心肺蘇生ガイドライン2010から2015への変更点についてもよく勉強しておいてください。
認定内科医試験完全対策 総合内科専門医ベーシック(全13回)第13回 総合内科/救急2016/06/08(水)公開 長門 直 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 呼吸器内科・アレルギー科部長最終回の総合内科/救急は、認定内科医試験では出題数は少ないですが、とくに確率統計に関する計算は毎年のように出題されているので必ず得点できるようにしておきましょう。 また、心肺蘇生ガイドライン2010から2015への変更点についてもよく勉強しておいてください。