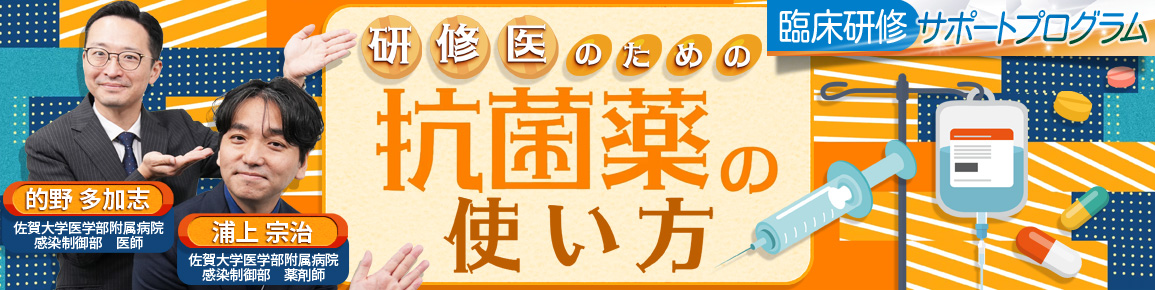番組検索結果
-
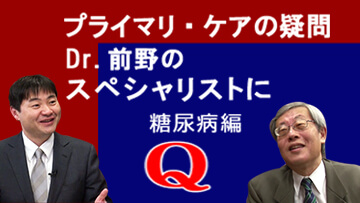 プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!(糖尿病編)(全12回)第14回 糖質制限食が適応になる症例はある?2014/12/03(水)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長糖尿病の食事療法の中でいま最も注目を集める糖質制限食。 情報が錯綜する中で専門医はどのように指導しているのか、ズバリお教えします。 日本糖尿病学会の見解は?糖質を減らした分脂質摂取が増えていいのか?数々の疑問にお答えします!
プライマリ・ケアの疑問 Dr.前野のスペシャリストにQ!(糖尿病編)(全12回)第14回 糖質制限食が適応になる症例はある?2014/12/03(水)公開 前野 哲博 筑波大学 教授/筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長糖尿病の食事療法の中でいま最も注目を集める糖質制限食。 情報が錯綜する中で専門医はどのように指導しているのか、ズバリお教えします。 日本糖尿病学会の見解は?糖質を減らした分脂質摂取が増えていいのか?数々の疑問にお答えします! -
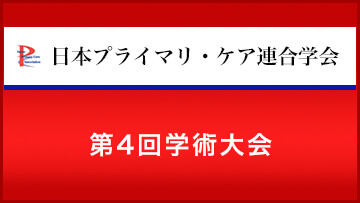 日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 学術大会(全14回)ワークショップ15 日常診療における抗菌薬の使い方 ~サンフォードを上手に使おう~2013/08/28(水)公開 見坂 恒明 自治医科大学 総合診療部日常よく遭遇する感染症疾患(中耳炎、咽頭炎、副鼻腔炎、肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎等)への実践的な抗菌薬の使用方法について、サンフォード感染症治療ガイドを使いレクチャーします。
日本プライマリ・ケア連合学会 第4回 学術大会(全14回)ワークショップ15 日常診療における抗菌薬の使い方 ~サンフォードを上手に使おう~2013/08/28(水)公開 見坂 恒明 自治医科大学 総合診療部日常よく遭遇する感染症疾患(中耳炎、咽頭炎、副鼻腔炎、肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎等)への実践的な抗菌薬の使用方法について、サンフォード感染症治療ガイドを使いレクチャーします。 -
 Dr.林&今の「防ぎえた死」をなくすための救急初期対応(全6回)第4回 胸痛2023/05/18(木)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授胸痛は非常に緊急性の高い症状です。今回は胸痛を伴う代表的な疾患である、心筋梗塞・大動脈解離・肺塞栓・特発性食道破裂について症例を示しながら今先生がわかりやすく解説します。折に触れて出題されるクイズや、今先生がヘモグロビンに扮して病態生理を面白おかしく解説するDr.今劇場など工夫が満載。楽しみながら視聴するだけで各疾患の特徴・鑑別...
Dr.林&今の「防ぎえた死」をなくすための救急初期対応(全6回)第4回 胸痛2023/05/18(木)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授胸痛は非常に緊急性の高い症状です。今回は胸痛を伴う代表的な疾患である、心筋梗塞・大動脈解離・肺塞栓・特発性食道破裂について症例を示しながら今先生がわかりやすく解説します。折に触れて出題されるクイズや、今先生がヘモグロビンに扮して病態生理を面白おかしく解説するDr.今劇場など工夫が満載。楽しみながら視聴するだけで各疾患の特徴・鑑別... -
 ユキティ先生の救急MRI読影教室(全8回)第3回 混じりけのある水2023/10/26(木)公開 熊坂由紀子 大原綜合病院 放射線科 主任部長MRIの信号強度は、液体に何が混ざっているかで変化します。今回は、漿液性、粘液性、血性の嚢胞性腫瘤を例に、混和物による画像の違いを見ていきます。基準となる漿液性の画像を確認したのち、粘液性では、T1WI、T2WIに加えてより変化を明確に捉えられる撮像法を解説。出血性では、急性期と慢性期それぞれの特徴を踏まえた読影のポイントを押さえましょ...
ユキティ先生の救急MRI読影教室(全8回)第3回 混じりけのある水2023/10/26(木)公開 熊坂由紀子 大原綜合病院 放射線科 主任部長MRIの信号強度は、液体に何が混ざっているかで変化します。今回は、漿液性、粘液性、血性の嚢胞性腫瘤を例に、混和物による画像の違いを見ていきます。基準となる漿液性の画像を確認したのち、粘液性では、T1WI、T2WIに加えてより変化を明確に捉えられる撮像法を解説。出血性では、急性期と慢性期それぞれの特徴を踏まえた読影のポイントを押さえましょ... -
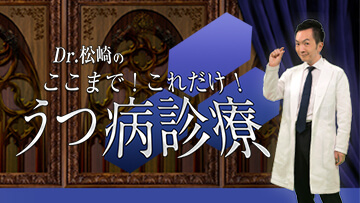 Dr.松崎のここまで!これだけ!うつ病診療(全8回)第8回 自殺させない患者との接し方2016/02/03(水)公開 松崎 朝樹 筑波大学精神神経科 講師うつ病診療では、医師の接し方自体が、薬物療法と並んで重要な治療効果を持ちます。 最終回は診察に際して押さえておくべきことと、治療的な話し方や聞き方を解説します。基本的な考え方が分かれば、すぐに実践できるテクニックをぎっしり盛り込みました。 診察室での患者本人との会話にも、家族への説明や注意などにも役立ててください!
Dr.松崎のここまで!これだけ!うつ病診療(全8回)第8回 自殺させない患者との接し方2016/02/03(水)公開 松崎 朝樹 筑波大学精神神経科 講師うつ病診療では、医師の接し方自体が、薬物療法と並んで重要な治療効果を持ちます。 最終回は診察に際して押さえておくべきことと、治療的な話し方や聞き方を解説します。基本的な考え方が分かれば、すぐに実践できるテクニックをぎっしり盛り込みました。 診察室での患者本人との会話にも、家族への説明や注意などにも役立ててください! -
 Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~まずは触ってみる~ <早期介入編>(全6回)第5回 関節注射の勘どころ2014/09/03(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(リウマチ)准教授関節リウマチ患者の関節の痛みを改善させる治療法の中で、とくに即効性があり、安価で副作用の少ない方法は関節腔内への注射療法ではないでしょうか。関節腔内・筋骨格軟部組織へのステロイド注射の手法は決して難しくなく、非専門医でも施行できます。ぜひ日常診療に取り入れて患者の悩み・痛みをピンポイントで解決してください。第5回「関節注射の勘...
Dr.ハギーの関節リウマチ手とり足とり~まずは触ってみる~ <早期介入編>(全6回)第5回 関節注射の勘どころ2014/09/03(水)公開 萩野 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(リウマチ)准教授関節リウマチ患者の関節の痛みを改善させる治療法の中で、とくに即効性があり、安価で副作用の少ない方法は関節腔内への注射療法ではないでしょうか。関節腔内・筋骨格軟部組織へのステロイド注射の手法は決して難しくなく、非専門医でも施行できます。ぜひ日常診療に取り入れて患者の悩み・痛みをピンポイントで解決してください。第5回「関節注射の勘... -
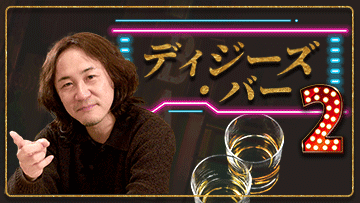 ディジーズ・バー2(全10回)第2回 梅毒2022/12/21(水)公開 國松 淳和 南多摩病院 総合内科・膠原病内科 部長前回に引き続き忽那賢志先生をゲストに迎え、昨今感染者数が増加している梅毒について語ります。 早期の段階でペニシリン治療を行えばほぼ完治する梅毒。標準治療、最新治療のメリットデメリット、神経梅毒の特徴など、気になる話を國松医師がとことん質問します。 日々の臨床で梅毒患者を診ることがあまりなくても、いざというときに有用な情報です。
ディジーズ・バー2(全10回)第2回 梅毒2022/12/21(水)公開 國松 淳和 南多摩病院 総合内科・膠原病内科 部長前回に引き続き忽那賢志先生をゲストに迎え、昨今感染者数が増加している梅毒について語ります。 早期の段階でペニシリン治療を行えばほぼ完治する梅毒。標準治療、最新治療のメリットデメリット、神経梅毒の特徴など、気になる話を國松医師がとことん質問します。 日々の臨床で梅毒患者を診ることがあまりなくても、いざというときに有用な情報です。 -
 Dr.安部の皮膚科クイズ 上級編(全6回)第2回 皮膚が黒くなったら2020/09/30(水)公開 安部 正敏 医療法人社団 廣仁会 札幌皮膚科クリニック 院長今回は皮膚が黒くなっている所見を2問出題します。第3問の所見は顔面、第4問は踵に小豆大の黒い変色。パッと見は同じに見えるかもしれませんが、それぞれに診断を導くために注目すべきポイントを解説します。
Dr.安部の皮膚科クイズ 上級編(全6回)第2回 皮膚が黒くなったら2020/09/30(水)公開 安部 正敏 医療法人社団 廣仁会 札幌皮膚科クリニック 院長今回は皮膚が黒くなっている所見を2問出題します。第3問の所見は顔面、第4問は踵に小豆大の黒い変色。パッと見は同じに見えるかもしれませんが、それぞれに診断を導くために注目すべきポイントを解説します。 -
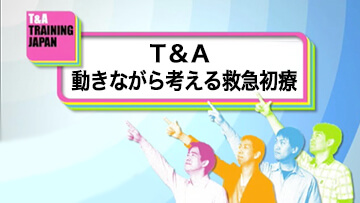 T&A 動きながら考える救急初療(全5回)第3回 診療所でみる胸痛―4 Killer chest painsを探せ!―2009/08/21(金)公開 齊藤 裕之 山口大学医学部附属病院 総合診療部・臨床教育センター、MD、MBA診療所で遭遇する致死的胸痛疾患-4 killer chest pains-とは何か?開業医の日頃の悩みにズバッと答えます!診断特性はそれほど高くない急性冠症候群の陽性尤度比(LR+)を患者の病歴と身体所見から丁寧に集め、診断に近づいていく救急初療デモンストレーションは一見の価値あり!
T&A 動きながら考える救急初療(全5回)第3回 診療所でみる胸痛―4 Killer chest painsを探せ!―2009/08/21(金)公開 齊藤 裕之 山口大学医学部附属病院 総合診療部・臨床教育センター、MD、MBA診療所で遭遇する致死的胸痛疾患-4 killer chest pains-とは何か?開業医の日頃の悩みにズバッと答えます!診断特性はそれほど高くない急性冠症候群の陽性尤度比(LR+)を患者の病歴と身体所見から丁寧に集め、診断に近づいていく救急初療デモンストレーションは一見の価値あり! -
 ダリワル先生が教える診断のエキスパートになる方法(全1回)ダリワル先生が教える診断のエキスパートになる方法2021/03/17(水)公開 ガープリート・ダリワル カリフォルニア大学サンフランシスコ校 総合内科教授UCSFのダリワル教授は巧みな臨床推論カンファレンスで有名です。 師匠であるティアニー先生が天才的な発想力によって診断を行うのに対して、 ダリワル先生は順序立った正確な診断に長け、AIの比較対象とされるほど。 そんな彼が診断のエキスパートになる方法についてレクチャーした 湘南鎌倉総合病院での特別講義を日本語字幕付きで公開!
ダリワル先生が教える診断のエキスパートになる方法(全1回)ダリワル先生が教える診断のエキスパートになる方法2021/03/17(水)公開 ガープリート・ダリワル カリフォルニア大学サンフランシスコ校 総合内科教授UCSFのダリワル教授は巧みな臨床推論カンファレンスで有名です。 師匠であるティアニー先生が天才的な発想力によって診断を行うのに対して、 ダリワル先生は順序立った正確な診断に長け、AIの比較対象とされるほど。 そんな彼が診断のエキスパートになる方法についてレクチャーした 湘南鎌倉総合病院での特別講義を日本語字幕付きで公開! -
 THE内科専門医問題集“見るラヂオ”2024(全10回)第3回 内分泌・代謝2024/03/25(月)公開 筒泉 貴彦 愛仁会 高槻病院 総合内科 主任部長ケアネットライブ「THE内科専門医問題集 “見るラヂオ”2024」のアーカイブ配信です。 『THE内科専門医問題集(Ver.2)2』(医学書院)から、Q5とQ8を取り上げます。
THE内科専門医問題集“見るラヂオ”2024(全10回)第3回 内分泌・代謝2024/03/25(月)公開 筒泉 貴彦 愛仁会 高槻病院 総合内科 主任部長ケアネットライブ「THE内科専門医問題集 “見るラヂオ”2024」のアーカイブ配信です。 『THE内科専門医問題集(Ver.2)2』(医学書院)から、Q5とQ8を取り上げます。
※ライブストリーミング配信日:2024年3月24日 -
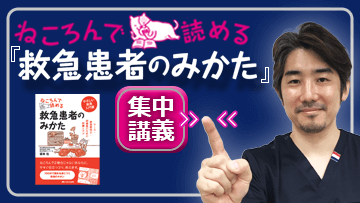 『ねころんで読める救急患者のみかた』集中講義(全4回)第4回 身体診察2023/05/25(木)公開 坂本 壮 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 救急救命科医長/ 臨床研修センター副センター長最終回は身体診察。テーマは「意識障害の患者さん、左右差に注目」「けいれんの患者さん、目に注目」「疼痛の患者さん、患部を直視せよ」「腹痛の患者さん、軟らかくても安心するな」そして「皮疹の患者さん、ABCDをチェック」の5つです。くも膜下出血・心因性痙攣・帯状疱疹・異所性妊娠・アナフィラキシーショックなどの見逃すと怖いあるいは見逃しや...
『ねころんで読める救急患者のみかた』集中講義(全4回)第4回 身体診察2023/05/25(木)公開 坂本 壮 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 救急救命科医長/ 臨床研修センター副センター長最終回は身体診察。テーマは「意識障害の患者さん、左右差に注目」「けいれんの患者さん、目に注目」「疼痛の患者さん、患部を直視せよ」「腹痛の患者さん、軟らかくても安心するな」そして「皮疹の患者さん、ABCDをチェック」の5つです。くも膜下出血・心因性痙攣・帯状疱疹・異所性妊娠・アナフィラキシーショックなどの見逃すと怖いあるいは見逃しや... -
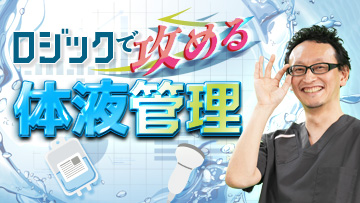 ロジックで攻める体液管理(全10回)第2回 細胞内液の異常と治療2025/07/24(木)公開 廣瀬 知人 筑波メディカルセンター病院第2回は「細胞内液の異常と治療」をテーマに特に高Na血症の管理に焦点を当てます 。Na異常が意識障害を招きやすい理由や、急速な補正に伴うリスクを解説 。最新のNa補正式や水分欠乏量の推算式、安全な補正速度を目標とした治療計画の論理的な立て方を学びます。早期かつ慎重な治療が求められる高Na血症への、より実践的なアプローチを身につけましょう。
ロジックで攻める体液管理(全10回)第2回 細胞内液の異常と治療2025/07/24(木)公開 廣瀬 知人 筑波メディカルセンター病院第2回は「細胞内液の異常と治療」をテーマに特に高Na血症の管理に焦点を当てます 。Na異常が意識障害を招きやすい理由や、急速な補正に伴うリスクを解説 。最新のNa補正式や水分欠乏量の推算式、安全な補正速度を目標とした治療計画の論理的な立て方を学びます。早期かつ慎重な治療が求められる高Na血症への、より実践的なアプローチを身につけましょう。 -
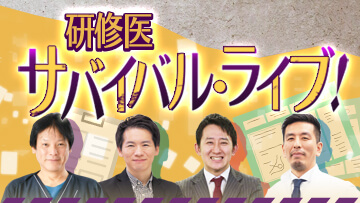 研修医サバイバル・ライブ!(全4回)第4弾 手技編 志賀隆先生2020/11/04(水)公開 志賀 隆 国際医療福祉大学救急医学講座 教授研修医サバイバル・ライブ!のラスト講義です。若手救急医がアニキと慕う熱血指導医の志賀隆先生が登場!
研修医サバイバル・ライブ!(全4回)第4弾 手技編 志賀隆先生2020/11/04(水)公開 志賀 隆 国際医療福祉大学救急医学講座 教授研修医サバイバル・ライブ!のラスト講義です。若手救急医がアニキと慕う熱血指導医の志賀隆先生が登場!
研修医にぜひマスターしてほしい3つの手技を厳選し、番組の映像も使いながら、パーフェクトな手技を行うための志賀流の極意を伝授します。
志賀先生のアツい!レクチャーで、手技のコツをしっかりと確認してください!
※ライブ配... -
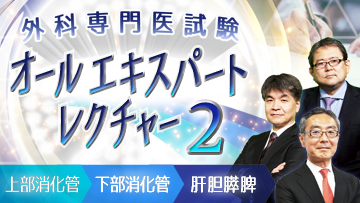 外科専門医試験 オールエキスパートレクチャー2(全11回)第4回 上部消化管42022/07/06(水)公開 深川 剛生 帝京大学医学部外科学講座教授上部消化管の最後は、胃のその他の疾患についてです。「胃GIST」「胃カルチノイド」「胃悪性リンパ腫」「胃MALTリンパ腫」「異所性膵」などを中心に、出そうなところを集中的に解説します。
外科専門医試験 オールエキスパートレクチャー2(全11回)第4回 上部消化管42022/07/06(水)公開 深川 剛生 帝京大学医学部外科学講座教授上部消化管の最後は、胃のその他の疾患についてです。「胃GIST」「胃カルチノイド」「胃悪性リンパ腫」「胃MALTリンパ腫」「異所性膵」などを中心に、出そうなところを集中的に解説します。
深川剛生先生から外科専門医を目指す方へのメッセージ:「外科医ですから手術が一番大事ですが、基礎研究・臨床研究を通して自分の専門疾患の理解を深め... -
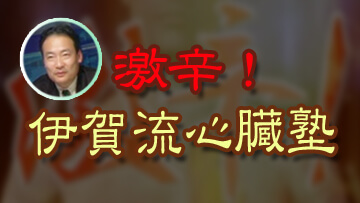 激辛!伊賀流心臓塾(全12回)第9回 避けては通れない臨床倫理の肝2005/09/09(金)公開 伊賀 幹二 伊賀内科・循環器科 院長6センチ大の腹部大動脈瘤が偶然発見されたとします。純粋に「医学的適応」のみ考えれば手術するのが妥当であり、手術の目的は突然死を予防することです。ただ、手術したからといって日常生活に変化があるわけではなく、逆に手術しないからといって痛みや症状があるわけでもありません。このようなとき主治医は、「医学的な判断のみにとどまらず、患者の...
激辛!伊賀流心臓塾(全12回)第9回 避けては通れない臨床倫理の肝2005/09/09(金)公開 伊賀 幹二 伊賀内科・循環器科 院長6センチ大の腹部大動脈瘤が偶然発見されたとします。純粋に「医学的適応」のみ考えれば手術するのが妥当であり、手術の目的は突然死を予防することです。ただ、手術したからといって日常生活に変化があるわけではなく、逆に手術しないからといって痛みや症状があるわけでもありません。このようなとき主治医は、「医学的な判断のみにとどまらず、患者の... -
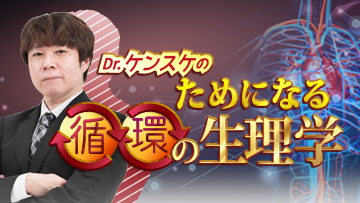 Dr.ケンスケのためになる循環の生理学(全11回)第6回 生理学に基づいた循環の見かた2023/12/21(木)公開 中村 謙介 横浜市立大学附属病院 集中治療部准教授これまで循環の2要素、酸素運搬oxygen deliveryと組織灌流perfusionについてじっくりと学んできました。今回はこの知見に基づいて臨床で循環をモニタリングするポイントについて説明します。尿量目標の背景にある考え方、血圧管理が最優先される理由などがスッと理解できます。いわゆるCryptic Shock(血圧正常なショック)についての解説も必見です。
Dr.ケンスケのためになる循環の生理学(全11回)第6回 生理学に基づいた循環の見かた2023/12/21(木)公開 中村 謙介 横浜市立大学附属病院 集中治療部准教授これまで循環の2要素、酸素運搬oxygen deliveryと組織灌流perfusionについてじっくりと学んできました。今回はこの知見に基づいて臨床で循環をモニタリングするポイントについて説明します。尿量目標の背景にある考え方、血圧管理が最優先される理由などがスッと理解できます。いわゆるCryptic Shock(血圧正常なショック)についての解説も必見です。 -
 研修医サバイバル・ライブ!2021(全5回)第4弾 手技編 志賀隆先生2021/12/08(水)公開 志賀 隆 国際医療福祉大学救急医学講座 教授志賀隆先生は、米国メイヨー・クリニックで救急研修後、ハーバード大学マサチューセッツ総合病院で指導医を務めた、救急医療のスペシャリストです。また、後進の育成に熱心に取り組んでおり、若手救急医からアニキとして慕われている熱血指導医。 そんな志賀先生のCareNeTV番組「Dr.志賀のパーフェクト!基本手技」は臨床医として必須の9の手技を、実...
研修医サバイバル・ライブ!2021(全5回)第4弾 手技編 志賀隆先生2021/12/08(水)公開 志賀 隆 国際医療福祉大学救急医学講座 教授志賀隆先生は、米国メイヨー・クリニックで救急研修後、ハーバード大学マサチューセッツ総合病院で指導医を務めた、救急医療のスペシャリストです。また、後進の育成に熱心に取り組んでおり、若手救急医からアニキとして慕われている熱血指導医。 そんな志賀先生のCareNeTV番組「Dr.志賀のパーフェクト!基本手技」は臨床医として必須の9の手技を、実... -
 Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第2回 Intravenous antihypertensive Treatment in Hyperacute Intracerebral Hemorrhage2015/02/11(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回紹介する論文は「Systolic blood pressure after intravenous antihypertensive treatment and clinical outcomes in hyperacute intracerebral hemorrhage: the stroke acute management with urgent risk-factor assessment and improvement-intracerebral hemorrhage study.」 【PMID:23704107】 テーマは「急性脳出血患者への降圧療法による...
Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談(全12回)第2回 Intravenous antihypertensive Treatment in Hyperacute Intracerebral Hemorrhage2015/02/11(水)公開 林 寛之 福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授今回紹介する論文は「Systolic blood pressure after intravenous antihypertensive treatment and clinical outcomes in hyperacute intracerebral hemorrhage: the stroke acute management with urgent risk-factor assessment and improvement-intracerebral hemorrhage study.」 【PMID:23704107】 テーマは「急性脳出血患者への降圧療法による... -
 Sedation for All―安全で確実な鎮静・鎮痛プログラム―(全9回)第7回 成人症例ディスカッション2014/11/26(水)公開 竹内 広幸 健和会大手町病院 麻酔科ここまで学んできたセデーションの手順と薬理学を、実際の場面でどう生かすのか。この回では、成人の急患が運ばれてきた想定で、何をポイントに、どのレベルの鎮静や鎮痛が必要かを考え、どんな手順で実施するのかを学びましょう。ここで示されるケースの男性はかなりの肥満体。この体格的特徴によって、セデーションを行うに際にどのような注意が必要...
Sedation for All―安全で確実な鎮静・鎮痛プログラム―(全9回)第7回 成人症例ディスカッション2014/11/26(水)公開 竹内 広幸 健和会大手町病院 麻酔科ここまで学んできたセデーションの手順と薬理学を、実際の場面でどう生かすのか。この回では、成人の急患が運ばれてきた想定で、何をポイントに、どのレベルの鎮静や鎮痛が必要かを考え、どんな手順で実施するのかを学びましょう。ここで示されるケースの男性はかなりの肥満体。この体格的特徴によって、セデーションを行うに際にどのような注意が必要... -
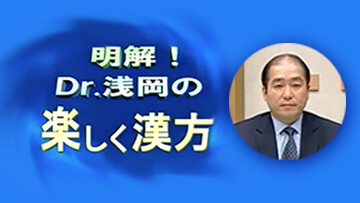 明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第10回 そろそろ更年期かしら…2005/11/25(金)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長のぼせ、イライラ、鬱傾向、月経不順、めまい…。中年女性にとってとても辛い更年期障害は、西洋医学的には「ホルモンの異常」としてとらえられています。「不定愁訴」といわれるこれらの症状はその名のとおり発現や症状が不定であり、治療がなかなか難しいところではないでしょうか。 しかしこれまで学習してきた「東洋医学のものさし」、具体的には「気逆」「...
明解!Dr.浅岡の楽しく漢方(全18回)第10回 そろそろ更年期かしら…2005/11/25(金)公開 浅岡 俊之 浅岡クリニック 院長のぼせ、イライラ、鬱傾向、月経不順、めまい…。中年女性にとってとても辛い更年期障害は、西洋医学的には「ホルモンの異常」としてとらえられています。「不定愁訴」といわれるこれらの症状はその名のとおり発現や症状が不定であり、治療がなかなか難しいところではないでしょうか。 しかしこれまで学習してきた「東洋医学のものさし」、具体的には「気逆」「... -
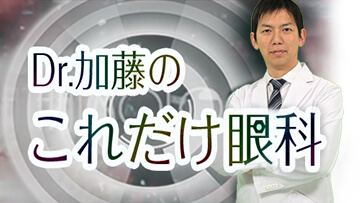 Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第5回 「加齢黄斑変性」はこれだけ2016/06/15(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授加齢黄斑変性は文字どおり加齢に伴い発症し、視野中心部の歪みを特徴する疾患です。 有病率は50歳以上の80人に1人。失明原因の第4位と高齢者のQOLを著しく害する疾患です。 しかしながら、病識が少ないため老化による視力低下として見過ごされることも少なくありません。 番組では、加齢黄斑変性のサイン、眼科医が行う検査や治療などについて加藤浩晃...
Dr.加藤の「これだけ眼科」(全7回)第5回 「加齢黄斑変性」はこれだけ2016/06/15(水)公開 加藤 浩晃 アイリス株式会社 取締役副社長CSO・ デジタルハリウッド大学大学院 特任教授加齢黄斑変性は文字どおり加齢に伴い発症し、視野中心部の歪みを特徴する疾患です。 有病率は50歳以上の80人に1人。失明原因の第4位と高齢者のQOLを著しく害する疾患です。 しかしながら、病識が少ないため老化による視力低下として見過ごされることも少なくありません。 番組では、加齢黄斑変性のサイン、眼科医が行う検査や治療などについて加藤浩晃... -
 Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第7回 外来アンチバイオグラム 62023/11/30(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表今回のターゲットはA群溶血性連鎖球菌(GAS)と黄色ブドウ球菌です。これらが起炎菌となる主な感染症としては溶連菌性咽頭扁桃炎、皮膚軟部組織感染症・蜂窩織炎・丹毒があります。JANIS(厚労省院内感染対策サーベイランス)のデータによる感受性を踏まえ、これらの感染症にどの抗菌薬を用いるべきかを具体的に解説。B群・C/G群連鎖球菌、メチシリン耐...
Dr.RIKIの感染症倶楽部 根本から学ぶ!外来での経口抗菌薬の使い方(全26回)第7回 外来アンチバイオグラム 62023/11/30(木)公開 永田 理希 希惺会 ながたクリニック 院長、感染症倶楽部シリーズ 統括代表今回のターゲットはA群溶血性連鎖球菌(GAS)と黄色ブドウ球菌です。これらが起炎菌となる主な感染症としては溶連菌性咽頭扁桃炎、皮膚軟部組織感染症・蜂窩織炎・丹毒があります。JANIS(厚労省院内感染対策サーベイランス)のデータによる感受性を踏まえ、これらの感染症にどの抗菌薬を用いるべきかを具体的に解説。B群・C/G群連鎖球菌、メチシリン耐... -
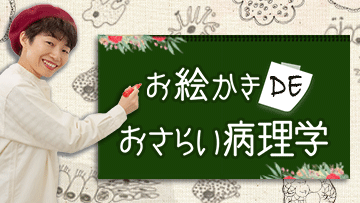 お絵かきDEおさらい病理学(全10回)第4回 感染症2022/09/14(水)公開 小倉 加奈子 順天堂大学練馬病院 病理診断科第4回は、感染症についてのおさらいです。病理学総論では、感染症で起こりうる病態はほとんどが炎症です。微生物ごとに特異的な病理組織学的特徴がありますので、臨床で遭遇しやすいウイルス性肺炎と細菌性肺炎の違いにフォーカスして見ていきましょう。
お絵かきDEおさらい病理学(全10回)第4回 感染症2022/09/14(水)公開 小倉 加奈子 順天堂大学練馬病院 病理診断科第4回は、感染症についてのおさらいです。病理学総論では、感染症で起こりうる病態はほとんどが炎症です。微生物ごとに特異的な病理組織学的特徴がありますので、臨床で遭遇しやすいウイルス性肺炎と細菌性肺炎の違いにフォーカスして見ていきましょう。